アーティストで研究者の久保田晃弘氏をナビゲーターに、次の100年に向けたアートとテクノロジーについて考える対談シリーズ。『コンヴィヴィアル・テクノロジー 人間とテクノロジーが共に生きる社会へ』(BNN新社、2021年)を上梓したデザイン・イノベーション・ファーム、Takram(タクラム)の緒方壽人氏との話は、つづいてテクノロジーへ。行き過ぎではない「ちょうどいい道具」としてのテクノロジーとは何か。かつてイヴァン・イリイチが投げ掛けた「コンヴィヴィアル」(共に生きる)というキーワードは、いまの私たちの社会の諸相の再考を促す。コンヴィヴィアルな教育、コンヴィヴィアルなアート、さらにコンヴィヴィアルな組織のあり方まで、久保田氏と緒方氏の話題は派生的に広がっていく。
 左から、久保田晃弘氏、緒方壽人氏
左から、久保田晃弘氏、緒方壽人氏
以下、撮影:畠中彩
教育と学校
緒方:この本は、教育関係の方にも多く読んでいただいていたようです。子どもや大学生くらいの若い人たちにも、「ちょうどいいテクノロジー」について一緒に考えたり、伝えていきたいなと改めて思います。
久保田:私も長年教育現場にいることで、「行き過ぎ」な状況を目の当たりにすることが増えてきました。教育は、サービスでもエンターテインメントでもなく、教育は教育なんです。でも現状は学校にビジネス的な活動を強要したり、論文数のような「数」で研究の価値を測るなど、教育という本来の目的が見失われつつあります。教育とビジネスは、本質的に折り合わないところがあります。
緒方:本書で引用しているイヴァン・イリイチも『脱学校の社会』(註1)という本を書いていて、手段と目的が逆転することを懸念しています。学ぶ喜びを得られる場であるはずの学校が、いつのまにか良い学校に行くための勉強、良い教育を受けるための教育の場になってしまう。イリイチの「デスクール」という言葉が、日本で「脱学校」と略されたので「学校がいらない」と受け取られることもあり賛否両論を生んでいますが、ただ単に学校が不要と言っているわけではないようです。
久保田:イリイチの批判で重要だと思っているのは、教員が、例えば「これは良い作品です」と価値を事前に規定したり、制度化することの危険性です。教育にとって大切なのは、信じることを避け、疑いを持ち続けるようにすることです。効率や生産性を求められた教育は、非効率な本質を隠蔽し、既存の価値によって評価された結果をわかりやすく、つまりディテールを取捨して体系化し、それを信じ込ませることを良しとしてしまう。それは教育のプロパガンダ化です。イリイチは、そうした近代的な学校に対する異議申し立てをしたのです。選ぶことは、わかりやすいことと並んで、常に危険と表裏一体です。
緒方:イリイチの著書をいろいろと読み、彼は淡々としていてもの静かな人という印象があります。拡声器を使って話すことは自分がやりたいこととは違う、と。スピーチもほとんど残っていません。ただ著作の分野が政治や医療、ジェンダーなど多岐にわたっていて、それらの翻訳のされ方や時代が後押ししてセンセーショナルに伝わり、各地で誤解や賛否両論を生んだりしているのではないかと思います。
久保田:叫んだり、戦ったりすることは時として必要ですが、それは本当に最後の手段ですよね。例えばグレタ・トゥーンベリさんの、2018年の国連気候変動会議での叫びのようなスピーチには、必然性と説得力がありましたが、叫ばなくてもいい人が声高に叫んだり、話題をつくるために作為的にふるまったりすることのほうが遥かに多い。緒方さんの著書では、センセーショナルな言葉づかいを、意識的に避けようとしていることに共感しました。
緒方:ただ本当に届けたかった相手には、むしろセンセーショナルな伝え方をしないと読んでもらえなかったかなというもどかしさもあります。
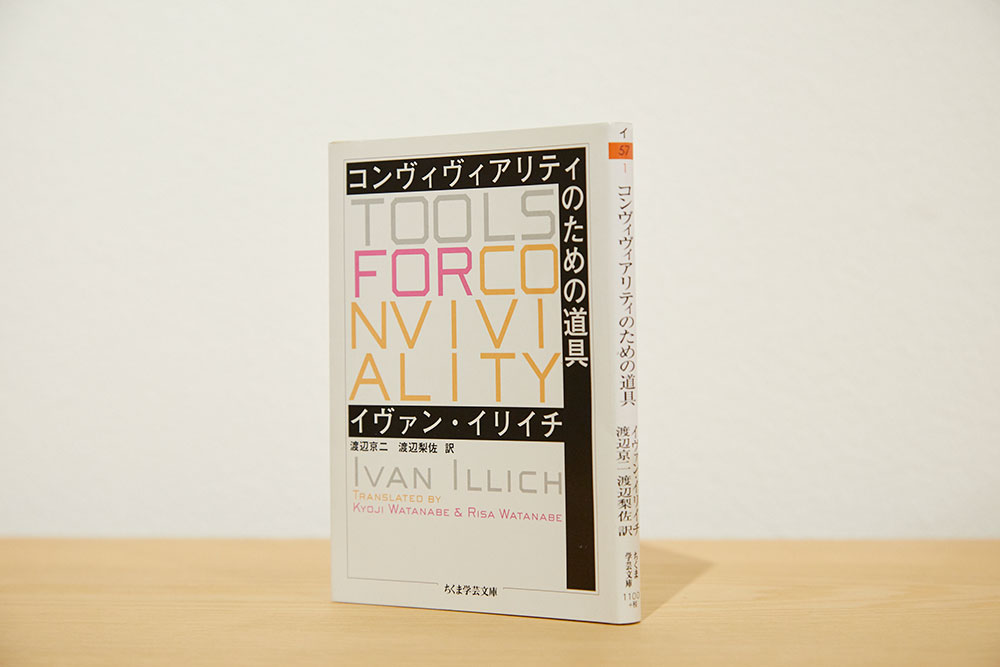 イヴァン・イリイチ『コンヴィヴィアリティのための道具』渡辺京二、渡辺梨佐訳(筑摩書房、2015年)書影
イヴァン・イリイチ『コンヴィヴィアリティのための道具』渡辺京二、渡辺梨佐訳(筑摩書房、2015年)書影
拡大という病
久保田:届ける相手という点では、本のなかで「コミュニティ」についても言及されていますよね。
緒方:例えば、民藝運動では「生活に根ざした美」が目指されていました。それは純粋に日常生活で使うものを美しくしたいから始まったかというと、決してそれだけが出発点ではなかったのではないか、と思うのです。自分でつくったものを身近な人に見せたり贈ったりして「いいね」といわれて自信になり、そこから広がっていった面もあるのではないかと。歴史的な大きな出来事の背景にも、小さなコミュニティやマーケットがあった。そのことが重要ではないかと思います。
久保田:そうですね。民藝運動は、日常生活の美以前のものごとを取り上げた出発点は良かったのですが、のちに選ばれたものに対して「真の美」や「日本の美」といってみたり、自らを「正しい」民芸として区別したことによって、逆に権威やナショナリズムと結びついてしまいました。
緒方:自然発生した小さなマーケットから、それを拡大して権威化、形式化すると、分水嶺を超えてしまいますね。山崎亮さんが以前「現在の民藝は、YouTubeだと思う」とおっしゃっていて、かつての民藝は誰でも参加できる、小さく無数なコミュニティという意味でYouTubeに近かったのかもしれません。
久保田:なるほど。むしろあのスケールだからこそ、つまり巨大であることと微小であることが共存しているからこそ、それが維持できるのかもしれません。誰かがYouTubeを規格化しようとしたり、序列化して「これが真のYouTubeだ」などといったとしても、あの規模のプラットフォームに対しては、ほとんど無意味ですからね。
緒方:ただ、小さなコミュニティやマーケットを維持するために、大きくなりすぎることは危険ですよね。それこそ手段と目的が逆転してしまう。
久保田:それこそが、現在の資本主義が抱える大きな問題ですね。貨幣も、本来は自分が持っていないスキルやものを、ほかの人と交換するための手段だったのかもしれませんが、いつのまにか、お金を儲けたり、資本を増やすこと自体が目的になってしまった。作品の内容よりもオークションで落札された価格のほうがニュースになったり、企業の活動内容よりも株価が前面に出されるような世界です。
ヴィクター・パパネックは、70年代すでに、人間の欲望以上に拡大せざるをえない生産能力の問題を指摘しています。先ほどのバーネイズのプロパガンダが、その状況をさらに加速し、悪化させ続けます。「拡大」こそが近代の大いなる病ではないでしょうか。ですので、SNSにしても「フォロー可能な人数は1,000人まで」だとか、まず技術によってその規模を制限すればいいのかもしれません。「拡大」という病を治療する技術こそが必要なのだと思います。
緒方:どうしても人間は拡大を目指してしまうものなのですかね……。
 久保田氏は手段と目的が逆転していることの一例として資本主義を挙げた
久保田氏は手段と目的が逆転していることの一例として資本主義を挙げた
いつでも手放せるように
久保田:だからこそ、緒方さんの本でも取り上げられていた、アーンスト・シューマッハーの『スモール イズ ビューティフル』(註2)、すなわち「小さいこと」の大切さを再確認することが必要だと思っています。彼が示唆した「適正技術」の生態学的ネットワークは、地球温暖化の対応にこそ必要です。あとがきにも書かれていましたが、緒方さんが東京から長野に引っ越されたことも、拡大を目指さない適正技術の実践につながっていると思いました。
緒方:長野へ拠点を移したことは、新型コロナウイルスの流行がきっかけではありましたが、同時に「そのテクノロジーは人間から自然環境の中で生きる力を奪っていないか」というイリイチが投げかけた問いのひとつにハッとしたところはありました。この本でも「手放せる道具」という言い方をしていますが、「都市」という道具を一度手放してもいいのではないか、と。都市という道具を捨てるのではなく、使い終わったら置いて、また使うときに手に取るような付き合い方ができないかと考えました。例えば人里離れた山奥で自給自足の生活となると、資本主義という道具をまったく使えない状態に置いてしまうことにもなるので、そういうこととも違うかなと。
久保田:まさに、ロングテールライフの実践ですね。手放せなくなったら、それこそ依存です。無意識のうちに中毒にさせるビジネスは、現代社会に深く根付いてしまっています。一度買ったら買い続けなければいけない。使い続けなければいけない。都市生活もそうだと思うんです。田舎の生活が想像できなくなり、現状の良し悪しの判断さえできなくなっているとすれば、それは中毒にほかなりません。だからといって、逆にテクノロジーを使わずに捨ててしまえ、という反動的な活動でもなく、身近なものとしてうまく使いこなしながら、同時に常に手放せるようにしておく。それはコンヴィヴィアルであるための必要条件でもあります。依存も放棄もせず、常に中庸の感覚で。
 拠点を長野県へ移し、仕事をつづけながら農作業にも取り組む緒方氏
拠点を長野県へ移し、仕事をつづけながら農作業にも取り組む緒方氏
コンヴィヴィアルなサイズ
緒方:サブスクリプションも解約のフローがわかりにくいことがたびたび問題になりますが、そういった姑息なことではなく、もっと自然な状態で、サステナブルなビジネスの設計をできないのかなと思います。でもどうしても拡大を目指してしまうのですよね。
久保田:良い仕事を一つひとつ行うことから、いつしか現状を維持することが目的になってしまいがちです。さきほどの手段と目的の入れ替わりは、自分も含めて、どの世界でも起こりがちです。スケールの問題は教育現場では特に重要です、美術大学のクラスの人数が、なぜ20人かせいぜい30人が限界なのか。人間が協力し合える、環境や規模には限りがあって、コミュニケーションには適正なサイズがありますね。
緒方:Takramも最初は数名でスタートしたのが、いま50人になってチャレンジングな段階に来ていると思っています。放っておくと、創業時のコアメンバーが決定権をもち、その下にリーダーがいて、チームができる、といったヒエラルキーのピラミッドが発生します。そのほうが効率はいいんですよね。ただ、そうすると組織がどんどん硬直化していく危機感を感じて、創業時のメンバーを「ディレクター」とよび、ディレクターだけのミーティングで組織の意思決定もしていましたが、その肩書きを外し、情報の格差をなくすためにディレクターだけのミーティングもやめました。
久保田:フラットになったら、効率や生産性は低下するかもしれないけれど、余計なことに配慮せずに意見が言えるようになるのは良いことですね。どんなことにも、両側面があります。組織が階層化することの危険性のひとつは、これまでとは違うことを、特に上に立つ者が言いにくくなることかもしれません。大学の場合は、毎年学生が入れ替わります。そうした開放系のおかげで、毎年思考も行動もリフレッシュできます(笑)。
緒方:Takramの適正規模は手探りですが、ヒエラルキーをつくってしまう制度を辞めることもひとつだし、副業を許容することもひとつかもしれません。ピラミッドを大きくしない新しい組織のあり方を探っていきたいと思っています。
久保田:切実な問題ですね。僕自身は、授業の人数に限らず、人間の認知的、身体的な能力として、全体を見通せるのが、最大でも30人くらいだと感じています。50人になったTakramが、それにどのように適応し、どのように変わっていくのか。チャレンジであると同時に、楽しみにでもあります。
大きな変革というのは、ドラスティックに突然起こるものではなく、日々のなかの小さな変化の積み重ねの現れだと思います。「コンヴィヴィアル」であるためにまず必要なのは、適切なサイズを維持すること。そのうえで、「ちょっとこれを思いとどまろう」とか、「こっちにしよう」だとか、一人ひとりが生活の価値や選択を少しずつ変えていく。それが世界の人口の80億集まれば、かなりの変革を引き起こすのではないでしょうか。
(脚注)
*1
イヴァン・イリイチ『脱学校の社会』東洋、小澤周三訳、東京創元社、1977年。
*2
F・アーンスト・シューマッハー『スモール イズ ビューティフル』小島慶三、酒井懋訳、講談社、1986年。
緒方壽人[おがた・ひさと]
ソフトウェア、ハードウェアを問わず、デザイン、エンジニアリング、アート、サイエンスまで幅広く領域横断的な活動を行うデザインエンジニア。東京大学工学部を卒業後、国際情報科学芸術アカデミー(IAMAS)、リーディング・エッジ・デザインを経て、ディレクターとしてTakramに参加。主なプロジェクトに、「HAKUTO」月面探査ローバーの意匠コンセプト立案とスタイリング、NHK Eテレ「ミミクリーズ」のアート・ディレクション、紙とデジタル・メディアを融合させたON THE FLYシステムの開発、21_21 DESIGN SIGHT企画展「アスリート展」ディレクターなど。2005年、ドイツiFデザイン賞、2012年、第16回文化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作品など受賞多数。著書に『コンヴィヴィアル・テクノロジー 人間とテクノロジーが共に生きる社会へ』(BNN新社、2021年)。
久保田晃弘[くぼた・あきひろ]
1960年生まれ。多摩美術大学美術学部情報デザイン学科メディア芸術コース教授/国際交流センター長。アーティスト。東京大学大学院工学系研究科船舶工学専攻博士課程修了、工学博士。数値流体力学、人工物工学に関する研究を経て、1998年より多摩美術大学にて教員を務める。芸術衛星1号機の「ARTSAT1:INVADER」でアルス・エレクトロニカ 2015 ハイブリッド・アート部門優秀賞をチーム受賞。「ARTSATプロジェクト」の成果で、第66回芸術選奨の文部科学大臣賞(メディア芸術部門)を受賞。著書に『遙かなる他者のためのデザイン 久保田晃弘の思索と実装』(BNN新社、2017年)、共著に『メディアアート原論』(フィルムアート社、2018年)ほか。
あわせて読みたい記事
- メディアアートを育む学校file1. 多摩美術大学 情報デザイン学科:久保田晃弘×宮崎光弘(後編)2019年11月7日 更新
- メディアアートが問う自然との共生2020年11月4日 更新











