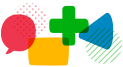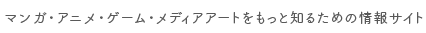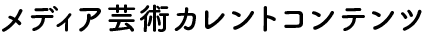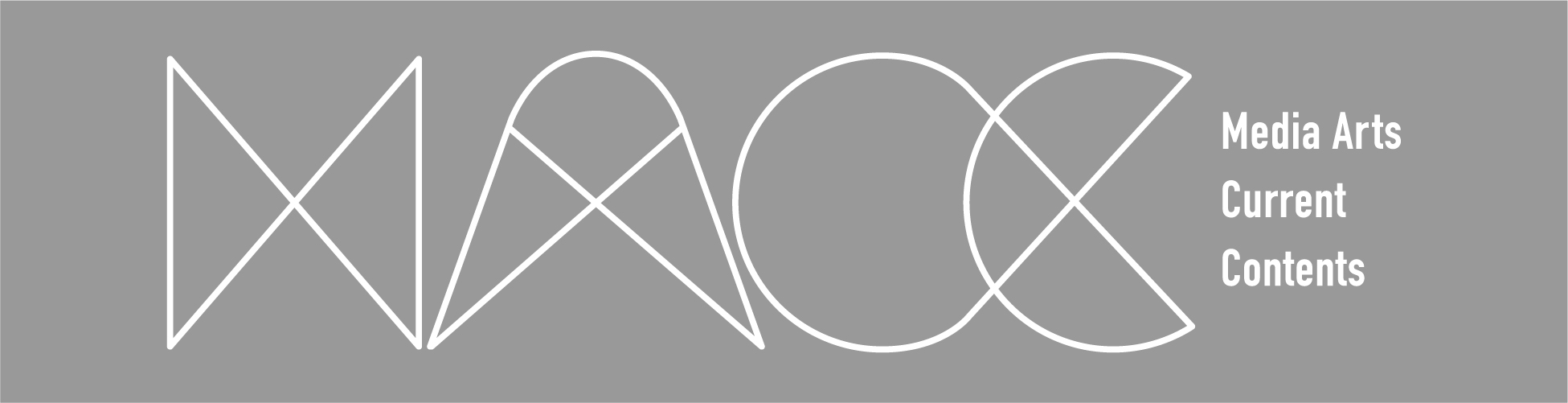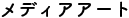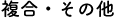読まれている記事一覧
多くの人々に親しまれているマンガ『ちびまる子ちゃん』の作者、さくらももこ。マンガ家としてだけでなく、エッセイストとしても活躍しており、1991〜1992年...
描かれている絵/画自体に焦点があてられがちなアニメーションだが、ボケ、広角、魚眼などレンズを通して得られる効果が表現として取り入れられている。本... 9月23日(木)から10月3日(日)にかけて「第24回文化庁メディア芸術祭受賞作品展」が開催され、会期中にはトークセッションなどの関連イベントが行われた。9...2021年11月29日 更新
音を文字で表す擬音語に、様子を文字で表す擬態語。これらの「オノマトペ」は、マンガにおいて欠かせない表現のひとつとなっている。本コラムでは、ありきた...
「ピクセルアート」あるいは「ドット絵」という視覚表現がある。ピクセルアートは、1970~90年代のビデオゲームのグラフィックの主流であったおかげで、「... 社会的な問題に対して、視覚的に何らかの意思を訴える「社会派アート」。本コラムでは、そんな社会派アートのなかでも、これまで芸術的評価の土俵にすらあげ... 第20回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞も受賞した、松本大洋の「自伝的作品」とされる『Sunny』は、松本がデビュー以来温めてきた作品だ。本作の、他の...
今や3Dグラフィックスは、ゲーム機やPCはもちろんのこと、スマートフォン、自動車の情報ディスプレイ、飛行機の機内エンターテインメントシステムにも採...
「妖怪」と聞いてその姿形を思い浮かべられる人は少なくないだろう。私たちが認識しているそんな妖怪はどのように形成されていったのだろうか。現代の妖怪...
アニメ・特撮・ゲームなどのメディア芸術の世界における「音」の表現を切り拓いてきた先駆者にお話しをうかがうインタビューシリーズ。その第1回目にふさわ...
市川春子の同名マンガを原作とした、京極尚彦監督による『宝石の国』のアニメーションは、全11話が2017年10月から12月にかけて放映された。人型の宝石たち... ◯HDRの持つ可能性(2)
◯アニメの色数?
その昔...おそらく『クラッシャージョウ』(1983)の特集記事ではないかと思うのだが、安彦良和氏が『機動戦士... Pixel art (dotto-e in Japanese) is a form of visual representation. The term “pixel art” may imply retro game graphics as it was the mainstream of ...
世界最大の博物館のひとつとして知られるイギリス・ロンドンの大英博物館で、2019年5月23日(木)~8月26日(月)、マンガ展「The Citi exhibition Manga」... 世界各地のビデオゲームには、『スーパーマリオブラザーズ』(1985年)をはじめ1980~1990年代に生まれた日本のビデオゲームを様式やジャンルの原型とするも...田中 治久(hally)2021年11月19日 更新
長い歴史を持ち、現在では一大ジャンルとも言えるグルメマンガ。基本的にモノクロ表現で、音も匂いも、もちろん味もしない、視覚だけが頼りとなるマンガ表...
Pixel art (dotto-e in Japanese) is a form of visual representation. The term “pixel art” implies “retro game graphics” as it was the mainstream o...
「食」をテーマにしたビデオゲームは少ない。そんななか、「料理」をテーマにしたユニークなタイトルが「クッキングママ」シリーズだ。本作はまた日本もさ...
2020年2月16日(日)、国立新美術館にて「2019年度メディア芸術連携促進事業 研究成果マッピング シンポジウム」が開催された。「研究マッピング」...2020年3月5日 更新
2022年3月18日(金)から8月31日(水)にかけて、国内の展覧会史上、最大規模となるロボットをテーマにした展覧会、特別展「きみとロボット ニンゲンッテ、ナ...
ページの先頭へ