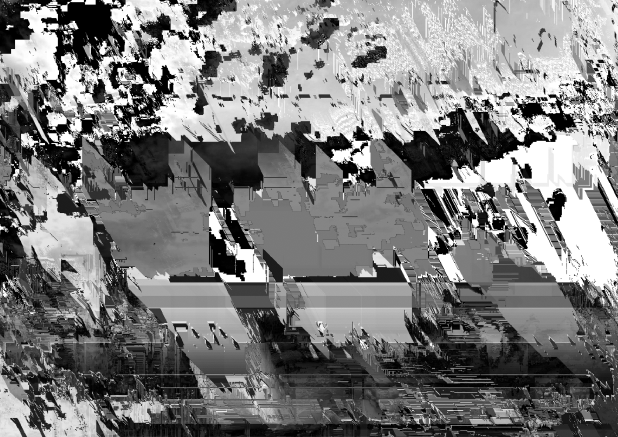
「メディアアートへの視座」と題したこの連載では、メディアアートに関連するキーワードをひとつ取り上げて、その学術的な背景を概説していきます。そのことによってメディアアートをより深く楽しみ、考えるための視座を提示することを目的としています。その第一回となる今回は、基礎情報学、表象文化論を専門とする原島大輔氏に「サイバネティクス」という観点から論じてもらいました。
0
サイバネティクスからのメディアアートへの視座。それをここではひとことで次のように言ってみよう。《メディアアートとは中間の芸術である》。中間とはここでは、矛盾する二つの過程が共立するところ、という意味である。メディアという語はそもそも一般的な意味での中間を言い表すメディウムの複数形でもあるし、他にもいろいろな意味をもつので多様に解釈することができるけれど、ここではあえてこの特異な中間という意味にしぼって解釈してみることで、メディアアートとサイバネティクスとの関係について、そしてメディアアートへの視座について、どのように理解することができるか、ひとつの論考を展開してみよう。この前編では、まずその準備として、サイバネティクスについて、その理論において観察者はどこにいるのかということに注目しながら紹介する。その議論にもとづいて、続く後編では、中間の芸術としてのサイバネティクス的なメディアアートへの視座をつくりだしていこう。
1
サイバネティクスは、アメリカ合衆国のノーバート・ウィーナーが1948年に出版した『サイバネティクス----動物と機械における制御と通信』によって知られるようになった、科学技術的なひとつの方法である(1)。端的に言ってそれは、制御と通信と統計力学という観点から、動物と機械の機能を統一的に理論化するものである。人間も動物も機械も、情報処理という観点でみれば、みんな同じである、というのがサイバネティクスの衝撃的な仮説だった。しかしこれは注意が必要な両義的な仮説でもあった。どういうことか。まずはそれについて順を追ってみていこう。
情報、メッセージ、コミュニケーション、コントロール、フィードバック、ネットワーク、確率、統計、インターディシプリン/トランスディシプリン、......といった、20世紀後半から現在にいたるまでのグローバルな科学技術社会的基盤の構築に決定的な影響を与えてきたアイデアたちを、ひとつの統一的な理論のなかで展開した巨大な知性が、サイバネティクスである。だから、サイバネティクスという言葉はいまあまり普段みかけなくなっているかもしれないけれど、サイバネティクスで論じられたこれらのアイデアはいまやますます身近なものになってきているので、わざわざここで何かを手解きするまでもなく、みんな普段それと意識することなくサイバネティクスからの視座でものをみているのだと言いたくなるほどだが、しかしそう言ってしまうと大事な問題がみえなくなってしまう。サイバネティクスについて考えることがいま重要な理由は、それが現代の科学技術や芸術文化の基礎的な設計理念に強い影響を与えたからというだけではない。
(1)ノーバート・ウィーナー『サイバネティックス----動物と機械における制御と通信』池原止戈夫、弥永昌吉、室賀三郎、戸田巌訳、岩波書店、2011年。また、ウィーナーとサイバネティクスについては、西垣通『デジタル・ナルシス:情報科学パイオニアたちの欲望』岩波書店、2008年、西垣通、伊藤守訳『よくわかる社会情報学』ミネルヴァ書房、2015年も参照。
2
ウィーナーはどのような視座からサイバネティクスをつくりだしたのだろうか。ウィーナーは数学者でもあり哲学者でもあった。いや、そう表現するだけでも足りない。サイバネティクスはたくさんの異なる領域の研究者たちの交流のなかでかたちづくられた。ウィーナーがサイバネティクスをつくりあげた動機のひとつには、専門化と細分化が高度に進行した諸学問領域を統合するということもあったようだ。それは、文理融合、科学芸術、領域横断、そういうトランスディシプリナリーな学問再編の試みだった。サイバネティクスの守護聖人にウィーナーはライプニッツをかかげていた。すでに20世紀中盤当時の学問は専門分化が進み、同じ学科であってもちょっとでも方法論が違えばまったく話が通じない、という状況がはじまっていたから、ライプニッツの頃のようにすべての学問に通ずるというわけにはいかないかもしれないけれど、ウィーナーは、いろいろな専門分野のあいだで、方法論や術語は違っても、じつは同じ関心やアプローチが共有されていることが少なくないことに気づいていて、それらをなんとかして統合することくらいはできるはずだと考えた。そうしてたくさんの専門領域の研究者たちとの交流のなかでサイバネティクスができあがった。だから、ウィーナーは数学者や哲学者というより諸学の統合をめざすサイバネティクス学者だったと言ったほうが適切かもしれない。
そんなサイバネティクスだから、いかにその成果の諸断片が便利に応用可能だったとしても、それらがいったい何を見据えていたのかを理解するのは難しい。それに、そんな大それた試みが、はたして成功し、目標が達成されたのか、それもまた難しいところだ。ただ、サイバネティクスがある決定的な誤解のもとで応用されてしまった、ということは言えるだろう。それは、人間や動物や社会や自然を機械化する理論としてサイバネティクスが応用されたということである。つまり、電子回路や神経系のメタファーで生物や社会を計画的に予測し制御するための基礎理論としてのサイバネティクスの利用である。ウィーナー自身はそのような機械への還元には抵抗していたのにもかかわらず。
動物の神経系と電子回路を同一視するような還元によってサイバネティクスは次のように応用される。たとえば、サイボーグやサイバースペースは、語源的にもサイバネティクスから派生してはいるものの、それは多くの場合この還元にもとづいた応用である。また、コントローラーやオペレーションやガバナンスといった制御や操作のための理念や制度が一般化した制御社会の状況もこの一例であり、たとえばかつてのチリの「サイバーシン計画」は実現にはいたらなかったものの計画的で統一的な制御社会をめざしたものだったし、効率性と計画性を最優先して費用対効果と未来予測を重視するという意味では現在のグローバル市場経済もまた同様であり、神経系のメタファーにもとづく機械学習による予防や先制の先端テクノロジーもまたそうであるとも言える。それから、人間を機械に還元できるという信念は、高度な科学技術によって人間を超えた存在をつくりだそうという欲望を駆動し、人工知能やポストヒューマンやトランスヒューマンや技術的特異点などを理想化し続けてきた。
こうしたサイバネティクスの応用の是非はここでは問題ではない。問題は、そもそもこうした応用の多くがサイバネティクスの重大な欠点を見落とし、したがって重要な肝所をとらえそこねてもいることである。それを説明するには、グレゴリー・ベイトソンとマルティン・ハイデッガーによる、サイバネティクスへの対照的な評価を比較してみるのがよいかもしれない。すなわち、サイバネティクスを倫理的な生態学に応用したベイトソンと、サイバネティクスを人間を道具化して制御する方法論として批難したハイデッガー(2)。同じサイバネティクスについてどうしてこうも極端に反対の評価になるのだろうか。どちらか一方の理路だけが正しいということでもないように思われる。むしろ、両者とも同じ罠にはまっていたとは考えられないだろうか。そして、じつはウィーナーもまた同じ罠にはまっていたのであり、だからこそ、こんなにもたやすくサイバネティクスは生態学の基礎理論になるかとおもえば制御社会の基礎理論になりさえもするのではないだろうか。その反転の回転軸は、サイバネティクスのなかに散在している。それは確率や統計やメッセージや伝達や情報量やエントロピーといった概念たちである。たとえば、「通信と制御と統計力学を中心とする一連の問題が、それが機械であろうと、生体組織内のことであろうと、本質的に統一されうるものである」(3)というふうにウィーナーは記述することがあるが、こうなると、サイバネティクスが統一的な制御社会や超越的な神秘主義の基礎理論であるようにみえてもしかたがない。ここで観察者の視座が重要になってくる。どういうことか。
(2)グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学』佐藤良明訳、新思索社、2000年、マルティン・ハイデッガー『技術への問い』関口浩訳、平凡社、2009年。
(3)ウィーナー『サイバネティックス』45頁
3
サイバネティクスは端的に言えば統計にもとづく予測の理論だが、ウィーナー自身はそれらが有効である場面とそうでない場面を分けて考えることに慎重であろうとした。実際、そうしないと、サイバネティクスが単純な神秘主義や制御理論になってしまう。ここに視座がかかわる。というのも、サイバネティクスの基礎であるこの確率と統計が意味をもつためには、状況にたいして超越的で客観的な視座から観察していなければならず、サイバネティクス的な予測は、起こりうる出来事のすべてのケースを把握したうえで予測されなければ、根底からくずれる不確実性を絶対的には払拭しきれないものだからである。極端に限られた、たとえばサイコロの出目についてであれば、そういう客観的視座に限りなく近づいて予測することもできるだろう。しかしそれであっても、生きられた現実の環境でサイコロを投げてみたら、サイコロが割れて目の数が六つではなくなることさえありうるのであり、そういうことまで考えはじめると予測はどんどん難しくなってくる。そして実際に生きている観察者としての動物が生活している環境は、そういう規格外の変動が無数にもつれあっていて、しかも同一の条件で何度もやり直すことはできない、歴史的一回性である。そんな環境において起こりうるすべての事象を把握できるような真に客観的な視座がこの世にありえるのだろうか。そういう普遍的な知性は存在するのだろうか。そして、もし存在するとして、この科学技術によってその知性にあずかることはできるのだろうか。もしそれが可能だと一足飛びにあるいはそれと気づかずに措定するならば、その特権的な視座の主観性は宇宙の全体を見渡す超越的な客観性の視座と重なることになるだろう。そしてその視座からであれば、あらゆる動物たちと機械たちが制御と通信の対象になるだろう。だから、もしそのような超越的客観的な視座にもとづくなら、サイバネティクスは神秘主義と制御理論が裏表で一致する知になる。
4
こうしてみると、サイバネティクス的なるものはたんに20世紀に誕生したひとつの新しい学問というわけではなさそうだ。形式論理や客観的で普遍的な知性の探究として、それは西洋的思考の巨大な系譜に連なるものである(4)。ウィーナーがライプニッツをかかげたのは伊達ではない。そのような制御と通信の可能性の条件を考えるなら、それは、メディアアートをこれまで基礎づけてきた条件であると同時に、メディアアートが理解したり変革したり創造したりしようとしてきた条件でもあり、そしてまた、これからもそうであり続けようとしている条件でもある。だから、メディアアートは、それと向き合うことなしには、サイバネティクス的なものの重力にとらわれてしまい、そこから飛び出すような芸術的に新しい宇宙をつくりだすことは困難である。もちろんこの困難は、それだけメディアアートがこのサイバネティクス的なものの重力と近いところで試みられている探究であるということの証にほかならない。それは生きていて運動するものだから、無矛盾で完璧でそれゆえに永遠不変で静止してもいるような論理だけではとらえられない。しかし、かといって何の論理もなければ単純に混乱しているだけであり、これでもまた何もとらえられない。両者の重ね合わせの絶妙な中間、まさにメディアのアートだけが、これを観察し、飛び出す力に触れることができる。
いくつか例をあげてみよう。たとえばネットワーク型の集合的創造は、創造の苦労を消費者のフリーな生産消費活動への参加にアウトソーシングすれば自動的に達成されるようなお手軽なものではない。そこには、およそ創造と呼ぶにふさわしい活動につきものの不思議で慄然とする矛盾が潜んでいるものである。それは、自由と拘束の共立である。自由でありかつ拘束されてもいるという矛盾、あるいは自由と拘束が重なる中間は、文字通り中間の芸術としてのメディアアートにとって主題となるにふさわしい問題であり、実際この問いに取り組んできた芸術家たちは少なくない。たとえば、ステラークの数々のパフォーマンス(5)、マシュー・バーニーの「拘束のドローイング」(6)、アーサー・エルセナーの「artifacial」(7)、三輪眞弘の「逆シミュレーション音楽」(8)、それから西垣通の「HACS」と「N-LUC」による集合知の探究(9)や、エリン・マニングとブライアン・マッスミらの「能力をあたえる拘束」による集合的表現の実験的な研究創造(10)。あるいは、初音ミクも、たんにウェブサービス上のユーザーたちの創作や交流によって自然発生的にムーヴメントになったのではなく、伊藤博之(クリプトン・フューチャー・メディア)による規則整備や保護育成が重要な役割をはたしてきたことが知られている(11)。これらのメディアアートが教えてくれることは、集合的創造というものが、トップダウンで達成されるものでないのはもちろんのこと、たんにボトムアップだけによっても達成されえず、何らかの意味でのリーダーや中枢や拘束がその自由な創造の条件となっているということ、つまり、拘束と自由が共立するような中間において両者が同時に発現するのが集合的創造であるということである。
これは極めて微妙な線を探索する活動にならざるをえない。一歩間違えれば、集団によって徹底的に制御されることを自由だと勘違いしてしまうような状況になりかねないし、創造的環境の管理者にとっても勝手にユーザーが価値を生産すると勘違いするとせっかくの創造的環境が持続性を失うことになる。これらは先に述べた動物の機械化としてのサイバネティクスの応用と同じ誤解にもとづいている。
たとえばそれはインタラクティヴィティと呼ばれてきたものにも潜んでいる。インタラクションは一般的にはメディアアートの特徴のひとつとして理解されているが、これもまた集合的創造と同様に危うい両義性で成立しているものであり、単純なインタラクションは制御を徹底化しかねない。というのも、インタラクションとは、もしメッセージ通信的に考えるならば、何かメッセージを獲得するときに、必ずこちらのメッセージも提供する、ということだからだ。情報インフラがますますインタラクティヴになってゆくなかで、この問いもまたメディアアートにとっての主題となっている。そうなると、たとえば、インタラクション的な双方向性ではなく、あえて一方通行を再評価するという戦略での研究創造の試みが行われることにもなる(12)。より古いメディアである新聞やテレビのような一対多の一方通行の放送よりも、より新しいメディアであるインターネットのような多対多の双方向のインタラクションの方が、より民主的であったり創造的であったりするようにもみえるが、制御と通信という視座からみれば、必ずしもそうとは限らないところもある。技術革新に素朴に進歩主義的に順応するのではなく、創造的に新しいメディアの可能性を探究することもまた、ひとつのメディアアートである。それは、ときに既存のネットワークをハッキングすることもあるだろうし、あるいはさまざまな理由で絶滅したメディア技術を復刻して、それらがもし生き延びていたらいまどうなっているかをシミュレーションしてみることもあるだろう(13)。
(4)西垣通『ペシミスティック・サイボーグ』青土社、1994年。
(6)http://www.drawingrestraint.net
(8)http://www.iamas.ac.jp/~mmiwa/rsm.html、三輪眞弘『三輪眞弘音楽藝術:全思考一九九八−二〇一〇』アルテスパブリッシング、2010年。
(9)西垣通『集合知とは何か』中央公論新社、2013年。西垣通『ネット社会の「正義」とは何か:集合知と新しい民主主義』角川学芸出版、2015年。西川アサキ『魂と身体:計算機とドゥルーズで考える心身問題』講談社、2011年。西川アサキ『魂のレイヤー:社会システムから心身問題へ』青土社、2014年。
(10)http://www.inflexions.org. Erin Manning and Brian Massumi, Thought in the Act : Passages in the Ecology of Experience, University of Minnesota Press, 2014.
(11)柴那典『初音ミクはなぜ世界を変えたのか?』太田出版、2014年。上記の集合知論と、ドミニク・チェン『フリーカルチャーをつくるためのガイドブック:クリエイティブ・コモンズによる創造の循環』フィルムアート社、2012年も参照。
(12)Alexander R. Galloway, "Networks," in W.J.T Mitchell and Mark Hansen eds., Ctitical Terms for Media Studies, Chicago University Press, 2010, pp. 280-296.
(13)たとえばhttp://pamal.org
5
ところでサイバネティクスがこれまでたんに超越的客観主義的に普遍論理を追求してきただけかというと、そうではない。たとえば、サイバネティクスにおける制御は何が何を制御するのかという、視座のことをもっとよく考えてみると、それは客観的に対象を制御することだけを目指していたのではなく、主観的に自らを制御することを目指していた側面もあることがわかる。観察者の問題、つまり主観と客観の矛盾した重ね合わせの緊張が、そもそもサイバネティクスには潜在していた。
「われわれの状況に関する二つの変量があるものとして、その一方はわれわれには制御できないもの、他の一方はわれわれに調節できるものであるとしましょう。そのとき制御できない変量の過去から現在にいたるまでの値にもとづいて、調節できる変量の値を適当に定め、われわれに最もつごうのよい状況をもたらせたいという望みがもたれます。それを達成する方法がCyberneticsにほかならないのです。」(14)
サイバネティクスが制御するのは、他者ではなく自己である。サイバネティクスが、どの視座から、何を観察記述しているのか。これをうやむやにしてしまうと、先に述べた罠にはまることになる。だからサイバネティクスにとって視座が重要なのである。実際、1970年代頃になると、ハインツ・フォン・フェルスターやウンベルト・マトゥラーナやフランシスコ・ヴァレラらによって、観察者の観察記述という自己準拠性・自己産出性を問題にすることでサイバネティクスを発展させる新しいサイバネティクス(セカンドオーダー・サイバネティクスやオートポイエーシス)がうまれることになる(15)。この新しいサイバネティクスは、サイバネティクスを時代遅れにして乗り越えることを目指してきたというよりは、サイバネティクスのポテンシャルが単純な制御と通信におちいらないようにするために、むしろそのポテンシャルを観察問題という視座からすくいあげることでより増強することを目指してきたと言える。この新しいサイバネティクスは現在でもネオサイバネティクスとして探究が続けられている(16)。
(14)ウィーナー『サイバネティックス』5頁。
(15)Heinz von Foerster, Understanding Understanding : Essays on Cybernetics and Cognition, Springer, 2003、ウンベルト・マトゥラーナ+フランシスコ・ヴァレラ『オートポイエーシス:生命システムとはなにか』河本英夫訳、国文社、1991年。
(16)たとえば、Bruce Clarke and Mark B. N. Hansen eds., Emergence and Embodiment : New Essays on Second-Order Systems Theory, Duke University Press, 2009、『思想』2010年第7号(第1035号)特集「ネオ・サイバネティクスと21世紀の知」岩波書店、西垣通、河島茂生、西川アサキ、大井奈美編著『基礎情報学のヴァイアビリティ:ネオ・サイバネティクスによる開放系と閉鎖系の架橋』東京大学出版会、2014年。
(原島大輔)











