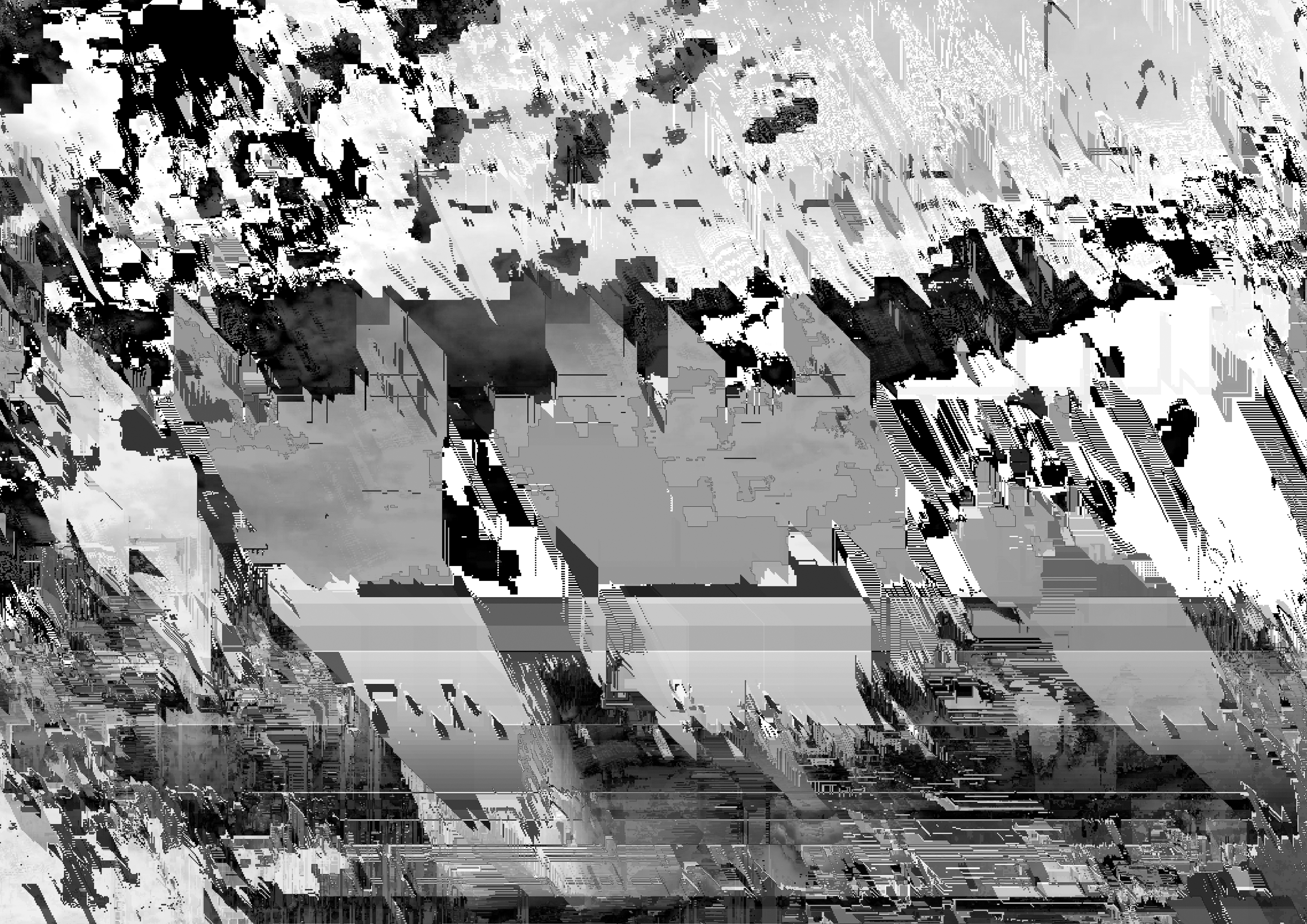
「メディアアートへの視座」と題したこの連載では、メディアアートに関連するキーワードをひとつ取り上げて、その学術的な背景を概説していきます。そのことによってメディアアートをより深く楽しみ、考えるための視座を提示することを目的としています。
6
サイバネティクスからメディアアートをみるとき、無矛盾な形式的機械と矛盾した直観的身体の、あるいはデジタルなものとアナログなものの、どちらが優位かとか、どちらが本来的かとか、そういう両者を単純に対立させることは問題ではない。本来的ということでいえば、どちらも本来的なのであり、だから本来的という観念はここでは適切ではない。ましてや、機械的なものは非人間的であり身体的なものは人間的であるといったような図式化は、たとえそれが、人間的なもののうちにも非人間的なものがつねにすでに条件としてあるということを表現するために持ち出されるのだとしても、的外れなものになってしまいかねない。なぜなら、形式的で機械的なものもまた、まぎれもなく人間的なものだからだ。これは非人間的なものという概念の企てそのものを否定しているわけではない。生態学における脱人間中心主義的な思考や、超領域的学問の試みにおけるポスト人文学的な思考のなかで、非人間的なものという概念をつくりだし、つかってみることはありえるだろう。ただし、メディアアートへの視座としては、非人間的という概念には注意が必要である。人間的なるものと機械的なるものを区別するような図式は、ポストヒューマンやトランスヒューマンといった理想とすぐに結びつく。たとえば、形式論理的な知性は人間的な知性ではなく機械的な知性に属するものであると区別してしまうことは、人間的なものにすでに備わっているはずの形式論理的なものへの傾向を人間的なものから奪い去り、それをポストヒューマンやトランスヒューマンに割り当てる。別の言い方をすれば、これは格差の拡大と見分けがつかない。
そうではない中間的な理解であれば、人間的なものと非人間的なものとの二元論で考えるとき、人間は、もう人間的なものでも非人間的なものでもなくなり、人間的かつ非人間的な中間的な何かになるだろう。なぜここでこんなことを言っているか。それは、まさにこの中間的なものこそ、サイバネティクスが目指しえたはずのメディアにほかならないからである。『サイバネティクス』がその副題に「動物と機械における制御と通信[control and communication in the animal and the machine]」を掲げたとき、それは実際のところ何を言っていたのだろうか。それは、たとえウィーナー自身があたかも動物も機械も統計力学で形式論理的に制御できるかのように記述していたとしても、そういうことではなくて、動物も機械もまだ謎のままにとどまり続けている何か両義的なものを潜ませている中間つまりメディアのアートにほかならないということではなかっただろうか。だから「制御と通信のなかの動物と機械」ではなく「動物と機械のなかの制御と通信」なのである。
7
サイバネティクス以後の超領域的な科学技術や研究芸術ないしメディアアートは、これからますます、制御と通信のなかの動物と機械ではなく、動物と機械のなかの制御と通信を探究し創造してゆくだろう。動物や機械を制御と通信のなかに外部から抑圧しようとしたり、逆に動物や機械がそのような制御と通信を内部から超越しようとしたりする試みは、サイバネティクス的パラダイムではきっと成功しない。サイバネティクスはそれらの試みとは相性がよくないからだ。サイバネティクス的な探究や創造は、支配や超越には効果がない。物資や人材を効率的に利用するための予測には向いていない。規則や制度を経済的に絶滅するための投機にも向いていない。そういうものに役に立つようにはできていない。確率と統計にもとづく動物と機械の制御と通信は必然的に偶然的であり失敗するのである(そのような確率と統計が有効な問題もあるということを否定しているわけではない。これらの方法が向かない領域もあるということだ。それは『サイバネティクス』においてウィーナー自身が注意を促していたことである)。
だから、目的論的に役に立つかどうかが第一原理であるような環境においては、もしかするとこう思われるかもしれない。このような必然的に偶然的で失敗する不完全な技術知が、何の役に立つのだろうか。どうしてこのようなサイバネティクス的なるものがいまだに探究され、それどころかますます現代の効率的で普遍的な制御の条件たる情報科学技術的なインフラとして状況のなかに浸透し続けてきているのだろうか。さらにそのうえ、いまだにメディアアートを理解するためのキーワードとしてとりあげられさえするのは、どうしてだろうか。まだサイバネティクスがメディアアートにおいて果たすべき役割があるというのだろうか。まだサイバネティクスが潜在的に格闘し続けている謎があるというのだろうか。その答えとして、わたしにはいまこのひとつくらいしか思いつかない。共感。
8
つまるところ、新しいサイバネティクス(セカンドオーダー・サイバネティクス、オートポイエーシス、ラディカル構成主義、基礎情報学、ネオサイバネティクスなど(1))は、サイバネティクスにおけるこの《共感》という謎を問いにしたと言える(新しいサイバネティクスの術語としてはたとえば構造的カップリングと呼ばれている)。コミュニケーションというのは謎だ。とくに、動物たちのコミュニケーションは電子回路の部品たちがメッセージを入出力し送受信するようにしては働いていないのではないかという疑いが、新しいサイバネティクスには共有されている。動物の観察行為すなわち認知のプロセスは、外部に実在する存在を多かれ少なかれ歪曲された写像として内部に反映させる表象ではなく、攪乱が生じた内部の状態の変動を自己調節しながら整合的な世界観を産出する構成である、という考え方だ。つまり、知るということを、外部を参照するのではなく内部を参照する、作動的に閉鎖した再帰的な自己産出のプロセスとして考えるのだ。たとえば、新しいサイバネティクスの代表的な理論のひとつであるオートポイエーシスは、動物の視覚研究のある実験をきっかけにして発想されたそうだが、それは、動物の視覚神経系のふるまいが外部からの入力に相関しているようにはみえないという、表象主義的モデルとは両立しがたい実験結果を説明するためのひとつの解釈として、視覚システムの自己産出的な作動的閉鎖性が理論化されたのだった。認知のプロセスがあくまで自己産出的に閉じた円環を描くなら、そこには電子回路のようにはメッセージの入出力や送受信は起こりえない。言い換えればそれは、通信工学的な制御とは異なる、新しいサイバネティクス的なコミュニケーションの条件である。
ここで、どうしてそもそもサイバネティクスが「制御と通信[control and communication]」の二つの語を副題としたのかについて、こんな意味づけをしてみたくなる。すなわち、制御だけでも通信だけでもなく「制御と通信」なのは、両者が異なる領域におけるプロセスだからであり、そしてその一方だけでなく両方ともがサイバネティクスには必要だったのである。二つの矛盾するものの重ね合わせがすでにここに潜在していた。つまり、認知的に閉じたプロセスのシステムが、どのようにして他者や環境とコミュニケーションできているかのようであるのか(もし、コミュニケーションできるためにはシステムが他者や環境に対して開かれていなければならないと考えるなら、閉鎖システムは原理的にコミュニケーション不可能ということになるはずなのに)、ということが、新しいサイバネティクスにとって重要な問いのひとつとなる。
共感は、いまだ謎であり、問いになる。それは新しいサイバネティクスにおける問いであるだけでなく、メディアアートにおける問いであってもよい。そして実際、現代の科学技術や研究創造にはこの共感の領域で探究と創作を進めているものがある(2)。それはまた、たとえば身体や情動の領域として探究されているものでもあるだろう(3)。サイバネティクスからみれば、身体や情動といったややもすると単純に神秘化されがちな力の場を、対象を制御する方法としてではなく、自己産出的な共感としてつくりだしていくことは、メディアアートのひとつの課題であるにちがいない。
(1)たとえば、Heinz von Foerster, Understanding Understanding : Essays on Cybernetics and Cognition, Springer, 2003、ウンベルト・マトゥラーナ+フランシスコ・ヴァレラ『オートポイエーシス:生命システムとはなにか』河本英夫訳、国文社、1991年、エルンスト・フォン・グレーザーズフェルド『ラディカル構成主義』西垣通監修・橋本渉訳、NTT出版、2010年、西垣通、河島茂生、西川アサキ、大井奈美編著『基礎情報学のヴァイアビリティ:ネオ・サイバネティクスによる開放系と閉鎖系の架橋』東京大学出版会、2014年、Bruce Clarke and Mark B. N. Hansen eds., Emergence and Embodiment : New Essays on Second-Order Systems Theory, Duke University Press, 2009.
(2)たとえば、アレックス(サンディ)・ペントランド『正直シグナル』柴田裕之訳、みすず書房、2013 年、渡邊淳司『情報を生み出す触覚の知性:情報社会をいきるための感覚のリテラシー』化学同人、2014年、Chris Salter, Alien Agency : Experimental Encounters with Art in the Making, The MIT Press, 2015.
(3)Brian Massumi, Politics of Affect, Polity, 2015.
9
サイバネティクスからメディアアートへの視座のひとつは、心窩で鑑賞することだ。もちろん大脳を働かせて鑑賞することを否定しているわけではなくて、それはそれでよい。ただ、胸の内での鑑賞についても意識できるようになってよい。ひとはここでもまたものを考えているのだから。おそるべき素敵なアートと出逢うとき、みぞおちのあたりから胸の真ん中あたりがじんわりしてくるのを感じないだろうか? どうしようもないアートと出逢うとき、みぞおちのあたりから胸の真ん中あたりがむかむかしてくるのを感じないだろうか? もしそれらを感じたら、いったい何が起こっているのかをよく観察し記述してみること。生物は脳以外でも思考していることはおそらく間違いない。ただ、それに気づいておしまいではしかたがない。それでは身体的なるものを神秘的なものに物象化するだけだ。ここでサイバネティクスとメディアアートの出番である。胸のなかで何が起こっているのか。このなかで通信と制御はどうなっているのか。それをよく探究してみること。みぞおち。胸の内。胸の真ん中の中間のメディアアート。それがサイバネティクスからメディアアートへの視座のひとつである。
10
サイバネティクスからメディアアートをみることへの誘いとは、運命の出逢いへの誘惑である。そういう、おどろくべき、おそるべき、強烈な身震い。中間の瞬間。その瞬く間に世界が色づいて、もうこれまでとは全く違って見える、何かに触れてしまった瞬間。人間も、動物も、機械も、すべてが生き生きと輝いて見える。そんな不思議で特異な感動こそが、メディアアートと呼ばれるにふさわしい。サイバネティクスの視座からみたメディアアートとはこの特異性を知覚するセンサーのことである。
そうして触発されてつくること。ただし、同じものをつくるのではなく、出逢いの感動と同じ力の感動をつくりだすこと。恋する作品にそっと捧げるささやかなお供え物のようにつくりだすこと。それだけの作品と出逢えば自然とそうなる。同じものをつくるのではなく、同じ力の感動をつくるのだから、たとえば音楽に感動してアニメをつくったっていいし、アニメに感動してインスタレーションをつくったっていいし、インスタレーションに感動して哲学をつくったっていいし、哲学に感動してゲームをつくったっていい。既存のカテゴリーは問題ではなくて、重要なのはそれらのカテゴリーを超えて計測される新しいカテゴリーの感動の質と量を発明することである。きっと無数にあるそのような新しいカテゴリーをつくりだしていく、ひとつひとつの視座こそ、ここでいうメディアアートへの視座である。たとえば、この作品とあの作品はジャンルは全然違うけれど何か同じような感動があると感じたら、それがあなたにとって重要であり、それが新しいカテゴリーを発明する手掛りである。それらはきっとまだ発明されていないカテゴリーでみたら、同じ質と同じ量をしているに違いない。その謎の質と量を計測できるカテゴリーをつくりだすこと。それをひとつつくりあげることができたときにはじめて、新しい視座がうまれる。それはまずはあなただけの視座である。自らを自らのやり方で制御する新しいルールをつくりだすこと、そうしてはじめて通信の、共感の、可能性の条件もまたうまれる。
11
古典的なサイバネティクスはある罠に掛かっていたため、その思想が容易に真逆に理解され応用されてしまうポテンシャルを抱えていた。それは、情報的な意味での閉鎖系(自己産出的で自律的なシステム)と開放系(他者産出的で他律的なシステム)の区別を設けなかったことによる。この区別は物質的な意味での閉鎖系(熱力学的な平衡に向かう孤立系)と開放系(新陳代謝や自己組織化をする非平衡系)の区別とはまた違うものであり、したがってこの情報的システム観と物質的システム観の区別もまた重要である。これらの区別を設けたのが新しいサイバネティクスだった。もし情報的な開放系として理解されたなら、人間だろうが動物だろうが機械だろうが何だろうが、外部から与えられた規則にのみ従って作動する情報処理メカニズムとしてすべて客観的に理解しきることができるだろう。このような客観主義的な開放系論においては、いかなるシステムにも主観性のようなものが潜む場はないことになる。つまり、主観性は存在しないということになる。あなたが主観性をもたないと確信しているなら、このような開放系理論でもよいだろう。ところがわたしには主観性がある。この主観性を、この開放系理論は説明してくれないし、それどころかこの理論にもとづいて構築されたメディア環境は、わたしのこの主観性を抑圧してくる(なぜなら、そういうメディア環境においては主観性などあってはならないからだ)。主観性にとってこれは困る。そして幸いなことにここに困難を見いだしたのはわたしだけではなかったようだ。情報的な開放系ではなく閉鎖系としてサイバネティクスを理解し発展させてきたひとたちがいるのである。それが新しいサイバネティクスである。新しいサイバネティクスは情報的閉鎖系のシステム理論であり、情報的開放系のシステム理論とは決定的に異なる。そうすることで、新しいサイバネティクスは、サイバネティクスを更新したりサイバネティクスと訣別したりするというよりは、サイバネティクスのポテンシャルを増強する。サイバネティクスは、何らかの対象を客観的に制御する理論ではなくて、何らかの変動のただなかで自らを自らのやり方で制御する理論ではなかったか。そしてそのときに、いかにして人間機械(ポストヒューマン、トランスヒューマン)をつくりだすことで問題を乗り越えていくかではなく、いかにしてメディア技術の力をかりることで問題をつくりかえていくことができるかを探究する学問ではなかったか。そうすると、自らが自らを制御するサイバネティクスにとっては、主観性あるいはシステムの作動プロセスを、外から観察するのではなく、内から観察することが重要であるということになるだろう。
こうして新しいサイバネティクス的なメディアアートは、この主観性がどのように産出され、また望むならどのように変化してゆくことができるのか、という主観性の問題に取り組むメディアアートになる。たとえば、かつてフェリックス・ガタリは、主観性の生産とポストメディアというキーワードで、そのような新しいサイバネティクス的なメディアアートの活動に従事し参加を呼びかけた(4)。それは、視聴者や消費者としてメッセージを受信して処理するためのメディアではなく、自らのやり方で身の回りのもので自分なりに自分の条件をつくりかえ新たにつくりだしていくためのメディアアートである。インターネットもなければウェブ2.0のような概念もなかったが、当時はたとえばラジオがそのようなポテンシャルをもつメディアとして活動的な芸術家たちによって実験的に利用されていた。その点では、手紙やヴィデオもまたそのようなメディアとして実験されてきたメディアアートの歴史を忘れるわけにはいかないだろう。
かくして、サイバネティクスからのメディアアートへの視座は、実践的なものになる。あなたがメディアアートをすることへの呼びかけになる。あなたの日々の生活をメディアアートにすること。そのような実践的な活動が、サイバネティクス的メディアアートである。そしてそのようなメディアアートをはじめるのに十分な技術を、あなたはすでに持っている(5)。そしてそのようなメディアアートをはじめるのに十分な誘惑を、あなたはすでに知っている。
(4)フェリックス・ガタリ、粉川哲夫、杉浦昌昭『政治から記号まで:思想の発生現場から』インパクト出版会、2000年。フェリックス・ガタリ『三つのエコロジー』杉浦昌昭訳、平凡社2008年。
(5)河合政之、宇野邦一「欲望のアナログな流れ」宇野邦一編『ドゥルーズ・知覚・イメージ:映像生態学の生成』せりか書房、2015年。
12
メディアアートとは中間の芸術である。サイバネティクスのパラダイムの科学技術は潜在的に中間的である。この中間性を知覚し創造する感性的経験が、サイバネティクスからメディアアートへのひとつの視座である。そういうメディアアートの鑑賞や創作は、大脳だけでなく、心窩もまた必要とするだろう。どちらか一方だけではない。両方。感じずに考えるのでも、考えずに感じるのでもなく、感じかつ考えること。この二つが中間で重なるプロセスに、共感が生まれ、それはまるで恋に落ちるような強烈な触発となって自らつくりだすことを可能にしてくれる。このような中間性がサイバネティクスからのメディアアートへのひとつの視座である。《メディアアートとは中間の芸術である》。











