マンガ雑誌が活況を呈していた1985〜95年を知る編集者の証言をもとに、マンガの出版市場で何が起きているのかを探る連載の第2回。前回に引き続き、『週刊少年チャンピオン』の元編集長、神永悦也(かみなが・えつや)に、マンガ雑誌編集の舞台裏を語ってもらった。
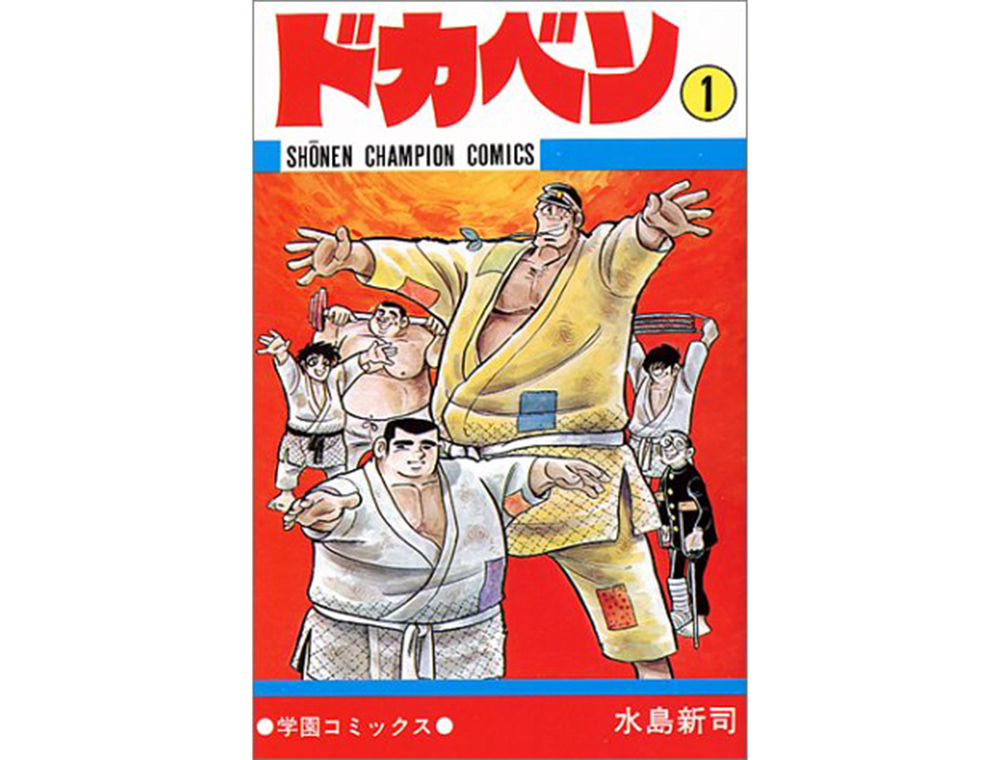 水島新司『ドカベン』第1巻(1972、秋田書店)
水島新司『ドカベン』第1巻(1972、秋田書店)
菊地秀行の伝奇ロマンをマンガに
苦しい時代ではあっても記憶に残る作品はしっかり出ていた。
80年代後半の「週刊少年チャンピオン」連載陣の中で記憶に残るのは菊地秀行・原作の「魔界都市シリーズ」のコミカライズだった。
菊地秀行は1982年に朝日ソノラマ(現・朝日新聞出版)から『魔界都市〈新宿〉』を発表してデビュー。バイオレンスとエロスを描く伝奇ロマン小説の旗手として、同世代の夢枕獏とともに注目を集めていた。
「ちょうど伝奇ロマン小説がブームだったんです。菊地さんに頼みにいったのはぼくです。もともとSF方面は好きなんです。『プリンセス』(月刊プリンセス)でも、『アメリカン・パイ』(1976)のあとで一度、SF作家の原作で萩尾望都さんにSF長編を連載してもらおうと交渉したことがありました。萩尾さんが光瀬龍さんの小説『百億の昼と千億の夜』をやりたいとおっしゃったので、光瀬さんに紹介して準備を進めていたのですが、ギリギリになって、『チャンピオン』(週刊少年チャンピオン)での連載(1965〜66)が決まってしまった。同じ秋田書店内でマンガ家の先生や作品を取り合うのも変な話ですし、萩尾さんが少年誌で描きたがっていることもわかっていましたから、こちらが引いた形になったんです。萩尾さんにはそのあとで、『プリンセス』に、SF短編の『A-A'』(1981)と『モザイク・ラセン』(1982)を描いてもらっています。菊地さんの小説もデビューした頃から読んでいて、おもしろいと思っていました。ただ、少年誌の場合、バイオレンスはいいけどエロスはまずいのでそのへんは薄めて……。マンガ家の細馬信一さんは、エロ劇画誌で描いていた人なんですけど、絵柄がぴったりなのでお願いしました。菊地さんと組んで『黙示録戦士』(1985)という作品を6回だけ連載してもらって、評判が良かったので『魔界都市ハンター』(1986〜89)の連載が始まったはずです。ただ、そのとき、ぼくはもう少女誌に戻っているんですよ。夢枕獏さんの『キマイラ・吼』(1982〜)も交渉したけど、OKしてもらえませんでした。あの作品も少年誌向きなんですけどね」
編集は試行錯誤の連続
1985年の春。壁村耐三が「週刊少年チャンピオン」編集長に復帰する。再登板となった壁村は「少年マンガの王道への回帰」を掲げ、内容の刷新を進め、硬派の学園モノに力を入れていく。その中から立原あゆみの少年極道マンガ『本気!』や、みやたけしの熱血サッカーマンガ『風のフィールド』(1986〜89)、七三太朗(なみ・たろう)・原作、川三番地(かわ・さんばんち)・作画の野球マンガ『4P田中くん』(1986〜1996)などが人気作品になっていく。しかし、多くの新連載が短命に終わっているのもこの時代だった。
89年の途中で壁村編集長は退任して、後任には『ブラック・ジャック』などを担当した岡本三司が就任。しばらく苦闘時代は続く。
「編集者は試行錯誤の連続なんです。創刊誌なら短いながらも準備期間があって、マンガ家の先生たちとも打ち合わせを重ねることができるし、読者の求めているものをリサーチすることもできます。ところが、週刊誌をテコ入れするのは、毎週やってくる打ち合わせや締切、入稿、校正といった仕事をこなしながらですから、とにかくいいと思ったことはやってみてダメならやり直す、という手法しかないのです。よそはグラビアが人気らしいと聞けば、“うちも”ということだし、藤子不二雄Ⓐさんの『プロゴルファー猿』(1974〜80)のアニメが好調と聞けば“ゴルフマンガをやってみるか”ということになる。そういうことを地道に繰り返しているうちに、柱になる作品が生まれてくる。これしか方法がないと思います。結果として、91年に板垣恵介さんの『グラップラー刃牙』(1991〜99)、93年に浜岡賢次さんの『浦安鉄筋家族』(1993〜2002)が登場してやっと一息つけたわけです。もうこのころ壁村さんの体調はそうとう悪くて、入退院を繰り返すようになっていたんですけど……」
1990年に64万部まで落ち込んでいた推定発行部数(全国出版協会・出版科学研究所『出版指標年報』による)は95年には70万部に回復。山口貴由の近未来格闘技マンガ『覚悟のススメ』(1994〜96)や、やまさき拓味の競馬マンガ『優駿の門』(1995〜2000)、高橋葉介の学園ホラー『学校怪談』(1995〜2000)など新たな人気作も生まれてきた。さらに、95年には『ドカベン プロ野球編』(1995〜2004)がスタート。誌面はさらに活気付いた。
マンガ雑誌衰退の原因とは?
残念ながら、97年からは推定発行部数(同)は減少に転じて、回復の気配はないまま現在に至っている。マンガ雑誌に起死回生のチャンスは残っているのだろうか?
「これはあくまでも一般論ですけど、マンガ編集者もマンガ家も読者もマニアックといえば語弊があるかもしれませんが、マンガに対して真面目になりすぎた。これがマンガ雑誌が売れなくなったひとつの原因ではないかと考えているんです。ご存知だと思いますが、水島さんの『ドカベン』はもともと柔道マンガでした。水島さんは野球以外のスポーツものを描きたいという気持ちがあって、初代の編集長の成田清美さんの時代に柔道マンガの『ドカベン』を始めたんです。ところが、次の編集長の壁村さんが途中で“先生、やっぱり野球でいきませんか。そっちの方がお詳しいのだし”と相談して、野球マンガにしてもらったんです。山田太郎とバッテリーを組むピッチャー里中を登場させて山田を野球に目覚めさせたのは水島先生のヒットです。野球にしたとたんにドカンと人気が出ました。秋田書店で四六判ハードカバーの豪華本で『ドカベン』を出した時には、柔道の部分はカットしちゃったんです。つまり、雑誌の連載マンガはそういうものだったんですよ。そこにおもしろみがあって、読者は毎週楽しみに買ってくれていたんだと思います。ところが、だんだんそういうおおらかさがなくなって、編集者もマンガ家も伏線とかつじつま合わせに気を遣うようになってしまったんです」
たしかに世界観の統一や伏線の回収といったことはマンガの世界でも当たり前のように言われるようになっている。矛盾点を発見して「これはこういう裏の意味がある」という評論記事なども多く見かける。『ドカベン』の柔道編にもネットなどでは「本編に進むための壮大なプロローグ」という分析があるようだ。世界観や伏線を気にするあまり、ストーリー展開は遅くなってしまう。読者は雑誌で読むよりも単行本が出るのを待ってまとめて読んだほうがいいと考える。たしかに雑誌衰退の一因ではあるようだ。
ベテランを超える新人はどこに
もうひとつ気になるのは、2000年代になって各雑誌を引っ張るような新連載がほとんど生まれていないということだ。「週刊少年ジャンプ」ですら、尾田栄一郎の『ONE PIECE』が1997年。岸本斉史(まさし)の『NARUTO』(註1)が1999年。「週刊少年マガジン」では森川ジョージの『はじめの一歩』が1988年から続いている。「週刊少年チャンピオン」も91年代に発行部数回復に貢献した「刃牙」シリーズと『浦安鉄筋家族』が柱のままだ。これらのマンガ家を超えるような新人が出てこないことが、マンガ雑誌の活力を衰えさせているのだとしたら。
「新しい描き手を育てることはたしかに大切です。かつて、“ベテラン・マンガ家の再生工場”と呼ばれていた『チャンピオン』はそこが手薄だったんじゃないでしょうか。ベテランの再生がうまくいった結果、新人の育成ができていなかった。そのツケが80年代に出てきた可能性はあります。新人を育てるためには描く場を与えることも大切なんです。新人マンガ家で印象に残っているのは、あしべゆうほさんです。あしべさんの『悪魔(デイモス)の花嫁』(1975〜シリーズ継続中)は、『プリンセス』の創刊から描いてもらって、最初は読み切りでしたが、読者アンケートで5位以内と好評でした。以来、いまに至る人気連載になっています。あしべさんは秋田書店で最初に専属契約を結んだ作家でした。ぼくが“他のマンガ雑誌もやっているんです”と社長を説得しました。筆が早くない作家さんは、寡作になるので続けて雑誌に描いてもらうためには専属にしないといけない、と考えたのです。当時、1年間の契約でしたけれど、他では描かないでとお願いすることになりました」
現状では大手・中堅の出版社は新人の活躍の場をウェブマガジンに移している。雑誌は安定したベテラン中心のラインナップになりがちだ。一方で、若いマンガ家からは「ウェブでは食えない」という声も聞かれる。こうした課題を克服できればマンガ雑誌は復活できるのだろうか。
「ぼくは定年退職して時間も経っているから、今のマンガに関してとやかく言う立場にはないけど、少年マンガでも少女マンガでも、マンガらしいマンガが生まれるのが一番いいことではないかと思いますね」
(脚注)
*1
本編は2014年に完結したが、『NARUTO』の主人公の息子・ボルトの世代を描いた『BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS-』が、岸本斉史による原作・監修で2016年より連載中。
神永悦也(かみなが・えつや)
1943年生まれ。東京経済大学卒業後、1966年に秋田書店に入社。「少年チャンピオン」「月刊プリンセス」「ひとみ」に創刊時から携わり、1983〜85年に「週刊少年チャンピオン」編集長を務める。2011年退社。
| ◀ 第1回 | 第3回 ▶ |











