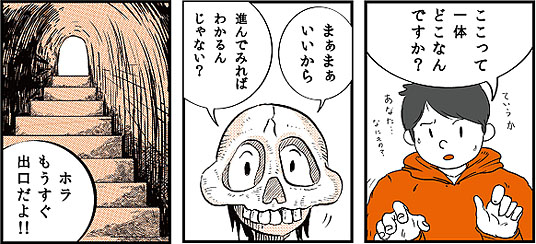
イベント概要
開催日:2011年1月10日(月・祝)14:00 〜 17:00 (13:30 開場)
会場:京都国際マンガミュージアム 多目的映像ホール
スピーカー:島本浣 藤幡正樹 吉岡洋 吉見俊哉
メディア芸術という言葉の侵入
もう一昨年になってしまいましたが、文化庁が主導しての「国立メディア芸術総合センター(仮称)」構想といった大規模なプロジェクトがありました。そのときは「えっ、メディア芸術って?」というのが一般的な反応だったかと思います。もともと、カテゴリーとしてメディア芸術というものが意識されたのは、もう14年前でしたでしょうか。 知らない人もいるかもしれませんが、文化庁メディア芸術祭というイベントがあり、東京の展覧会では12日で約6万人を動員する大きなイベントになっているらしいのです。そういったこともあり、何となく「メディア芸術」という言葉が頭の中に少しずつ侵入してきていることは、間違いないと思っています。
ただし、メディア芸術という言葉というか、文化庁メディア芸術祭ということもそうなのですが、このメディア芸術という枠、カテゴリーというのが何なのかということが、あまり議論されないままに、ここまでやってきてしまっているように思っています。とりたてて、ここでカテゴリー論みたいなものをやろうというわけではありませんが、「メディア芸術って何なのだろう?」というテーマで考える機会があっても良いのではないかということで、去年2010年の11月から少しずつ、メディア芸術という言葉でみんなどのようなことを思い、考えている人はどういうことを考え、つくっている人はどういうことを考えているのか話を聞く場をつくってきました。話を聞きながら、こちらサイドとしても、メディア芸術ということについて、もう少しだけクリアな、とりわけ外の世界、つまり一般社会に対してクリアに説明をしていきたいと考えています。
すでにオープントークを2回開催し、今回が3回目になるわけです。メディア芸術と言われるものの中には、マンガ、アニメ、ゲーム、それからメディアアートの4分野がありますが、本当にこんなことだけで良いのかという議論があるわけです。沖縄で開催された2回目のオープントークでも出ているし、東京で開催された1回目にも出たような話です。最近の状況として、メディア自体が従来考えられていたメディアのカテゴリーを横断的に超えつつあるだけでなく、メディアそのものが作り手や受け手である人間の中で重層的に入り込んでいるという新しい状況が芸術の中で起こってきています。もう一度、こういった問題を考えるために、言葉の問題だけではなくて、それ以上にこれが意味しようとしていることを議論していくのが良いだろうと考えています。
僕は東京藝術大学にいて、ご存知の方はアーティストという立場で僕のことを見ていらっしゃるかもしれません。ただ、僕の問題意識は、やはり日本の文化的状況があまりにも海外のアートの受容のスタイルとかけ離れていて、そのことによって、僕が考えていることを他人に説明しようとするときに、非常に長い道のりを経て説明しなければならない状況があります。実際にいくら説明してもわかってもらえない、「何がおもしろいのか?」といった反応しか結局は得られないようなことがよくあります。
その根源をずっとたどっていってみると、実はメディア芸術という言葉が混乱を起こしていることとかなり同根な部分があり、ここを解かないと、やはり西欧が中心になっている芸術概念というものを、いつまでたっても日本は受け入れられない。こうした状況の中で、今また新たに「芸術」ということばについて議論しなくてはならなくなっているというのは、明らかに外圧です。これまで僕たちがマンガやアニメーションを読みながら楽しんでいるものが、海外でも受け入れられた。しかし、この根源が何かということがわからない。今、僕らに突きつけられているのは、猛烈な外圧ですね。海外からいっぱい人が来て、「何なんだ? 説明しろ」と言われて、我々自身が説明できなくなっているという状況です。
そして、これは昨日沖縄で開催した第2回メディア芸術オープントークでの発見だったのですが、これまで僕が嫌ってきた工芸や芸能、丁寧に何かをつくるとか、遊び心とか、型にはめるとか、何かそういったものの中に、日本独自の優れた文化芸術のポイントがあるんじゃないか。だとすれば、その部分をきちんと突き詰めておかないと、僕自身も完璧に浮いたまま行き場がなくなるということを思っています。
「新しい芸術」という意味での「メディア芸術」
メディア芸術振興における文化庁の取り組みをグローバルなところから比較検討する上で、もし他の国との政策の違いなどがあれば、前提として教えていただきたいと思います。
例えば韓国は、今、アニメーション、マンガをものすごく支援推進しています。韓国の場合には国が小さいので非常に危機感を持っていて、韓流映画のときもそうなのですが、韓国の映画産業がつぶれそうになったときに、映画業界に従事する人たちが大きな反対運動をやって、それで映画学校ができたりするのです。ところが、それで復活した韓流映画が再び寂れてくると、今度は映画関係の助成金がガクンと減るとかですね。かなり激しい変化をするけれども、つけるときには徹底的に盛り込むということを、僕の知っている範囲ですが韓国はやっていると思います。そして、それは直接国が絡んでやっています。
ヨーロッパの場合、国によってちょっとずつ違うのですけれども、NPOのような活動で、草の根的に出てきた人たちが、あるレベルまでいったときに助成金を出すというようなことが行われている国もあります。アバンギャルドなコンテンポラリー・アートをずっとサポートしてきたNPOのギャラリーが、3年間継続すると経費の半分を国や地域の行政が出してくれるという形で助成しているところもあります。ただ、「文化庁メディア芸術祭」のように奨励、要するに賞金をあげたりするというのは、ケースとしてあまり多くないのではないかと思います。結局、そこには特定の目的があって、判断する人が必要になってくるわけですが、今の時代には奨励のための判断をするということ自体が難しく、あまり意味がなくなりつつあると思います。
だから今、日本でもアーティスト・イン・レジデンスが流行りになっているわけですが、もともとヨーロッパの人たちが必要だと思ったのは、特定ジャンルやテーマの奨励ではなく、異文化交流しながら作品制作をしてほしいという要請がヨーロッパ連合という国を超えた交流を目指している形式の中で出てきたからなのです。そういった社会的な背景、要請があってアーティスト・イン・レジデンスという方法が有意義だというふうに考えられてきたわけです。
僕が専門とするフランスなんかで見てみると、例えば80年代後半に、ラジオ・テレビ・写真というのを「メディアアート」としてグループ化してそれを第8芸術とカテゴライズし、第7芸術は映画、というような形で公に芸術カテゴリーを整備していくわけです。そして、同時にメディアアート・インターリレーションセンターのような施設を国がつくる。そして、次には第9芸術としてバンド・デシネが定義され、今はついに第10芸術を射程に入れて議論されていく。芸術論みたいなものが堆積のように積み重なっていく構造になっているわけですね。今はゲームの世界を第10芸術と呼ぼうとして論争しているようです。
ただ、そのようなフランスのある種の機械的なナンバリングを施すような定義に対して、日本のようにメディア芸術という名前で、一括してグルーピングする、この無謀とも言える、大胆とも言える試みというのは、逆にひょっとしたら、こちらの方がこれからの時代のメディアの本質を突いているとさえ思えるような、何かそういう可能性を秘めたネタがあるという気が、僕はしています。
もちろん、可能性があるとしたらそこだと思います。要するに、フランスの例でもわかるように、芸術というものがあって、その中での類概念がきちんとあり、その中で相互のカテゴリーが種差みたいな形で含まれてヒエラルキーを構成しているわけですね。それもかなりはっきりとした形で。日本のメディア芸術と呼ばれているものというのは、そうじゃないですね。何か新しいものが出てきた。そしてそれを「メディア」という言葉を使ってカテゴライズしたがために「そもそもメディア芸術とはなんなのだ?」という話が、このオープントークで起こってきているわけです。ただ一方で、僕はあまりくそ真面目に問題化する必要はないという気もしてきたのですよ、何か無責任に聞こえるかもしれませんが(笑)。
つまり、「メディア芸術」の「メディア」というのは別に、いわゆるメディアアートの「メディア」とか、それからいわゆるデジタル・メディア、マスメディアとか、そういう意味をしっかり持っているような言葉ではなくて、とりあえず「新しい芸術」みたいなことだと思うのです。だから、内容がよくわからなくても、状況に即してそこに含まれる分野が入れ替わったりするのだと思います。
ガラパゴスが普遍性を持つ
フランスでの論争ではカバーできない部分が僕ら日本の中にはあるけれど、それは、ただ、そのカテゴリーをフランスの人々がつくったということで、私たちが問いたいのは「カテゴリーが必要か?」みたいなことですね。かつて「文化」という言葉が「新しい」ということ、あるいは「近代的」という意味で使われました。文化住宅、それから文化アルミ、文化包丁という言葉が一時期ありました。先の吉岡さんの議論はそういう意味で、「メディアを使っちゃえば、メディア包丁とか、メディア住宅みたいなことで考えれば楽勝だよね」ということですね。
文化について言えば、すごく話が複雑だと思います。まず「culture」を「文化」に訳したというところでの意味のずれがあるのだけれども、でも、そもそもの「culture」はいつ出てきたのか、これもある種、近代の発明みたいなところがあって、つまり、18世紀から19世紀にかけて、近代国民国家というのができてきたときに、その国民一人一人を、文化的な主体にする必要があったのですね。だから、国民一人一人を「文化化」するというか、「cultivate」するということが国家の役割になって、そのために、国民に人文科学といった学問や教養を身につけさせるための機関として大学をつくっていったということがあります。私たちは「教養というものを身につけなくてはいけない」という観念を、そのときから持ったのです。
でも、その「教養」という言葉がまた問題で、知識を増やして溜めることが教養じゃなくて、本来の教養は、「自分で物事を判断できる能力」ということですね。そこも日本では、ずれてしまっていると僕は思います。
そうなんです。だから、そのときの教養も、知識の総量ではなくて、これは吉岡さんの方が専門だと思うのですが、ものをちゃんと自分で考える主体になるということ、それを国民国家が必要とし、その国家と国民、あるいは個人の関係が近代においてつくられていき、それがまた大きな問題を含んでいるわけですね。現在、国家と個人の関係が大きく揺さぶられて、崩れてきているところで、でも、そもそもそういった国家と個人との関係が日本にあったのかどうかも、よくわからないようなねじれた状況が生まれつつあるわけです。
だから、その辺のところが曖昧なまま明治以来続いているわけですよね。ただ、本家のヨーロッパで、もう個人主義がくたびれてきてしまっている、個人主義に付き合ってゆくのがやりきれないというような状況もあったりするので、僕は日本で国家と個人、そして文化の関係を考え直すための良いタイミングだと思っています。
そう考えると、日本のマンガが海外で受けているひとつの理由は僕が考えるに、個人主義的な意味での人格の一貫性が無かったりするということです。例えば、ころころと言うことが変わる。果てはキャラクターのデザインも変わってしまう。八頭身の劇画調タッチが二頭身のギャグマンガ調タッチに突然変わったりする。いわばそのメタレベルにキャラクターがある。その変化の一貫性が人格を作っているような、とてもヨーロッパ的には想像できないような、全然見かけないキャラクターが出てくるようなマンガをおもしろいと思ってしまう背景にはそういうものがあるのだと思います。しかも、個人主義が確立されていない国でありながら、あんなに経済的に繁栄しているということは、明らかにミラクルに見えるわけで、そういうミステリアスな関心を背景に、日本のマンガが読まれているのではないかと思うところもあります。
今、藤幡さんの言っていたことは、例えばこういうことかなと思います。かつては日本の特殊性というふうに、日本人も思いたがっていたし、外からも見られていて、例えば、日本が戦後に奇跡の経済復興を遂げたということに関しても、「なぜだ?」と思われてきたわけです。それはひとつには、北米的な契約社会とは違って、日本の会社というのはすごく家族的なコミュニティとしての性質を濃厚に持っていたからです。会社が傾いても、社長さんが土下座して、「もう1年頑張ってくれ」みたいなことを言われたら頑張ってしまうみたいな(笑)。そういった日本の精神性のあり方、同時に日本の経済的な成功の秘密かもしれない要素について、それは日本社会が特殊だからで、世界には通用しないと思ってきたわけです。
マンガとかに関しても、やはり2、30年前は海外において確かにマニアックなファンはいたけれども、今みたいに一般的な受け入れ方というのはなかったと思います。それは日本がそういうガラパゴス的な非常に特殊な進化を遂げた社会だからこういうものがあるのだ、と日本人も外国人の多くも思ってきたわけです。
ところが、今は日本がガラパゴスだと言われつつも、グローバリズムと情報化が進展するにつれ、ある意味世界全体がガラパゴスになっていると言うこともできるかと思います。その結果、世界の中に何か日本がガラパゴス的に育んできた、発展させてきた生活スタイルとか、世界観の形式が、ある程度共有できるようなものを図らずも作り出してしまったということかもしれません。
紙芝居は「メディア芸術」か
よくこういう考え方があると思います。つまり、メディアの発展を単線的に考えて、映画からテレビへ、テレビからデジタルへというふうに展開している、そしてそれぞれのメディアについて、やはりハイカルチャーと、マスカルチャーとかサブカルチャーという縦軸があると。例えば映画の中にも芸術としてのものと、娯楽としてのものがあるというような、時間軸の発展と芸術/娯楽が二軸として直交するような整理ですね。
だけれど、そういったシンプルな前提を持つ限り「メディア芸術ってわからないぞ」という話にはならないのですね。だから「わからないぞ」というふうに言う意図は、「やはり、これ、ちょっと変なんじゃないの。」という意識が、私たちの中というか、ここの4人で共有されている問いとしてあるんだというふうに思います。こういった図式には2つ問題があると思います。
例として紙芝居の話をします。私たちがよく知っているのは、このスライドショー型というか、画用紙ぐらいの大きさにいろいろな絵が書いてあって、こう抜き去って次々とお話をしていくというスタイルですね。この紙芝居が最初に出てくるのは1920年代以降です。これを「絵話型の紙芝居」というんですけれども、この紙芝居の登場に決定的な影響力を持ったのは映画なんです。だから、すごく重要なことは、紙芝居があって映画が出てきたわけではないのです。実は紙芝居よりも映画のほうが先行して登場しているということです。近代的なというか、絵話型の紙芝居より前に映画があって、映画で看板を描いていた人とか、とりわけ弁士ですけれども、弁士がトーキーの導入で失業していくと、紙芝居屋さんになっていくんですね。だから、労働者、つまり決して都市の中で豊かな層ではない人たちも気軽に見ることができる娯楽として、ある意味で映画と似たようなものとして都市の中に入っていったという時代があると思います。
ここにおいて、とても重要なことは、つまり近代的な映像技術や複製技術の決定的な重要性、つまり、メディア芸術ということを、あるいはマンガを語るときに、鳥獣戯画まで戻るのはやめましょう、あるいは江戸時代の何か浮世絵だとか、そういうものに戻るのもやめましょうということです。そうじゃなくて、やはり、19世紀末の映像技術が決定的に重要なのです、映像的な複製技術というものが、全世界に広がっていくときに、その日本のコンテクストの中で展開していったのが紙芝居だったんじゃないか? そこから先にマンガの関係も考えることができるだろうということです。
そういう問いを立てると、「紙芝居はメディア芸術か?」と思いますが、多分、紙芝居もメディア芸術なんだと思います。メディア芸術の概念はともかく、少なくとも「紙芝居はある種の映画である」ということが言えると思のです。それはどういうことかというと、「紙もメディアであり、紙芝居というのも大衆的な芸術だから、メディア芸術だ」ということではないんです。そうではなくて、視覚的な、つまり映像的なテクノロジーを前提に、紙芝居ですら出てきているのだから、おそらくマンガですらそうなのだと思います。
そして、地政学的な文脈でアートや芸術について触れておくと、明治以降の近代化の過程において輸入された芸術概念が、さらに大きな歴史的な転換点としての戦後アメリカの占領政策との関係で、どのように変化していったのか。その点も非常に重要な問題で検証が難しい領域ですが、考えていく必要があります。特に今はそういった地政学的な秩序が、グローバリゼーションや国民国家のある種の衰退というような動きの中ですごく変わってきていて、そういった社会背景の中で、あらゆるカテゴリーの境界線がものすごく曖昧になってきているということです。美術と言おうが、芸術と言おうが、アートと言おうが、どうも境界線がよくわからなくなっている、よくわからなくなっているのは、私たちの定義が曖昧だからという理由もあるのですけれども、もうひとつは、やはり、歴史的な必然というか、すごく乱暴に言えば、国民国家の衰退ということがある。
だから「メディア芸術ってよくわからないぞ」ということを考えていくということの意味は、「もっとちゃんと定義しようよ」みたいなことでは必ずしもなくて、「わからないぞ、ということを考えていくと結構深いところにいくな」と、私たちは「わからないぞ」と言いながら、そういうことを考えているような気がします。
型破りな創造性
さきほど映画の話がありましたが、写真についてもそれが登場した際に、例えば、絵画であれば写実というものの存在意義が問われるという流れから栄華に続いたと考えられると思うのですが、そのあたりはいかがでしょうか。
おっしゃるとおりで、多分、先ほどのような形でメディア芸術を考えようとすると、写真から考えなくちゃいけないんです。ただ、写真から考える、写真のことと、あるいはもっと遡ればカメラ・オブスキュラ(カメラの原型)かもしれないです。そして、そこから考えるんでしょうけれども、写真と映画の違いは、やはりひとつは大衆性という問題にあると思います。写真にしても、確かに19世紀の初頭にすでに技術的には発明されているのですが、だれでもが撮れるカメラをKodakが発明して、フィルムの大量生産、大量複製方式の複製システム、工業化・産業化されたシステムを生み出すのは、もう19世紀の終わり、1890年代です。ですから、大衆的な普及段階のタイミングというのは映画とほぼ同時なんですよ。
映画も何が非常に大きかったかというと、新しい複製視覚テクノロジーと、それから興行、プロジェクションして大衆的な興行にしていったというところが、やはり非常に新しかったのです。
でも、ここで言っている話は写真じゃないと思います、やはり物語なのではないかと。物語が先にあって、物語が映画に転写したのであって、写真の延長線じゃないと思います。写真は今おっしゃったようにパーソナライゼーションに向かうから鏡の延長なのです。自分を映す鏡として写真が発達したということです。例えば、明治の初期に、もしかすると今我々が知っているような大きな姿見はなかったと言われているんですよ。丸い手鏡はあったけれど、全身を映すような鏡は相当高価だったはずで、「写真館に行って撮った写真で初めて全身の姿を見た可能性がある」ということを言っている人もいます。ですので、写真はパーソナライゼーションの方、個人のクリエイティビティの方に向かっていったわけですが、今言っている「コンテンツの複製をつくる」という枠組の中で考えると、文学から映画が生まれたという方が正しいんじゃないかなというふうに思います。
僕は、写真か映画かということで言えば、確かに物語は決定的だとは思います。ただ、写真と映画というのは、複製技術として非常に複雑に交わりながら、少しずれていくような関係を保ってきたと思います。さっきも指摘されたように、ダゲレオタイプのときには、普通の人が簡単に真似のできない高度なテクノロジーの産物だったものが、19世紀の末にポータブルカメラが出てきて簡単に自分で撮れるようになったということは、ちょうど現代において動画に関して起こっていることと同じだと思います。もう間もなく多分、簡単に自分で3Dの動画映像が撮れるようになると思います。そういう形で、多極化ということと結びついていると思います。
大衆化という論点で言えば、質の良いお客様がいるところで、質の良い映画がやっぱりできるわけです。僕が東京藝術大学の映像研究科でアニメーション専攻を3年前につくったら、1期の卒業生があちらこちらで賞を獲ってしまった。こんなに質が高いものができたのは、やっぱり土壌があるのだと思います。アニメーションを子どものときからものすごい量を見ている。やはり土壌の深さで言うとものすごい。知らない間に、あのアニメ的動きが身体感覚として身についているとしか思えない。
藤幡さんが言ったような、例えば質の問題は、なかなか、これまた、すごくやっかいな問題で、例えば、質の問題をずっと一番頑固に、制度的にも押し通してきたのが、実は近代というか、ボザールやファインアートのシステムなのではないかと思います。そこでは、必ず決定的に質というものが議論され、判断されるわけですが、今現在、そういった質について語ることは非常に難しいのも事実です。
明治以降行われてきたことの質の頂点は「美」でしょう。「美というのは絶対的なものだ」と教わり、「その美を習って、お前もその美をコピーできるようになれ」というのが、東京藝術大学がずっとやってきたことだと思います。いまだに同じことを言うんですよ。要するに「修練しろ」と。そんな問題じゃないだろうと、僕は思います。だから、例えば、僕は「型破りな創造性」ということにすごく価値を見る。つまり新しいメディアをつくってしまうこと。だから映画を見てから紙芝居をつくってしまうという創造性の方が、古典的な美よりもはるかにおもしろい創造的な行為だと思います。
「メディア芸術」の訳語
「メディア芸術」とあった中に、また「メディアアート」とあって、「マンガ」があったりするわけですが、例えば、これはもしかすると文化庁の方で何かそういう言葉が出ているのかもしれないのですけれど、メディア芸術を英語で言うと何になるのでしょうか。メディア芸術を英語で説明するとき、その中にもうメディアアートはあるという状況が、ちょっと気になったのでお聞きしたいと思います。
それは僕の知る限りは、もう決まっていて「media arts」と呼ばれているみたいです(笑)。僕が考えたんじゃなくて、実際にそういうふうに公表しているようです。
僕も今、指摘された「media arts」の中に「media art」があると、おかしいな、ねじれているなと思いましたし、みんなそう思うと思います。だけれど、それは何というかな、ちょっと直しようがない。例えば、「メディア芸術」という言葉はもう「メディア芸術」で良いんじゃないかというのと一緒ですね。
何でも良いと言っても良いのかと思います。
いやいや、案もあるんですよ。つまり、ローマ字で「geijutsu」という言葉を無理やりあてる。「Art」には翻訳できないものなんだというふうに打ち出すという、そういうオプションも今はされていないけれども、あるにはあるのです。
他の例で言うと、例えば、感性工学という分野があって、「感性」って、美学のことを感性学と言ったりしますけれど、この「感性」という日本語を「sensibility」とか、「sensitivity」、「sensation」とかいろいろ訳しても、どれにも合わないので、「kansei」という言葉で実際流通しているのです。だから、「芸術」も「geijutsu」にしてしまおうという選択もあるけれど、僕自身はこれは新たな壁を造り出すことになって、あまり良いと思っていないです。
「メディア芸術」における音楽の位置
お話を伺っていて、「メディア芸術」という言葉でかなり広いいろいろなものを考えることができるんだなと思いました。「メディア芸術」を考えるきっかけのひとつとして、複製芸術として映画から考えるのは、ひとつのやり方だろうというような意見を聞いておもしろいなと思いました。そこで「メディア芸術を考えるのは美術史を再考するやり方のひとつだ」という観点がありましたが、そこで「あれ、音響記録複製テクノロジーの話がないな」と思いました。ぜひ美術の歴史を考え直すなら、そこに音の歴史の話も入れ込んでほしいなと思いますが。
音楽が入っていないのは絶対におかしいです。ただ、それを実際に正面から入れようとすると、今度は政治になってしまうわけです。そこでひとつの突破口として考えられるのはコンピュータです。「メディア芸術」の定義に「コンピュータや電子機器を用いた表現」と書いてあって、そこはひとつ音楽を扱う上での切り口になりえると思っています。でも、そうすると話がややこしくて、ダブルスタンダード、トリプルスタンダードになってくる可能性があります。というのは、文化庁メディア芸術祭とは別に文化庁芸術祭なるものがあり、そこではすでに音楽というジャンルがあって、そこは小唄とか日本の伝統音楽も扱われているのです。坂本龍一さんがこの間、芸術選奨を受賞されましたが、彼がとったのは大衆芸能部門なんです。「えっ」でしょう? さらに「メディア芸術」という枠組の中に音楽を入れると、もう入っているわけですよ。コンピュータなどを用いたシンセサイザーを使ったYMO以降の音楽は、もうメディア芸術だと。何ですか、これ。 めちゃおもしろい。だから、「このめちゃめちゃな状態を、そのまま受け取った方がおもしろいんじゃないの?」ということも提案しているわけです。それをもういっぺん整理し直して、西洋のカテゴライゼーションを当てはめ直すと、余計に話がややこしくなっちゃうから、「このトリプルスタンダード、クアドラプルスタンダードみたいな状態こそが日本の文化だ」みたいなことを言いきってしまいたいと思っているのです。
「media arts」の中に「media art」が入っているというのは、何か自己相似性みたいな、フラクタル図形みたいな構造ですね(笑)。
極めて重要なテーマがいくつかあり、そのひとつは音楽、音響の問題だと思います。ここには教育の問題も関連してきます。ただ、その辺を全て語ろうとすると、話が極めて複雑になるので音響、音楽の話をあえてひとつするとすれば、まず社会の側から言うと、映画とか紙芝居といったビジュアル技術と、それから音楽に関連する音響技術の大衆化は全く同時代だったということは明確に言えます。
つまり、蓄音機産業が大衆社会に入っていくのは、日本の場合だったら1920年代です。世界的に見ても19世紀の末の終わり、1890年代あるいは1900年代からだから、日本であれ、ヨーロッパであれ、ある明確な同時代性があります。
同時に、ここからがややこしいのですが、同時に語れる部分がありつつ、音楽とか、特に歌の問題を考え出すと、今度は文芸との関係が出てきます。つまり言葉の問題が出てきます。
例えば、私の学生の一人に童謡の研究をしている人がいますが、彼の議論だと、「童謡は最初、文芸や子どもの詩という言葉のほうに力点があって、音楽というカテゴリーよりは、文芸という文学の方のカテゴリーだった」と言います。そうすると、これは音楽の話なのか、出版というメディアとの関わりを検証する必要が出てきますが、実際そこまでスコープを広げてメディア芸術の議論する必要があるかというと、少し難しいという気もしています。
「メディア芸術」の可能性
皆さんがおっしゃっていたのは、「文化庁メディア芸術祭におけるメディア芸術は結構、適当な概念でやっているところの、そのいい加減さ、曖昧さがおもしろいんじゃないか」ということかと思います。それ自体は、まあ、おもしろいとは思いますが、ただ、「概念」というふうなところで考えると、もうちょっとそこら辺は慎重に考えていく必要があるのではないでしょうか。「メディア芸術」という名称を、とりあえず与えることによって、不用意に概念が一般化してしまうことについて疑問として感じるところもあります。
1995年に「文化庁芸術祭五十年戦後日本の芸術文化史」という本が出ているのですが、その中で加藤秀俊さんが、「メディア芸術」という言葉を使っています。加藤秀俊さんは、マスコミュニケーションとかマスメディアを専門とされている方であるという背景もあると思うのですが、そこで彼は、「戦後、美空ひばりが『リンゴの唄』をテレビ・ラジオを通して歌った、これこそがメディア芸術である」と書いています。ここでのメディア芸術というのは、マスメディア芸術という意味なのです。まずはそういった形でメディア芸術という言葉が生まれてきた中で、各種の議論を通じて、2001年に制定された文化芸術振興基本法では最終的にメディア芸術が法的には「映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術」として規定されるわけです。メディア芸術という言葉はその登場のころからも定義については揺れがあるわけです。
ただ「メディア芸術という言葉がいい加減だ」というふうには必ずしも思っていなくて、むしろ「あやしいと捉えたい」と僕は思っています。どういうことかというと、言葉がどうしても必要なときというのがあるわけですよ、名指している対象があるにもかかわらず、名称がはっきりしていないときに、どんな言葉であれ、その言葉をつくっておかないと物事が進まないということがあります。
僕も当初は「メディア芸術はあやしすぎるから、関わらない方が良い」と思っていたわけです。しかし、いろいろ考えていくと、これは非常に重要な問題で、ひいては自分の存在にも関わってくるということがわかってきたので、僕はこういうことを積極的にやっているのです。なぜ、これが僕の生死に関わる問題かというと、要するに「個人主義と民主主義がこの国で必ずしも市民社会の中に根づいていない」ということに繋がるからです。
日本では世間がどう考えるかということばっかり、アーティストでさえ、世間のことを考えている。自分がつくる作品ではなくて、自分がつくる作品がどう見られるかということを気にしているのです。ところが、世間を気にせずにつくり続けてきたものに意味があると思いますし、実際におもしろかったりする。例えば、漫才であるとか、マンガであるとか世間の外に出た人たちの表現がおもしろい。極端な言い方をすると外道といったり、アウトサイダーの方がおもしろいものをつくってきたようなところがあります。つまり、コメディアンは自分が世間の外側にいるということによって、政治的な発言を自由にできるということが起こってしまう。一方で普通の人は世間があるから、言いたいことを言えないわけです。
そういう部分を解釈しつつ、僕は今、マンガや漫才、歌とかがおもしろがられているのは、実はそこに世間を超えたメッセージがある、すなわち、そこに個人主義の始まりがあるかもしれないと思っているんです。それを認めることによって、だれもが自由に世間のことを考えずに発言できるという世界が生まれるかもしれないと思っていて、このメディア芸術というものがそのきっかけになれば、初めて日本に本来のアートが根づくかもしれないと、実は思っています。
「メディア芸術」ってよくわからないぞ
メディア芸術の定義で、藤幡さんが「加藤秀俊さんが最初にメディア芸術っていうふうに使っている」という話をしました。そのことにちょっと注釈を加えておくと、加藤さんがメディア芸術といったときの、その前提には明らかに鶴見俊輔さんによる「純粋芸術」「大衆芸術」「限界芸術」という3カテゴリーが前提になっているんですね。
もともと鶴見俊輔さんの「純粋芸術」というのは、いわゆるファインアートです。「大衆芸術」はマスメディアに媒介された芸術行為で、「限界芸術」というのは日常的な活動の中での芸術行為、例えば、しゃれを言ったり、こういうふうにしゃべったりすること、鶴見さんなら「これも芸術だ」と言うのです。そうすると、鶴見さん、あるいは思想の科学研究会の1950年代60年代の人たちは、なぜそれを芸術と言ったのかということを、これは明らかに西洋的な芸術概念に対するアンチテーゼを出そうとしているわけです。
必ずしも労働者階級とか人民とか、そういうんじゃない、もうちょっと広い、「庶民」とか「人々」というような集合体が日本にはあるんだと、それがある創造性を発揮して、ある表現行為をしている。それをあえて西洋的な概念である芸術をそこに無理やり入れることによって、西洋的な概念の芸術という概念を相対化しようというふうな意図が、鶴見さんにはかなりあったんです。
問題は、今現在の意味でメディア芸術というときに、「50年代の、あるいはテレビなどが台頭し主流化する前に鶴見さんたちがリアリティとして持っていたような人々とか共同性を前提にメディア芸術とか大衆芸術と私たちが言えるか」ということで、それは相当難しいと思っています。
ただし、あえて「メディア芸術」という言葉を使っていくのであれば、今、先ほど藤幡さんが触れた民主主義との関わり方というものが、たいへん示唆的だと思います。そこでのメディアというのは、藤幡さん流の意味の変容が起こっていて、ある種の関係性というか媒介性、つまり、個人・個の芸術ではない、関係性の表現としてメディア芸術を再定義しようという話だったのだと思います。
明治以降、ずっと近代を超える論争というのが、必ず日本ではあって、その論争は「西欧に対して違う物差しでやりましょう」という一方で、反芸術もそうだったのですが、構造的には全く同じものになってしまっていたわけです。ただ、これだけ新しい表現形式があふれるように出てきて、ある種の可能性が見え始めると、それを整理しようとする動き、すなわち概念規定論争というものが起こるわけです。
今のクールジャパンの中にも、「西欧的なものに対して日本的なものの魅力を打ち出そう」という議論があります。ただ、本当にそこで日本的なものが出ているのか。その背後に隠れているのは、やはりヨーロッパ的な近代性であって、それをベースにして日本的なものが対比として見えてくるという構造があります。その構造での堂々めぐりがずっと続いてきているのです。「メディア芸術」という言葉をきっかけにして、もし何か希望を見出し得るとすれば、その循環を断ち切る可能性があるはずだと、漠然とではありますが実感しています。
ただ現状については、「メディア芸術」の概念規定の不整合を解決するために可能な限りの概念操作は試みましたが、今のところ、まだ答えがありません。ここにいる4人はみな、「そういうものが曖昧なまま流通している」という事実は認識しています。定義については、深く考えれば考えるほど、何か芋づる式に大きな問題が、藤幡さんがお話された「アーティストとしての個人」のような、そういった問題まで出てくるのです。だから、そこに何かあるなということはわかっているのですが、それを分析するための装置が確かにまだ不完全だということです。
逆に言えば、新しい言葉をつくるより、古い言葉を復活させざるを得ない場合もあるかと思いますし、それが概念操作になっていくのかもしれません。今日も結局、「メディア芸術ってよくわからないぞ」という会になりました。とはいえ、それゆえにまた生産的だったというようにも思います。













