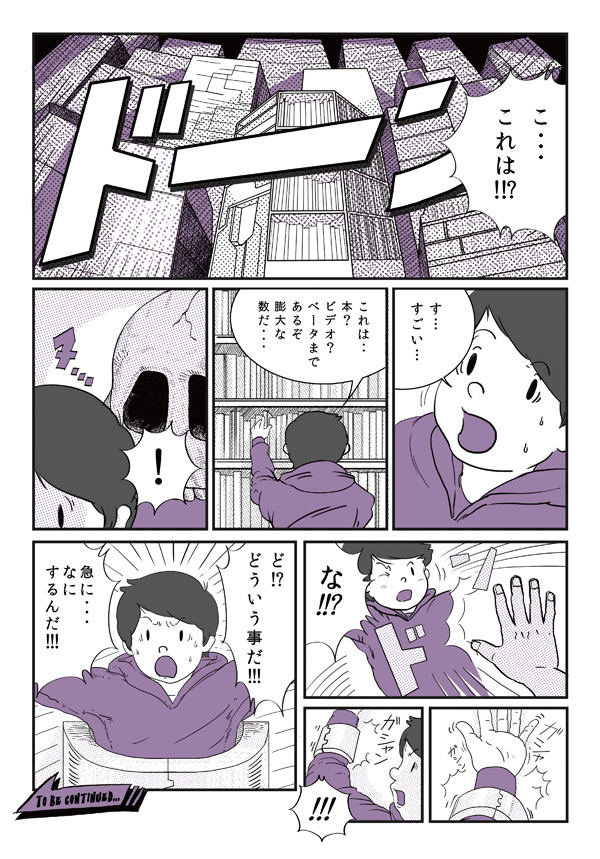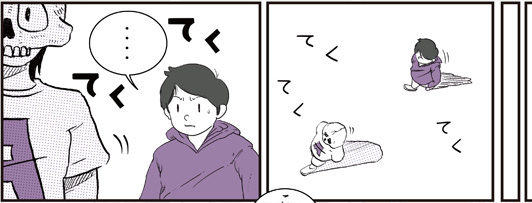
イベント概要
開催日:2011年2月26日(土)14:00〜17:00(13:30開場)
会場:せんだいメディアテーク スタジオシアター
スピーカー:島本浣 藤幡正樹 吉岡洋 吉見俊哉
ゲストスピーカー:とちぎあきら
メディア芸術は「ひょうたんから駒」である
メディア芸術オープントーク「『メディア芸術』ってよくわからないぞ」ですが、今回5回目になり、僕なりにわかってきたことがあります。「ひょうたんから駒」ということばがありますね。それがこの議論の結論だと思い始めています。なんのことだかわからない「メディア芸術」ということばが「ひょうたん」で、この場合の「駒」は、すごく大きな、文明的な規模の問題なのではないかと思っています。
ヨーロッパにおいて今日の後半のテーマでもある映画は、第7芸術と呼ばれています。つまり積み上げ方式で、芸術を細分化・専門化するということがルネサンスから続いてきて第七まできているということです。
しかし現在、テクノロジー、特にデジタルメディアや通信技術という新しいメディアが、人間の表現の問題として、ひょっとしたら何か新しい総合を求めているというシチュエーションが生まれてきているのではないかという気がしています。
僕みたいに、これまでカテゴリーを細分化した上で、芸術や表現を理解してきた人間にとっては、ひょっとしたら積み上げ方式でない事態が本当に出てきていて、もっと大きな、文明論的な規模から「『メディア芸術』ってよくわからないぞ」と思い始めています。
先週、東京で「世界メディア芸術コンベンション」という国際会議を開きました。そのことを踏まえて、いま島本さんが言った「ひょうたんから駒」ということを考えてみると、確かに私たちは現在、文明の大きな大転換みたいな場所に立っていると感じます。
その会議のテーマは「『メディア芸術』の地域性と普遍性」というものだったのですが、「メディア芸術」が日本語話者以外の人たちにも案外理解されて、びっくりしました。翻訳語として「芸術」があり、「アート」というのがまた別の意味を持って使われているという複雑な状況で、「メディア芸術」はとても特殊だと思っていたのですが、これが案外わかるらしいということは、文明論的で普遍的部分が、やはりあるのだと思いました。
なぜこういうことばが要請されてきたかという議論の中で、メディア芸術はひとつの「アンブレラ・ターム」だという人がいました。つまり、いろんなものをその傘下に置く、そういうことばなのではないかと。「アンブレラ」というのは両義的で、つまり包括的概念だというのと同時に、必然性なしに上からかぶせただけだというようなニュアンスがあると思います。
「現代アート」と「メディア芸術」
現代アートのことも、コンベンションでも議論になりました。つまり、「現代アート」ということばにも別に共有された確定的定義があるわけではなくて、文化圏によってかなりの温度差があるということです。
欧米の現代アートのモデルは、その中にメディア系のものが入っても、マンガが入ってもアニメが入っても、政治的活動でも、全部アートにしてしまいます。どんなものが入ったってアートになる、これこそ巨大なアンブレラです。
ところが日本やアジアの他の国々のように、もともと欧米文化ではなかったところに欧米の基準が入ってくると、異なった状況が生まれる。日本のように急速な近代化が成功した事例では、欧米的なアート概念も独特な仕方で内面化されています。しかし日本でも、例えば、現代作家がマンガとかアニメーションとかそういう要素をアートの中に取り込む身振りに関しては、それはアートか? と疑う人もおり、アート概念は欧米に比べると不安定です。これが例えばインドネシアとかにいけば、もっと不安定になる。アートという概念の拘束力が弱いのです。これらは近代的な考え方から見たら「遅れ」なんですね。つまり、近代的な芸術の制度性がまだ十分定着していないというふうにみえるわけです。だけど逆にみたらそれは強みでもある。要するに、芸術の拘束力にとらわれていない分、新しい文明に対するある種の適応力があるということになるわけです。弱みと思われていたものが、もしかしたらメリットになるかもしれないと。
こういうことに関わる問題が、「メディア芸術」ということばの中にもあると思います。英語に訳したら「media arts」なのに、その中に「media art」が含まれている、みたいな歪み。しかしその歪みはある現実には触れている部分があって、積極的に展開していけば、文化を超えて共有できるものがあって、ヨーロッパでも有効かも知れない。
吉岡さんの話を補足すると、やはり現代芸術というものはなぜ必要かというと、国同士のアイデンティティーを明確化するとか、個人のアイデンティティーを明確化するという行為が、全部アートになっているからだと思います。つまり「おれはこういうものが好きだ」みたいなことを大声に出していえる場でもある。そういう意味の自由が担保されている場所がアートということなのです。
私たちの思考の中には多分、江戸時代以前からずっと保ってきた美学が、知らない間にいろいろと刷り込まれているのだと思います。その刷り込まれ方の基本は「習い」で、前代の人のことをまねすることから入ってきた。学ぶことは、真似することからはじまるんです。日本の芸術文化の伝統からすると、やはり先代が持っている型を、柔道みたいにまねるところから始まって、ずらす部分におけるセンスとかが評価されるという基本がある。
こういうことにヨーロッパの人たちも気付いていて、重要視して、回帰している感じがあります。だからこういう方法で美的価値が保証されていく中で、新しいアイデンティティーがメディア芸術に付与されていくことの面白さで、世界的に何かできるのではないかと思っています。
日本は「ずらしの美学」って、近代だって、みんなずらしているのに、そこに光を当てる人がいないだけの話なんだと思うんですね。近代が「ずらしのような遊びは、どこかまじめじゃない」みたいな領域を作り出したということだったのではないかな。
まったくその通りだと思います。「日本人が作るものは全部オリジナリティがない」みたいにいわれるのに対して、対抗する意味で「メディア芸術」ということばを置いて、そこから生まれてきたものに、光を当てていくことは可能であると思います。
「芸術」の中の文化財というニュアンス
グーテンベルクが活版印刷を発明したことで、知識や文化が機械的に複製可能になりました。それに続いて、ヨーロッパでは近代国民国家の成立から文化概念ができたわけです。
しかし日本では、こうしたメディアと文化、芸術の概念が微妙にずれているということがあると思います。つまり、明治国家が、日本の国民国家の起源として出してきたのは文化財だった。文化財行政が出てきて、それは第2次世界大戦後も続いているわけですね。すると印刷にしろ、映画にしろ、複製技術が私たちの生活とか文化に深く入ってくるプロセスとも重なった時代に起こっているのだけれど、なにかずれているわけです。
いま起こっていることは、この2つがくっついているようなところが、「メディア芸術」ということばの気持ち悪さに現れている気がします。島本さんが指摘したように、文明論的な変化が起こっているわけだけれど、そこにある種の気持ち悪さみたいなのがあって、これをどう考えるかということを毎度議論してきている気がします。
先ほどコンベンションで意外に外国の人たちと理解が共有できたと言いましたが、できなかった部分もありました。できなかった部分は何かというと「芸術」ということばの日本語的意味に関わることです。それは何かというと、近代ヨーロッパの芸術概念が日本に入ってきて、日本語の「芸術」ということばがつくられるときに、そのモデルはいま現在行われている活動というよりも、むしろ文化財として発見された過去の伝統だったわけですね。
つまり明治の初め、前近代の伝統的文化に対してどうしたら良いかわからなかったので、「廃仏毀釈」(仏教の排斥運動)のようなひどい扱いをしたけれど、反省したわけです。なぜかというと欧米人が仏像を見て「こんな素晴らしいものがあるじゃないか!」と言ったから。その視点をいわば内面化して、ナショナリズムに転換したわけです。ナショナリズムというのは常にそうした対抗的メカニズムで作られるので、いわば自分よりも強い他者の視点を自分の中に内蔵するわけです。それによって日本の伝統文化は、近代国家のアイデンティティーを支える本質的な概念となった。
この経緯が「芸術」ということばのニュアンスを決めたので、欧米的な「ファインアート」とか「ボザール」ということばが内包している、前衛的・実験的な現代の芸術というイメージが、日本の「芸術」には希薄になった。「芸術」ということばの中に文化財的な響きがあるので、新しい試みをしている人たちには何か違和感があり、それが「アート」という語を要請したのではないでしょうか。
第2部は東京国立近代美術館フィルムセンターのとちぎあきらさんのプレゼンテーションになります。よろしくお願いします。
重要文化財指定された映画フィルム
前半のお話の最後に文化財の話が出ました。2009年に映画フィルムが初めて国の重要文化財指定を受けました。指定を受けた作品は『紅葉狩』(1899年)です。2010年には、『史劇 楠公訣別』(1921年)が2本目の文化財指定を受けました。
『史劇 楠公訣別』は、楠木正成と正行父子の「桜井の別れ」という、太平記に基づく講談などで有名な演目ですが、この映画は、そもそもふたつの文化財に関連があります。この映画が撮影されたのは、湯島聖堂内にあった「東京博物館」(現・東京国立博物館および国立科学博物館)でした。そこで開かれた「活動写真展覧会」(1921年11月20日〜12月10日)に、当時の皇太子、すでに摂政宮と呼ばれていた後の昭和天皇が台覧をした際に、その見学にあわせて、聖堂の中庭で撮影が行われました。当時の映画界の大スター・尾上松之助が演じ、撮影をしているところに摂政宮が訪れるという、ある種イベントだったのです。
どのように文化財と接点があるのかというと、文化財保護法は、1950年に制定されましたが、この種のいちばん古い法律は、古社寺保存法(1897年)です。廃仏毀釈から社寺を守ることから始まっていて、先駆的な文化財保護の法律のひとつでした。その他に、史蹟名勝天然紀念物保存法(1919年)があり、これは歴史的な名勝、天然記念物の保護を目的としています。この法律ができてまもなく、楠木父子が別れたとされる、古代律令制度下の宿駅跡である桜井駅跡(大阪府三島郡島本町桜井)が、1921年に史蹟となりました。つづく1922年には、湯島聖堂も史蹟となっています。つまり、『史劇 楠公訣別』の撮影前後、桜井駅跡、湯島聖堂が相次いで史蹟となり、2010年になってフィルムが重要文化財になったという、なんといいますか、歴史の因縁を感じます。
映画芸術という居心地の悪さ
映画もメディア芸術に含まれるわけですが、その歴史を考えたときに「映画芸術」とはいったい何なのかが問われてくるように思います。
先ほどの「活動写真展覧会」では、いわば史蹟名勝で史蹟名勝を舞台にした古事が演じられている。昔ながらの国民説話を、尾上松之助という日本でいちばん最初の大衆的な映画スターが演じて撮影される。このある種の「気持ち悪さ」。こうした「気持ち悪さ」を考えたときに、一方で映画を芸術化するという動きがまさにこの時期に始まっていることを見逃すわけにはいきません。
私の直感として断っておくと、日本の表現形式、表現行為の幹、ないしは、根を張ったものとして、芸能という側面を考えておかなくてはいけないと思っています。芸能からいろいろなことが派生し、内在的な理由、外圧的な理由から、いわゆる芸術化していくという歴史を繰り返してきたように思います。
映画の芸術性と猥雑性
日本の映画史において、「映画芸術」が議論された最初は1917年頃だと思います。この頃から、純映画劇運動(日本映画の近代化を求める運動)が、いろいろな映画会社からの何人かの映画監督や脚本家によってスタートしました。
1919年には、帰山教正(かえりやまのりまさ)が、「映画藝術協會」を設立します。海外の文献やすでに輸入されていた欧米の映画を研究し、執筆活動を活発にしていた帰山は、この年から映画製作をはじめ、残っていないのですが、『深山の乙女』『生の輝き』という2本の映画を撮りました。
1920年には、歌舞伎界、つまり日本の演劇界の中枢にあった松竹が、松竹キネマを設立し映画を撮りはじめます。このとき松竹キネマの中心人物だったのは小山内薫という、近代演劇の第一人者でした。
では何が「純映画劇」だったのか? いくつかの要素がありますが、映画ならではの物語形式ということになります。例えば、撮影前の段階できちんとした脚本を書く。画面を分割して連続性のあることを描く。撮影時に人工的な照明を使う。オーバーラップを使用する。移動撮影をすること等。特に有名なのは、女形を廃止したこと。弁士による説明を廃して、画面上の字幕で物語を説明したことだと指摘されます。つまり、歌舞伎などのいわゆる舞台芸術、口承的な芸能の伝統から独立していくことが純映画劇だった。
これが「映画芸術」だとすると、芸術であるということの保証は、ある種の純粋性、ほかの表現形式との差別化にあったといえるでしょう。
1920年代後半から、映画には音がついて、トーキーが始まります。ところがトーキーが出始めた当時の映画雑誌、『キネマ旬報』などですが、「キネマ」と書いてある場合は無声映画を指しています。音が入っている場合は「トーキー」。つまり、キネマが純映画的、ないしは映画芸術的なものとされ、音に対しては、雑なものが入ったとして抵抗をしています。映画に音声を入れることは、その純粋さを奪うものとして語られた時代があったことになります。しかしそうはいっても、私には映画の伝統には、いわゆる純粋化されない猥雑な、良い言い方をすれば、ハイブリッドであるという本質が、非常に大きくあったと思います。
現在のアニメーションの形成──1960年前後
映画のハイブリッドな側面を示す意味でも、第2次世界大戦前から戦後、さらに現在にいたるまで発達をしてきた、アニメーションの歴史をみてみましょう。
まず現在のアニメーションを形成する3つの大きな流れが生まれたのは、大体1960年前後ということが定説になっています。
ひとつは、長篇アニメーション映画が映画館で公開されるようになる。これは東映という大手の映画会社が東映動画という子会社をつくり、そこで年に1、2本、劇場公開する映画を製作し始めたこと。1958年の『白蛇伝』でスタートします。
つぎは、1960年に久里洋二、柳原良平、真鍋博が「アニメーション三人の会」を草月アートセンターではじめる。自主制作をした16mmのアニメーションを紹介し、「自分たちが作っている映画はアニメーションです」といったわけです。「アニメーション」ということばを明確に宣言して上映を行ったのは、このときが初めてではないかと思います。
そして、戦前に「フクちゃん」等を描いて映画も撮っていた横山隆一が、1961年にフジテレビで『インスタント・ヒストリー』という、「今日は何の日」みたいなものをアニメーションでやる3分間のテレビシリーズが放送されました。それが、いわゆるテレビアニメのスタートだといわれ、1963年には『鉄腕アトム』が始まります。
この1960年を境にした現在のアニメーションを形成する3つの流れ、劇場用長篇アニメーション、アート・アニメーション、テレビ・アニメーション、これらがこの時代にできたわけです。
それ以前は、アニメーション以前と呼んで良いかもしれません。その時期、長い間、アニメーションは漫画映画と呼ばれ続けてきました。
ただし1960年代、70年代になっても実は「漫画映画」ということばはずっと残っていました。東映動画が提供してきた「東映まんがまつり」には、高畑勲や宮崎駿が作った映画もあり、ポスターにも長篇漫画映画と書かれていて、アニメーションということばは出てこなかった。
東映動画が、現在の東映アニメーションという社名になったのも1998年と、比較的最近のことでした。だから、アニメーションということばそのものが定着したのは新しいことですね。いや、むしろ「アニメ」という省略形によって大衆化したといいますか、各々の流れを差別化することなく認知されるようになったわけです。
漫画と啓蒙と芸能
戦前のアニメーションはなぜ漫画だったのか? その理由は、結局、子ども相手の映画でしかあり得なかったからです。1917年に日本で初めてアニメーションが作られます。3人の作家それぞれが、映画会社と組んで、劇場で公開するためにアニメーションを作ることを試みましたが、映画会社はすぐにこれをやめてしまいます。すでに輸入されていたヨーロッパやアメリカの作品のほうが、クオリティが高いし、観客も集められるということで劇場にかける可能性がかなり失われてしまったのです。一方、実際にアニメーションを製作していたのは、中小の工房のようなところですから、短編作品を手掛ける以上の資本がなかったわけです。
先述の「活動写真展覧会」は文部省が開いた展覧会でしたが、1920年代になると、国が映画を、ある種の道徳、啓蒙のような役割で積極的に利用する時代が訪れます。そのときに、アニメーション=漫画映画の持っていた、とりわけ子どもに対する影響力の強さが重視され、文部省がアニメーション映画をたくさん作らせるようになりました。
1925年には、映画史の中で初めて、国の統一的な検閲を内務省が始めます。検閲の中で、漫画映画は「描画」という名前でひとつのジャンルとして固定され、アニメーション映画はその枠組みの中で展開していくという歴史をみせはじめます。
大手の映画会社も時にはアニメーションを作ろうと試みますが、大体すぐに挫折してしまいます。戦中に松竹が長篇アニメーション『桃太郎 海の神兵』(1945年)を作りますが、これも一時的なものとなりました。文部省が、アニメーション映画を、ある種の教育映画と位置付けたことにより、子どもを対象にした道徳的、啓蒙的メッセージを持たせることになった。そこで、映画に先立つ日本の芸能が作ってきた語り物の伝統、例えば民話・伝承・講談・落語・浪花節・紙芝居、それから舞踊、能、狂言、歌舞伎、さらに文芸を導入し、物語の背景にある種の宗教的な衝動というか、教えを伝えたり、説教をしたり、訓話をするといった要素が、アニメ的なファンタジーの世界で再利用されていったということが、戦前のアニメーションにあったように思われます。
これから見ていただくのは『動絵狐狸達引(うごきえこりのたてひき)』という1933年の映画ですが、「動絵(うごきえ)」とはアニメーションの意味です。「達引(たてひき)」とは、歌舞伎などの外題にある「意地の張り合い」の意味で、ここではキツネとタヌキが化かし合いをすることを指します。
これを見ると、戦前のアニメーションの教育的な要素が、いかにさまざまな伝統的な芸能の要素と混交しているかがわかります。また、1930年頃から大量に輸入されたディズニー映画を通じて、アメリカのカートゥーンの影響を受けつつ日本のアニメが発展したこともわかるでしょう。
(『動絵狐狸達引(うごきえこりのたてひき)』(1933年)上映)
映画が持つ猥雑でハイブリッドな感じをより理解していただけたと思います。説話の形式、キャラクターの創造、ギャグ、映画的なカメラワーク等いろいろなことが指摘できますが、このゴチャゴチャ感を生み出している大きな要因として、音の存在が挙げられます。この作品は東宝の前身のひとつであるP.C.L.映画製作所の映画なのですが、トーキー・システムの開発をしていた会社なので、いろいろな音を聞かせたいということも背景にあったわけです。
保存すべき3C(コンテンツ・キャリア・コンテクスト)
近年、フィルム・アーカイブの世界では、何を保存すべきかということに関して、ひとつの考え方として、「3つのC」ということがよく言われます。
ひとつ目の「C」は、画と音の情報そのものであるコンテンツ(CONTENTS)。
ふたつ目の「C」は、その画と音という情報をのっけている、普通にいえばメディアですが、映画の場合はフィルムそのもの、これをキャリア(CARRIER)と呼んでいます。
みっつ目の「C」は、そのキャリアにのっかったコンテンツをできるだけ忠実に再現させるために必要な装置とかシステム、機械の仕様や、それを作る背景となった歴史的な文脈などを総称したコンテクスト(CONTEXT)です。
これらを不即不離なものとして護っていこうと考えています。この考え方の背景には、デジタル技術の急速な進化とデジタルメディアの膨大な生産・流通があり、こうした状況に対しフィルムの保存にとって何が必要なのかが問われているわけです。1920年代末、初期のトーキーにもう一度戻ってみると、いま見ていただいたように、フィルム上に音が記録されているフィルムだけでなく、エジソンから始まるもうひとつの音の流れがあります。レコード式トーキーという、映画を見せながらレコードをシンクロさせて見せるというやり方です。ただ、システム的にお金もかかるし安定性も悪く、結局なくなってしまいました。しかしこのシステムは一時期、一般家庭にも広まりました。フィルムの幅が35mmではなく、16mmとか9.5mmという小さい幅のフィルムで家庭に売られ、もう一方でレコードも売られていました。家庭でフィルムを回しながらレコードをかけて楽しみましょうという、家庭用レコードトーキーが、人気のあった時代があるわけです。
この時期にいわばホームムービーを作り始めた、飯田東吉という人物がいます。別に映画史に出てくる人ではないのですが、その息子さんが、東吉の作った130本ぐらいのフィルムを寄贈してくれました。寄贈フィルムの一部にはSP盤のレコードも付いている。SP盤のレコードをかけながら、映画を家で見ていたわけです。その中の1本に、時代劇やアニメーションではなく、飯田東吉が寄贈者であるお子さんを撮ったホームムービーがあります。つまり、既存のレコードに併せて撮影したものですね。
現在では同じシステムを再現することはできないので、現代の技術で、画は画で複製し、音は音でデジタル化し、フィルム上で画と音を合わせて再現させるという、家庭用のレコードトーキーの復元を2008年から2009年にかけて行いました。
(『大きくなるよ』(1931年)上映)
80年前の映画ですが、いまのお父さんと変わらない。典型的なホームムービーの楽しさを感じます。ホームムービーであれ一般公開された映画であれ、復元していく作業というのはフィルム・アーカイブにおける一つの仕事です。単純にいえば、フィルム・アーカイブとは集める、残す、見せるということを、ひとつの流れとして行っているところと言えるでしょう。
アーキビストという仕事
映画フィルムに即して、アーカイブの仕事をお話しすれば、フィルムを収集する、フィルムそのものの寿命を持たせる、安全な環境を整えて長期保管するなどがあります。ただ保護していてもそれが悪くなったり、すでに劣化していたり、1本しかフィルムがないので使用するにはリスクがある。その場合は、そこから複製することによって、コンテンツを保存、復元します。そうした成果を、上映し、公開する。また、映画に関連する資料の場合には、それを展示する。最後に、このような所蔵品に対して外部の方々からリクエストがあって、見せたいとか、コピーをしたいということへの対応として、アクセスという仕事があります。
この幾つかのプロセスを含むひとつの流れは、それぞれに大変専門的な知識と経験が必要です。ある部分ではマンパワーが集約的に必要になります。そういった面を研究とか調査という側面から行うのが、アーカイブにおけるいわゆる研究員の役割ですが、やはり研究員だけでは動かない。実際には、たとえば収集に当たっては、予算のことなども含め、いわゆるマネジメント的な事務方の仕事も大きくあるわけですから、研究員と事務員が密に連携しながら、共同で、先ほどのプロセスをひとつひとつこなしていくことが、全体の仕事なのだと、現場感覚として思います。プロセスのどこかひとつを取り上げて「アーカイブ」を議論することに違和感を持っているわけです。プロセス全体の中で働いている人間すべてが、ある種のアーキビストだということではないかとも思います。
複製芸術としての映画
映画における復元という作業は、映画というものが複製芸術であるということからもわかりますように、複製によって常にコンテンツを再現させ、蘇らせるといことの繰り返しをしていくものなんです。もちろん、現物そのものを長く護ることは、オリジナルというものを考えたときに非常に貴重な行為であり、それによって最良の復元物ができるのを保証することにもなります。
復元技術は、映画の世界の中では、現像所がそれこそ映画史の早い時期から継承してきたものです。この10、15年、フィルム復元の世界にはDI(デジタル・インターミディエイト)という技術が導入されています。デジタル化することによって、いろいろな修復を施し、細かく精度の高い復元によってフィルムを蘇らせるということが実現できるようになってきています。ただし、この作業には、多くの人と多額の費用、復元の方向性を決めていくディレクション、予算やスケジュール管理などのマネジメントが必要になっています。つまり一つのプロジェクトとして行う仕事になっています。
その例として、2004年に復元を行った溝口健二監督『新・平家物語』(1955年)のデモンストレーション・フィルムを上映します。全編をデジタルで復元する作業は、フィルムセンターと著作権者である角川映画が共同で、オランダの現像所に発注して行いました。
(『新・平家物語』(1955年)上映)
映像文化の膨大な領域
とちぎさんと別のところで一緒に行っているプロジェクトですが、戦後、アメリカ占領軍のCIEという民間情報教育局が広めて、公民館や学校で上映した「CIEフィルム」という映画があります。これも教育用の映画でものすごく普及した。しかし今日の発表を伺って、映画を見ると、戦前から学校や神社などの公共的な場で上映する映画が膨大にあって、そういう場でアニメが発達した側面がある。あるいは、国家のプロパガンダという形で発達した。おそらく、劇場でやられる映画の外側に、こうした映像文化の膨大な領域があったのだと考えました。劇場だけ見ていると、本当に氷山の一角で、その外にはホームムービーのような、35mm以外のフィルムもあって、そこまで広げて映像の保存を考えないといけないということがみえてきました。
何を集めて、何を保存して、何を復元させていくかというときに、ミュージアムとアーカイブは違うんだとよくいわれます。ミュージアムはある種の選択的な考え方があって、例えば西洋美術とか、20世紀美術とかを選ぶわけです。アーカイブは、あるひとつの領域の中では網羅的に集める。もちろん、なかなか実現できないわけですけど。
実は日本は映画大国です。つまり劇映画だけでも、この100年ぐらいで約3万数千本、それ以外にもニュース映画、記録映画、文化映画、PR映画、産業映画、科学映画、アニメーション映画、テレビ用映画がある。しかもホームムービー、これを加えたら本当に想像の範囲を超えます。映画はもうあまねく作られ、浸透し、どの人にもなじみ深いものになっていたということが、アーカイブの世界にいるとよくわかってきます。おそらくメディア芸術全般に通じることだと思いますが、メディアの発達の中で、アーカイブは単にコンテンツだけじゃなくて、いわゆるシステムを含めたメディア自体のことも考えなくてはならないわけです。
藤幡さんから今回のお話をいただいたときに、著作権のことに触れられました。映画の著作権は、基本的にコンテンツに関わることです。コピーライトとは、文字通り複製権ですね。複製をすることに係わってくる。しかし、映画全体をキャリアやコンテクストを含めて考え直したときに、フィルムという製品があり、映写機という機械がある。こうしたモノやメカニズムには、特許とか実用新案に関わる世界がありますね。そういう技術的なものはどんどん失われてゆく。でも、それもアーカイブし、かつ残し、見せることが非常に大きい役割だと思っています。
アーカイブ、さまざまな権利問題
オープントークは、USTREAMしていますが、映像の上映だけUSTREAMでは見られない。象徴的なことだと思います。この理由をすこし説明したほうが良いでしょう。
3作品それぞれ多分、経緯が違います。所有者が違う、製作者が違う、目的が違うわけです。ところが、同じフィルムセンターにある。そしてフィルムセンターのとちぎさんに講演の準備をいただいて、同じところからここに持ってきて、私たちは見たわけですが、USTREAMは駄目。この話は、とちぎさんのほうから駄目だということなのですか? その理由を話すと面白いと思いますけれど。
痛いところを突かれた質問です。いま私たちがフィルムを保管しているのは、美術館の所蔵品として持っているわけですが、その収集の際にひとつの契約として、美術館という建物の中での利用については認めてくださいとしています。それを外に持ち出す場合は、許諾が必要になります。
これは一般論としてですが、普通に映画が、劇場などで、フィルム投影で映写される形態以外で流通する場合、今回のUSTREAMもそうですが、大体の著作権者のスタンスは、「それについての権利は別の権利だから」というケースが多いです。
いま製作会社は、改めて権利処理を行い、音楽著作権、肖像権なども含めて契約を結び直して、「DVDを出してもいいですよ」「テレビ放映してもいいですよ」という形にすることが通例になっています。別のメディアへの変換、その映写、送信等、そういうことに対しては、著作権者はセンシティブになっているのが現状だと思います。
この問題は、明らかにメディア芸術の問題と関係があって、昔の週刊マンガ誌とかが図書館にあり、それを閲覧して読むということは可能だけれども、電子化された場合にどうなるのかという議論と同じですよね。
先ほどの、コンテンツ、キャリア、コンテクストに即せば、コンテンツ、キャリアが急速に変容しているわけですよね。そうすると、過去のものを復元し、あるいは保存して復元するときに、キャリアが大きく変化している時代の中で、コンテクストももちろん変わっているわけですが、過去のものを保存して活用するということに関して、新たなフレームがまだできていないということになりますか?
新たなフレームはできていないわけですね。著作権とは違う領域で、業界(間)との話がうまくできていないということもあるわけですね。国ないし公共的な事業としてのアーカイブの立場から、業界(間)との契約関係、責任分担、そういうことの整備から始めていく必要があることが明白なのですが、なかなか追い着いていないですね。
「購入」と「寄贈」と「寄託」
この話は、先ほどの「集める、残す、見せる」と関係があると思います。デジタルのリマスタリングにあたって、フィルムメーカー等と話合いが生じるのはわかります。しかし、「集める」というところがよくわからない。映画会社だけじゃなく、飯田さんの場合、個人からの寄贈ですよね。例えば、おじいちゃんが撮っていた映画をフィルムセンターに寄贈したいというような場合とか、何かその「集める」に関して、持ち主の側にいろいろバリエーションがあったり、さまざまな場合があるわけですね。それをどう考えていくのかということじゃないですか?
「集める」ことに関しては、いまの藤幡さんの観点に即していえば、物の譲渡を受けることについては、法律的には著作権には関わらないことなので、これを我々が受けることについては、著作権と抵触しないんです。持っているものから複製を作るとか、それを映写にかける場合に、著作権が係わってくる。別の観点では、私たちがフィルムを集める場合、対価を払って行う「購入」と、譲渡してもらうという「寄贈」、そして制度的には多く運用していませんけれども所有権を持たない「寄託」という、3パターンでフィルムを保護しています。これからもますます膨大に、世の中にすでにあるもの、これからも生まれてくるもの、それらをアーカイブとして集めていくわけですが、どういう制度設計が良いのかというのは、まだまだ課題です。
映画をメディア芸術と呼ぶかどうかはともかくとして、メディア表象という、ある種の文化媒体の中で、最も歴史が長く、深いわけです。20世紀を通じて最も影響力を持った媒体でもあります。ですから、映画について話しているのは、今後ほかのメディア芸術にも、同じ問題が起こってくるということがあるだろうということからでもあります。
記録と作品とメディアの新たな関係性
大変面白い話をありがとうございました。『紅葉狩』等は、オリジナルの歌舞伎の記録でもあるわけですが、いま逆にむしろシネマ歌舞伎みたいな形で、映画としての歌舞伎みたいなことに変わりつつある側面もあると思われます。
どうしても役者は30年も50年も生きられないわけで、その人も死んでしまうという中で考えると、そもそもオリジナルとはどういう意味を持つのでしょうか? メディア芸術ではないかもしれませんが、記録してのメディアだったものが、表現のメディアになるという可能性もあるのではないかと思いました。
まったくその通りだと思います。演劇を記録したビデオが売られているときに、それは何だということですね。演劇? DVDコンテンツ? あるいはフィルムで撮っているのだから映画? わからないですよね。
美術でも、アート・ドキュメントといいますが、イベントが終わったら消えてしまう作品の記録ですね、すると今度はドキュメントとして残されたものが作品のようにもなってくる。いろいろな状況が絡んでいると思うし、メディアの変化も当然あります。表現者側の変化もあるわけです。だからメディア芸術ということばを広くとらえると、本当に何でも入ってくるとは思います。どこかで線引きができるのかというその仕方を、メディア芸術オープントークでは議論してきたわけです。
文化庁メディア芸術祭の枠組みでは、4つの分野が置かれています。その間で分野をお互いにつなげるなんていうことはまだないですね。おそらくそういう時期が、もうすこしするとやってくるのではないでしょうか? 考えてみれば、僕なんか、実際に絵を見るよりも、絵を撮った映画みたいなのに感動して、そこから絵を好きになったりするわけですが、メディアを通して何か、フレキシビリティが高い関係性ができてきているのではないでしょうか。「どうすれば良い」という話ではないと思います。ひとつのものから複数のメディアに変わっていく。マンガはおそらく典型的な増殖をするメディアですね。マンガには原作があって、映画やテレビ、何でも新しいものを生み出していくみたいな、そういう時代がやってきているなと感じます。
先ほど話した『紅葉狩』が2009年に重要文化財になったわけです。しかし、文化財保護法の中には、映画は文化財として明記されていない。どういう定義で映画が文化財になったかというと、あくまでも歴史資料です。つまり資料性として認められたということ。もちろん、私たちは「資料性だけじゃない」といいたいわけです。文化財に指定されて良かったなとは思いますが、そういうカテゴリーになっているということが現実ではあります。
また『紅葉狩』に関する話で、これは1899年に撮影されたのですが、9代目の市川団十郎と5代目の尾上菊五郎が撮られています。しかし、これはすぐには一般的に公開をされなかった。
初めて一般公開されたのは、尾上菊五郎が亡くなった後です。1903年に亡くなった後、尾上菊五郎の葬儀映像とあわせて『紅葉狩』が公開された。すると『紅葉狩』が公開されたときに普通の人が見た印象は追悼だったのです。つまり、映画は生まれた当初から追悼のメディアとしてあったということにもなります。
作品の同一性、経験の同一性
アーカイブに関してですが、コンシューマー・ジェネレイテッド・メディア(CGM)のような観点から考えると、今後ますます、オリジナルとコピーに関わる問題がでてくると思います。作品の同一性がどこに存在するのか? オリジナルとは何か、また、複数の消費者によって作られたメディアの中の、アートの同一性、アイデンティティーはどこにあると考えるべきなのか、ご意見を伺えればと思います。
本質的な問題ですね。分野によってかなり違うとは思いますが、文学作品の場合は、たとえば「Kindle」などの電子的なリーダーで漱石の作品を読んだからといって、作品が何か違うものになるわけではないという意味での同一性はもちろんあります。文学作品の場合はイデアルな同一性であって、作品は現実の物質的な支持体と結合していなくてもよいわけです。
やはり問題は音楽や映像ですね。そういうものが電子的な記録を通して複製された場合に、同一性はどこにあるのかということが問題になってきます。
例えば、シネマ歌舞伎で「歌舞伎を見た」とはいえるけれど、「歌舞伎に行った」と言えば嘘をついたことになりますね。なぜかというと歌舞伎の場合、やはりオリジナルはパフォーマンスだという考え方が共有されているからです。「行く」という行為は、現場に身体を置く、臨場するということだからです。
でも見ているものは同じじゃないかと反論されるかもしれない。シネマ歌舞伎ではできず、歌舞伎に行かないとできないことは何かというと、それはお弁当を食べられるということです。これはとても大事なことです。半分は冗談ですが、でも半分は真面目な話で、つまりその場に身体があるからお弁当が食べられるわけですね。
過去の映画を映画館で見るというのは、ある意味でオリジナルに近い体験かもしれないけれど、その1950年代、60年代の映画を実際そういう形で見られることは極めて少ないわけじゃないですか。すると可能なのは、フィルム・アーカイブで見るか、レンタルしてという経験になるわけですよね。それは、映画のもうひとつの経験という感じもしますよね。
現代映画の場合、何が本物の経験かという問題が面白い形で出てきますよね。「『アバター』観た」と学生にいっても、「先生、それ3Dじゃないと観たことになりません」とか言われたりします。逆に学生の頃の映画体験だと、スーパーマーケットの2階みたいな、時々床にネズミが走るような名画座で、朝から晩まで洋画を3本立て続けに観たりとかしましたけど、今同じ作品を快適なシネコンで観たり、自宅でDVDで観ても、作品として同一であることは確かなんですが、経験はあまりにも違うということですね。
オリジナル・ネガというアルゴリズム
映画のフィルムの多くは、生まれたときから、ネガとポジというふたつのものがあって成立する世界なわけです。カメラの中に入っているのは、多くの場合、基本的にネガ・フィルム。しかし私たちが見るのは、ポジ像ですね。だから、オリジナル・ネガといった場合に、ネガがあることは大変重要ですが、私たちが見ているのはポジで写された像を見ている。ということは、オリジナルは見ていない。オリジナルは見てないけれど、ポジを作るためにネガが存在しているので、そのときに必要なのは、オリジナル・ネガという「モノ」と同時に、設計図です。「このようにネガが焼かれるべきだ」という設計図が必要なのです。そこの設計図の部分が、現像所のある種の技術的な情報であったりして、そういう情報も残されなければ、ポジ像を見ることができなくなってしまう。
また、アーキビストが映画を復元しようとするには、潜在的な可能性がたくさんあります。例えば、ネガそのものの忠実なコピーをつくることだったり、できるだけ最初に公開したときに近い内容を復元するとか、再上映されたときに近い内容にするとか、本来監督が意図した内容に作り変えるとか、現在の観客にとって非常になじみやすく作り変えるとか、いろいろな可能性があるわけです。
仮に1955年のネガがあり、それをいま蘇らせるには、当時の現像システムは現在と全然違うし、フィルムそのものも違う。まったく違っているものを使って、できる限りオリジナルに近い状態にするわけですが、この状態を私たちはオリジナルとは呼ばず、オーセンティシティ(真正性)と呼ぶわけです。つまり、オリジナルに限りなく近い状態で再現をするということ、これが少なくともアーカイブが考える復元の倫理です。簡単にいえば、「修復、復元する人間による恣意的な判断をできる限り避ける」ことがボトムラインだと思っています。
ZKM(ドイツ、カールスルーエにある現代美術やメディアアートの研究・展示施設)のディレクター、ピーター・ヴァイベルが、「ヴァーチャルミュージアム」というテーマのシンポジウムで話したことを思い出しました。
「ヴァーチャルミュージアムという概念に沿って考えると、そこは物を集める場所ではない。物を集めない代わりにアルゴリズムを集める」場所だといっていました。
そして、「アルゴリズムと、それをサポートするシステムがあれば、いつでもそれは人間の感覚でとらえるものに変換できる」と。
とちぎさんのいった「ネガは設計図だ」という、ネガ+ハードウェアで、私たちが見られる映画になるという指摘は、印刷技術以降、新しく生まれてきたメディアの問題と意外と共通なところです。根源的なことだと思いました。
映画も戦略的に「文化財」と言うことによって、問題もあるんだけれども、それが有効に機能する部分もある。メディア芸術というのも、ある意味では同じではないかと思います。メディア芸術という概念そのものに、さまざまな問題があることは十分わかっている。けれども、それを有効に機能させるということはどういうことか、ということを考えているような気がします。そのときにとても重要なことは、今日も話に出た、生成のプロセスや最終的な作品だけがメディア芸術という形で考えられるべきではなくて、それをめぐる、ある生成のプロセス全体、キャリアとかコンテクストという話がありましたが、そういうものを含めた全体の中でこの問題を考えなくてはいけないということは今日の新たな視点だったような気がいたします。