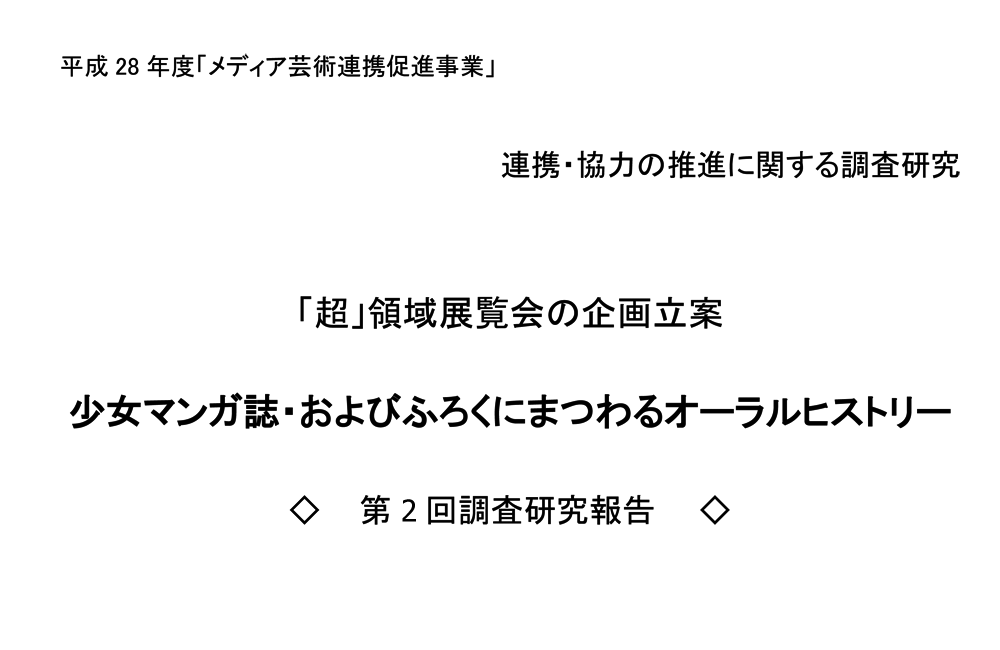
1.調査研究の目的
「超」領域展覧会の研究目的は、マンガ、アニメ、ゲーム、メディアアートの4領域の史資料やコンテンツ等の「共同利活用を実現する」ため、特に史資料やコンテンツの利活用のモデル(案)として、連携展覧会(領域横断・資源シェア型)が効果的であることを実証する「モデル展覧会(案)」の立案を行うことにあります。
昨年度事業として実施した「少女雑誌ふろくの歴史・展示」研究では、戦前から刊行されている代表的な少女マンガ雜誌や、戦後刊行され現在も継続し、60年の歴史を持つ集英社『りぼん』とその「ふろく」に着目して、それらが果たしてきた社会的な意義、読者への影響などを読み解く「展覧会」を開催するための準備作業を行いました。
今年度はこの成果を基に、少女マンガ誌史上最高発行部数である255万部を達成した、1990年代の『りぼん』編集者や関係者への聞き取り調査を行い、オーラルヒストリーとしてのとりまとめを行っています。昨年と今年の研究成果は、2016年12月から2017年2月まで京都国際マンガミュージアムで開催され、2017年6月まで明治大学米沢嘉博記念図書館にて巡回している「LOVE♥りぼん♥FUROKU 250万乙女集合!りぼんのふろく展」の展示内容にも活用されています。
2.調査結果の公開
聞き取り調査は以下の方々へ実施しました。
| りぼん編集長 | 冨重 実也氏 |
|---|---|
| りぼん副編集長 | 後藤 貴子氏 |
| 元りぼん編集者/児童書編集部 編集長 | 江本 香里氏 |
| 元りぼん編集者(現在は集英社を退職) | 岩本 暢人氏 |
| 元りぼん編集者/学芸編集部企画出版 編集長 | 小池 正夫氏 |
| 元りぼん編集者(現在は集英社を退職) | 宇都宮 紘子氏 |
貴重な研究成果が得られたため、聞き取り調査の記録を公表することとしました。公表は、とりまとめが完了した順に実施していく予定です。
調査記録の公開に際して
1955年の創刊以来、日本の少女マンガ誌およびふろく文化を牽引してきた一つに『りぼん』があります。本誌は特に1980年代後半から1990年代前半にかけては発行部数が上がり1994年には少女マンガ誌史上最高発行部数となる255万部を達成しました。その記録はいまだに破られていません。当時の『りぼん』では、読者のことを「250万乙女」と呼び、作品のキャッチフレーズなどに採用していました。
さて、かつての「250万乙女」は今や30代。仕事に子育てに活躍している女性が主です。なぜ今のアラサー女子がこんなにもパワフルなのか?そのパワーの根源に『りぼん』は存在するのではないでしょうか?250万という膨大な数字が現在の女性たちとリンクしないはずはありません。『りぼん』は読者に明日を前向きに切り開く様々な術を教えてくれました。もちろん、この世代や『りぼん』に限ったことではありませんが、今回はこの250万乙女の原風景はいかにして作られたかに迫りたいと思いました。
今回のオーラルヒストリーで対象としたのは、80年代から現在までを対象に、『りぼん』を作った編集者たちの話です。特に、ふろくについては、70〜80年代までの研究蓄積は先行研究本や展覧会で語られることはありましたが、それ以降の年代については、ほとんど語られることが少ない分野になります。
なお、このオーラルヒストリーの内容は、京都国際マンガミュージアムで2016年12月から2017年2月まで開催され、2017年6月まで明治大学米沢嘉博記念図書館で巡回中の「LOVE♥りぼん♥FUROKU 250万乙女集合!りぼんのふろく展」の内容の参考にもさせていただきました。オーラルヒストリーと合わせてお楽しみいただければ幸いです。
倉持佳代子
京都国際マンガミュージアム
京都精華大学国際マンガ研究センター
調査記録2 小池正夫氏(元りぼん編集者/学芸編集部企画出版 編集長)
第2回は、最も『りぼん』の発行部数が上昇した90年代前半において数多くの名作を支えた編集者・小池正夫さんにお話をうかがいます。小池さんは「天使なんかじゃない」など当時の『りぼん』を代表するヒット作を担当し、一方で多数の新人マンガ家の育成にも心を砕きました。当時、マンガ家たちとどんなやりとりがあったのか、編集部の空気、『りぼん』を離れ『週刊少年ジャンプ』を経た後、2001年に『りぼん』に戻ってきた時の話......多岐に渡る話題から、『りぼん』のスピリット、『りぼん』のメンタルとは一体何かについてを探ることができました。
少女マンガ誌・およびふろくにまつわるオーラルヒストリー 第二弾
実施日:2016年10月18日(火)
- 対象者
- ■小池正夫氏(元りぼん編集者/学芸編集部企画出版 編集長)1990年集英社入社
りぼん在籍期間:1990年5月〜1994年9月/2001年10月〜2012年6月 - インタビュア
- 倉持佳代子、ヤマダトモコ
- 構成
- 倉持佳代子
■『りぼん』に着任、担当したマンガ家
―小池さんには、これまでも京都国際マンガミュージアムの展示やイベントなどでお世話になっていて、お会いする機会も多かったですが、こうして改めてお話をうかがうのは初めてですね。よろしくお願い致します。まず、小池さんが『りぼん』に来て最初にしたお仕事を教えてください。
<小池>
新入社員はみんなそうだと思いますが、読者ページをやりましたね。『りぼん』本誌ではなくて、『りぼんオリジナル』という隔月の増刊があり、そこの読者ページをやって、あとは口絵のプレゼントとかを担当しました。しかし、割とすぐに担当を持たせてもらってそれが沢田とろ先生と森本里菜先生と柊あおい先生、新田明未先生だったんですね。
―いきなり4人同時ですか?
<小池>
そうですね。森本里菜先生と新田明未先生は『りぼんオリジナル』の方で載ることが多かったんで、連載としては柊先生と沢田先生の2本だったんですけど、すぐに担当するマンガ家さんの数は増えました。
―どういうふうに担当って割り振られるものなのでしょうか?例えば、新人には割合、締め切りを守ってくれるマンガ家を割り当てるとか?
<小池>
当時はそんなことは全然わからなかったですが、僕自身副編集長の立場になってわかったのは、まずは性格をみますね。新入社員の性格を見て、そのキャラクターと合いそうなマンガ家さんを担当させるという感じだったと思います。新入社員のときは、夏くらいまで僕はスーツで来ていたんですよ。銀行員みたいって同僚からもからかわれたし、真面目な感じだったらしいので、割り当てられた先生もそういった真面目な方が多かった。上司が僕の性格を見て、合うかどうかを見て決めたんだと思います。
―なるほど。相性なんですね。
<小池>
はい。年2回ぐらいの社内の異動のタイミングとか、そろそろ担当替えしたほうがいいかもね、いうような時があると、それぞれの仕事ぶりを見て、担当を振り分けていたと思います。
―先ほど、担当するマンガ家が増えていったとおっしゃっていましたが、具体的にはどんなペースで増えましたか?
<小池>
4人しか担当していない時期はすごく短いです。当時、「りぼん漫画スクール」はものすごい量の投稿があり、毎月のようにデビューが決まっていましたが、投稿作品から担当した新人さんはデビューしたら連載するまで担当するのが常でした。新人マンガ家の担当がどんどん増えていった形です。言ってしまえば、1ヶ月か2ヶ月ごとに1人ずつ増えていくみたいな感じでしたね。担当の決め方でいうと、よく覚えているのは、茶畑るり先生というギャグ四コマのマンガ家さんがいますが、ペンネームからしても察することができるように出身が静岡県の沼津。「小池、静岡出身だから担当やれば」みたいな。そういう決め方だったんです(笑)。
―割とざっくりとした決め方!(笑)。しかし、共通の話題があることは重要ですね。
一人の編集者で最大何人ぐらい担当されるものなのでしょうか?
<小池>
30〜40人は普通にもっていますよね。デビュー前の漫画スクールでの投稿者まで含めたらそれ位の数になります。デビュー前の子をだいたい20人ぐらい担当していたので、新人ノートというか担当ノートみたいなのを作っていました。多いと思われるかもしれないけど、これが普通でした。
―30〜40人くらいを担当するって、『りぼん』に限らずですか?
<小池>
限らないと思いますよ。『マーガレット』とか『別冊マーガレット』などもそういった状態だと思います。
―たくさんのマンガ家さんを担当するものなのですね。その中でも思い出深い作品などをうかがえますでしょうか?
<小池>
そうですね。やっぱり矢沢あい先生ですかね。
―小池さんは「天使なんかじゃない」(以下「天ない」)の完全版の巻末マンガにも登場していますよね。ぜひ、その矢沢先生とのお話を。
<小池>
私が入社2年目に、矢沢先生の「マリンブルーの風に抱かれて」という連載が終わり、読み切りを描かれたんですね。高校野球をテーマにしたお話。
―「うすべにの嵐」「空を仰ぐ花」。1991年発表の作品ですね。
<小池>
そうです。この2つが前後編だったんですが、前編の「うすべにの嵐」を前の担当者、後に編集長になる中森美方さんがやって、次からはお前が担当だと言われていたんです。「空を仰ぐ花」が終わって新連載をやりましょうという打ち合わせを喫茶店でしたんですが、矢沢先生から「案が2つある」と言われました。一つは新設高校を舞台にした生徒会もの、もう一つはロカビリーバンドの話と。「小池さんどっちがいいと思いますか?」と言われて、10秒ぐらい考えて「生徒会ものにしましょう」と答えたんです。
―それで「天ない」が始まったわけですね。そしてもう一つは「NANA」!?
<小池>
矢沢先生はこのことをすっかり忘れていてみたいですが、後々、「ああそうやった。バンドもんやりたかったんや。「NANA」の始まりはここにあったのかあ。でも、それにしてもロカビリーって!(笑)」みたいな話をしたことがあります。僕は集英社に入る前はマンガを全然読んでいなかったんです。読んだことがあるのは、姉の部屋にあった「ベルサイユのばら」と「オルフェウスの窓」と「エロイカより愛を込めて」ぐらい。その代わり、映画は死ぬほど見ていて、お芝居とかもよく見ていました。もともと僕は活字の本が作りたくて集英社に入ったので、マンガって全然わからなかった。マンガって何?ということを一から考えないとこの世界に入っていけなかったレベルなので、そういう観点でいくと、その時の僕の中では、マンガは音が出ないからバンドものは難しいよね、という気持ちがあったんです。もちろんその頃、すでにバンドもののマンガはいっぱいあったし、力のあるマンガ家さんなら描けると思いましたが、当時の矢沢先生がそれをやるイメージがわかなかったので、生徒会ものというように言った記憶があります。
―なるほど。「NANA」的な作品がもしかしたら「天ない」より先に生まれていたかもしれない。だけど、「天ない」以降のキャリアがあったからこそ描けた世界だったのではと思いますし、温めてよかったかもしれません。
<小池>
そうかもしれませんね。それで生徒会ものって決まった時に「取材に行きたいから高校探してください」と言われたので、あちこち探して......というところから始めました。タイトルロゴもスーシャという書体をもとにして......と、そういうのも一から作った感じでしたね。
―「天ない」は始まるときから最終回までの構想はあったんですか?
<小池>
いやなかったと思いますよ。
―設定だけは決まっていて、連載していくうちに話が決まっていった感じですかね?
<小池>
そうですね。「天ない」のラストは決めないで描かれていたと思います。矢沢先生の中では密かに決まっていたのかもしれないですけど。「ラストどうなるんですかね?」みたいな打ち合わせはしなかったですね。
―「天ない」はまさに250万部時代を代表する作品ですが、小池さんとしてはこれを絶対にヒットさせるとか、計算してやっていた部分がありましたか?
<小池>
どうでしょうね。それまでの矢沢先生の作品は、「マリンブルーの風に抱かれて」もそうですが、『りぼん』の中で5〜6番手ぐらいの立ち位置だったと思います。しかし、どう考えても才能があると編集部全員が思っていた。だから僕が何かを計算してやったとかじゃなく、「天ない」で矢沢先生自ら殻を破ったのではないでしょうか。当てようと思って描いたとおっしゃっていましたし。「次の連載の主人公はクラスの真ん中にいるような人気者の子にするんだ」て言って始めたのが「天ない」でした。僕はとにかくこの作品に出てくるキャラクターたちが大好きで、褒めることしかしなかったです。嘘やおべんちゃらはマンガ家さんに伝わっちゃうんですけど、僕は本気で良いと思っていたし、本気で次のネームを楽しみにしていましたね。
毎回、原稿をいただいた後、次の打ち合わせをして「次はこうなってこういう感じですかね」みたいな話もしていましたが、その後、ネームで全然違うものが出てくることが多く、それがすごく面白い。作品やキャラクターが自分でどんどん動いていく、そうした状態になるのが「天ない」は早かった。矢沢先生自身がのっていたし、それがキャラクターの魅力につながっていきました。絵もそれにともなって変わっていきましたね。
―連載中、どんどん変わっていった印象があります。
<小池>
「天ない」で矢沢先生の絵柄は大きく変化しましたよね。そういう意味では矢沢先生が化けていく様を一番近くで見られたということは貴重な経験だったと思います。周りの先輩からは、「仕掛け方がうまいなお前」とか言われましたけど、僕には全然仕掛けた意識はなく、前のめりになっていく矢沢先生に一緒に乗っていったぐらいの感じです。
―「天ない」の終盤ぐらいからはデジタルを導入されていたことも印象深いです。
<小池>
そうですよね。デジタル導入したマンガ家さんの先駆けでしたね。デジタルだけではなく、いろいろな事を試していた時期だと思うんですよ。写植はもっと大きくしてくれとか結構言われたな。
―写植の大きさまで指示する先生は珍しいほうですか?
<小池>
たまにいます。しかし、はっきり言ってしまうと、そこまでお気になさらなくてもいいんじゃ......みたいな場合が多い(笑)。しかし、矢沢先生の場合は「ここをこう読ませたいから、もっと前に出したいんだ」という意図が伝わってきたので、僕としては、「わかりました。もっと大きくします!」という感じでやっていましたね。
―新人育成にも心を尽くされていたのではと思いますが、才能を見出して育てていく上で、作品のどういうところを見ていましたか?
<小池>
新入社員の頃はそういうのは分からないので、単純に勘なんですよ。こういうのがいい!など理論は全然なかった。管理職になって現場を離れてからは、スタッフには理論しか言えないので、スタッフと話す時にはまず理論から入って、そこからどうはみ出していくか、そのはみ出し方が作家さんの才能だよ、みたいな話をしますが、そんなこと全然分からない新人の頃は、勘が大きいです。僕が投稿時代から担当したマンガ家さんだと、高須賀由枝先生がいますが、高須賀先生は、一瞬見て「すごい絵がうまい」と思い、この絵があればオーケーだなと思いました。デビュー作なんかはすごくシンプルな話だったんだけど、絵が新しい感じがして良いから、絶対ものになると思ったんです。
―高須賀先生は読者の感覚でも「新しい」と感じたマンガ家さんの一人でしたね。
新人マンガ家たちにはどんなアドバイスをされていたとか、心がけていたことなどはありますか?
<小池>
全ての打ち合わせって、打ち合わせすることが目的ではなく、作品がよくなることが目的なので、本当は打ち合わせなんかしないのが一番いいんですよ。マンガ家さんの頭の中にあるものがそのまま出てきて、それが最高に面白ければそれが一番いいんです。だけどなぜ打ち合わせが必要かというと、マンガ家さんの頭の中にあるものってまだ作品として形をなしていないことが多い。それにフレームを与えるというか、形にするためにきっかけを与えるのが打ち合わせだと思っています。そうした中で、このマンガ家さんの良さはなんだろうとかは常に考えていましたね。この人の才能の肝はどこにあるかというようなことはいつも気にしていました。
僕が担当するマンガ家さんは純愛ものを描く方が多くて、逆に「赤ずきんチャチャ」や「ちびまる子ちゃん」などのコメディ系は2年先輩のI さんが担当することが多く、入ってくる新人さんもそういう人が自然と割り振られるようになっていた気がします。
―ラブストーリーは小池さんね、といった形に振り分けられていたこともあったということですね。他に新人時代から担当したマンガ家はどんなマンガ家がいますか?新人でなくてもほかに担当した方は?
<小池>
柊あおい先生には、少女マンガの叙情性みたいなことを教えていただきました。あいざわ遥先生もぐんぐん伸びていきましたね。北條知佳先生や片桐澪先生との仕事は楽しかったです。「天ない」が終わった後は矢沢あい先生の担当が別の編集者になり、池野恋先生の担当になりました。「ナースエンジェルりりかSOS」の第1話は僕が打ち合わせしたんですよ。
―アニメ化を前提として始まった作品でしたよね。原案・原作が秋元康先生で。
<小池>
そうですね。アイデアのプロットを秋元先生からいただき「好きにやっていいですよ」と言われて、それを池野先生にお渡しし、1話目のネームができたんです。そこで僕は異動になってしまいました。編集長が僕の異動を知らないわけないから、矢沢先生の担当が交代になった理由はそれででしょうね。「ナースエンジェル」に関しては、1話目ぐらいで担当が変わっても問題ないからという感じだったのだと思います。
■『りぼん』の読者について
―小池さんは読者のニーズとか『りぼん』の読者はきっとこういうのが読みたいだろうな、みたいなことは、どれぐらい意識されていましたか。
<小池>
全くしていないです。わからないですもん。小学生の女の子の気持ちなんて(笑)。ただ、マンガってキャラクターだと思うんです。キャラクターの感情を描くのが少女マンガだと思うので、まずはキャラクターの感情をしっかり描いて、その感情が読者に届く強さがあれば受けるなと。それは入社して2年目ぐらいで感じていました。そういう意味では読者の方じゃなくて、マンガ家さんの方を見ていますよね。このマンガ家さんはどんな感情を描く人なのか?どんなキャラクターを作ったら活き活きとした感情を描けるのか、ということを意識していました。マンガ家さんのほうが読者と近いところの感性を持っているので、マンガ家さんが読者のニーズとかを自然と汲み取ってくるし、編集者はそれが面白いか面白くないか、そして、どうやったらもっと面白くなるかというところの手助けだけだと思います。
―読者に向けて受けて作るとか、そういったことはマンガ家さんは意識されていたかもしれないけど、編集者側は意識していなかった。実はこれまでオーラルヒストリーでお聞きした編集者も同じことをおっしゃっていたんですよね。
<小池>
そうでしょうね。読者だけを見たらだめなんです、本当は。有名な話でマクドナルドとかの店頭でアンケート取ると、「ヘルシーなメニューがほしい」とか「もっと野菜をいっぱい食べたい」という風なアンケート結果になるけど、いざヘルシーなメニューを出しても売れないと。読者像とか読者のアンケートとかいうのはあくまでデータであって、それを超えていくものをどんどん作らないと。読者の方を向いてばかりだといい作品はできないです。
―一方で、読者の声にも真摯に対応していたと思います。当時は電話対応に追われることが多かったと他の編集者さんからもお聞きしましたが、印象的な読者の声や読者との思い出などはありますか?
<小池>
りぼんフェスタとか、イベントはだいたい大都市中心でやることになるので、「なんでうちの近くではやってくれないの?」って泣きながら電話かけてきて、3時間ぐらい相手をしたことなど、そういうのはよくありましたよ。あとは、「天ない」で翠と晃が初めて結ばれる、いやはっきりと描かれてないですが、結ばれるようなシチュエーションになった時、電話で「二人はやったんですか?」というのが何本もかかってきました。
―(笑)。それは小学生からかかってきたんですか?
<小池>
小学生。後ろできゃっきゃ言っている友達と。きっと「電話かけて聞いちゃおうよ」みたいなノリでしょうね。
―ちなみに、それはどうやって答えたんですか?
<小池>
「ご想像にお任せします」というふうに答えるしかないですよね(笑)。「作品の中に描いてあることが全てなので」と言っていましたね。僕らの年代が小学生の頃は、編集部に電話をかけるなんて発想すらなかったけど、当時は電話かけるというハードルは低くなっていた頃だと思うので、読者の電話はすごく多かったですね。冨重くん(冨重実也氏)も話していたと思いますが、「応募者全員サービス」が届かないとか、そういうことはすごく多かったです。
―そもそも「応募者全員大サービス」でテレフォンカードとかがあった時代ですものね。テレカを使って、友達といたずら心もあって電話していたんだろうなと思います。
<小池>
かわいいものです。小学生の電話ですから。大概、電話は新人がとるものなんですよ。「応募者全員サービス」がまだ来ないっていう電話は1日に20〜30本は受けていました。それをちゃんとメモして発送していましたね。1日の4分の1ぐらいはそうした対応でつぶれていたかもしれません。特に「応募者全員サービス」が始まって1週間後、2週間後ぐらいからそういう時期が始まるんですよ。その時期がくると、「また電話とらなきゃいけないな」という感じではありました。
■『りぼん』編集者の仕事
―当時は特別忙しかったといった印象はありますか?
<小池>
そんな印象はあんまりないですね。ウェブ関連の仕事もなかったですし、バイトさんもいっぱい来てくれていました。ものすごく忙しくなるということは、連載を抱え、イベントの担当になり、自分の担当作品がメディア化されるとか、色んなことが重ならない限りはなかった記憶があります。
―当時の編集者の1日のルーティンみたいなのってどんな感じでしたか?
一日のルーティンは、締め切りが近い、近くない時期でも変わりますが、だいたい午前11時から11時半ぐらいに出社、事務的なことをやります。午後2時ぐらいにお昼を食べに出て、夜は8時から9時くらいまで、遅い時は夜中までという感じでしたね。ネームを読んだり、電話対応したり、口絵の打ち合わせだったり、記事の打ち合わせだったり、何かしらやることはあって、マンガ家さんとの打ち合わせはだいたい夜です。読者から夕方にたくさんかかってくる電話応対が終わると、6時〜7時ぐらいからマンガ家さんと打ち合わせ、といった感じでしたね。打ち合わせも5分で終わることもあれば、1時間、2時間かかることもあります。
―マンガ家さんとの打ち合わせは電話が主ですか?
<小池>
電話ですね。マンガ家さんも学生だったり、OLだったりが多くて、打ち合わせは学校や仕事が終わってからになりますし、地方在住の方も多いですから。
でも昼間に動けて、東京近郊の方とは直接会って打ち合わせをしていました。
―高校生でデビューするマンガ家さんも多かったですものね。そういうマンガ家さんって学校が終わり帰って、描きつつ電話で打ち合わせして、みたいなそういう生活をしていたんですよね。
<小池>
そうですね。当時はマンガを描いていることを親に知られたくないとか、親からマンガをやめなさいと言われる子がすごく多かったので、こっそり夜中に描く子とか授業中にネーム描いているという子が多かったと思います。打ち合わせができるのは必然的に夜になりますよね。
―反対する親から電話を取り次いでもらえなかったなどは?
<小池>
それはさすがになかった。有望だという子には会いに行くんです。
―あぁ、親御さんにご挨拶に行くんですね!
<小池>
はい。例えば、茶畑るり先生のご両親にはすぐに会いに行きました。「嫁にください」位の勢いで正座して。当時、茶畑先生は中学生でしたが、「学業とかには絶対支障がないようにしますので」というふうにご挨拶しに行きました。「怪しいものではありません。しっかりしている会社です」ということを親御さんに説明しに行くことは何回かありましたね。それで絶対ダメって言われることはなかったです。自然とネームを送ってくれなくなっちゃう子とかは結構いましたが、面と向かって拒否されたということはないです。
―中学生ですから親も心配でしょうし、そういう形で挨拶に来てくれると安心しますよね。それにしても四コマのマンガ家さんって、当時は中学生デビューが多かったですよね。
田辺真由美先生や津山ちなみ先生もそうですね。
<小池>
ストーリーマンガより四コマの方がハードル低いと思って、描き始めるマンガ家さんが多いからかもしれませんね。
―作風もシュールなものが多かった気がします。茶畑先生の「へそで茶をわかす」も始まった時、当時の私には笑いのセンスが高度すぎて変な四コマ始まったなーと思っていたんですが、何回か読んでいたら面白くなってきて(笑)。当時なぜあんなシュールな四コママンガが集まったんでしょうか?
<小池>
なんででしょうね。スケールメリットじゃないですか。雑誌が売れていたし。『りぼん』のすごいところは、岡田あーみん先生とさくらももこ先生がいることですよ。それは大きいです。
―なるほど。『りぼん』なら私もいける!みたいな意識が。
<小池>
これでもいいんだみたいな意識があったと思います。
―笑いのセンスもそうだし、絵柄に対するハードルもこの二人の存在が基準となりますからね。絵が下手でもいける!みたいに思った読者は多かったかもしれません。実際にはこの二人、めちゃくちゃ絵も上手いですし、なろうと思ってなれる存在ではないんですけどね。しかし、当時の読者にとって、この二人がいる雑誌なら私の作品も受け入れてくれるっていう意識は確かにあったと思います。そういう雰囲気は『りぼん』の一つの色でしたね。
<小池>
雑誌のカラーって、女性誌とかはわからないですが、マンガ誌の場合は編集者が作るものじゃないんですよね。マンガ家さんが作っていくものなので、編集者がエッジのきいたギャグをいっぱい載せようとか、そういう意識は一切なかったと思いますね。ただ、集まってきた投稿者、新人さんの中から才能をちゃんとピックアップできていれば自然に面白くなっていく。それがスケールメリット。当時の『りぼん』にはそれがありましたね。
―では、ギャグ枠は何本だけとか決まっていたわけでもなく?
<小池>
あんまりないですね。厳密にいえば、雑誌の基本の仕組はあって、この連載が終わったから、この枠にシリアスをはめようとかはありましたが、それほど厳密ではなかったです。特にギャグに関してはなかったと思います。
―面白い四コママンガが出てきたらどんどん増やしていこうぐらいの感じだったんですね。作風がかぶるような話を増やしちゃいけないとか、制約とかも特になかった。
<小池>
はい。なかったですね。ギャグが少ないからこういうのほしいよねとか、ファンタジーがないからほしいよね、みたいな話は雑誌だから当然しましたけど、ギャグ枠とかファンタジー枠みたいなものはなかったです。それよりは作家さん優先でした。この時期からこのマンガ家さんの新連載始めようとか、そろそろこのマンガ家さんは3回連載をやってもいいんじゃないとか、そういうことを考えることが中心ですね。
―当時、他誌はどれぐらい意識していましたか?『なかよし』とか『ちゃお』とか。
<小池>
全く意識してないです。
―読まれてもいなかった?
<小池>
なかったですね。気になる作品は読んでいましたけど。「美少女戦士セーラームーン」とか。しかし、他誌がこうだからこうするということは一切考えてなかったです。
―要は意識していたからじゃなく、「セーラームーン」は面白いから読んでいたということですか?それとも売れていたから?
<小池>
売れていたから、話題になっていたからですね。うちではこういうの作れないよねみたいな感じで読んでいました。別にライバル視していたとか、そういうことは全然ないです。
―『なかよし』でこういう作品が売れているから『りぼん』ではこうしようみたいなことはなく?
<小池>
そうです。だから武内直子先生とかCLAMP先生の作品って、『りぼん』の土壌からは出てこないし、無理に作ろうとしても絶対うまくいかない。『りぼん』は今いるマンガ家さんと、これから入ってくる新人さんの良さを伸ばすんだと。マンガ家さんの作家性で勝負するんだみたいな感じでした。これは『週刊少年ジャンプ』と『週刊少年マガジン』の違いでも同じだけど、コンセプトを外枠から作っていく講談社と作家性を重要視する集英社の違いです。
―集英社は作家、作品主義だと。
<小池>
そうですね。『なかよし』とは方向性が違うので、ライバルという感じではなかったです。
―では、他誌に「これはやられた!悔しい」みたいなものも特になく?
<小池>
全くないです。それは『りぼん』の方が売れていたからとか、王道だったからという意味ではなく、やり方が違うものと比較してもしょうがないと。当時の中森さんという編集長がおっしゃっていたのは、「『りぼん』のライバルは『なかよし』じゃないぞ。『りぼん』のライバルはディズニーランドや」と。『りぼん』を一冊買えば色んな作品、キャラクターがいて、ふろくもあって、様々な感動や楽しみを味わえるというようなものを目指していたんです。中森さんの頭の中ではアニメ化とか商品化とか、メディアミックス関連もそういう一部だったと思います。中森さんの話を聞いて、雑誌はエンターテインメントなんだ。ただマンガを作っているわけじゃなく、マンガという形式を借りたエンターテインメントを作っているんだと思っていました。
―江本さんのオーラルヒストリーの際も中森さんのその話はされていましたね。マンガの形式を借りたエンターテインメントを作っている、というのは当時の『りぼん』をまさに表す言葉ですね。
<小池>
中森さんの話でもう一つ印象的だったのは、悲しい話なんですけど、車の中に排気ガスを引き込んで心中した一家がいた。その車の中に『りぼん』が1冊残されていたと。女の子は死ぬ間際まで『りぼん』を読んでいたんじゃないか、と。結局その子は死んでしまったわけだけど、その中でも『りぼん』を開いている間は楽しい思いをしていたんじゃないかって。そういうものを作らなきゃいけないんだよ、と。そんな話をしんみりとしてくれました。
―中森さんのそうした雑誌に対する考え方に他の編集者も共鳴していた。
<小池>
当時、僕はマンガを全く読んでない状態で『りぼん』に来たので、さっきも言ったようにマンガとは何かをずっと考え続けていたところで中森さんに出会ったので、ウマがあったのかもしれません。中森さんも元々はマンガ畑の人じゃなくて、宮沢賢治の研究書で賞をとったり、自分でも詩を書かれているような文学気質の方だったんで、当時の編集部の空気と僕は合っていたのかなあ。他の編集者が共鳴していたかどうかはわかりませんが(笑)。
―当時、1ヶ月の間に『りぼん』を何回も読み返していましたよ。細かい読み物にいたるまで隅々と。例えば、「りぼん漫画スクール」の講評も、マンガ家になりたい子はもちろんですが、そうでない子も目を通していた感があります。文学気質な編集部と今お聞きしたので、そういうコーナーも読み物としての面白さみたいなのは追求していたんじゃないかなと思いましたが、それはどうでしたか?
<小池>
「りぼん漫画スクール」って投稿者個人の批評をするだけじゃなく、雑誌としてのマンガに対するスタンスが問われるので、「りぼん漫画スクール」を担当することは「お前が次のエースだぞ」と言われることと同じで、編集部の中心になってひっぱっていく人が指名されることが多かったんですね。新人作家を発掘する「りぼん漫画スクール」は雑誌を運営する上で生命線ですから、ものすごく重視していたことは確かです。
―「今日は特に辛口でいくぞ」みたいな宣言がされて、かなり厳しめの講評が載っていることもたくさんありました。例えば、矢沢あい先生の投稿時代を改めて見てみたら、一コマ載るカットだけでも「上手い」って分かる人には分かるんですが、講評はめちゃくちゃ厳しいことが書いてある。だから、次に同じ人が賞をとったりすると、「今度はすごく褒められている。よかった」と、いつの間にか応援していたこともありましたね。
<小池>
投稿者にもファンレターとかきていましたしね。当時は、デビュー作だけを集めたコミックスも出ていました。
―はい。「7つの〜」で始まるシリーズの単行本ですね。
新人のデビュー作だけ集めた単行本がシリーズとして続いていた。しかも売れていたんですよね。
<小池>
売れていましたね。それも一つの『りぼん』でデビューするステイタスになっていたんじゃないかな。
―ああ、やはりそうですか。それが売れたのも「りぼん漫画スクール」が熱かったからこそですね。
<小池>
投稿欄に載るのはカットと編集者が書いた簡単なあらすじ、批評だけですけど、作品は読んでなくてもファンがつくんですよね。さくらももこ先生と矢沢あい先生ってデビューが同じ年で、お互いに投稿時代から意識していて、お互いに「この人すごい!」って思っていたらしいです。同時期にデビューして、集英社のパーティーで会った時、「あなたが!」みたいな感じで抱き合ったっていう話があります。
―あの小さいカットや批評だけでその人のすごさが分かることもある。実は私(ヤマダ)の同級生に『りぼん』でデビューしてたマンガ家さんがいます。その頃、もうひとり、友達がマンガ家デビューしているんですが、二人とも投稿時代から「矢沢あいはすごい」って言っていたんですよね。私はその頃はさくらももこ先生のすごさはわかったけど、矢沢あい先生のすごさって本当にわからなくて、でも描く人には最初からわかるんだなと思いました。
<小池>
不思議ですよね。
―それは一体なんでしょうね。矢沢先生の魅力って小池さんはどこだと思っていますか?
<小池>
ありきたりな言い方になりますけど、感情の濃さじゃないですかね。例えば、人が人を好きになる。その思いが届けばいいけど、届かなかった時の、悲しみ、苦しみ、切なさ。そういうところまで含めて描き出せる。恋愛感情だけではなく、友情や家族の間の感情も含めて。光が眩ければ、その分闇も濃い。逆に闇の濃さを捉えられれば、より光は眩く見えるじゃないですか。そういう感じでしょうか、矢沢先生は。キャラクターの感情のそういう部分をマンガという形式でうまく表現できる文体を、始めから持っていた気はします。
―そういえば、私(ヤマダ)のそのマンガ家の友達は「矢沢先生は普通のお話を面白く描けるのがすごい」って言っていました!高校生ぐらいの子って変わったものを描きたいって思うだろうし、若い時から普通のお話を面白く描ける作家って少ないんだと思います。
<小池>
そのとおりだと思います。マンガというものの捉え方が矢沢先生は、他のマンガ家さんとはちょっと違う気がしますね。要するにマンガというものは感情でしょ、という。感情を描くんだったら、正統も異端もないよねって。食パンくわえて遅刻遅刻って言って、ドンってぶつかった子が転校生として入ってきて......といった話をどう面白く描けるかというのがマンガ家の才能ですよね、みたいな話はよくしていました。
―『週刊少年ジャンプ』はアンケート至上主義で有名ですが、『りぼん』で人気作というのはどういうふうに測っていましたか?。
<小池>
『ジャンプ』と一緒でアンケートです。ファンレターの数とかでもわかるかもしれませんが、完全にアンケートです。山のようにはがきが来て、それこそ毎月10万枚とかきましたから、それを基にしたアンケートですね。
―『りぼん』はふろくで人気ぶりとか雑誌が推している作品がうかがえました。アイドル4人トランプとか。カレンダーは1月と12月が花形だったとかそういうのを聞いたこともあります。ふろく一つとっても自分の人気や立ち位置が目に見えてわかるわけなので、シビアな場でもありますよね。
<小池>
トランプはベスト4とかでしたが、カレンダーはそこまで区別なかったですよ。編集部の側からは競争心をあおっていたかとかはないですね。
―確かに競争しあっているとかギスギスした感じは『りぼん』のマンガ家さんにはない感じがしました。コミックスの欄外とかあとがきなどに、作家同士の交流みたいなのが書かれていることが多くて、読者もそれを見るのが嬉しかった。『りぼん』という一つの大きなコミュニティにマンガ家さんたちも一緒にいて参加しているといった感覚がありました。マンガ家同士の交流は、パーティーなどの場以外に編集者があえて交流の場を作ったとかはあったのでしょうか?
<小池>
パーティー以外だとスクーリングがあるんですね。投稿者の上位入賞者を集めて、講師に連載作家さんを招いて、マンガの描き方とか物語の作り方を教える教室を開くんですが、出張スクーリングをしょっちゅうやっていました。地方でのスクーリングにマンガ家さんを二人ぐらい連れていくこともあるし、地元のマンガ家さんにお願いすることもあって、そういう場で食事したりして、自然とマンガ家さん同士が仲良くなっていく感じでした。あとは、りぼんフェスタとかイベントの場がマンガ家さん同士の交流になっていたと思います。250万部売れていたので当然雑誌につく宣伝費も潤沢でしたから、そういうイベントがたくさんありました。
■『りぼん』を離れて、戻ってきたときのこと
―小池さんは一度『りぼん』を離れて『週刊少年ジャンプ』へ異動、2001年にまた『りぼん』に戻られてといった経歴をお持ちですが、戻ってきたときに感じた変化などはありましたでしょうか?
<小池>
『ジャンプ』に移ったら『りぼん』は読まなくなるわけで。戻ってきて改めて読んでみたら、あまり連載陣が変わっていないことに驚きましたね。
―なるほど。逆に変わってないということで驚いたのですね。
戻られた時に小池さんが最初に担当したお仕事というのは何ですか?
<小池>
種村有菜先生の「満月をさがして」をすぐ担当しました。アニメにするからと当時の編集長に言われましたが、枠もスポンサーも決まっていないのでバンダイさんに出向いて、スポンサーになってほしいと頭を下げたりとか。その時は副編集長にもなっていなかったんですが(笑)。水沢めぐみ先生や小花美穂先生、倉橋えりか先生、彩花みん先生、椎名あゆみ先生なんかもその時一緒に担当したのかな。
―ちなみに、小池さんはふろくとかは全く担当したことはなかったんですか?
<小池>
していなかったです。シールとかメインのふろくではないものは担当したことがありますが。
―細々としたふろくならやったことがあるということですね。
<小池>
そうです。応募者全員サービスもやったことありません。懸賞プレゼントなど特製品はやったことがあります。
―2001年からはふろくの状況が大きく変化しますが、戻られた時もふろくは担当はされていない?
<小池>
していないですね。前は無理やり「10大ふろく」とか「13大ふろく」とか言って、これも1個と数えるのか〜みたいな感じでしたが、ふろくの規定が変わってから、プラスチックや缶のペンケースなどの1点もので大きいふろくなどがつくようになって、メインがどんとあって細かいふろくがあと3つ、くらいになっていました。
―デジタルとかインターネットとか普及し始める時期で、戻られた2001年って色んなことの過渡期だったと思いますが、マンガ家さんの制作現場とか、編集者の仕事は、どういうふうに変わっていきましたか?
<小池>
この頃はまだ原稿そのもののデータを送ってもらうといったこともなかったので、そういう面での作業的なことは変わってなかったんですが、インターネットの影響はものすごく大きいですね。「2ちゃんねる」全盛の時代だったから、作家さんは気にしちゃって……。ファンレターだけの頃は、ネガティブレターは排除もできたんですけど。ネット上のネガティブな書き込みをやみくもに目にしてしまう機会がとても多くて、「見ない方がいいですよ」とアドバイスしましたが、見ちゃう人もいる。
―気にして描けなくなってしまうマンガ家さんもいた。
<小池>
こういう方向性でいいのかと、自信をなくしたり迷ったりする方が多かったです。
―今はそうした世界にある程度慣れてきたとは思うけど、今までそんなの全くなかったところにふってきたものですからね。大変だったでしょうね。
<小池>
ネット上の住民に向けて描いてしまうみたいなケースもありましたから。
―そこに書きこんでいる人は多いように見えて、実はすごく少数だったりするわけですからね。
<小池>
そうなんですよ。そういうネットの書き込みは、矢沢先生や吉住先生、水沢先生、さくら先生世代だったら、見なければいいってことで終わるんですが、2001年の頃の主力作家さんってだいたい当時30歳前後でしたが、見るなと言われてもやっぱり見ちゃうという感じでしたね。色んなことにネガティブになっちゃうんですよ、ネットの影響で。ネガティブな思考回路の人が読者にもマンガ家さんにも世間にも増えてきて、ちょっとのミスが叩かれたりする。だから、戻ってきてからの『りぼん』は、マンガ家さんのメンタルに気を使わなくちゃいけないことがとても多くなっていたと思います。
―今だと、Twitterをやっているマンガ家さんが多いですよね。これがマンガ家と読者の距離を決定的に変えたツールだと思うんですよね。
<小池>
基本的に、作品はマスに向けて作っているし、多くの読者が買ってくれることで我々もマンガ家さんも収益を得ているわけですが、Twitterなどで直接読者とつながってしまうと、目線がすごく短くなっちゃう。ネットの向こうにいる2、3人か、20〜30人かはわからないけど、その子たちの会話のやりとりでコミュニケーションができちゃうと、それより大きなものに届くパワーが出しにくくなっちゃうという感じがあります。かつては150キロの球を投げられたのに、130キロの球でその狭いコミュニティに届いてしまうと、結局は130キロの球しか投げられなくなっちゃうみたいな気がして。でも、Twitterやブログをすることは強制的にやめさせることはできない。ただ、僕が副編集長になったとき、「マンガ家さんにやるかどうかの相談をされたら今言ったようなことを説明して、できればやらないように言ってください。ただ強制的にダメということではありません」とスタッフに言いました。やるのは個人の自由だし。東村アキコ先生のような感じで、ご自身そのものをキャラクターとして押し出せる知恵や経験がついたなら、どんどんやればいいと思いますが。まだデビューしたばかりの新人マンガ家さんがそれやると、トータルとしていいことがあまりないような気がしています。
―SNSをうまく扱うのは難しいですよね。使い方のルールとか自分で決めちゃえば有効かもしれませんが、それがなかなかできない。
<小池>
コミュ二ケーションツールとしてはすごいもので、今は時代も変わりましたし、うまく使っているマンガ家さんももちろんいて、とても良い効果が出ている場合も多いですけどね。
■過去作のリバイバルブーム、電子書籍の流れ
―ここ数年は「赤ずきんチャチャN」や「グッドモーニング・キス」「ママレード・ボーイlittle」だったり、そういうリバイバルというか続編が企画される流れが続きました。こういうのが企画された背景とか反響とかあれば教えてください。
<小池>
完全に商売です(笑)。要するにかつては250万人読んでいたわけで、母数が大きいので、その頃の読者に向けてです。
―当時の読者も30代ですし、自分に出せるお金が増えてきた。それを狙って。
<小池>
そうです。あとは当時の作品がそのマンガ家さんの代表作だったりしますし、当然マンガ家さんはその作品のキャラクターを把握されています。そういう意味ではクオリティは保証されているという話でもあります。
―リバイバルする作品というのはどうやって決めたんでしょうか?
<小池>
作家さんとの話し合いです。例えば「ママレード・ボーイlittle」なんかは、『ココハナ』の編集長が吉住先生にオファーした。僕が『Cookie』にいた時、椎名あゆみ先生に描いていただきましたが、先生とはずっとコミュニケーションが続いていて、「マンガ家としてもう一花咲かせたい」とおっしゃっていたので、それなら、「『ベイビィ★LOVE』の続編、お願いします」という発想になると思うし、当然僕も頭にあったんですけど、「新作で勝負します」とおっしゃったので、新作を描いていただきました。だけど「せあらちゃんって、今何してんのかな?」みたいな話をするとやっぱり盛り上がる。こっちも椎名先生も盛り上がるから、「次はやっぱり『ベイビィ★LOVE』の続編だね」みたいな話はしていました。ただやはりマンガ家さんの中でも絶対描かないという方もいます。しかし、あのキャラクターが今どうなっているの?みたいなことは読者だけでなくマンガ家さんご自身も考えたりするだろうし、続編を描くことは読者にとってもマンガ家さんにとっても良いことだと思います。今後もどんどん増えていくと思いますよ。
―実際リバイバルものは、売れましたか?
<小池>
爆発的なヒットというレベルはないですけど、確実にコミックスは売れています。
―それでもまずは雑誌に描いてほしいという思いはあったわけですよね。
<小池>
もちろん、雑誌がある以上は。しかし今の時代、どう考えても雑誌は文化的な使命を終えている。だけど、雑誌という文化が終わっても、マンガというものは未来永劫終わらないものだと思います。
僕は紙の雑誌にこだわらなくてもいいのではと思い、『Cookie』を集英社の少女マンガ誌の中で最初に電子化したんですが、完全に電子書籍だけに移行したらどうなるか。締め切りがないと描けないマンガ家さんもいます。
―つまり、電子書籍なら印刷する必要もないから絶対的な締め切りという概念がなくなる。
<小池>
デジタル原稿が上がったらその日にアップすればいいってなってしまうし、ページ数も自由になってしまいますよね。絶対にこの日までに何ページで描いて、というようにできなくなる。だから両方あるのがベストです。
―今、電子は全体の売上の何パーセントぐらいなんですか?
<小池>
『Cookie』でいうともう10パーセントは電子ですかね。アメリカでは電子の売上はあるところで頭打ちになったんですよね。だから同じように頭打ちになるのか。このまま順調に増えていくのか。それはまだわからないけど、紙の雑誌のステイタスというのは、確実にマンガ家さんの中にあるし、例えば、雑誌が紙をやめてデジタルだけにしますといった途端に、その雑誌が生命力を失うことは確実なんですよ。
―今の『りぼん』の読者くらいの世代はすでに電子で読んでいて、それに馴染んでいるといった時、これからどうなっていくのかなというところはあります。雑誌のよいところって、自分が意図して選ばないものに触れる機会があるところだと思うんですよね。読んだ時はまったく反応しなかったとしても、年を経て理解できたり興味を持つことがあったりする。今はそもそもそうした読み方をしている人は少なくなっているし、電子で配信される雑誌が持つ意味というのも変わる気もします。
<小池>
そうですね。紙の雑誌っていうのはそういう点でものすごく優れたメディアなんですけどね。
■感情を描く〜恋愛もの担当だった理由とは?
―話をすごく戻してしまうんですが、先ほど、編集者の中でもラブストーリーを担当することが多かったというお話でした。小池さんはどうして恋愛ものが得意だったと思われますか?
<小池>
いやわからないです。自然に。
―学園ものが多かった90年代前半の『りぼん』らしさを小池さんが担当することで作っていたのではと思いますが。
<小池>
全然そんなことないです! でもそういえば人づてに聞いたことですが、矢沢先生は、「マサオは女だからさ」とおっしゃっていたそうです(笑)。
―(笑)。乙女心があったということですかね。
<小池>
僕は姉と妹がいて真ん中なんですが、「女兄弟絶対いるよね」とは誰からも言われるんですけどね(笑)。
―私(倉持)の個人的な感覚かもしれませんが、『りぼん』と『なかよし』の違いって共感性みたいなところが大きかったように思うんですよね。感情の機微が描かれるのが『りぼん』だとすれば、『なかよし』はそこより女の子が憧れる設定とかを重視する。この子がなぜこの子を好きになっていくかということがすごく丁寧に描かれていたのが『りぼん』だった気がします。なので、私はそれをきちんと見せてくれない物語が、マンガでも映画でもアニメでも苦手で。いきなり両思いになったり、運命の相手だからとくっついても、「え、なんでなんで?」ってなってしまう(笑)。それは、多分『りぼん』を読んでいたからかなと思っていて、小池さんはもしかしたらそういう部分を大事にされていたんじゃないかなと。
<小池>
そうですね。入社した時はマンガのことは全然知らなかったんですが、さっきも言ったように映画はたくさん見ていたんですね。僕が一番好きな映画、「クーリンチェ少年殺人事件」という作品なんですが、その映画を見た時にあるシーンで腰を抜かしたんです。座席からずり落ちるぐらいに感動して。それはすごく政治的な映画で、とある人が拷問に近い取り調べを受けて、解放された朝のシーンだったんですが、ドアの外がいきなり映り、枯葉が1枚落ちていて、風にあたってその枯葉がかさっと動くんですよ。そのシーンを見てもう号泣してしまって。解放された喜びとか、政治的なことに関わってきたむなしさとか、家族に対する思いとか、いろんな感情がこの枯れ葉がかさって動くシーンに入っていた。なんでオレはこのシーンにこんなに感動しているんだろうと考えた時に、感情というのはどんな形ででも描けるんだなと思ったのです。例えば、泣いているアップとか、笑っているアップとかを映さなくても、枯葉が一枚動くだけで感情は伝わり、人は感動するのだなと。でもこれって、もしかしたら映画よりマンガのほうがそういう表現ができるんじゃないのか。マンガってそういうところが凄いんじゃないのかなって、逆説的ですが、そう思ったんですね。逆にマンガの凄さ、特質に気づいた、というか。それが入社して2年目だったのかな? 確か。
―枯れ葉が動いただけであらゆる感情が描ける!確かにマンガは映画より意図的にそれを読者に見せることができますよね。
<小池>
自分はギャグセンスがあるわけでもないし、そもそも編集者のセンスって何かわからない。恋愛ものが得意だったというよりは、キャラクターの感情というものにフォーカスすることしか自分はできなかった。それで自然にそういう作家さん、作品の担当になっていったということじゃないでしょうか。あとはやはり矢沢先生と柊あおい先生の担当だったから。
―「天ない」が成功したというのは大きかったでしょうね。
<小池>
ということですね。あと「銀色のハーモニー」からもたくさん勉強させていただきました。「銀色のハーモニー」も、空の色とかピアノの音色とかが、キャラクターの感情に直接結びついていましたよね。柊先生はそういう表現がすごく上手かった。
―『りぼん』の作品は大きな事件があるわけじゃないと思うんです。例えば「ときめきトゥナイト」や「姫ちゃんのリボン」はファンタジーだし、現実にはありえない設定もあるけど、それで壮大な敵と戦うわけじゃないし、主人公の身の回りに起きていることとか、身近な問題をファンタジーな設定を借りて解決していくという感じ。だから、どんな設定でも主人公に感情移入して読めたのではと思います。
<小池>
そうおっしゃっていただいて、嬉しいです。よくマンガ家さんに言っていたのは、マンガなんて所詮つくりもので、紙という二次元の上で作るフィクションであると。じゃあ、なんで読者が読むかというと、そこに描かれた感情が読者の心の中の感情とシンクロするからだよ。だから感情をしっかり描かないとダメだよ、と。
また、今の話で思い出しましたが、例えば、明日隕石が落ちて地球が滅亡するかもしれないというドラマと、好きな子と偶然下校が一緒になって、手と手が触れちゃってどうしようというドラマの二つがあったとしたら、そこにあるドキドキは読者にとってどっちも同じくらいだよ、といったことは新人のマンガ家さんに言っていました。感情のドラマという点でどっちが上とか下とかはないですよね。なので、「あなたは地球が滅亡する話より手と手が触れ合うだけでこんなにドキドキするという感情を描いた方がいいよ。あなたにとってのドキドキのドラマを描いてください」ということはよく言っていましたね。
―そうした小池さんのアドバイスが『りぼん』のドキドキする学園ものの名作につながったのかもしれません。今、こうしたオーラルヒストリーを行っているのも、250万という膨大な読者が果たして『りぼん』からどういう影響を受けていたかというのが気になっていることもあるからです。もちろん『りぼん』だけに限らないと思いますが、今の女性の生き方に必ず反映されていると思うんですよね。感情を細やかに描いていたからこそ、特に恋愛観はそうだし、ものごとの考え方とか生き方までに今の女性たちと密接につながっていると思います。
<小池>
250万乙女の今でしたら、『BAILA』での特集記事なんかはお読みになられましたか?
―はい。集英社の女性誌ですね。250万部時代の特集をされていましたが、反響があったと聞きました。『BAILA』の読者はまさに当時の『りぼん』リアルタイム世代、30代の女性ですから、ど真ん中の記事だったのでしょうね。
<小池>
そうですね。あの記事で当時の後輩の江本さんは「編集部はりぼん愛だけで作っていた」といったようなことを言っていたけど、ぼくはそれは違うなって思います。みんなとっとと帰っていたし、編集長の中森さんは夕方6時に帰る人で、僕も仕事が終ればさっさと帰っていた(笑)。仲が悪いわけではないけど、編集部みんなで飲みに行くなどもないし、マンガ論を戦わすこともない。それぞれが独立した存在でした。
―編集部内での交流はそんなになかったんですね。
<小池>
なかったですね。仕事上で相談したい事があっても「そんなの俺に聞くな」ぐらいな先輩たちばかりでした。そういう中で自分はどうすればいいんだということを一人で考えていたと思います。わいわい作っていたというより、それぞれで考えながらやっていく感じ。これはこうしなきゃダメとか、少女マンガはこういうものだとか、読者はこういうものだって言われたことは一度もない。それがよかったのかもしれないです。編集長がほっておく人で、副編集長の岩本さんもそんな感じだったし、後輩になる冨重くんにとっての僕もそういう感じだったらしいです。
―チームというよりは個人プレイ。もちろん目指している方向はみんな同じに走っていても、みんなで目指そうといった感じではなく、それぞれが考えてそれぞれのやり方で動いていた。編集者の個性、マンガ家の個性を大事にしていたと言ってもいいかもしれませんね。
<小池>
それが『りぼん』らしさ、というか集英社らしさでしょうね。
―この間、米沢嘉博記念図書館で開催した赤塚不二夫展のイベントでうかがったお話ですが、『週刊少年マガジン』では一人のマンガ家に担当が必ず二人つくそうです。最初、私は一人が病気になってもちゃんと引き継げるようになのかなって思ったら、違う。要は一人で出すアイデアより大勢で出すアイデアの方がいいということらしいのです。マンガ家を含めて、一つのチームという感じで動く。特に企画ものはこの方法で作っていく。これは五十嵐隆夫さんが進められたことで、赤塚不二夫先生のマンガの作り方、ブレーンを置いて何人かでアイデアを出して作っていく形を参考になさったそうです。そうしたやり方で、「金田一少年の事件簿」とか「GTO」とかのヒット作をたくさん出し、『週刊ジャンプ』の部数を一時期抜かれましたね。
<小池>
なるほど。それは集英社と全然作り方が違いますね。
僕は極端な事を言えば、ストーリーはどうでもいいと思っています。マンガって、ストーリーで覚えてないんですよ。キャラクターとセリフとシーンで覚えていて、映画も同じなんですが、そういう部分って、編集者の左脳的な考えからは出てこないんですよ、絶対。編集者っていうのはマンガ家さんの脳みそを素手で触るような仕事です。デリケートだしそんなことしていいのかなと思うんですけど、触らなきゃいけない。編集者の頭の中より、マンガ家さんの脳みそから生まれるもののほうが絶対に面白くなると僕は思っている。
―どちらの方法がいいとかではなく、向き不向きですね。大事なのは、でもその作家さんのもともと持っている才能とか「らしさ」、個性を大事にすることだとも五十嵐さんはおっしゃっていました。
<小池>
おもしろいですね。『りぼん』は放任主義だからこそうまくいっていたというか、それぞれがどうやったら面白くなるかみたいなのを考えていたから、それがうまく作用していたというのはあると思います。
―お話の全体をお聞きし、『りぼん』は何かを当てようとして一から編集部で作っていくというやり方より、そのマンガ家さんが持っている能力を最大限に生かされる術を大事にしている、ということですよね。『週刊少年ジャンプ』は違いましたか?
<小池>
『ジャンプ』も同じですよ。一人の編集者が一人のマンガ家さんを担当する。『ジャンプ』では「こち亀」という大事な作品を任されました。新人だと「こいつ天才かも」と思った武井宏之先生を担当して、彼をどうにかしてヒットさせようと思い、その時は『りぼん』のときにはない感じに戦略的に考えましたけど。
―『りぼん』の時、そんなに忙しくなかったとおっしゃったのは、もしかして、次にいった『ジャンプ』が忙しすぎてそうおっしゃったのかなとなんとなく思ったんですが......。
<小池>
そうですね。残業は月に50時間以上は当たり前でした。週刊ですから、1週間単位で打ち合わせして、でもサイクルは決まっているから、サイクルが決まれば月火水は暇みたいなのがあるんですけど、連載2本とイベント担当とかだと、もう殺してくれみたいな感じで忙しくなる。「こち亀」だと、ちょうど20周年100巻、舞台化、アニメ化と続き、どうしたらいいんですか僕は......みたいな時はありました(笑)。
■これからの『りぼん』へ
―これからの『りぼん』について、どんなふうになってほしいか。またどんな存在になっていくかといった予測は?
<小池>
「いつまでも少女の夢でいてください」みたいなありきたりのことは言わなくていいですよね?(笑)。少女マンガというジャンルが曖昧になっていく、社会から少女性が損失していくというのが時代の流れとしてあって、それが少女マンガ誌全体の部数減につながっています。その中で、『りぼん』がこれからどうなっていくかというのは、もう実は会社がどう考えるかでしかないんですよね。それが現状です。ただし、『りぼん』がなくなっても少女マンガは終わるわけではない。むしろ今後、いろんなジャンルでいろんなことが細分化し、デリケートに、ソフィスティケイテッドしていく世の中だと、少女マンガの持っている人間の感情の機微、喜怒哀楽を描くという特性はますますアドバンテージを持っていくのでないかなと僕は思っています。どういう形かわからないけど、少女マンガというのは今後もっと影響力をもつかもしれない。そういう意味では、『りぼん』は常に才能を持ったマンガ家さんが集まってくる装置であってほしい。作家性を大事にして、作家さんが持っている一番いいところを形にすることができる、作家さんにとって魅力的な編集部で有り続けて欲しいなと思っています。『りぼん』は絶好調の時も厳しい時も経験している雑誌で、今も厳しい状況なんですけど、そういった精神は捨てないでほしい。30年後も50年後も残るようなマンガ作りを目指してほしい。時間、時代を超えて残るのは、作家性とそこに描かれている感情しかない。そういう作品を生み出す装置でいてほしいなと思っています。
―小池さんは編集者人生の中で『りぼん』を担当したことは単純に楽しかったですか?それともつらい記憶の方が多かったですか?
<小池>
考えてみれば、僕は入社してから『ジャンプ』に異動になるまで、4年半しか『りぼん』にいなかったんですよね。その短い間に、雑誌のいい時期を体験できた。良い経験をたくさんさせてもらって、編集をやることの醍醐味を味あわせてもらったなと思っています。その一方で、それまでマンガのマの字も人生になかった僕みたいな人間が、マンガの編集やってていいのかな、僕なんかがやっていてすみません、みたいな気持ちも、心のどこかに、常にありました。
―なんでマンガのことをやっているんだろうといった気持ちがあった。どこかしっくり来ないような?
<小池>
これが天職! みたいな感情はありませんでした。もちろん全身全霊で仕事はしていたし、真剣に取り組んでいたと胸張って言えます。ですがどこか自分の人生と重なっていない感じはありました。当時の『りぼん』の編集者はみんなそうだったと思います。みな少女マンガをやりたくて集英社に入ってきた人間ではありませんから。どこか重なっていないという距離感、違和感みたいなものが、マンガ家さんや作品を見る上での客観性になっていたのかもしれません。今はそういうふうに考えています。そんな自分ですが、250万部時代の編集部に在籍して、素晴らしいマンガ家さんにいっぱい会えた。とてもラッキーだったと思います。そういう現場、そういう人達と出会えないで編集人生を終える人もいるわけですから。
―『りぼん』にいたことが次の『ジャンプ』で役に立ったなと思ったことは?
<小池>
役に立たねーよ! と最初は思っていました(笑)。でも結論として少女マンガも少年マンガも結局、キャラクターの感情を描くものだというところは同じで、そこへのアプローチの仕方が違うだけでした。それがわかってからは、なんだ、めちゃくちゃ役に立っているじゃん! と思いました。
―ちょっと答えにくい質問かもしれないですが。先程『りぼん』はどうなっていってほしいかといった質問をさせていただいきましたが、これがもし『ジャンプ』に代えての質問だったら答えは変わりますか?
<小池>
変わらないですね。ただ、『ジャンプ』は『ジャンプ』という装置があまりにもでかすぎるので、それが壊れた時が怖い。絶対壊れるんですよ、装置とかシステムというものは。だから今のうちに負け戦をいっぱい体験しておいた方がいいんじゃないでしょうか。ダーウィンの進化論ではないけど、時代にあまりにも適合しすぎたものは、次の時代に生き延びられないじゃないですか。次の時代に生き残れるだけの投資と実験と経験をいっぱい積み重ねて、どんな世の中でも最も先鋭的な場であり続けるという意思がジャンプの場合大事なんだと思いますし、実際にジャンプの現場はそういう意思を持ち続けていると思います。雑誌の時代が終わるのならば、終わらせるのは『ジャンプ』であってほしいですね。なぜそんな質問を?(笑)
―少年誌と少女誌の最前線を両方経験していらっしゃる方なので、お聞きしたいなと思って。先ほど、少女マンガというジャンル、それこそ少女性というものがなくなっていくというお話をされていましたが、それはなくなっていくのではなく、実は『ジャンプ』も含めたすべてのジャンル、あるいは雑誌を超えたすべてのところに、少女マンガが培ってきたメンタルみたいなものは、浸透していったと思うんです。読者はそれが少女マンガ的なものだということすらもう意識もしてもいない。
<小池>
なるほど。あぁすごい!わかります。ひょっとしたら少女マンガというジャンルは、例えばそれこそ平安時代の女流文学とかから綿々と続いてきた日本的情緒みたいなものが、すごく先鋭的に、端的に、マンガという形をとって現れたものかもしれないですね。その中の良いもの、明るいもの、前向きなものが、あの頃の『りぼん』には宿っていたのかもしれません。250万部売った頃の『りぼん』はもうないけど、あの頃の『りぼん』が形にしたものは、形を変えて日本中というか世界中のあらゆる現場で浸透していてくれたら嬉しいです。
―各所に染み込んでいる気がしますよ。特に今のアラサー女性のメンタルって『りぼん』のメンタルだって人は多いと思います。『りぼん』は、目の前のことにどう立ち向かっていくかということをひたすら描いていて、それが原風景にあるから今の30代の女性はものすごく元気な人が多いし、なにか問題が起こっても立ち向かう術を持っている。何かしら、このメンタルは別の形で生き続けていると思います。
<小池>
今思い出しましたけど、中森さんがディズニーランドの話と並んでよくおっしゃっていたことがあって、「読者は人間じゃないぞ。動物やぞ」と。「読者はマンガに対して本能と生命力だけで向かってくる。だからお前らの小手先なんか通じる相手じゃない。それに負けないだけの本気で作りなさい」ということ。
でも......言わずもがなのことなんですが、当時本当に、本気で死ぬ気で頑張っていたのは、マンガ家さん達です。あの頃のマンガ家さんの頑張りを思うと、胸が詰まるような気持ちになりますね。
―読者は小学生ぐらいだし、面白くなければ残酷なくらい読まなくなりますからね。
子どもにはこういうのがうけるだろうとか、こびたりしたら多分もうみんな興味をなくしていく感じだったんだと思いますし、本能で読んでいるから『りぼん』メンタルが骨身にしみている。そして、それはまた別の形で拡散している。
今日は色んなお話が聞けて楽しかったです。本当にありがとうございました!











