2000年代半ば以降、「アートゲーム」と呼ばれるビデオゲームのカテゴリーが目立ったかたちで現れてきた。本稿では、アートゲームの特徴を大まかに示したうえで、いくつかの作品を取り上げながら、ビデオゲームの前衛的な表現の方向性について探っていく。
 ジョナサン・ブロウ『Braid』(2007)
ジョナサン・ブロウ『Braid』(2007)
「アートゲーム」と呼ばれるビデオゲーム(註1)のカテゴリーがある。簡単にいえば、芸術映画(アートハウス・フィルム)のゲーム版だ。アートゲームは、おおむね作家主義的、実験的、自己批判的、非娯楽的、非商業主義的、社会批判的・政治的、プレイ時間が短い、といった特徴を持つ傾向にある(もちろんこれらの特徴をすべて持つとはかぎらない)。また、作家主義と非商業主義のほとんど必然的な帰結として、ふつう個人または少人数チームによる制作というかたちをとる。それゆえ、アートゲームはインディーゲーム(註2)の下位カテゴリーとして考えることもできる。
アートゲームは、名前からするとアート(註3)とゲームが合わさったものだ。とはいえ、ここでいうアートゲーム以外にも、ゲームとアートの関係のあり方はいろいろある。本稿では、アートとゲームの関係を整理したうえで、アートゲームの典型例を見ながら、ゲームにおける前衛的な表現のいくつかの方向性について考えてみたい(註4)。
アートゲームとゲームアート
ゲーム研究者のジョン・シャープ(John Sharp)は、「ゲームアート」(game art)と「アートゲーム」(artgames)を区別している(註5)。
シャープによれば、アートゲームは「ゲームが本来持つ諸性質――とりわけ、インタラクティブ性、プレイヤーの目標、プレイヤーに挑戦課題を与える障害物――を使って反省的で意義深いプレイ経験をつくり出す」(註6)ものである。シャープは、ジョナサン・ブロウ(Jonathan Blow)の『Braid』(2007)を例として取り上げている。『Braid』は、『スーパーマリオブラザーズ』に代表されるような古典的な2Dプラットフォーマージャンルをベースにしているが、プレイヤーが時間を自由に巻き戻せる(それゆえつねに失敗をやり直せる)という点で独特な作品である。シャープによれば、この作品の時間遡行のメカニクスは、単に複雑なパズルや不思議なプレイ感覚をプレイヤーに提供するためだけのものではない。そのメカニクスは、人生をやり直すことについての、そして人生には決してやり直せない事柄もあるということについての省察をプレイヤーにもたらすものだという。その意味で、この作品は「芸術的」なゲーム――アートゲーム――なのだ(註7)。
一方、ゲームアートは「ゲームからつくられたアート」(註8)、つまりゲームを作品の素材にしたアートのことである。シャープがゲームアートとして想定している作品は、例えばマヴァヌイ・アシュモア(Myfanwy Ashmore)の『Super Mario Trilogy』(2006)、コリー・アーケンジェル(Cory Arcangel)の『Super Mario Clouds』(2002)(註9)、JODIの『Jet Set Willy Variations ©1984』(2002)などだ。いずれも既存のゲームを素材にしてつくられた作品だが、その作品自体はゲームとは言えない。ゲームアート作品には、ゲーマーがゲームに期待する要素(インタラクティブ性、目標、障害物、適度な挑戦など)がほとんどない。一方で、それらの作品は、独特の知的刺激を与えるという点でメディアアート好きの期待には応えるだろう。その意味で、それらはゲームではなく、ゲームを使ったアートなのだ(註10)。
 コリー・アーケンジェル『Super Mario Clouds』(2002)
コリー・アーケンジェル『Super Mario Clouds』(2002)
雑な言い方をすれば、アートゲームとゲームアートの違いは、ゲーム(目標を伴ったインタラクティブな構造物)として鑑賞することが求められているか、あるいはアート(独特の思索や知覚の経験をもたらすもの)として鑑賞することが求められているか、というカテゴリーの違いだ。シャープによれば、このカテゴリーの違いは、作品それ自体が持つ特徴の違いというよりは、ターゲットの違い、つまりそれがどんな受容者コミュニティに向けられた作品であるか――意識の高いゲーマーに向けたものか、新しいもの好きのアートファンに向けたものか――という点での違いである(註11)。
「ゲーム」と「アート」という言葉の結びつきはそのほかにもいろいろあるが(註12)、それらは本稿では取り上げない。本稿で問題にするのは、今述べた意味でのアートゲームにはどんな種類があるのかということだ。特に以下で挙げるのは、作家自身の個人的な思想を表現するゲーム、社会批判的なゲーム、そしてゲーム批判的なゲームである(註13)。それらを通して、ゲームにおける前衛的な表現の方向性のいくつかが見えてくるだろう。
個人的なヴィジョン
ジェイソン・ローラー(Jason Rohrer)の『Passage』(2007)は、アートゲームの話題になると必ずと言っていいほど例として持ち出される作品である(註14)。プレイヤーは、5分程度の単純で刺激のないゲームプレイ――プレイヤーは歩くことしかできないし、銃もゾンビも出てこない――を通して、将来とは何か、伴侶と生きるとはどういうことか、追い求めるべき価値とは何か、老いとは何か、といったことを考えさせられる。ようするに、『Passage』は人生とは何かを省察させるゲームだ。それは、標準的なゲームのように刺激や没入や気持ちよさを与える作品ではないが、ある種の思索と感慨をもたらす作品ではある。
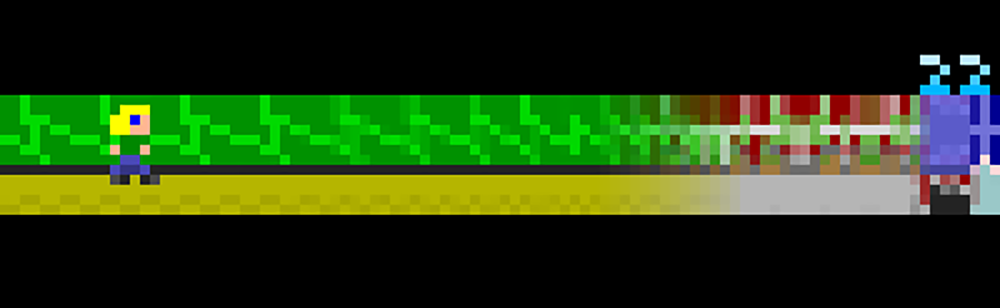 ジェイソン・ローラー『Passage』(2007)
ジェイソン・ローラー『Passage』(2007)
プレイヤーキャラクターの金髪碧眼の男性はローラー自身であり、途中で出会う茶色い髪の女性はローラーの妻に似せたものらしい(註15)。そのことが示唆するように、『Passage』は、人生について何か一般性のある哲学的な主張をしている作品というよりは、単に作家の個人的(personal)な人生観を表現している作品として見たほうがいいだろう。そこには、ローラーが自身の人生について抱いている価値観やものの感じ方や感情が表現されているのだ。
実際のところ、『Passage』を含めたローラーの諸作品は、古めかしい家族観やジェンダー観を前提にした保守的なロマンティシズムを表現した作品として、いく人かの論者に非難されている(註16)。とはいえ、内容は保守的であったとしても、その表現の形式はそれまでのゲーム文化にはなかったものだ。シャープはローラーの諸作品のコンセプトを「自伝的な黙想」(autobiographical meditation)と評しているが(註17)、『Passage』はまさに自伝小説ならぬ自伝ゲームと呼ぶべきものだろう。そしてその作品は、ゲームを通して個人的なヴィジョンを提示するという表現のあり方――「少なくともインディーゲームの業界ではもはや珍しくない」(註18)表現のあり方――の可能性をミニマルなかたちで示したものだと言える。
社会を批判するゲーム
小説や映画には、政治的なメッセージを提示し、社会のあり方を批判する作品が数多くある。それと同じように、社会批判的な内容を持ったゲームもまた少なからずある。例えば、小島秀夫自身が言うところによると、『メタルギア』シリーズには「一貫して「反戦・反核」というメッセージがある」(註19)。とはいえ、そうしたゲームの大半は、その社会批判的な側面が主な見どころなわけではない。それらはふつう、まず第一にゲームとして楽しめるようにつくられており、政治的な側面はおまけであることが多いのだ(作者の意図はどうあれ、少なくとも大半のプレイヤーにとっては)。
しかし、政治的なメッセージを伝えることだけを目的にしたゲーム作品は、ごく少数ながらある。パオロ・ペデルチーニ(Paolo Pedercini)を中心としたゲリラ・プロジェクトであるモレインドゥストリア(Molleindustria)の諸作品は典型だろう。モレインドゥストリアは、ウェブサイト上で多数の政治的なFlashゲームを発表している(註20)。
 モレインドゥストリア『McDonald’s Video Game』(2006)
モレインドゥストリア『McDonald’s Video Game』(2006)
物議を醸した作品『McDonald’s Video Game』(2006)は、タイトルの通りファストフード産業を題材にした経営シミュレーションゲームだ(註21)。このゲームは、農場・飼育場・店舗・営業部の4つのセクションからなる。経営者であるプレイヤーは、それぞれのセクションを切り替えながら、肉牛と飼料を生産し、肉牛の頭数と栄養を管理し、ハンバーガーショップのスタッフを雇用・管理し、顧客を呼び込むための広報活動や政治家・活動団体への根回しをしなければならない。
これだけならありがちな経営シミュレーションなのだが、『McDonald’s Video Game』の特徴は、会社の倒産を避けるためには倫理的に問題のある行為に必ず手を染めなければならない――例えば、狂牛病の恐れのある牛をそのまま出荷する、農地を確保するために森林や住民の住居を破壊する、不満の多い労働者を解雇する、環境保護団体のネガティブキャンペーンを黙らせるために金をばらまくなど――という点にある。さらに、そうやって収支のバランスを維持したとしても、最終的には生産の基盤になる土地がすべてやせ細ってしまい、経営が立ち行かなくなる。つまり、どうやってもバッドエンドになる。この作品は、ファストフード産業が(ひいては資本主義が)本質的にはらむ問題を戯画的にシミュレートすることを通して、社会に対する批判的な見方をプレイヤーに伝えることを意図した政治的なゲームなのだ(註22)。
もちろん、風刺画に典型的に見られるように、この種の社会批判的な表現はさまざまな媒体で伝統的になされてきたことだ。しかし、『McDonald’s Video Game』は、それをゲームならではの仕方でおこなっている。つまり、単に言葉や絵や映像でそうした状況を批判的に描くのではなく、ゲームのルールや法則を通してそれを描いている――シミュレートしている――のである。
ゲーム研究者のイアン・ボゴスト(Ian Bogost)は、こうしたシミュレーションを利用した表現技法を「プロシージャル・レトリック」と呼んでいる(註23)。古典的なレトリックにおいて言葉や絵が人々を説得するのに使われてきたのと同じように、ゲームもまた人々を説得するのに使われる。そのようなゲームは娯楽としてはほとんど機能しないかもしれないが、プレイヤーに批判的な考えを伝え、社会問題に目を向けさせることはできる。プロシージャル・レトリックとしてのゲームのあり方もまた、アートゲームのひとつの方向性として考えられるだろう。
ゲームを批判するゲーム
哲学者のアレクサンダー・ギャロウェイ(Alexander Galloway)は、「カウンターゲーミング」という概念を提示している(註24)。これは、簡単にいえば自己批判的なゲーム、つまり私たちがふだん自然に受け入れているゲームのあり方についての反省を促すようなゲームのことだ。
ギャロウェイは、上で言及したJODIの諸作品のようなゲームアートを例にしながら、カウンターゲーミングのパターンをいくつか挙げている。例えば、プログラムコードや素材のデータをそのまま見せてしまっているもの、インタラクティブ性を削いだもの、三次元的な事物の表象としてのグラフィックというよりグリッチのように二次元の画面上の模様としてのグラフィックのあり方を強調するもの、自然な物理法則の代わりにありえない物理法則を提示しているもの、コントローラの入力と操作対象の挙動が調和していないものなどだ。ようするに、不自然さと抵抗感を与えることで媒体(伝統的に「透明」であるべきだとされてきたもの)それ自体に目を向けさせるという、モダニズムの――文学理論や美術批評に多少触れたことのある人ならおそらくおなじみの――理念のゲーム版である。
とはいえ、ギャロウェイによれば、こうした事例は単に視覚表現として前衛的なだけであって、ゲームプレイとして前衛的なわけではない。それらはむしろ、ろくにゲームプレイを生み出さないという意味で「行為の形式としては反動的」(註25)なのだ。ギャロウェイの考えでは、「ラディカルな行為」、「オルタナティブなゲームプレイのあり方」を提示するような本当のカウンターゲーミングは、「いまだ実現していないプロジェクト」だという(註26)。しかし、これはけっこう微妙な考えだ。
実際のところ、藤田直哉が最近の論考で論じているように(註27)、広い意味で自己言及的なゲームは、「カウンターゲーミング」などという概念をわざわざ持ち出さなくともゲームの歴史のなかでごくふつうに見られる。それは、単なるパロディ(例えば『パロディウス』、『セガガガ』)の場合もあれば、確立したフォーマットに対する皮肉(例えば『Moon』、『McPixel』)の場合もあるし、プレイヤーを挑発してこけにするもの(例えば『たけしの挑戦状』、『Getting Over It with Bennett Foddy』)の場合もある。そして、そうしたものの多くは、ある意味でオルタナティブなゲームプレイを提示しているだろう。
もちろん、藤田が適切に指摘している通り、ゲームをメタに捉えるゲームがすべて自動的に「カウンター」になるわけではない。パロディが典型だが、自己言及は、それ自体が遊び・笑いとして消費される可能性がつねにある。藤田の言い方を借りれば、自己言及的なゲームが批評性を持つためには、プレイヤーを「戯れさせる」のではなく「突き放す」必要がある(註28)。同じことは、ギャロウェイが挙げるカウンターゲーミングのパターンについても言える。例えば、Valveの『Portal』(2007)やテリー・キャヴァナフ(Terry Cavanagh)の『VVVVVV』(2010)は、不自然な物理法則を提示して独特の違和感や知覚の混乱をプレイヤーに与えるが、その特徴がゲームに対する反省をもたらすことはない。むしろ、それはパズルやアクションの楽しさをつくり出す要素になっている。逸脱は、遊びの楽しさに回収されてしまって批判につながらないことがあるのだ(註29)。
しかしだからと言って、とにかくゲームから楽しさをなくしてプレイヤーを突き放せばそれでいいのかというと難しい。アートゲームから例を出そう。筆者の考えでは、ギャロウェイのカウンターゲーミングの理念を十全に実現している作品のひとつは、ロブ・ラック(Rob Lach)の『POP: Methodology Experiment One』(2012)だ。
 ロブ・ラック『POP: Methodology Experiment One』(2012)
ロブ・ラック『POP: Methodology Experiment One』(2012)
この作品は、サイケデリックなビジュアルとシンセウェイブで彩られたミニゲームのオムニバスになっている。音楽と視覚表現には見るべきところが多々あるのだが、ゲームプレイとしてはすべて端的につまらない。もちろん、作者の意図を踏まえてプレイすれば(作者が単なるクソゲーを意図していないことは明白であり、同時に楽しいゲームをつくろうと意図していないことも明白だ)私たちがふだん接しているゲームに対する反省がもたらされる。その意味で、この作品はたしかにカウンターゲーミングとして成功しているだろう。しかし、同じことが単なるクソゲーのプレイ経験にも言えてしまう。意識の高いプレイヤーにとっては、クソゲーはすべてカウンターゲーミングの例として鑑賞できるかもしれない。ようするに、十分に発達したクソゲーはカウンターゲーミングと区別がつかない可能性があるということだ。
そういうわけで、自己批判的なゲームという概念には、根本的な実現の難しさがある。批判性を失うか、単なるクソゲーになるか。その合間で試行錯誤することがカウンターゲーミングの宿命かもしれない。
そして批評的なプレイへ
以上、個人的な表現、社会批判、自己批判としてのゲームのあり方をそれぞれ見てきた。ここで挙げたアートゲームはすべてミニサイズの作品であり、ほとんどコンセプトを打ち出すだけで終わっていると言えるかもしれない。とはいえ、だからこそ、それらはゲームを媒体にした表現のポテンシャルをわかりやすく示唆するものになっている。
もちろん、前衛的なゲームは前衛的なものとして解釈されなければ意味がない。芸術映画を娯楽として見れば退屈な駄作になるのと同じように、アートゲームをふつうのゲームとしてプレイすればただのクソゲーでしかない。前衛的なゲームから豊かな意味を引き出すには、作者の工夫に目を凝らし、作品自体が持つ力を吟味する意識的なプレイ――つまり批評的なプレイ――が必要である。
前衛的なゲームは、批評的な鑑賞をプレイヤーに要求すると同時に、ゲームが批評的な鑑賞に値する媒体であることに気づかせるものでもある。実際のところ、おそらく多くのゲーマーは、アートゲームではないふつうのゲームに対しても批評的な態度で日々接しているはずだが、そのことにそれほど自覚的ではないかもしれない。そうしたゲーム文化の豊かな実践の存在を目に見えるかたちで明確に示すこと。これもまた、前衛的なゲームのひとつの方向性だと言えるだろう。
(脚注)
*1
煩雑なので、以下では「ビデオゲーム」を「ゲーム」と略す。
*2
「インディーゲーム」は、文字通りにとればインディペンデントなゲーム、つまり個人や小規模チームの開発者が、出資者や出版者からの制約抜きに自分たちの好きなように開発するゲーム一般を指す。とはいえ、実際には、2000年代後半から北米やヨーロッパで興隆した作家主義的なムーブメントを牽引した作品群と、思想的・様式的にそれらにつらなる作品群が「インディーゲーム」と呼ばれる傾向にある。以下を参照。Maria B. Garda and Paweł Grabarczyk, “Is Every Indie Game Independent? Towards the Concept of Independent Game,” Game Studies 16, issue 1, 2016.
*3
本稿では、「アート」という語に特に概念的な規定を与えないが、「ファインアート」または「美術」とおおよそ交換可能な語として使っている。「芸術的」についても特に規定を与えない。
*4
あらかじめ注記しておくと、いわゆるアートゲーム以外にも芸術的あるいは前衛的な表現を持ったゲーム作品はいくらでもある。本稿の目的は、いくつかのアートゲームの紹介を通して前衛的なゲームの方向性を探ることであって、アートゲームだけがゲームの前衛的表現だと主張することではないし、ゲームの前衛的表現の事例を数多く紹介することでもない。
*5
John Sharp, Works of Game: On the Aesthetics of Games and Art (Cambridge, MA: MIT Press, 2015), pp. 8–15.
*6
Sharp, Works of Game, p. 12.
*7
筆者の個人的な印象でいうと、商業的に成功した作品である『Braid』をアートゲームの代表として挙げることにはやや違和感がある。とはいえ、どこまでアートゲームに含めるかはそれほど明確ではない。フェラン・パーカーによるアートゲームの例示においても、『Braid』をはじめ『Journey』、『Papo & Yo』、『Gone Home』といった商業的に成功した作品が挙げられている。Felan Parker, “Playing Games with Art: The Cultural and Aesthetic Legitimation of Digital Games” (PhD diss., York & Ryerson Universities, 2014), pp. 171–172.
*8
Sharp, Works of Game, p. 14.
*9
『Super Mario Clouds』の画像は収蔵先のホイットニー美術館のサイトから取得。Accessed January 4, 2019, https://whitney.org/Events/99ObjectsSuperMarioClouds.
*10
アートゲームと同様に、ゲームアートもまた国内で十分に紹介・周知されているとは言えない。谷口暁彦による以下の記事が今のところもっとも詳しい紹介だと思われる。「ゲームアートにおけるゲーム世界の自律性」エクリ、2018年、http://ekrits.jp/2018/05/2620/。ちょうど本稿の執筆時にNTTインターコミュニケーション・センターで始まった企画展「イン・ア・ゲームスケープ」(http://www.ntticc.or.jp/ja/exhibitions/2018/in-a-gamescape/)は、ゲームアートを大々的に取り上げた展覧会としては国内初だろう。
*11
シャープは、受容者コミュニティがある文化形式に期待するものを「アフォーダンス」と呼んでいる。シャープの考えによれば、ゲームとアートの違いは、アフォーダンスの違い、つまり受容者コミュニティがそれぞれに期待するものの違いである。Sharp, Works of Game, pp. 4–7.
*12
例えば「ゲームアート」や「アートワーク」という言葉は、ゲームの視覚的表現の側面(ようするに見栄え)を指すのに使われることがよくある。これは「舞台美術」や「映画のアートディレクション」などというのと同じ意味で「ゲーム美術」や「ゲームのアートディレクション」と言い換えられるものであり、本稿の議論には関係がない。
*13
ブライアン・シュランクは、「政治的/形式的(political/formal)」の軸と「急進的/事なかれ主義的(radical/complicit)」の軸を掛け合わせた四象限で前衛的なゲームを分類している。Brian Schrank, Avant-garde Videogames: Playing with Technoculture (Cambridge, MA: MIT Press, 2014), pp. 12–24. 本稿の分け方はシュランクの分類を踏襲しているわけではないが、ゲームにおける前衛的な表現についての理解のいくつかはシュランクの議論に拠っている。
*14
http://hcsoftware.sourceforge.net/passage/.
*15
Sharp, Works of Game, p. 56.
*16
Sharp, Works of Game, p. 121, n. 7.
*17
Sharp, Works of Game, p. 56.
*18
Sharp, Works of Game, p. 63.
*19
「「メタルギア」の小島秀夫が考える“エンタメが戦争から逃げられない”理由」文春オンライン、2017年、http://bunshun.jp/articles/-/3899?page=3。
*20
http://www.molleindustria.org/.
*21
マクドナルドからの抗議を受け、現在ではモレインドゥストリアの公式サイトからはこの作品のFlashが削除されている。
*22
同種の有名な政治的ゲーム作品に、ゴンサロ・フラスカ(Gonzalo Frasca)の『September 12th』(2003)がある。クリス・クロフォード(Chris Crawford)の『Balance of Power』(1985)は、こうした「社会派」的なシミュレーションゲームの先駆けと言えるかもしれない。
*23
Ian Bogost, Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames(Cambridge, MA: MIT Press), chap. 1, esp. pp. 28–40; Ian Bogost, “The Rhetoric of Video Games,” in The Ecology of Games: Connecting Youth, Games, and Learning, ed. Katie Salen (Cambridge, MA: MIT Press, 2008), pp. 117–140.
*24
Alexander R. Galloway, Gaming: Essays on Algorithmic Culture (Cambridge, MA: MIT Press, 2006), chap. 5. 日本語での紹介は、吉田寛「〈抗い〉としてのゲームプレイ――ゲーム的リアリズム2.0のために」『ユリイカ』49巻3号(2017年)、141–152頁を参照。
*27
藤田直哉「「カウンターゲーミング」と「メタフィクション」――批判的ゲームの可能性」限界研編『プレイヤーはどこへ行くのか』所収(南雲堂、2018年)、239–256頁。藤田は「メタフィクション」という言い方を採用している。
*28
藤田は「戯れ」と「突き放し」に加えて、「物語への再導入」というパターンを挙げている。物語への再導入とは、メタ的な表現をフィクション上の事柄として回収する(それゆえ全体としてはフィクションの整合性の枠内で理解できる)ものだ。こうした表現は、たしかによくできた表現ではあるだろうが、藤田自身が述べるように、自己批判性の観点からすれば不十分だと思われる。そうした表現は、結局のところフィクション経験の「感傷」に帰着してしまって、媒体自体に対する批判的な「覚醒」をもたらさないのである。
*29
ミゲル・シカールが強調しているように、そもそも遊びや遊び心には本来的に批判的な性格――カーニバル性――が含まれているという考えもある。Miguel Sicart, Play Matters (Cambridge, MA: MIT Press, 2014), chap. 1. つまり、遊びは、権威・伝統・主流の転覆や無力化を図る働きをつねに部分的に持つということだ。この考えからすれば、遊びや笑いに解消されるということは、それ自体である種の批判性の表れだということになる。実際、ゲームの歴史においてパロディや皮肉といった逸脱的な表現がふつうに見られるのは、ゲーム文化が遊び心に満ちたものであるおかげだろう。とはいえ、ここで問題にしているのは、そうした遊び一般に見いだせる批判性というよりは、もう少し限定的な批判性――ビデオゲームという媒体とそれをプレイする文化に対する自己反省――である。
※註のURLは2019年1月17日にリンクを確認済み
あわせて読みたい記事
- 3Dゲームグラフィックスの歴史第1回 3Dゲームグラフィックスの幕開け2021年7月29日 更新











