今回で27回目を迎えるバーチャルリアリティやインタラクティブ作品のコンテスト「国際学生対抗バーチャルリアリティコンテスト(IVRC 2019)」(主催:日本バーチャルリアリティ学会IVRC実行委員会)。この決勝大会が2019年11月16日(土)・17日(日)にテレコムセンタービル、日本科学未来館(東京都江東区)で開催された。個性豊かな10作品が並んだ会場の模様をレポートする。
 『Tabletop ARrietty』(写真はすべて筆者が撮影)
『Tabletop ARrietty』(写真はすべて筆者が撮影)
VRを担う次世代の人材育成を目的にスタート
国際学生対抗バーチャルリアリティコンテスト(IVRC)がスタートしたのはWindows3.1日本語版が発売され、「マルチメディア」が流行語になった1993年のことだ。当時は大型アミューズメント施設で体感バーチャルリアリティ(VR)ゲーム機が登場するなど、産業&学術界でもVRブームにわいていた。IVRC実行委員長の舘暲氏(東京大学)は審査発表の場で「VRの未来を切り開く若い世代に向けたコンテストが必要だった」と設立理由を説明。実際に多くのIVRC経験者が、さまざまな分野で活躍していると語った。
この言葉にたがわず、今年もフランスからの招待作品(註)を含む、個性豊かな10作品が会場にならんだ。このうち総合優勝に輝いたのは、消防士の訓練体験ができる『VR消防体験 -炎舞-』(筑波大学)で、協賛企業賞を含む三冠に輝いたほどだ。これに対して観客の投票で決まる観客大賞には、高校生チームが作った『渡し舟教習所始めました』(立教池袋高等学校)が大学生チームを退けて受賞した。10作品のうち9作品でVRヘッドマウントディスプレイ(HMD)が使用されていた点も印象的だった。
今回は開催日が週末となり、サイエンスコミュニケーションイベント「サイエンスアゴラ」内での開催も手伝って、会場は終始親子連れで賑わっていた。審査結果は次のとおり。
審査結果
| 総合優勝 | 『VR消防体験 -炎舞-』 CyberSpaceLab(筑波大学 システム情報工学研究科) |
|---|---|
| 日本VR学会賞 (総合2位) |
『La Plume et la Lanterne』 Frenchie Kokonattsu(Arts et Metiers ParisTech) |
| 川上記念特別賞 (総合3位) |
『昆虫体験・かぶとりふと』 餅は餅屋(慶應義塾大学 大学院メディアデザイン研究科) |
| 審査員特別賞 | 『Tabletop ARrietty』 借りぐらし(東北大学 電気通信研究所) |
| 『悪い、やっぱつれぇわ、生理痛』 ふあふあ☆ゆーとぴあ(甲南大学 知能情報学部) |
|
| Laval Virtual Prize | 『きになるき』 チルドレン(東京大学 大学院情報理工学系研究科) |
| 観客大賞 | 『渡し舟教習所始めました』 かつぞう、かわをわたる(立教池袋高等学校 数理研究部) |
| GREE賞 | 『グランドサーフィン』 鯖缶(大阪大学 基礎工学部) |
| Unity賞 | 『おかえり感覚』 AKチーズバーガーズ(東京藝術大学 絵画科、関東学院大学 理工学科) |
| 『超・呼吸体験: VReath』 ももまる(慶應義塾大学 メディアデザイン研究科) |
|
| ソリッドレイ賞 | 『VR消防体験 -炎舞-』 CyberSpaceLab(筑波大学 システム情報工学研究科) |
| チームラボ賞 | 『グランドサーフィン』 鯖缶(大阪大学 基礎工学部) |
| ドスパラ賞 | 『VR消防体験 -炎舞-』 CyberSpaceLab(筑波大学 システム情報工学研究科) |
※GREE賞、Unity賞、ソリッドレイ賞、チームラボ賞、ドスパラ賞は協賛企業賞
IVRC2019副実行委員長で審査委員長を務めた岩田洋夫氏(筑波大学)は表彰式で、「上位入賞作品が感覚フィードバックと世界観を重視したものに分かれた」と講評を述べた。
 『VR消防体験 -炎舞-』
『VR消防体験 -炎舞-』
総合優勝を果たした『VR消防体験 -炎舞-』は、これまでVRで消化活動体験を表現する場合、映像表示が中心であったが、新たに力覚・温冷覚・風覚を加えて、総合的な消火活動訓練を可能とした作品だ。火災現場を再現したVR HMDの映像に加えて、消防用散水ホース型コントローラーをDCモーターで後方に牽引することで、散水時の水噴流反力を表現。また、ジャケットに紐をつけ、DCモーターで振動させることで強風を表現したり、顔にファンで温風を当てたりして、火災現場の臨場感を高めている。
総合3位の川上記念特別賞を受賞した『昆虫体験・かぶとりふと』も同様だ。VR世界でカブトムシとなり、餌場をめぐってほかのカブトムシと戦うという内容で、バトルでは実際に頭部を動かし、カブトムシの特徴的な「角」を相手にぶつけたり、相手をひっくり返したりするようなアクションがとれる。頭部の左右ではCDが回転し、頭を振るたびに独特のフィードバックが返ってくる点も新鮮に感じられた。このように1位と3位の受賞作は、感覚フィードバック側の作品となる。
これに対して2位の日本VR学会賞に輝いた『La Plume et la Lanterne』は、パリ国立工芸学校の学生チームによる作品で、世界観をつくり込んだ点が評価された。ランタンをかざしながら絵本の世界を探索するという内容で、VR HMDを装着して実際に探索する側と、本型コントローラーで仮想世界に介入する側に分かれて、2人1組で体験できる。審査員特別賞を受賞した『Tabletop ARrietty』も同様で、こびとの世界がVR世界とAR世界の両方でしっかりとつくり込まれている。
岩田氏は「『Tabletop ARrietty』は審査員の得票数でいえば実質4位で、3位との差があまりなかった。1位と3位が感覚フィードバック、2位と4位が世界観で評価された作品というわけだ。このように今年度はVRの本質が感覚フィードバックと世界観にあることを、あらためて示した結果となった」と評した。
 『La Plume et la Lanterne』(左)、『昆虫体験・かぶとりふと(右)』
『La Plume et la Lanterne』(左)、『昆虫体験・かぶとりふと(右)』
制作チームへのインタビューを交えた各作品の概要
もっとも、筆者としては4位以下の作品の方がより印象深く感じられた。そこで、それらの作品の制作チームに、後日メールインタビューを行った。ここでは、メールの文面を引用しながら、その内容を紹介する。
『グランドサーフィン』
 『グランドサーフィン』
『グランドサーフィン』
ウィンドウサーフィンによるセーリング体験を疑似再現した本作。プレイヤーは波の揺れを提示するボード型デバイスの上に乗り、バランスを維持しながらセイル型デバイスを操作し、VR空間内の移動を制御する。VR空間内には鯨やブイなどが存在し、これらを避けながらゴールをめざすことが目的だ。それに加えて、前方から送風機で風と海の匂い(扇風機の羽根にマリン系の香水を塗布している)を送ることで、没入感を高めている。VR HMDにはオールインワン型のOculus Goを使用し、体験の自由度を向上している(そのため、すべての処理はOculus Go内で行われている)。
ボード型デバイスは板にバネを取り付けた構造で、体験者の重心移動で揺れが発生する。板にはアクチュエーターが取り付けられており、板を上下させることで縦波を再現している。「振動子やトランスデューサで振動を与えると高周波が発生するため、アクチュエーターで実装しました」。これに加えてマストに取り付けた加速度センサーでマストとブームの傾きを検知し、Wi-Fiを介してVR HMDにセンサーの値を送信する。VR HMDが両者の傾きとゲーム内世界で流れる風の向きを計算し、ウィンドウサーフィンの向きや速度が変化する仕組みだ。上手く操作できると速度が上がり、それに応じてVR HMDからWi-Fiモジュールにデータが送信され、サーボモータが回転して、扇風機の出力が変わる。
企画のきっかけは、「インタラクティブなコンテンツ」をつくりたいということだった。「自分の動きがバーチャル空間に反映され、自由に動けるということは、とても楽しいことだと思います」。決勝大会では、より体験の没入度を高めるため、操作した世界に応じて現実世界に感覚をフィードバックするように設計を工夫したという。このように本作は感覚フィードバックに主眼を置いてつくられた作品で、プレイすると上下にゆられるボードの上でバランスをとり続けることで、想像以上に足の筋肉に負担がかかる。1プレイが終了すると、心地よい疲れが得られたほどだ。ただ遊ぶだけでなく、体幹をトレーニングするのにも適しているように感じられた。
もっとも時間内に詰め切れなかった要素もあった。「操作の説明やプレイ中のアドバイスをゲーム内で完結させること」だ。「VR HMDを被る前に操作説明をしたり、外部からアドバイスを出したりするのではなく、操作説明をゲーム内のチュートリアルで行い、アドバイスもゲーム内で補助できるなどは一例です。または、インカムを用いて外部から体験者に伝える機構にすれば、よりゲームの完成度が高まったと思います」。
『Tabletop ARrietty』
 『Tabletop ARrietty』
『Tabletop ARrietty』
VR HMDを装着してVR体験をする人と、スマートフォンを使ってAR体験をする人とが、360度カメラ映像やネットワークを介して同じバーチャル空間を共有し、一緒に楽しめる対戦型ゲームコンテンツ。VR HMDを装着した人は小人(ARrietty)となり、バーチャル空間内で魔法の種を収集する。バーチャル空間内の背景画像には、現実空間の全天球映像が利用されており、まるで巨人のように感じられるスマートフォンユーザーの様子を見ながら、相手に攻撃を繰り出すこともできる。
これに対してARユーザーは巨人となり、バーチャル空間内を走り回るARriettyの様子と現実空間のHMDユーザーの様子を同時に見つつ、種を集めるARriettyの邪魔を行う。VR HMDユーザーは1人、ARユーザーは最大3人までゲームに参加することが可能だ。
開発のきっかけは、複数人で楽しめるVRゲームが少ないという現状が続いていることだ。「特にVRコンテンツに親しみがあまりない人たちにVR体験をしてもらうためには、この状況を解決することが必須だと考えました。そこで『ポケモンGO』等で世間的にも認知されつつあるスマートフォンARを利用することで、特別な装置を必要とすることなく、みんなでVR/AR体験を楽しむことができるような企画ができないか……ということで本企画に至りました」。
過去にもVR HMDの装着者と非装着者とのインタラクションを取り上げた研究は多数存在した。しかし、スマートフォンと360度カメラという身近なデバイスや、スマートフォンのキャリア通信を利用してクロスデバイスインタラクションを実現したコンテンツをつくり上げた点は、本作ならではだ。
もっとも、それだけに開発は試行錯誤の連続だったという。「VR/AR体験をしている体験者がお互いの様子を把握しつつ、ゲームに没入できるような視点移動や動線を実現するために、バーチャル空間内のレイアウトはもちろん、現実空間でのVR HMD装着者の位置、360度カメラの位置、ARユーザーの位置を考慮してレイアウトをすることが必要でした」。
また、純粋に「ゲーム」としてのUX(ユーザーエクスペリエンス)設計や、ゲームバランスの調整などを行うため、決勝大会直前は徹夜続きだったという。その成果がみのり、当日は会場の天井がきれいに映り込み、各ユーザーの位置関係もうまくバランスがとれた。また、今回のIVRCは「サイエンスアゴラ」内での開催だったため、12歳以下の子どもがたくさん来場していた。VRと違いAR側は年齢制限が必要なく、スマホAR側の操作をシンプルにしていたこともあり、多くの子どもたちに遊んでもらえたという。「このようにAR側に関してはUX設計に関してかなり手応えを感じることができました」。
一方でVR HMD装着者側のUXが下がってしまった点は否めなかった。移動操作が難しかったり、魔法の種の配置が分かりにくいなどの課題がクリアしきれなかったりしたからだ。「360度映像を利用した、バーチャル空間と現実空間の融合については高評価だっただけに、残念でした」。筆者もVR HMD側でプレイしたが、残念ながら制限時間内に魔法の種を集めきることはできなかった。もっとも、これ以外の点については高いクオリティを実現できていた。今後もさまざまな形で、VR HMDとスマホARのインタラクションをテーマにしたゲームが期待できそうだ。
『悪い、やっぱつれぇわ、生理痛』
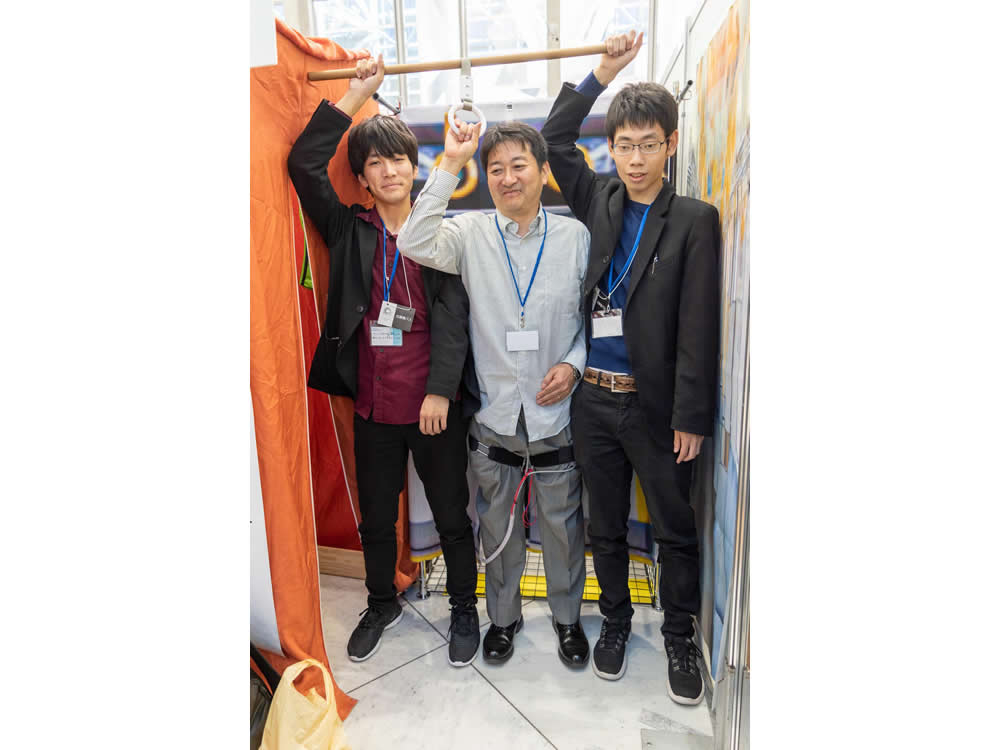 『悪い、やっぱつれぇわ、生理痛』
『悪い、やっぱつれぇわ、生理痛』
電気信号を筋肉に直接与えるEMS(Electrical Muscle Stimulation)パッドと、電圧をかけると温度が上昇するペルチェ素子を併用することで、誰でも生理痛の痛みや出血の不快感が疑似体験できるようにした作品。体験者は腹部にEMSパッドを利用した生理痛体験デバイスを張り付けるとともに、足の付け根にペルチェ素子を用いた出血体験デバイスを装着する。EMSパッドには最大0.03Aの正弦波波形の電圧を100Hzの周波数でかけ、生理痛特有の重みがある、体の内側からの痛みを再現した。またペルチェ素子で太ももを温めることで、立ったり座ったりする動作で生じる出血感も再現されている。
本作品を体験展示するうえで、もっとも効果的なシチュエーションとして選ばれたのが「満員電車」だ。体験者は左右をスタッフに囲まれながら、車内で立ったり、座ったりする動作を強要される。この時、デバイスの位置を3次元位置計測センサーのPatriotで検出し、その値をゲームエンジンのUnityに渡すことで、シチュエーションに合わせた電気刺激や出血感が提示される仕組みだ。
制作チームは開発のきっかけについて、「生理痛体験デバイスを身に付けながら、『電車で通勤通学する』という男女共通の生活動作をすることで、普段の生活との差を感じてもらい、生理について少しでも知ってもらえるきっかけになることを目的として開発しました」と回答を寄せた。男性に知ってもらうだけでなく、女性同士で生理の痛みの個人差を知ってもらい、お互いの理解を深めてもらうことも目的に掲げられた。なお、痛みなどの調整はチーム内の女子学生2名の意見を取り入れて行ったという。
制作でもっとも大変だったのは、意外にも展示のレイアウトを考えることだった。展示スペースが限られているため、事前に展示の模型を作成し、実際に研究室内で設営をするなど、試行錯誤を重ねた。その結果、なんとか制限サイズ内にまとめることができたという。
もっとも、やり残したこともあった。EMSによる痛み提示のインパクトが強すぎて、ペルチェ素子による温感提示の感覚が薄れてしまっていたことに、当日まで気づかなかったことだ。「何人かに体験してもらって、あまり刺激が感じられないという意見を受け、気がつきました。下手に調節すると失敗する恐れもあったので、できませんでした。ペルチェ素子の出力を上げ、もう少し出血感を増したかったです」。実際の展示会場では、作品のインパクトは非常に大きく、会場内で高い注目を集めていた。
『おかえり感覚』
 『おかえり感覚』
『おかえり感覚』
従来のVRコンテンツではVR HMDを装着中に面白いことがおきる。しかし、本企画の面白さのピークは、VR HMDを外して現実を見る瞬間にある……。このような、まったく新しい文脈で制作された作品が『おかえり感覚』だ。
体験は部屋の様子が分からない状況で、VR HMDを装着するところから始まる。その後、VR空間内に広がる部屋の中で捜し物ゲームを行う。その後、VR HMDを外すと目の前にVR空間内と同じ部屋が、現実空間に現れる。ただし、VRの部屋の方が30%ほど大きくつくられているので、その分だけ体験者は背が伸びたと錯覚する。先にVRの部屋を見せてから、それに即した現実空間を見ることになるため、脳が現実の方が変化したように錯覚する仕組みだ。
制作チームは企画・立案・VRコンテンツ制作が東京藝術大学の山本佳奈、家具デザイン・モデリングは関東学院大学の山本尚弥の姉弟コンビだ。「VRゲームをし終わってVR HMDを外す時、近くに人がいてびっくりしたことがあったので、VR HMDを外す瞬間をテーマに何か作品をつくれないかなと思いました」(山本佳奈)。姉がメンバーを集めることに難儀し、困っていたところを、弟がみかねて手伝ってくれたことで、企画が実現した。
本作のもうひとつの特徴は、モノトーンを基調とした造作のデザインだ。展示作品中でも一番で、ともすれば「段ボールとガムテープでつくられている」と揶揄されがちなIVRCの作品群の中でも異彩を放っていた。もっとも、色については確固たる理由がある。現実世界と色を近づける時、色相、彩度、明度のうち明度を似せられれば、色相と彩度は完璧ではなくても、あまり目立たないのだ。これにより、少ない労力でVR空間と現実を似せることができた。芸術系大学ならではの知見だろう。
もっとも、本作でやり残した点もあった。「部屋のセットの美しさ」「錯覚を起こすための現実とVRの部屋の大きさの差」「ゲームの成立」という3要素のバランスがとりきれなかったことだ。「期間中に完成させるため、予選と本選でそれぞれ1パターンずつしか試せず、最終的に無難なバランスでつくりました。もっといろんなパターンを試してみたいです」。
ほかにも自分が樹木となり、鳥や小動物とたわむれる『きになるき』や、息を吸ったり吐いたりする感覚を増幅する『超・呼吸体験:VReath』など、一般的な展示会では見られないユニークな作品群が並んだ。前述の通り、高校生チームの作品『渡し舟教習所始めました』が観客大賞を受賞したのも今年のトピックだ。本作はIVRCのなかでも20歳以下の学生限定による「ユース部門」の作品で、2人で渡し船を漕ぐ教習が受けられるというもの。教習をクリアするには、お互いが的確に声がけをするなどして、チームワークを意識する必要がある。こうしたコミュニケーションの特殊性が来場者に受け、観客大賞につながった。
 『きになるき』(左)、『超・呼吸体験: VReath』(右)
『きになるき』(左)、『超・呼吸体験: VReath』(右)
 『渡し舟教習所始めました』
『渡し舟教習所始めました』
VR HMDとゲームエンジンの普及により、VRやインタラクティブコンテンツを制作するための間口は、どんどん広がっている。岩田氏が講評したとおり、今後はVRの本質的な要素である「感覚フィードバック」を、どのように体験者に提示するか……すなわち「世界観」が重要視されることになるだろう。世界観はまた、作品を通してクリエイターが社会に訴えたいテーマにもつながる。次回もどのような作品が登場してくるか楽しみだ。
 参加者による記念写真
参加者による記念写真
(脚注)
2003年よりヨーロッパにおけるVRの最大のイベントであるLaval Virtualと相互に優秀作品の招待参加を実施。
(information)
第27回国際学生対抗バーチャルリアリティコンテスト 決勝大会
(一般学生部門予選通過・ユース部門選抜・国際部門招待作品)
会期:2019年11月16日(土)、17日(日)
会場:テレコムセンタービル
主催:日本バーチャルリアリティ学会IVRC実行委員会
https://ivrc.net/2019/
※URLは2020年2月10日にリンクを確認済み











