新型コロナウイルス禍において、アート作品のオンライン上での展示が世界でさまざまに試行された。ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離の拡大)を経験した私たちは、今後、これまでとは異なる展覧会の活動モデルを想定していく必要があるだろう。メディア・テクノロジーを駆使し、ネットワーク上での作品公開などを展開してきたメディアアートは、ポストコロナ時代の芸術、そして展覧会のあり方と親和性があるのではないか。新型コロナウイルスが示唆する、展覧会の新しいヴィジョンとその可能性を探ってみたい。
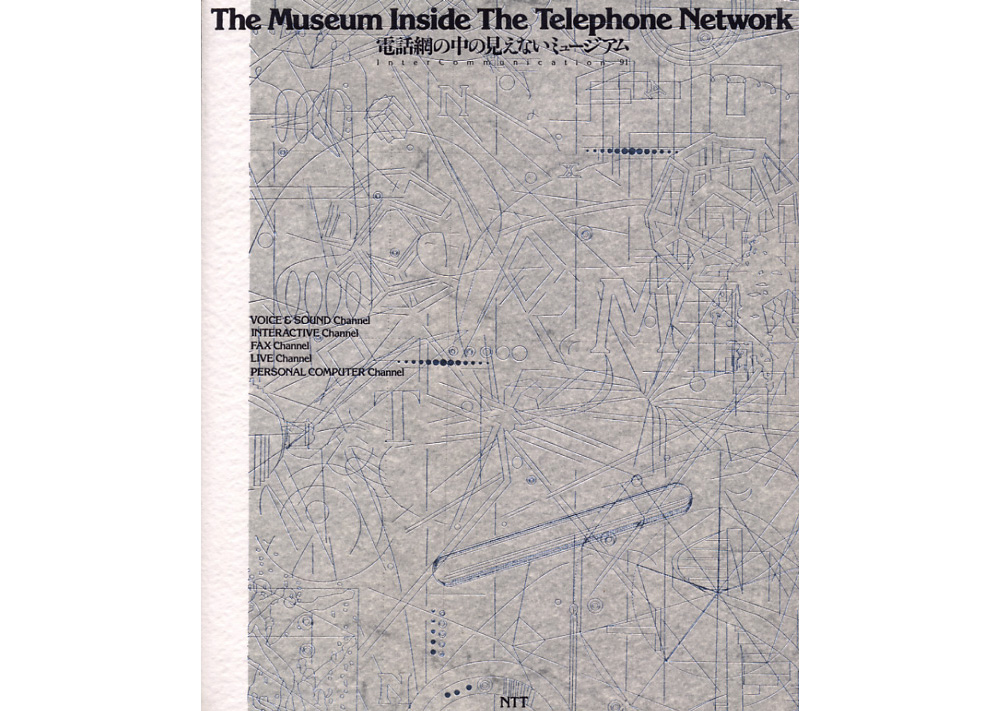 「インターコミュニケーション’91 電話網の中の見えないミュージアム」カタログ
「インターコミュニケーション’91 電話網の中の見えないミュージアム」カタログ
新型コロナウイルス禍におけるオンライン展覧会の試み
新型コロナウイルス(COVID-19)の世界規模の感染拡大により、日本では、2020年2月末から国内の美術館、博物館の多くが開催中の展覧会を中止し、臨時休館となりました。当初2週間ほどとされた外出自粛要請が、4月に入り、感染拡大に伴う緊急事態宣言の発令を受けて延長されると、いくつかの展覧会はそのまま会期を終え、また、準備されながらも一般公開されることなく、実質中止を余儀なくされたものもありました。5月の段階では(註1)、展覧会の再開予定日を明確に提示することができないまま待機状態の展覧会が多くありましたが、中旬以降は緊急事態宣言解除を前提に、感染防止に配慮した対策を講じたうえで再開への動きが見られるようになります。そして、5月25日の緊急事態宣言解除後、6月上旬には、多くの美術館、博物館が展覧会の再開を発表、7月現在では、事前予約制や、定員制限を設けたり、当初の会期を延長したりするなどして、多くの美術館が活動を再開しています。
新型コロナウイルス禍において、感染拡大防止の措置として、人と人との接触を可能な限り控えることが必要とされるため、不特定多数の人を会場に集める展覧会という催しは、実施することが一時的に困難となりました。そのような、私たちが展覧会を体験する機会を失った状況のなかで、美術館では、中止になってしまった展覧会や、始まったものの観客を迎え入れられない展覧会を、それを待ち望んでいる観客に届けるための方法として、インターネットを使用したオンラインでの公開を始めました。
展覧会の様子を記録撮影した動画配信、VR(バーチャルリアリティ/仮想現実)によるインタラクティブに展覧会を体験できるプログラムなどをはじめ、キュレーターによる展覧会の解説など、自宅にいながら展覧会を疑似体験するための、各館による独自の非常時への対応が行われたのです。
オーストリア・リンツのアルス・エレクロトニカ・センターでは、センターの休館に伴い、展覧会のガイドツアー、フューチャーラボの見学などを自宅で体験できるプログラム、Ars Electronica Home Deliveryを開始しました。
 Ars Electronica Home Deliveryトップページ
Ars Electronica Home Deliveryトップページ
国内美術館では、一例として、広島市現代美術館での「式場隆三郎:脳室反射鏡」展のオンライン版「おうちで式場展」、森美術館(東京)での「未来と芸術展」、東京国立近代美術館での「ピーター・ドイグ展」などが、360度映像によるバーチャル展覧会を公開しています(註2)。また、アーティストからも、展覧会場という現実の場を持たない、オンラインでの作品発表が試みられています。
ポストコロナ社会では新たな展示モデルが模索される
こうした試みは、非常時への対応、開催できない展覧会の補完といった目的を持ったものではありますが、それらは何らかのかたちで、それ以後の世界に対する示唆を含んだものとならざるをえないはずです。もちろん、展覧会においては、実際の展示空間において作品を体験することが重要であるという認識は、どの美術館での展覧会でも(メディアアートの展覧会においてもまた)共通するものです。しかしその一方で、新型コロナウイルス禍以後の社会が示唆するのは、それだけではない体験共有の方法が模索される可能性だと言えるでしょう。
新型コロナウイルス禍以来、世界はその様相を一変させました。そして、その完全な収束には長い時間がかかるであろうこと、その後の社会はそれ以前とは異なる生活様式を私たちに要請するものとなるだろうと予測されています。そうした、まったく予期せぬ社会の変動のただなかで、展覧会を体験することにおいてもまた、これまでとは異なるあり方、公開の形態を前提に考えていくことになるでしょう。そうした模索は、特に多くの観客を集めなければならないという、これまでの展覧会の成立条件を危うくするものでもあります。多くの来館者を見込んだブロックバスター展(新聞社などと美術館との共催による、多くの観客動員を見込んだ展覧会)は、感染拡大に配慮すればこれまでのようなビジネスモデルとしては成立しなくなってしまうでしょう。
感染リスク低減のために密集を避けるソーシャル・ディスタンシングは、私たちの日常的なコミュニケーションを変え、人と接する際のスタイルを変えています。感染防止対策は、各館においては大きな負担を強いられるものです。それでも、美術館という場所とそこでの体験が私たちに与えてくれるものが、私たちにとって必要なものであり、むしろこうした非常時だからこそなおさらに、再開のためのさまざまな検討がなされています。しかし同時に、これまでとは異なる活動モデルを想定することもまた急務となっているのです。
改めて関心が寄せられるメディアアートの方法論
そうしたバーチャルな展覧会という方法論がさまざまに試行されている状況において、これまでメディア・テクノロジーを基盤として、ネットワーク上での作品公開などを展開してきたメディアアートに、改めて関心が寄せられるようになっています。
美術評論家で多摩美術大学教授の椹木野衣さんは、冷戦終了後のグローバリズムと、そのなかでのグローバル資本主義において、単に作品としての価値だけにとどまらず、観客と作品との関係性やコミュニケーションによって価値を生みだす芸術(ソーシャリー・エンゲイジド・アート)が展開され、それは従来の作品(あるいは展覧会)という概念を大幅に変更するものだったと論じています。そして、そうした同時代の芸術が、この新型コロナウイルス禍によって、移動、流通を制限されたグローバル経済の萎縮とともに停滞を余儀なくされていると指摘しています。しかし、このような状況において、だからこそメディアアートの行ってきた活動に注目しています。
椹木さんは、メディアアートを「新技術を積極的に導入した情報芸術」としての「リモート・アート」として捉え、さらには、「感染源となりかねない美術館のような大規模施設を必要としない。その意味では、「在宅芸術」(ステイホーム・アート)の典型と考えられる」と、新型コロナウイルス禍以後のビジョンを見出しています。また、椹木さんは、そうした「リモート・アート」としてのメディアアートの大規模な試みの始まりとして、1991年に行われた「電話網の中の見えないミュージアム」を挙げ、冷戦構造の終焉直後に、「スマホはおろかネットさえ普及していないなか、電話機とファクシミリを使い、100人に及ぶアーティストや作家が参加したこの仮想のミュージアムを、かつてのような時代を先駆ける先端的な表現としてではなく、家にひきこもる在宅芸術の原点と考えるなら、今あえて興味深い」と評しています(註3)。
「電話網の中の見えないミュージアム」に見る新ビジョンへの模索
「インターコミュニケーション’91 電話網の中の見えないミュージアム」(註4)は、日本の電話事業100周年(1990年)の記念事業としてのNTTインターコミュニケーション・センター[ICC]開館に先立ち、1991年にプレ・イベントとして開催された企画です。当時、そしてスマートフォンが主流となった現在も、私たちにとって「最も身近なコミュニケーション・ツール」である電話を使用して、首都圏の1都7県の電話回線内を会場とした「見えないミュージアム」というアイディアは、現在から見れば、インターネット時代以前にその登場を予感させる先駆的なイベントとして捉えることができます。
同企画は「電話やファクシミリ、コンピュータを通じてアクセスし、約100人のアーティストや作家、文化人等の作品やメッセージを鑑賞するという実験的イヴェント」(註5)で、電話やファクシミリといった身近なメディア、そしてその後急速に身近になっていくコンピュータの技術的拡張性がもたらす未来の可能性を提示するものでした。当時のパンフレットには、「目には見えないけれど、とっても広いこのミュージアム」(註6)といった言葉が見られます。それは、物理的な空間の制約が無い電話網を会場とし、多くの参加者の作品を発信することを可能とした、モノとしての作品ではなく出来事としての情報を発信する、情報通信時代のミュージアムを標榜したものでした。

「インターコミュニケーション’91 電話網の中の見えないミュージアム」パンフレットより
電話においては音声による出品作品が多くなりましたが、ファクシミリではドローイングや手書き原稿やマンガ、パソコン通信ではデジタルデータが鑑賞できました。さらには、プッシュホンを使ったインタラクティブな作品体験、そして電話によるライヴ中継では、感想をファクシミリで送ることで双方向のコミュニケーションを行っています。
この「電話網の中の見えないミュージアム」は、電話というメディアにおいて、通話機能以外に使用可能な技術的拡張可能性が実用化されようとしていた、ある意味では通信メディアの過渡期に、その可能性を極限まで試みたイベントだったと言えるでしょう。ネットワーク上のミュージアムというコンセプトもさることながら、電話というどこか古いメディアに属しているイメージのあるメディアがモチーフになっていることによって、その革新性がより強調されているように感じられます。また、それは、そのメディアが内在しているにもかかわらず顕在化されてこなかった可能性を発見すること、道具を別の見方で捉え直したときに現われる、隠された潜在的な能力を引き出すこと、といったメディアアートの持つ性質と同様の試みであると言えるのです。
(脚注)
*1
政府による対処方針や、日本博物館協会によるガイドラインが下記のとおり発表されました。
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」令和2年3月28日、5月25日変更
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000633503.pdf
「博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」令和2年5月14日
https://www.j-muse.or.jp/02program/pdf/coronaguide0000.pdf
*2
ほかには例えば、川崎市岡本太郎美術館が、常設展示と企画展「音と造形のレゾナンス-バシェ音響彫刻と岡本太郎の共振」が3DVRや360°カメラで撮影された映像が公開されています。
https://www.taromuseum.jp/event/f・バシェ生誕100年、日本万国博覧会から50年音と造
*3
「連載・椹木野衣 遮られる世界〜パンデミックとアート〈第8回〉」、西日本新聞4月23日朝刊掲載。ウェブマガジン「ARTNE」に転載。
https://artne.jp/series/1009
*4
「インターコミュニケーション’91 電話網の中の見えないミュージアム」1991年3月15日(金)~29日(金) 企画:浅田彰、伊藤俊治、彦坂裕 会場:電話回線内(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨1都7県)
*5
「NTT インターコミュニケーション’91「電話網の中の見えないミュージアム」」、ICC「展示&イヴェント」ページ
https://www.ntticc.or.jp/ja/exhibitions/1991/intercommunication-91-the-museum-inside-the-telephone-network/
*6
「インターコミュニケーション’91 電話網の中の見えないミュージアム」パンフレット
※URLは2020年7月7日にリンクを確認済み













