科学と芸術が融合した世界的にも注目度が高まる現在進行形の芸術潮流、バイオアートとは何か? イントロダクションとして、今、日本語で読める参考文献を紹介する。
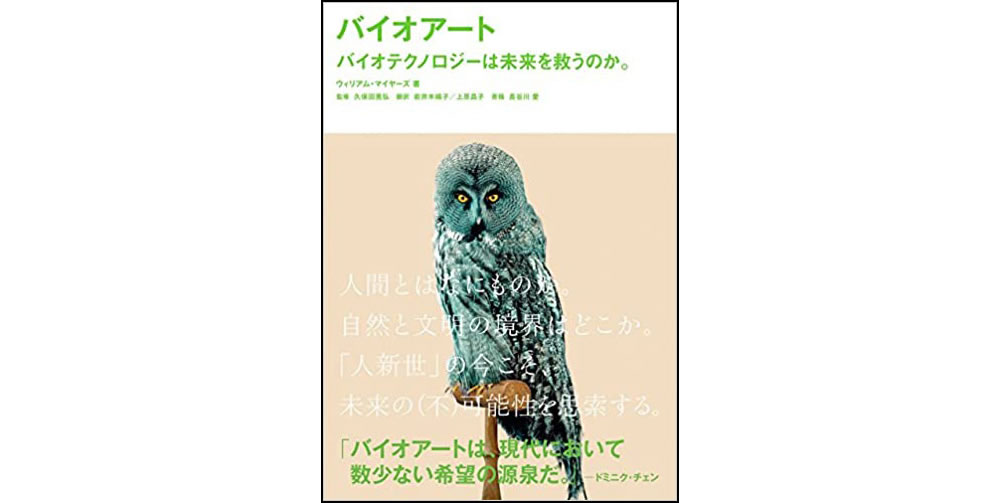 ウィリアム・マイヤーズ『バイオアート バイオテクノロジーは未来を救うのか。』表紙
ウィリアム・マイヤーズ『バイオアート バイオテクノロジーは未来を救うのか。』表紙
バイオアートとは何か?
近年、芸術の一ジャンルとしてバイオアートが注目を集めている。バイオアートとは、おおまかにはバイオテクノロジーを用いた芸術や、生きた素材を表現媒体とした芸術を指すが、使用される場面によって指し示す範囲が微妙に異なることもあり、必ずしも定義が定まっているわけではないのが現状であろう。人間は古くから突然変異と交配を利用して鑑賞用の動植物を作り出してきたが、これらはバイオアートの範疇で扱われないことが多い。また、生物の細胞に彩色したり、顕微鏡の拡大画像を使って生物に見られる造形美に着目した作品群があるが、今日的な意味でのバイオアートには含めないこともある。
1990年から2003年にかけてのヒトゲノム計画(註1)や1996年のクローン羊ドリーの誕生、2006年の人工多能性幹細胞(iPS細胞)(註2)の培養技術の開発など、遺伝子に関わる研究の進展とともに、バイオアートは興隆した。この間、生命科学の発達とともに、遺伝子組み換え作物(GMO)の是非、世界的な規模の食糧危機、地球温暖化などの環境破壊に伴う動植物の絶滅、人工生命や生死に関わる生命倫理、細菌やウイルスとの闘いと共生など、さまざまな課題が議論されてきた。バイオアートはその多くが、こういった議論を深めたり広めたりするような社会批評性をはらんでいる。バイオテクノロジーを用いて未知の領域に果敢に踏み込み、科学の専門家ではない人々にもアクセスしやすい形で公開され、ひとつの結論を提示するよりも敢えてさまざまな可能性や選択肢を広げてみせ、観る人の想像力を喚起するような性格を有するのがバイオアートの特徴である。
現代美術は次々と発表される作品の多様化や議論の深化によって定義が更新されていく。本稿では、バイオアートという現在進行形の芸術分野について知り、考えるための水先案内人となってくれる日本語で書かれた書籍を何冊か紹介する。
バイオアートとは何かを知るための文献
ウィリアム・マイヤーズ著、久保田晃弘監修、岩井木綿子/上原昌子翻訳、長谷川愛寄稿『バイオアート バイオテクノロジーは未来を救うのか。』(ビー・エヌ・エヌ新社、2016年)は、バイオアートの展覧会を数多く手掛けるウィリアム・マイヤーズが2015年に執筆した『Bio Art: Altered Realities』(註3)を翻訳したもので、日本語で読めるバイオアートの基本文献として外せない1冊である。さまざまな地域で活動する約60名(組)のアーティストを取りあげ、作品のカラー写真と解説を掲載している。遺伝子操作技術を使って参加者がDNAを改変することができる作品、生物の生態系を人工的に作り出そうとする作品、生殖に関する固定観念を覆すようなアイデアを提示する作品など、まだ定義の定まらないバイオアートの多様性や可能性を拓く多彩な作品が選ばれている。著者は2012年に『Bio Design』(註4)を執筆しているが、本書では実用性の高いバイオデザインと社会批評性が高いバイオアートの違いについても言及している。バイオアーティストには「文化の変容を通訳する役割」(註5)があり、バイオアートは人間が生み出した現代の諸問題に対する「『危機意識』の凝縮物なのだ」(註6)と述べることで、現代社会に対して警鐘を鳴らし、さまざまな未来像を目に見える形で提示しようと試みるバイオアートのあり方を浮き彫りにしている。
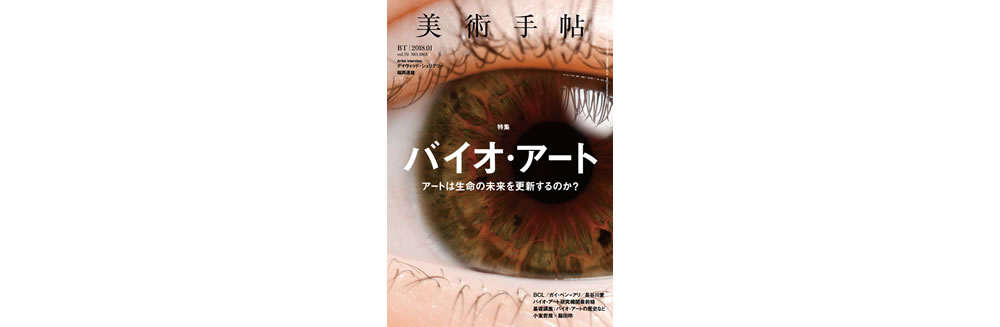 『美術手帖』2018年1月号表紙
『美術手帖』2018年1月号表紙
『美術手帖』2018年1月では、現在進行形のバイオアートについて、さまざまな側面からの紹介を試みる特集「バイオ・アート アートは生命の未来を更新するのか?」が掲載されている。バイオアートの分野で次々と作品を発表しているアーティストへのインタビューと作品紹介のほか、生物学や芸術学の研究者やキュレーター、弁護士などさまざまな立場の専門家による寄稿が充実している。さらにバイオアートを生み出す国内外の先端的な機関の紹介、バイオアートの用語辞典や文献紹介など、数年前の特集ではあるが、バイオアートのおおまかな輪郭や論点を把握するのに大変便利な1冊である。ちなみに、同誌2020年6月号の「特集 新しいエコロジー 危機の時代を生きる、環境観のパラダイム・シフト」でもバイオアートがいくつか紹介されている。エコロジーをキーワードに新しい世界観を提示しようとする作品やアーティストを紹介するこの特集からは、今やバイオアートがけっして新奇なものではなくなり、現代美術の表現のひとつとして欠かせない分野となっていることが読み取れる。
 『Я[アール]:金沢21世紀美術館研究紀要』2017年第7号表紙
『Я[アール]:金沢21世紀美術館研究紀要』2017年第7号表紙
『Я[アール]:金沢21世紀美術館研究紀要』2017年第7号は「バイオテクノロジーと芸術」の特集号である。金沢21世紀美術館は日本においてバイオアートの紹介を積極的に行ってきた数少ない施設で、美術館としては世界で初めてiPS細胞を用いた作品を展示した「Ghost in the Cell:細胞の中の幽霊」展(2015〜2016年)や、「コレクション展2 死なない命」展(2017〜2018年)といった企画を通してこの分野の牽引役を務めてきた。この特集号にはバイオアートに関する4本の論考が掲載され、そのうちの2本はバイオアートの基本文献として知られる『Signs of Life』(註7)所収のエドワルド・カッツとジョー・デイヴィスの論考を日本語に訳したものである。エドワルド・カッツは聖書の一節をDNA塩基対に変換しバクテリアに組み込んだ《Genesis》(1999年)や遺伝子工学によって誕生した緑の蛍光色のウサギ《GFP Bunny》(2000年)といったセンセーショナルな遺伝子組み換え作品を制作したアーティストで「バイオアート」の命名者でもある。ジョー・デイヴィスは地母神を表すルーン文字の形をDNA配列に暗号化した《Microvenus》(1988年)など遺伝子組み換え技術を用いた作品を早くも80年代より手がけ、先駆者として知られるアーティストである。3本目は哲学者のニック・ボストロムによるポストヒューマンをテーマとした論考で、人間性や生命について問い続けるバイオアートを理解する助けとなる。4本目は金沢21世紀美術館で上述した展覧会のバイオアートの展示を企画した髙橋洋介による論考で、遺伝子組み換え生物を芸術作品の媒体として用いることの意味を考察するほか、美術館などでバイオアートを扱う際の実際的な課題についても言及しており興味深い(註8)。
 森美術館監修『未来と芸術 Future and the Arts』
森美術館監修『未来と芸術 Future and the Arts』
(「未来と芸術 AI、ロボット、都市、生命――人は明日どう生きるのか」展図録、美術出版社、2019年)表紙
本書は2019年11月19日から2020年3月29日まで森美術館で開催された「未来と芸術」展の図録である。同展はAI(人工知能)、バイオテクノロジー、ロボット工学、AR(拡張現実)など先端的なテクノロジーを用いたアートや建築、デザインなどを紹介することを通して、未来の都市や人間の生活についてさまざまな角度から考察することをテーマとしている。「都市の新たな可能性」「ネオ・メタボリズム建築へ」「ライフスタイルとデザインの革新」「身体の拡張と倫理」「変容する社会と人間」の5つの章で構成され、バイオアートを含む多様な表現手法による作品が展示された。実験室のような「バイオ・アトリエ」に、「ゴッホの耳」の再現を試みたディムート・シュトレーベの《シュガーベイブ》(2014年~)や、微生物のDNAを音楽の記録媒体としたやくしまるえつこの《わたしは人類》(2016、2019年)など生きた細胞や微生物を用いた作品群が実物展示されたほか、微細藻類が酸素を生成し続ける建築のシミュレーションを行うエコ・ロジック・スタジオの《H.O.R.T.U.S.XL アスタキサンチン g》(2019年)や、3人以上の親の遺伝子を持つ子どもとその家族の形を問う長谷川愛の《シェアードベイビー》(2011、2019年)といった、バイオテクノロジーの進展によって変わりえる生活や社会のあり方を考えさせる作品も展示された。本展図録には多摩美術大学教授の久保田晃弘による論考「バイオメディアのパフォーマティヴィティ」、ポンピドゥー・センターのシニアキュレーターであるマリー=アンジュ・ブレイエによる論考「『生きた』人工物としてのデザイン」、シンガポールのアート・サイエンス・ミュージアム館長のオナー・ハーガーによる論考「生命の次なるもの――人工の身体、合成自然、シェアされる未来」などが掲載され、多角的な視点からバイオテクノロジーと芸術の接点を考察している。展覧会のサブタイトルにもなっている「生きる」ことを思考するうえで、生命とは何か? という問いに鋭く切り込むバイオアートが存在感を増していることが実感できる1冊である。
デザイン、科学、哲学などの隣接領域を通して
バイオアートをより深く知るための文献
 アンソニー・ダン/フィオナ・レイビー『スペキュラティヴ・デザイン 問題解決から、問題提起へ。――未来を思索するためにデザインができること』表紙
アンソニー・ダン/フィオナ・レイビー『スペキュラティヴ・デザイン 問題解決から、問題提起へ。――未来を思索するためにデザインができること』表紙
アンソニー・ダン/フィオナ・レイビー著、久保田晃弘監修、千葉敏生訳、牛込陽介寄稿『スペキュラティヴ・デザイン 問題解決から、問題提起へ。――未来を思索するためにデザインができること』(ビー・エヌ・エヌ新社、2015年)は、2005年から2015年までロンドンのRCA(Royal College of Art)のデザイン・インタラクション学科長であったアンソニー・ダンと、同校の研究者であり2011年から2015年までウィーン応用芸術大学の教授を務めていたフィオナ・レイビーが2013年に出版した『Speculative Everything : design, fiction, and social dreaming』(註9)の日本語版である。スペキュラティヴ・デザインとは、課題解決のために商業活動と密接に結びついたりするような従来型のデザインとは異なり、問題設定そのものを問い直し、思索や議論を促す性格を持ち、現在とは異なる形の世界を人々に想像させる挑戦的なデザインである。スペキュラティヴ・デザイン分野においては、例えば生物学などの科学技術の発達に対して考察を促す研究が積極的に行われており、その実践の結果としてバイオアートは重要なパートを占めている。本書では、ゲオアグ・トレメルと福原志保が結成するアーティスティック・リサーチ・フレームワークであるBCLや長谷川愛など、RCAでデザインを学んだアーティストによる作品についても触れており、社会批評性が高く未来志向型のバイオアートと先端的なデザイン思考との関係性を知ることができる。ちなみに、長谷川愛はMITメディアラボや東京大学での自身による講義をもとにした『20XX年の革命家になるには──スペキュラティヴ・デザインの授業』(ビー・エヌ・エヌ新社、2020年)を出版しており、スペキュラティヴ・デザインの考え方をアートの世界で実践的に用いるための方法を具体的に説明している。
 岩崎秀雄『〈生命〉とは何だろうか 表現する生物学、思考する芸術』表紙
岩崎秀雄『〈生命〉とは何だろうか 表現する生物学、思考する芸術』表紙
『〈生命〉とは何だろうか 表現する生物学、思考する芸術』(講談社現代新書、2013年)の著者の岩崎秀雄は早稲田大学理工学術院教授で、2007年から生命をめぐる科学・思想・芸術に関わる表現・研究のプラットフォームmetaPhorestを主宰している。合成生物学の研究を行いながら自らも作品制作を手がけ、2019年の第22回文化庁メディア芸術祭においてバクテリアを用いた《Culturing〈Paper〉cut》(2018年)がアート部門優秀賞を受賞している。本書は現在の生命科学が目指す方向性を平易な文章で説明するとともに、科学の領域、特に生命について哲学や芸術といった視点から語る必要性を訴える。第5章「現代芸術における生命」ではバイオアートの具体的な作例や研究機関についても挙げられ、生命科学の研究者でありアーティストでもあるという立場からバイオアートを解説する貴重な文献である。
 秋山史典『あたらしい美学をつくる』表紙
秋山史典『あたらしい美学をつくる』表紙
『あたらしい美学をつくる』(みすず書房、2011年)の著者の秋庭史典は、名古屋大学大学院情報学研究科准教授で、美学・芸術学を専門としている。美を自然から出発するものと位置づけ、自然を知ろうとする科学や数学や情報学といった学問領域とのやり取りから、現代の美がいかなるものかという問いに対する解答を導き出そうと試みる本である。秋庭はイマヌエル・カントの美学を振り返り、バイオエステティクスやポストヒューマンといった思想の流れを経たうえで、自然の相互作用や共生や多様性といった観点が重要であるとし、最終的に、自然に対する科学的な探究と、人間はどう生きるべきかという哲学的な探究の両方を兼ね備えたもののなかに美の可能性があるとする。生命科学と芸術の領域を横断するバイオアートを理解するうえで、参考となる1冊である。
番外編:バイオアート的視点からも読めるマンガ
 萩尾望都『マージナル』表紙
萩尾望都『マージナル』表紙
萩尾望都『マージナル』(小学館、1999年)(註10)は「少女マンガの神様」と称され、「ポーの一族」シリーズ(1972年~)や『トーマの心臓』(1974年)といった文学的な作品のほか、『11人いる!』(1975年)や『スター・レッド』(1978~1979年)など数多くのSF作品を発表した萩尾望都の長編マンガである。西暦2999年、地球の環境汚染が進み、人間はウイルス感染によって生殖能力を失い、男性のみが暮らしている。この崩壊しかけた世界「マージナル」の外部には、じつはその世界をコントロールするもうひとつの世界「センター」が存在し、死への歩みを進める地球を壮大な実験場として、科学者たちが新しい人類を創造しようと試みていたのだった……。本書はバイオアートが問題とするような生命倫理、環境汚染、情報統制、ジェンダーと身体といったさまざまな切り口で現在と未来の姿に想いを馳せることができる良質なSFファンタジーである。
本稿では、バイオアートの扉を開くための基礎的な文献を紹介した。ほかにも、本稿で触れた『Signs of Life』をはじめ、Robert Mitchell著『Bioart and the Vitality of Media』(University of Washington Press、2010年)や、Alexandra Daisy Ginsbergほか著『Synthetic Aesthetics: Investigating Synthetic Biology’s Designs on Nature』(The MIT Press、2017年)といった未邦訳の文献があるが、また別の機会に取りあげたい。
(脚注)
*1
ヒトゲノム計画とは、ヒト染色体の遺伝情報(DNA配列)を解読し、染色体のどこにどのような遺伝情報が書かれているかを明らかにした米国による巨大プロジェクトである。ヒト染色体にはおよそ30億の塩基対があるため、解読には膨大な時間や費用がかかった。
*2
人工多能性幹細胞(iPS細胞)とは体細胞へ4種類の遺伝子を入れることによって得られる細胞である。さまざまな細胞に分化でき、さらに増殖することができるため、再生医療や創薬への応用が期待されている。
*3
William Myers, BioArt: Altered Realities, Thames & Hudson, 2015.
*4
William Myers, Bio Design: Nature, Science, Creativity, Museum of Modern Art, 2012. 本書については未邦訳である。
*5
ウィリアム・マイヤーズ『バイオアート バイオテクノロジーは未来を救うのか。』26ページより引用。
*7
Eduardo Kac ed., Signs of Life: Bio Art and Beyond, The MIT Press, 2007.
*8
なお、本号のテクストは金沢21世紀美術館のウェブサイト内の下記のページにて閲覧可能。
https://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=52&d=11
*9
Anthony Dunne and Fiona Raby, Speculative Everything: design, fiction, and social dreaming, The MIT Press, 2013.
*10
初出「プチフラワー」1985年8月号〜87年10月号、小学館。
※URLは2020年8月31日にリンクを確認済み
あわせて読みたい記事
- メディア・テレスコープ——メディアアートから思考する第1回 メディアアートとはどのような芸術なのか2019年6月12日 更新
- 「萩尾望都SF原画展 宇宙にあそび、異世界にはばたく」レビュー2018年7月6日 更新
- 2019年度メディア芸術連携促進事業 研究成果マッピング シンポジウムレポートメディアアート分野発表2020年4月24日 更新











