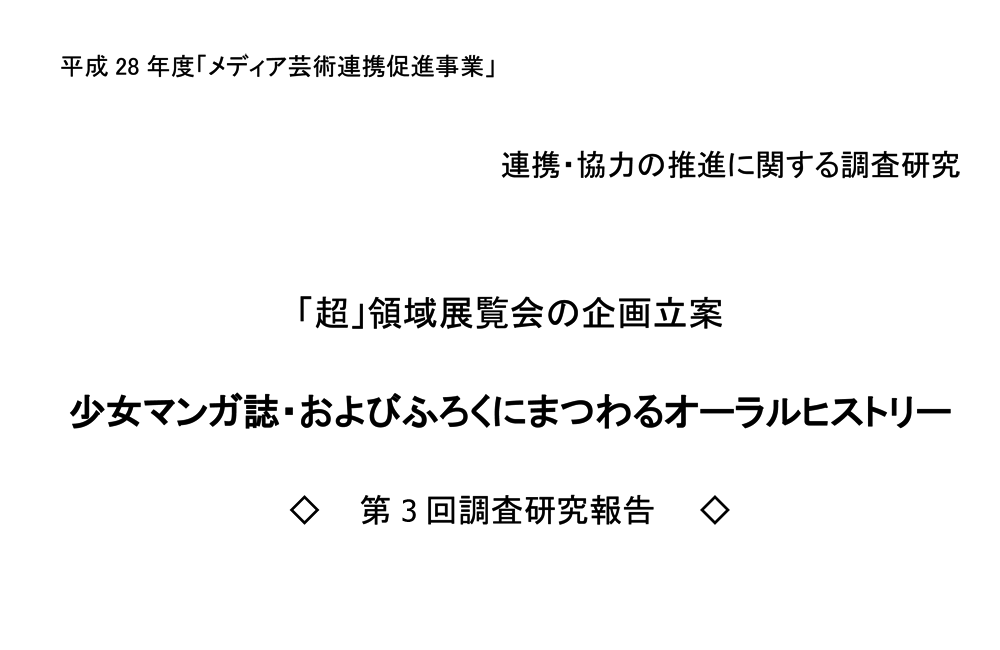
1.調査研究の目的
「超」領域展覧会の研究目的は、マンガ、アニメ、ゲーム、メディアアートの4領域の史資料やコンテンツ等の「共同利活用を実現する」ため、特に史資料やコンテンツの利活用のモデル(案)として、連携展覧会(領域横断・資源シェア型)が効果的であることを実証する「モデル展覧会(案)」の立案を行うことにあります。
昨年度事業として実施した「少女雑誌ふろくの歴史・展示」研究では、戦前から刊行されている代表的な少女マンガ雜誌や、戦後刊行され現在も継続し、60年の歴史を持つ集英社『りぼん』とその「ふろく」に着目して、それらが果たしてきた社会的な意義、読者への影響などを読み解く「展覧会」を開催するための準備作業を行いました。
今年度はこの成果を基に、少女マンガ誌史上最高発行部数である255万部を達成した、1990年代の『りぼん』編集者や関係者への聞き取り調査を行い、オーラルヒストリーとしてのとりまとめを行っています。昨年と今年の研究成果は、2016年12月から2017年2月まで京都国際マンガミュージアムで開催され、2017年6月まで明治大学米沢嘉博記念図書館にて巡回している「LOVE♥りぼん♥FUROKU 250万乙女集合!りぼんのふろく展」の展示内容にも活用されています。
2.調査結果の公開
聞き取り調査は以下の方々へ実施しました。
| りぼん編集長 | 冨重 実也氏 |
|---|---|
| りぼん副編集長 | 後藤 貴子氏 |
| 元りぼん編集者/児童書編集部 編集長 | 江本 香里氏 |
| 元りぼん編集者(現在は集英社を退職) | 岩本 暢人氏 |
| 元りぼん編集者/学芸編集部企画出版 編集長 | 小池 正夫氏 |
| 元りぼん編集者(現在は集英社を退職) | 宇都宮 紘子氏 |
貴重な研究成果が得られたため、聞き取り調査の記録を公表することとしました。公表は、とりまとめが完了した順に実施していく予定です。
調査記録の公開に際して
1955年の創刊以来、日本の少女マンガ誌およびふろく文化を牽引してきた一つに『りぼん』があります。本誌は特に1980年代後半から1990年代前半にかけては発行部数が上がり1994年には少女マンガ誌史上最高発行部数となる255万部を達成しました。その記録はいまだに破られていません。当時の『りぼん』では、読者のことを「250万乙女」と呼び、作品のキャッチフレーズなどに採用していました。
さて、かつての「250万乙女」は今や30代。仕事に子育てに活躍している女性が主です。なぜ今のアラサー女子がこんなにもパワフルなのか?そのパワーの根源に『りぼん』は存在するのではないでしょうか?250万という膨大な数字が現在の女性たちとリンクしないはずはありません。『りぼん』は読者に明日を前向きに切り開く様々な術を教えてくれました。もちろん、この世代や『りぼん』に限ったことではありませんが、今回はこの250万乙女の原風景はいかにして作られたかに迫りたいと思いました。
今回のオーラルヒストリーで対象としたのは、80年代から現在までを対象に、『りぼん』を作った編集者たちの話です。特に、ふろくについては、70〜80年代までの研究蓄積は先行研究本や展覧会で語られることはありましたが、それ以降の年代については、ほとんど語られることが少ない分野になります。
なお、このオーラルヒストリーの内容は、京都国際マンガミュージアムで2016年12月から2017年2月まで開催され、2017年6月まで明治大学米沢嘉博記念図書館で巡回中の「LOVE♥りぼん♥FUROKU 250万乙女集合!りぼんのふろく展」の内容の参考にもさせていただきました。オーラルヒストリーと合わせてお楽しみいただければ幸いです。
倉持佳代子
京都国際マンガミュージアム
京都精華大学国際マンガ研究センター
調査記録3 江本香里氏(元りぼん編集者・ふろく担当)
第3回のオーラルヒストリーは、『りぼん』が最大発行部数255万部を達成する90年代前半よりふろくを担当し、「ふろくファンルーム」では「かおりん」のキャラクターで読者に親しまれた江本香里さんです。売上がピークに達しようとする90年代、『りぼん』に新入社員で配属され、先輩女性編集者2人と助け合いながらふろく作りに切磋琢磨したこと、そして、ある時からその仕事を一手に引き受けなければならなかったことなど、当時の苦労話をたくさんお聞きしました。制作裏話からは、“大人が持っていても恥ずかしくない良質なふろくに”という江本さんのこだわり、ふろくにかける情熱が垣間見られます。かつて250万読者がふろくに夢中になったのは、そうした編集者の情熱が読者に伝播していたからこそ。そんなことを今回のオーラルヒストリーで実感したのと同時に、当時の良質なふろくは現代女性の高い美意識を形成したものの一つだと確信しました。
少女マンガ誌・およびふろくにまつわるオーラルヒストリー 第三弾
実施日:2016年10月18日(火)
- 対象者
- ■江本香里(現・児童書編集部 編集長)1992年集英社入社
りぼん在籍期間:1992年6月〜1998年6月 - インタビュア
- 倉持佳代子、ヤマダトモコ
- 構成
- 倉持佳代子
■売上ピーク時の『りぼん』のふろく担当に
―江本さんは90年代読者にとっては、ふろくファンルームの「かおりん」でおなじみの編集者さんです。私(倉持)はその当時リアルタイムで読んでいたので、今回こうした機会に恵まれて、とても嬉しいです。さて、江本さんが集英社に入社したのは1992年。6月に『りぼん』に配属されたとのことですが、着任後すぐのお仕事がふろくだったのですか?
<江本>
いいえ。6月というのは新人の仮配属の時期なんですね。6月から9月の4ヶ月間が仮配属期間で、10月1日が正式の採用となるのですが、仮配属された部署にそのまま正式採用されることがほとんどでした。私もそのままりぼん編集部に正式に配属されたわけですが、最初の月はいろんなことをやれという感じで、研修担当の編集者の仕事の手伝いを主にしていました。正式に配属になってからも、引き続きその編集者の仕事を手伝いつつ、ふろくもちょっと手伝ってみた、といった形です。つまり最初はなんでもやる感じです。マンガもふろくも懸賞ページも。今はなくなってしまいましたが、『りぼんオリジナル』という別冊があったので、そこの読者ページもやっていました。
―なるほど。一通りのいろんな仕事を経験して、10月1日の正式採用から細かく担当が振り分けられるというわけですね。それで江本さんはふろくの担当を割り当てられたということに?
<江本>
そうですね。当時、りぼん編集部には私を含めて女性は3人いましたが、主にその3名でふろくを担当していました。
―その3人のうち1人は、宇都宮紘子(第5回オーラルヒストリー公開予定)さんですね。「ヒロコ姉」の愛称でふろくファンルームでは親しまれていました。そして、もう一人は、ふろくファンルームで「トマトちゃん」の愛称で愛された編集者Uさんですね。
<江本>
そうです。新入社員の私が一番下っ端で、2人から割り当てられた仕事をやっていたという感じでした。しかし、1年半後の94年3月に2人とも別の部署に異動してしまいます。配属1年半の新人なのに、突然全部やれと言われてそこからが大変でした。ふろくの予算を何にどう振り分けるかなどは、もともとはメインで宇都宮さんがなさっていました。そこから急に私だけになってしまったわけで、教えてもらってないことが、まだたくさんあったのに、いきなり放り出されたという感じでした。
―それは戸惑ったでしょうね。では、94年4月からのふろくは、江本さんお一人でやっていたという感じなのでしょうか?
<江本>
入れ替わりでりぼん編集部に配属されたMさんもふろく担当に割り当てられていましたが、Mさんは営業部署からの異動で編集経験はそのときゼロでしたので、一緒にやるというよりは教えながらという感じでした。なので実質、最初は一人でやっていたことになりますね。6月ぐらいに泣きました。ふろくの質も保たないといけないし量も多すぎたので、精神的にいっぱいいっぱいで。「できません。無理です」って上司に泣きつきました(笑)。
―しかし、「ふろくファンルーム」の誌面上では、トマトちゃんなどのキャラクターは残っていましたよね?
<江本>
「ふろくファンルーム」に登場するキャラは一人でやっていると話がもたないんです。だから、キャラクターだけ残して続けていたのです。
―じゃあ実際はいなくても、あたかもいるかのように(笑)。
<江本>
そうです。キャラクターがいると漫才のように掛け合いができるじゃないですか。
―現実ではいなかったなんて……!
江本さんは集英社に入られたときから、ふろくをやりたいと希望を出していたのでしょうか? 「すごくやりたい!」と思っていたからそんな状況もなんとか乗り越えられたのでしょうか?
<江本>
入社したときは、実は青年マンガ誌がやりたくて『ヤングジャンプ』を希望していました。そのころ、『ヤングジャンプ』の対抗誌の『ビッグコミックスピリッツ』には柴門ふみ先生などもいて、女性も読める性差のないマンガ作品が作れたら良いなと思っていたので。
―そうだったんですね。『りぼん』は元々読まれていたのでしょうか?
<江本>
実は私はどちらかといえば小学館の雑誌をずっと読んでいました。『小学1年生』から『小学6年生』の学年誌、その後は『週刊/月刊少女コミック』や『ビッグコミックスピリッツ』と続きました。『りぼん』は正直あんまり読んでいなかったんです。だけど、小学校の時になぜかふろくだけをたくさん持っている友達がいて、少女マンガ雑誌のふろくだけを私にたくさんくれたんです。今思うと、多分その子のお父さんのお仕事の関係だったと思いますが、その友達のおかげで、『りぼん』や『なかよし』のふろくをたくさん持っていました。
―なるほど。そうした体験があったことは実際一人でふろくを担当することになったとき、すごく役にたったのではないですか?
<江本>
その経験は大きかったと思います。それがその後の人生にかなり影響しましたね。その友達には感謝しています。友達がくれたふろくのうち、陸奥A子先生のふろくなどは、特に記憶に残っていて、その時のふろくのスピリットは自分がふろくを作る側に立ったときに、無意識に引き継いでいたと思います。
■90年代、ふろくができるまで
―改めて当時のふろくができるまでの流れを教えていただけますか?
<江本>
大体雑誌の発売の半年ぐらい前に各印刷会社に依頼を出します。たとえば、「レターセットをメインでつけます」とか、「クリスマスなのでそれに関連したシールにしたいです」など、大まかなテーマを提示します。それを元に印刷会社からプレゼンテーションが大体5ヶ月ぐらい前にあります。プレゼンは、ほとんど丸一日かかりましたね。当時、プレゼンにきていた印刷会社は5〜6社ぐらいあったと思います。
―つまり、半年前にざっくりと編集サイドから「〜月号のふろくはこのテーマ」と案を出す。5ヶ月ぐらい前に印刷会社5、6社がプレゼンテーションする、といった流れですね。
<江本>
そうです。印刷会社からは見本や設計図だったり、アイデアスケッチのようなものだったりを持ってきてもらっていました。ふろくにかける予算はあらかじめ決まっていたので、その予算内で、メインとサブのふろくを決めていきました。編集部内では、ふろく担当者と編集長、副編集長の中でふろくの内容を決めていました。会議は「親分」がしきっていました。
―親分? なんですか? 誰かのあだ名ですか?
<江本>
いえ、違います。今いろいろ思い出しました。毎月誰が「親分」かを途中から決めていたんです。例えば、今月の「親分」は宇都宮さんで、次はUさん、その次は私みたいに。「親分」は、その月につけたいものを前もって印刷会社に依頼して、プレゼンテーションを受けた後、どれにするかを自分なりに予算内での組み合わせを考えておく役割です。「親分」が決めたプランをふろく担当3人で話して、「いいんじゃない」と同意したり、「私はこっちもいいと思ったけど」など意見を出し合っていました。その後、正式に編集部のふろく会議にかけるといった流れでした。大体ふろく担当3人が決めた通りになるのですが、たまに「もっと違うのがいいんじゃないか」と上司が言い出す時があって、その時はもう大変でした。でも、大体ふろく担当の意向でおおよそ決まっていました。それが決定してから、どのふろくをどのマンガ家さんに書いてもらうか、どのデザイナーさんに頼むかというのを決めていきます。あとは、ふろくを一つの印刷会社に全部頼むことはしないで、なるべくいろいろな会社に発注するようにというのが、制作部からの意向でありました。その辺の細かい微調整が意外と大変でした。
―この前はこっちの会社に頼んだから次はあちらの会社へみたいな流れもあったわけですね。
<江本>
ほかの書籍や雑誌もたくさん扱っている大きな印刷会社はまだいいかもしれませんが、ふろくメインでやってくださる印刷会社にとっては、ふろくの発注がまったくないと死活問題ですよね。だから、そこにゼロというわけにはいかないとかはありました。
―ライバルとなる少女マンガ誌のふろくはどれぐらい意識して作っていましたか?
<江本>
チェックはしていましたね。当時はふろくに関わる規定がけっこう厳しかったのですが、他誌がそれを破っていると気になったり……。たとえば、水着を入れるビニール製のバッグなどは、当時は厚さが〜ミリ以内など決められていたと思います。それなのに、他誌のふろくでどう見ても厚いのがあって、測ったらやはりオーバーしていたんです(笑)。向こうがそれやるならこっちだって丈夫なものをつけたい、となったりはしました。
■ふろくとマンガ家、読者の反響
―ふろくのイラストの割り当てはどんな風に決めていましたか? 例えば、メインのふろくは今一番勢いがある作家さんを割り当てたとか、どのように配分したのでしょうか?
<江本>
やはり大きいメインのふろくは、人気のキャラクターを割り当てていたと思います。しかし、月ごとになるべくキャラクターを変えていくようにはしたいなと思っていました。
―『りぼん』のマンガ家さんは「りぼん手帳」とかを任されるのがすごく誇らしかったみたいですね。カレンダーで1月と12月は花形だったとかそんな話も聞いたことがあります。
<江本>
トランプも花形でしたね。毎年8月号、夏休みにつけていましたが、スペードとクラブとダイヤとハートとマークが4つあるので、それぞれに人気の連載4キャラクターをつけていました。だから、トランプを見れば、その年どのマンガが人気だったかがわかると思います。
―マンガ家さんから「私こんなの描きたい」といったリクエストがあったりもしましたか?
<江本>
それは多分なかったですね。やっぱりマンガ家さんもふろくを頼まれたらそれはそれで大変なので、やりたいっていう気持ちはあるけど時間的に厳しかったり……。皆さんそれぞれ連載を持っていて、表紙やカットなど、たくさんの依頼があったので、人気マンガ家さんで自分から「このふろくのカットを描きたいです」といったリクエストはなかったと思います。
―それでは逆にふろくのイラストを依頼して、「無理です」と断られたケースは?
<江本>
「イラストはいくつか描くけど、あとはうまくデザインで使ってください」とか、そういった要望はあったと思います。便箋の表紙や中、封筒のイラストも何パターンか描いてもらったほうがこちらはありがたいけれど、忙しい方は大きいイラストをいくつか描いていただいて、「あとは全部デザインでなんとかお願いします」みたいなケースもありましたね。でもほとんどのふろくはみなさん、ほぼこちらの依頼通りにたくさん描いてくださっていました。
―当時はふろくだけじゃなくて、懸賞のグッズのイラストなどもすべて描きおろしで、仕事量はものすごかったでしょうし、そう言っちゃうのは仕方ないというか、今ではそれが普通ですよね。マンガ家さんへのイラストの依頼の仕方はどんな形で行っていたのでしょうか? 例えばボックスのふろくのこの面とこの面に何センチ×何センチでイラストを描いてください、とかそんな感じで依頼するのでしょうか?
<江本>
そうです。たとえば、「こういう形の貯金箱です」とイメージを見せたり、貯金箱の絵を自分で描いてFAXで送ったりしていました。「ここが何センチでこういう形になります、ここにイラストお願いします」といった説明を紙に書き入れて依頼をしていましたね。また、「ここには貯金箱の口があるので、この部分にはイラストを入れないでください」とか。今なら携帯電話でふろくの見本を写真で撮ってメールでおくることで簡単に解決することが、FAXと電話が通信の中心だったので、ふろくそのものを伝えるのに苦労しました。
―複雑な紙ものふろくが多い時代ですし、説明するのが大変そうですね。
ちなみに懸賞のグッズのイラストなども同じような感じで依頼していたのですか?
<江本>
懸賞のグッズにいれる印刷部分の寸法を担当編集者が測って、それをマンガ家さんに伝えてイラストを描いてもらっていたかと思います。ただ、誌面の懸賞ページの入稿までに、グッズにそのイラストが印刷されたものが間に合ってないケースが多いんですよ。グッズだけ撮影して、後で誌面上で印刷で絵をはめ込んだこともけっこうあります。
―そう言われて改めて見てみると、そんな感じのものもありますね。しかし、言われないと気づきません。じゃあ、実物はちょっと違ったとかも?
<江本>
それはあったかもしれません。
―懸賞に当たった読者だけが知っている事実ですね。
ちなみにこうした懸賞などのグッズは集英社には……残ってないですよね?
<江本>
ないと思います。現物は当時懸賞に当たったラッキーな読者と、あとはマンガ家さんによっては保管されているかと思います。
―ふろくファンルームの反響で、印象深い思い出や忘れられない読者の声などはありますか?
<江本>
やっぱり「すごく好き」とか「可愛かった」とかそうした反響は嬉しかったですね。「買い逃したから前の号のあれが欲しい」とかもあり、切手が同封してあって「これで買います」などのお手紙もありました。「申しわけありませんが」と丁寧にお返しして断っていました。
―買い逃したらもう手に入らないですからね。その気持ちもわからなくもない(笑)。80年代前半くらいまでだったら、ふろくファンルームに「ふろくの交換コーナー」がありました。個人情報の取扱のことなどもあってなくなっていったのだと思いますが、江本さんが担当していた時代は部数が莫大でしたし、あったらあったで大変なことになっていたでしょうね。
<江本>
そうでしょうね。もっと昔は住所なども誌面に載っていたこともあったみたいですね。
―ふろくファンルームの誌面はどんな風に作っていたのですか?
<江本>
まず誌面で最初に決めるのが、ふろくの作り方の解説をどのくらい入れるか、です。組み立て方が難しいと説明や作り方の図解もたくさん載せないといけない。だからまずその作り方の解説でどのぐらいスペースをとるか、ページの割り振りを自分でしていました。そのふろくの制作工程がいくつ必要かというのを、自分でふろくを作りながら考えて、どういう絵が必要かも考えました。それが決まってから、残りのスペースにお便りの紹介と次号のふろくの予告スペースが決まるといった流れです。
―ふろくファンルームは3ページでしたね。このページ数は決まっていたんですか?
<江本>
はい。しかし、組み立てものが多すぎるときは、前もって全体の台割を担当している副編集長にお願いしたりもしましたね。「どうしても作り方の図解が多くてページが足りないんで今月号は4ページほしい」など。
―器用な子はふろくファンルームは見ないで作れるんですけど、不器用な子にとっては、このページが最後の砦でしたよ。このページを見てわからなかったら、ふろくは永遠に完成できない(笑)。
<江本>
ふろくの組立図は、難しいものは、ラフの作り方の図を印刷会社にお願いして作ってもらいました。それをもとに、ふろくファンルームのイラストを担当していた「ふなつかみちこ」さんがとても丁寧に描いてくれていましたね。実際に組み立てながら描いてくださったと思います。印刷会社のデザイナーさんが作り方を描いたふろくもありました。描き文字をみると違う人が作り方の図を描いていることがわかると思います。
―ふろくファンルームは、担当編集のキャラクターの近況みたいなものもイラストで描かれていて、それも楽しかった。だから「かおりん」に一方的に親近感を抱いた読者は多かったはずです。投稿してくる読者は大体何歳くらい、あるいは何年生ぐらいが多かったのでしょうか?
<江本>
1年生とか2年生、3年生ぐらいまでが多かったですね。本誌読者の平均年齢より、少しだけ低い印象でした。
―ふろくが雑誌を買う最初の入り口になっていたことがよくわかりますね。小学校低学年の読者が一生懸命送ってくれるわけですね。
<江本>
たまに「もう少し大人っぽいのが欲しいです」といった声もありました。5年生ぐらいの子から「『りぼん』のふろくは子どもっぽい」と投書があったり。
―親から来ることはありましたか?
<江本>
親からは来なかったですね。
―ふろくファンルームの常連みたいな人もいましたか?
<江本>
「ふろく展覧会」のコーナーには、イラストが上手な子でいつも送ってくれる読者はいました。
―読者のニーズはふろくファンルームから吸い上げていたりもしていたのでしょうか? 今の小学生が何を望んでいるのかとか、そういうのを知るために特別にやっていたことなどはありましたか?
<江本>
つけてほしいふろくの希望も書いてありましたが、あまり現実的ではなかったんですよね。たとえば、「紗南ちゃんのレターセットがほしい」といったシンプルな意見や、絶対にふろくにできない難しいもの、夢があふれたものなど。そういった投書が多かったです。実際に市場でどういうものが売れているのかを見ることが参考になりました。書店、おもちゃ屋さん、雑貨屋さん、文房具屋さんなどに行き、色やデザインの流行りなど、市場調査はしていました。
―おぉ、そんな地道な努力があったわけですね。市場調査の結果、「これ使える」といって採用したものとかありますか?
<江本>
それはたくさんありますね。半年後のふろくを考えなければならないので、クリスマスカードやバレンタインカードなど、季節ものは前もって買っておきました。そうすると半年後に役立つのです。宇都宮さんからは「海外のカードなどはセンスがいいから、そういうのを買っておいた方がいい」と言われたことがあって、海外に行った際は積極的に買っていました。あとは自分が可愛いと思えないと絶対に無理なので、小学生の女の子のふろくとはいえ、自分が欲しいもの、可愛いと思うものを作りたいという思いが一番強かったと思います。読者がどうこうより、「私が欲しかったのはこういうのだな」という思い入れがありました。
―だから『りぼん』は子どもっぽいみたいな感じがしなかったんですね。使っていて、ちょっとお姉さんというイメージがありました。
<江本>
自分が好きだなとか、かわいいな、センスいいなと思えることを一番大事にしていましたね。だからあんまり子どものことは考えて作ってなかったのかもしれません(笑)
―自分たちが作って「これはいいぞっ」と思うものにしていたのですね。
<江本>
たとえばレターセットなどは、これで自分が友達に出して恥ずかしくないかどうかを考えて作っていました。ただキャラクターをつければいいというのではなく、大人の自分が使う時、キャラクターがついているから恥ずかしいって思わないかどうかっていうことは常に考えていました。キャラクターを生かすようにしつつ、デザインはすごく大事に思っていました。
■思い出のふろく
―ふろくを担当していた中で「これはうまくいった」というものや、うまくいかなくて大変だった、というものがあれば教えてください。
<江本>
大変だったことって忘れちゃうんですよね。大体(笑)。
―100シール(1993年4月号「りぼんオールスター大集合100シール」)とか大変そうですけど、全部描き下ろしですか?
<江本>
これは違います。今までに描いてもらった予告カットやふろくのカットなどを全部使いまわして。デザイナーさんが100個入れるのが大変だったと言っていましたね。何回数えても99とか101とかになっちゃって。
―ぴったり100なかったらだめですもんね。増える分にはいいかもしれませんが。
<江本>
100シールなので足りなかったらえらいことになります(笑)。あと当時は様々な素材や、印刷技術を駆使したふろくがついていました。においがついたり、水に入れると浮き出たり、水に溶けてなくなったり。でも、新しい素材や印刷技術を使うと、たまにそれがうまくいかないこともありました。たとえば、私の時代のふろくではないのですが、チョコレートのにおいがするバレンタインカードをつけたけど、においのつくインキがちゃんとついていなくて、チョコのにおいがあまりしなかったなどのトラブルはあったみたいです。
―におい付きは流行りましたね。江本さんが作っていた時代のふろくだと、「光希ちゃんママレード・レターセット」(1993年2月号)なんかも。
<江本>
そうそうオレンジの香りがするレターセットですね。とても可愛くて、いいにおいがして好きです。ふろくは本誌に比べてそういった特殊印刷が多いのもあり、締め切りとの戦いでした。特に途中からビニールバッグやカレンダーなどは海外制作になったこともあって、急に入稿を「2ヶ月早めるように」と言われることもありました。スケジュールが急に前倒しになって、急いでマンガ家さんにイラストを依頼しなくてはいけなくなったことも。常にタイトロープな状態でしたね。
―新しい素材や印刷技術を次々と取り入れたふろくが登場する。様々な挑戦がこの頃のふろくでなされていましたね。
<江本>
そうです。このふろくはお気に入りでしたね(1993年8月号「吉住渉の光希ちゃんサマーメール」)。透明な封筒に便箋をいれたら水族館の窓から覗いているような形になるんです。透明なビニール製の封筒はふろくではまだ珍しくて、単価も高かった。だからあんまり枚数がつけられなくて。
―そうなんですよ。数が少ないので使えないか、すごく大事な友達だけにあげたりしていました。
<江本>
そんな読者の声がいっぱい来ました。封筒の透明感を生かしたくて、水族館の窓から見えているような感じにしたいと吉住先生にお願いしましたね。夏らしい感じにしたかった。吉住先生はこちらの意図をくみ取ってくださり、こちらが頼んだ以上に可愛らしくさわやかな夏らしいイラストに仕上げてきてくれました。あとサマーメールと同じ号のトラベル・パスポート(「大塚由美の吹雪ちゃんのトラベル・パスポート」)がまさにそうですが、冊子もののふろくが大変でした。細かいカットも多いので。
―クッキングブックやゲームブックなんかもたくさんカットがついて大変だったと思いますが、確かに冊子ものはすごく大変でしょうね。このトラベル・パスポートのデザイン、すごく可愛いですね。
<江本>
ちょっと変わった絵柄にしたいと思って、メキシカン調で大塚先生にお願いしたのです。ふろくじゃないと遊べないデザインもありますので、そうしたオーダーに対してマンガ家さんも楽しんで描いてくれていたら、嬉しいのですが…。
―本編ではヒロインが恋人と別れる、といったシリアスな展開になっていても、ふろくでは仲良し、といったことも結構ありましたよね。読者としては、それにホッとしたことも……(笑)
<江本>
ふろくでは、キャラクターとして使っているわけなので、マンガ家さんも本編のマンガと切り分けて描いてくださっていたんですね。
―たとえば、急に売れた作品があったとして、予定にはなかったけど、急遽その作品のふろくをつけた、といったこともあるのでしょうか?
<江本>
スケジュールが間に合えばつけましたね。ふろくは半年前から計画していますが、3ヶ月か2ヶ月前でいきなり人気の出た作品があったりすると、上司から急にそのキャラクターのふろくをつけてほしいという要望もありました。
―ふろくを描いてくれたマンガ家さんとの思い出とか、こんな特徴があったとか、そんなお話もあればぜひ教えてください。
<江本>
印象深いのは吉住渉先生ですね。本誌だけでも大変お忙しいのに、ふろくもすごく一生懸命考えてくださいました。出来上がってくるイラストがすごく可愛くて、依頼した通りのものだけじゃなく、「こっちの方がいいと思いますよ」など、より良いものを考えてくださいました。もちろんほかの先生方もみなさんすごく一生懸命に描いてくださいましたよ。特にトランプのアイドル4人に入る先生方のふろく絵は非常に上手かったです。ふろくの絵は、キャラクターを3等身くらいにした「ガキ絵」と呼ばれる独特の絵柄で描いてもらうことが多く、最初は苦手な方も多いのです。これがうまく描けるようになるかどうかが、ふろくのイラストの良さにもつながっています。たとえば、矢沢あい先生なども超初期の頃はご苦労なさっていたかもしれませんが、どんどん可愛らしく描けるようになって。すごい先生です。
―矢沢先生は「天使なんかじゃない」の「スドーザウルス」が出てきたあたりから抜群にキャラクターのデフォルメがうまくなっていきますね。
<江本>
そうですね。「スドーザウルス」と「エンジェル冴島」のふろくは大人気でしたね。また、水沢めぐみ先生だと「姫ちゃんのリボン」の「ポコ太」とか、そういうキャラクターがいると、ふろくでも使いやすかったですね。
―キャッチーなキャラクターを本編に登場させたのは、もしかしたら、ふろくの絵を想定したり、人気を得るために学んだテクニックだったのかもしれませんね。
<江本>
そうですね。ふろくにしやすいキャラクターを作るというのも、『りぼん』で連載をする上ではひとつ重要な要素だったのかもしれない、と思います。
■ふろく作りの参考にしたもの
―先ほど読者のニーズを探るために市場調査をなさっていたとおっしゃっていましたが、具体的にどんなものが参考になったとかそういったものはありますか?
<江本>
サンリオの商品は意識していましたね。キャラクターをつけて「可愛らしさ」を保つというのが難しいので、どんな風にデザインしているか気になりました。
―単純にキャラクターグッズじゃなく、ファンシーグッズとしての側面を意識していたということですね。「かわいい」とか乙女心をきちんとくすぐるようなもの。
<江本>
デザインの参考でいうと、ハンバーガー屋さんの格好をキャラクターにさせたいと思って、デザイナーさんと2人でハンバーガー屋さんに実際に行ってふろくのデザインにならないか、リサーチしたこともありましたね。
―1994年9月号の「藤井みほなのエリカちゃんバーガーファイル」ですか?
<江本>
そうです。ちょっとおしゃれなハンバーガー屋さんに行って店内の様子や、ハンバーガーのパッケージなど、デザインの参考にしました。あとは先ほども言いましたが、昔、少女時代に自分が使っていたふろくから着想を得たものもあります。詳しく言えませんが、昔の他誌のふろくのデザインですごく可愛いものがあって、それを参考にしたということも(笑)。
―それはきっとお互い様ですよ。雑誌同士が影響し合うのはある意味宿命です。
<江本>
デザインも重要ですが、実用性も重視していました。自分が生活する中で必要だなと思うものをふろくにつけました。たとえば、私は傘をよく失くしてしまうので、傘に目印になるようなものがあったらいいんじゃないかと思って、傘につける小さなビニール製のマスコットをふろくにつけたこともあります。レポートパッドも、罫線が濃いと書きにくいと思ったので、ガイドラインとして見えるぐらいの薄さにして。使うときに邪魔にならないようにと意識していました。
―実用性高かったと思いますよ。ふろくは基本的には使っていたということですか?
<江本>
もちろん。やっぱり実際使ってみないと使い心地がわからないので。
―ランチボックスもふろくの定番でしたが、こういうのも使っていましたか?
<江本>
これはさすがに実際に使ったかは覚えていないですね。ランチボックスは食べ物を置く部分には印刷をしないようにということは考えて作っていました。次号の予告ページの写真のため、ランチボックスのお弁当の中身も工夫しました。スタイリストさんに用意して作ってもらったものです。
―予告ページのランチボックスに入ったサンドイッチやラップサンドがおしゃれで憧れました。使いたくて仕方なかったのですが、母親が「水分とか油がしみるから」と夢のないことを言って使わせてくれなかったことを思い出しました。
当時は、『りぼん』のアニメ化などメディアミックス全盛期でもあったと思いますが、アニメ関連のふろくはどんな風につけていたのでしょうか?
<江本>
アニメの視聴率が上がれば、本誌の売上にも結びつくので、私が自ら企画したというよりは編集部としての意向でつける、といったことが多かったかもしれません。
■部数上昇にともなった『りぼん』の変化
―江本さんがふろくを担当したのは92年から98年とのことですが、時を経るごとに変化していったふろく現場の仕組みとかふろく自体の形態とか、そういったものはありますか?
<江本>
『りぼん』がどんどん売れていくので、それにともなって、ふろくの予算も大きくなっていきました。1円のシールでも、りぼんの部数が100万部だと印刷会社にお支払するのは100万円、部数が200万部になると200万円となります。たった1円のシールでも印刷会社にとっては大きな利益になるわけです。しかし、部数が増えれば増えるほど、作るのに時間もかかるわけで、内職で作らなければならないようなふろくは、部数が増えれば増えるほど入稿もどんどん早くなっていくというのがありました。その部数だと発売日に間に合わない!って。
―部数が多いとその分入稿が早くなる!売れるのは嬉しいけど、現場は大変になってくるわけですね。
<江本>
私が入ったばかりの時は、『なかよし』の「美少女戦士セーラームーン」が立ちはだかっていて、ライバルがいたからここまで成長できたと思います。
―編集部が意識して、『なかよし』と『りぼん』の読者の差別化を図っていたところもありましたか?
<江本>
上の役職の人にはあったかもしれませんが、新人の私はそこまで考えてなかったですね。目先の自分の仕事をやることしか考えていなかったので、ライバル誌がどんなことをしていたかというのはふろく以外はあまり見ていなかったように思います。「セーラームーン」のふろくは、大人っぽくて、かっこいいなと思っていましたが、それとの差別化よりは、自分が好きか、かわいいと思えるかということを一番大事にしていたので。今思うと、すごく尊大だと思うんですけど。
―入った当時、江本さんはおいくつぐらいですか?
<江本>
22歳です。
―ちょっぴり大人な背伸びしたい読者にとって、22歳の江本さんがほしいなと思うものは、りぼん読者が欲しいと思うものともしかしたらそんなに変わらなかったのかもしれませんね。
<江本>
私が幼かったと思うんですけど(笑)。「女の子は赤とかピンクが好きだから」という固定概念がまだ強い時代だったと思いますが、私は「絶対そんなことない」と思って作っていましたね。もちろん、赤やピンクも好きだけど、水色とか緑のほうが大人っぽい感じがして良いという読者もいるはずだって。
―そうした固定概念とも戦ってきたわけですね。
応募者全員大サービスでも、1993年9、10月号「くいしんぼバッグ」はドーナツとか食べ物をモチーフにしたトートバッグで6種類から選べましたが、そもそも色ははっきりとピンクみたいな色はなかったですね。中間色でどれもすごくかわいかった!
<江本>
そうなんです。凸版印刷のデザイナーさんがすごく大人っぽいセンスの方で。こういう微妙な色使いのデザインをしてくれたんです。ビニールコーティングされいて丈夫で実用性もあるバッグでしたね。
―私も持っていましたが、みんなこれ持っていましたね。本を入れたりお弁当を入れたり。
<江本>
私たちも会社の近くに出かけるときなど、このバッグにお財布をいれて持って出たりしていましたね。可愛いですよね。印刷会社のデザイナーさんもみんないいものを作ろうという気持ちがすごく強くて、こっちが無理難題なことをお願いをしても、みなさん「できます」とおっしゃって、遅くまでやってくれていました。そういう情熱が255万部につながったんじゃないかなと思います。
―なるほど。255万部の裏側には関わる人の情熱があった!
少女マンガ誌史上最大発行部数を記録した時のことは覚えていらっしゃいますか?
<江本>
とにかく目の前の仕事をするのが精一杯で、売れているとかあまり考えていなかったですね。むしろ忙しすぎてこれ以上売れてほしくない位に思っていたかもしれません(笑)。今から思うとすごく思い上がった考え方だったのですが、売れていることが当たり前すぎて、当時はその幸せに気づかなかったのかもしれません。
―1994年に255万部を達成していますが、2月号表紙に「ヤッタネ!255万部達成」と、ものすご〜く控えめに書いてある(笑)。まだまだ売れると思っていたから、そんなに大きなこととも思っていなかったのかもしれませんね。
<江本>
その号のふろくは……(資料を見て)あぁサーカス・レターセット(1994年2月号「矢沢あいの翠ちゃんサーカス・レターセット」)の時ですね。そうか。このピエロのレターセットの時が255万部だったのか。これは海外のピエロのグッズを参考に作った記憶があります。この号は確か連載作品の全カラー扉に「特製フォトアルバム」の懸賞をつけたと思います。それがものすごく大変でした。
―この号は、「ありがとう史上最大255万部スペシャル企画」として様々なことをしていますね。江本さんおっしゃる懸賞は、その一つとして企画されたものですね。巻頭カラーが「ママレード・ボーイ」、カラー扉が「赤ずきんチャチャ」、「とまどいの姫君」、「ときめきトゥナイト」、「パッション♥ガール」、「あなたとスキャンダル」、「天使なんかじゃない」とあり、この7作品それぞれにキャラクターが印刷された「特製フォトアルバム」が懸賞でついた。それぞれ500名にプレゼントされたようです。
<江本>
そうそう。それぞれの扉絵にそのプレゼントの告知がしてある形でした。
―この号は「赤ずきんチャチャ」のアニメ化が発表された号で、チャチャの銀剥がしの懸賞もスペシャル企画としてやっています。加えて、通常通り、懸賞コーナーもあり、その懸賞がまたすごいですよ。CDラジカセや電話などの電化製品からマグネットクリップやカセットメモなど文房具が当たるんですが、全部で1万名にプレゼント、という企画です。1万人ってすごいですね。これなら当たるって当時は思いましたけど、全然当たらなかった……。
<江本>
応募数もすごかったですから。今見ると、やはり255万部達成ということで宣伝予算が多く付いたんだろうなと思います。
■マンガ家との交流
―ご担当したマンガ家さんはいらっしゃいましたか? 当時は、「りぼん漫画スクール」も膨大な応募があったようですが、そんな中で担当したというマンガ家がいれば。あるいは、担当してなくても、ご交流のあったマンガ家さんとの思い出などがあれば教えてください。
<江本>
持ちこみから担当した初めてのマンガ家さんは亜月亮先生でした。亜月先生は当時、大学生だったと思いますが、『りぼん』に投稿するには少し年齢が高いほうで、その頃の私と年がさほど変わらなかったんです。彼女は島根県出身で、確か高速バスで持ちこみにきていたんですね。絵はまだ荒削りだけどすごく話がおもしろいなと思い、人としても頭がよいし面白い方だったので、お友達にもなりたいとも思い担当になりました。当時の『りぼん』は変な話なのですが、年齢の低い人の方が伸びしろがあるというふうに編集部内で思われていて、亜月先生は持ちこみのとき、大学生だったので、どうだろう?という空気は周りにあったのですが、わたしは「絶対面白いから!」と強く推して、1993年冬のびっくり大増刊号でデビューしたんです。
―その後、看板作家になりましたよね!
<江本>
そうなんです!高速バスで持ちこみに来たそのガッツが結びついたなって思います。
―他にはいらっしゃいますか? 作品として思い入れのあるものでも。
<江本>
やっぱり水沢めぐみ先生は忘れられないです。「姫ちゃんのリボン」の後半は私が担当していました。前半は岩本さん(第4回オーラルヒストリー対象者:岩本暢人さん)が担当で、途中から私が。新入社員で正式に配属されたときにそうなることは言われていたので、「『りぼん』の四大連載の一つを私ができるわけがない!」と不安でした。後から聞いた話ですが、水沢先生も不安に思っていたらしく……。それまでは年上の男性の担当編集に教えられる形だったのに、突然年下の新人の女性編集者がつくんだから不安になるのも当たり前ですよね。そんな水沢先生に、岩本さんが「あなたもいいキャリアなんだから、そろそろ編集者を育てるということをしなきゃだめです」と言ったそうです。
―マンガ家が編集者を育てる、ということですか?
<江本>
そうです。「マンガ家もある程度のキャリアを積んだら、今度は新人編集者を育てなさい」と言われたと、水沢先生から後から聞いて知りました。水沢先生は本当に努力家で、そのお仕事ぶりはとても勉強になりました。
―まさに水沢先生は新人編集者を育てたわけですね。
<江本>
はい。作品自体も本当に素晴らしいですし。初々しい初恋を描き続けることができる水沢先生の感性は天才だと思います。「おしゃべりな時間割」という「姫ちゃんのリボン」の次に始まった連載も担当しました。水沢先生がちょっと短めの連載をやりたいと自分からおっしゃって始めた作品でした。話数が時間割の形式になっていて、1時間目、2時間目、3時間目というふうに。先生ご自身の半自伝的な作品にもなっています。
―私もあの作品大好きです。江本さんは「姫ちゃんのリボン」後半から、『りぼん』を離れるまでは水沢先生のご担当だったということですね。話を戻してしまいますが、持ちこみの作品など、当時はどのように編集部内でさばいていたのでしょうか?
<江本>
持ちこみの応対は、大体新人の役目でしたね。当時は「りぼん漫画スクール」に投稿が何百本と来ていたので、それを編集部全員で割り振って読み、ABCのランクをつけるというのを毎月やっていました。
―それが「りぼん漫画スクール」の誌面で発表されていたのですね。C以下の人は名前が載らない、といったことはあったのでしょうか?
<江本>
いえ、載っています。投稿している人は全員の名前が「漫画スクール」のページに載ります。ノートの切れ端にマンガを描いて送ってくる人とかもいましたが、そうした人もCランクに載っていました。毎月、良い作品を20本位に絞って編集部全員で回覧するのですが、「漫画スクール」の編集会議までに原稿が入っている封筒にコメントを書いておくんですね。会議で受賞者やデビューさせる人を話し合って……といった流れだったと思います。持ちこみからデビューしたマンガ家さんは亜月先生がレアケースで、当時はあまりいらっしゃらなかったような気がします。
―「りぼん漫画スクール」が大きくてスタンダードな登竜門だったわけですね。『りぼん』に投稿してくる人にはどんなアドバイスをしていましたか? また、どんな人が伸びていったでしょうか?
<江本>
たとえばの話ですが、「これだと『りぼん』では大人っぽすぎるよ」とか、「もうちょっと目を大きくしたら」とか、そうした編集者のアドバイスに対して直せる人はやっぱり伸びていく人でした。直さない人は自分の描きたいものと『りぼん』読者の求めるものとの間にどうしてもずれが出てくるので。冷たいようですが、他の雑誌にいったほうがお互いに幸せかなということになりますよね。
―デビューできる人よりも、落としていく人の方が断然多いわけですので、ダメだなという人にはどんな風な対応をされていましたか?
<江本>
それはもう批評を返すだけですね。担当がつくと大体デビューまではなんとかいきますが、マンガ家さんはデビューしてからが大変なので。年間何人もデビューしていきますが、そこからさらに残っていくのは、ほんのひとにぎりです。
―当時、「りぼん漫画スクール」も楽しく読んでいました。「この人うまくなっているからもうすぐデビューかな?」とか読者ながらに見守って、「あぁ、ようやくデビューした!」と思ったら、すぐいなくなって……。でも、今でも残っている方は、投稿作の小さなカットでも記憶に残るものがあった気がします。
<江本>
種村有菜先生も鮮烈でしたよね。絵がうまいと、最初から編集部でも話題になりました。
―種村先生の登場は衝撃でしたね。『りぼん』のこれまでの雰囲気とまた違ったマンガ家さんが出てきたなと思いました。
<江本>
そうですね。いわゆる「りぼんっぽい」雰囲気とは違ったファンタジーを描いていらして新鮮でした。
―藤井みほな先生が登場した時も新しい感じがしました。種村先生もそうですが、キャラクターがなんか色っぽかったんですよね。それまでの『りぼん』のヒロインって、大体胸もぺたんこだったのに、藤井先生の描くヒロインはボディコンとか着ているし、谷間が強調されていて。「キープくん」とか「アッシーくん」って単語が『りぼん』に出てきて、男の子の連絡先がずらって書いてあるアドレス帳を燃やして、あなただけよと言って(笑)。
<江本>
グラマラスな雰囲気でしたよね。「キープくん」、時代を感じますね(笑)。
―あとは彩花みん先生の投稿作(「われらハイスクールヒーロー」)のカットも鮮烈でした。めちゃくちゃ上手いって思ったし、そのワンカットでもう読みたい! って思ったんです。
<江本>
彩花みん先生の最初の連載「赤ずきんチャチャ」は、私が『りぼん』に正式に配属されたころにスタート(1992年10月号)したので、彩花先生とは同期のような感じなんです。実は私が最初に手掛けたカラー口絵は、彩花先生の口絵(「1992年8月号「赤ずきんチャチャわくわく銀はがしけんしょうバルセロナは、すぐそこっ!!」)でしたが、彩花先生もそれが初めての口絵のカット依頼だった。「初めて同士、お互いに頑張りましょうね」と言い合ったのを覚えています。
―それこそ忘れられないお仕事の一つですね。彩花先生の「赤ずきんチャチャ」は一気に看板作品になりました。ふろくもチャチャがどんどん増えていく。ギャグマンガの強さも『りぼん』の特徴の一つです。
<江本>
岡田あーみん先生とかさくらももこ先生もいらっしゃいましたし、こうした一連の作品は『りぼん』じゃなかったら生まれてなかったと思いますね。
―四コママンガも『りぼん』は豊作です。
<江本>
そうですね。シュールなのも多いですよね。
―前のオーラルヒストリー(第1回)で冨重さんから、『りぼん』は「なにかこうじゃなきゃダメだ」というこだわりみたいなのは実はないといったお話を聞いて、すごく納得したんです。『りぼん』はメインストリーム、少女マンガの王道を走る雑誌だと思いますが、王道は実は狭くない。その道はすごく広い。受け入れる作品の間口が広い印象があります。
<江本>
懐が深いですよね。バラエティに富んでいた。恋愛ものだけが当時の読者をひきつけたわけじゃないんですよね。
―当時、雑誌としてのバラエティのバランスみたいなものは考えられていましたか?たとえば、今度この先生がファンタジーを描くから、あの先生は学園ものを描いてもらおうとか。
<江本>
なかったと思います。ファンタジーものの作品が多かった時期もありましたね。アニメ会社とのタイアップ企画で魔法少女系が多くなったということもあったかもしれません。アニメによる雑誌の増売っていうのはやはり大きかったので。
―アニメとのタイアップ企画というのは大体どれぐらいのペースであるものでしょうか? 年間1本は何かアニメ化しましょう、みたいな話がある感じでしょうか?
<江本>
そうですね。やっぱり1 作品はアニメ化される作品を連載で持っておきたいというのはあったかと。個人的には「ママレード・ボーイ」がアニメ化された時は少し意外で、びっくりしました。
―確かにマスコット的なキャラクターがいるわけではないし、魔法が使えるわけでもないですからね。どうなるんだろうと思って見ていたら、トレンディアニメみたいな感じになって新境地でした。
■これからのりぼんに対して思うこと
―今は別の部署にいらっしゃいますが、これからの『りぼん』へ期待することなど、何かメッセージがあればお願いします。
<江本>
『りぼん』は時代が変わっても、少女の楽しみだと思うんですよね。私が当時の上司に言われたのは、『りぼん』は集英社の入口だと。『りぼん』で育った読者は、その上の『マーガレット』、『別冊マーガレット』へ、マンガを読まなくなっても『non-no』などの女性誌へとつながっていく。だから『りぼん』で離れちゃったら、その後の集英社の雑誌につながっていかないから、すごく大きな責任があると言われました。私も改めてそう思います。
『週刊少年ジャンプ』は男の子の入口になっていますが、この2誌は集英社にとってすごく大事な存在だと思うので、そういう雑誌として続いて欲しいですね。
今思い出しましたが、当時の編集長がよく言っていたのは、『りぼん』のライバルは実は『なかよし』でも『ちゃお』でもない、「ディズニーランド」なんだと言っていました。わくわくした気持ちで1日そこで楽しめる、ディズニーランドに行ったような気持ちを『りぼん』が与えるべきだと。可愛いものから怖いもの、面白いもの、ドキドキするものなど、いろいろあるべきだと。
―なるほど。当時の読者として代表して言わせてもらうと、『りぼん』はディズニーランドにも勝るものだと思います。
<江本>
それならよかったです。「りぼん250万部」の時代に、楽しいマンガや可愛いふろくを存分に作ることができたのは、編集者として本当に幸せな経験だと思います。あの頃の読者のみなさんにお礼を言いたいです。今、私は『りぼん』よりさらにその下の年齢に向けた児童書の編集をしております。『りぼん』より先に集英社の玄関になるところで、読者を獲得しなければいけないので、『りぼん』の頃に得た経験も生かして、これからもより読者に喜ばれる本を作っていきたいな、と思っています。そしてその子が次に『りぼん』を読み、さらにずっと雑誌や本を愛してくれるようになるといいですね。願わくば、集英社の本を…。
―最初に出会う本って大人になっても絶対どこかに影響しているし、すごく重要だと思います。江本さんのような編集さんが作る本に最初に出会った読者は幸せですね。今日はありがとうございました。











