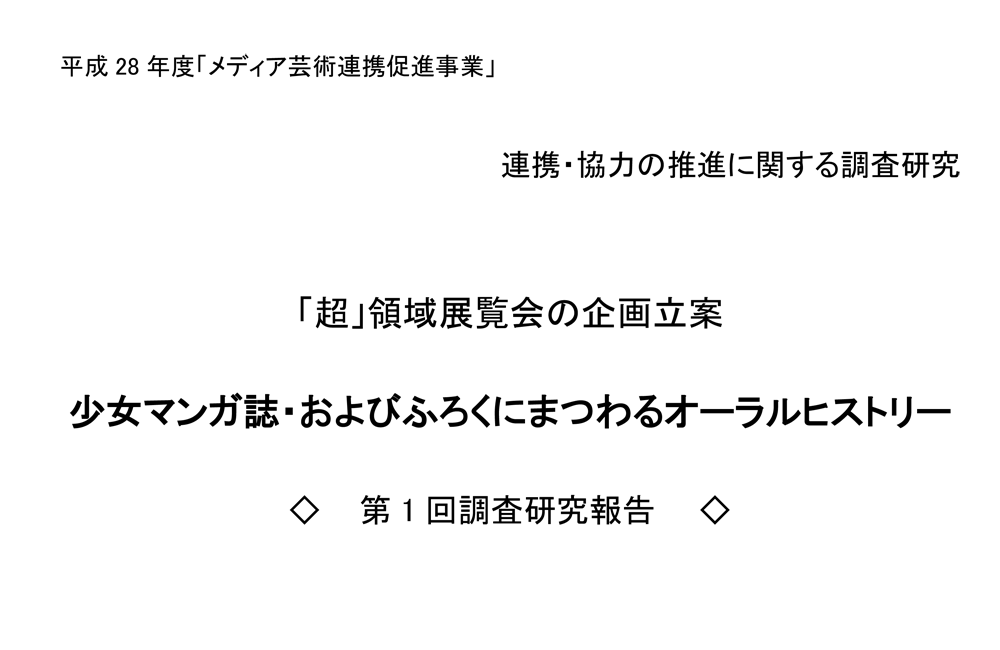
1.調査研究の目的
「超」領域展覧会の研究目的は、マンガ、アニメ、ゲーム、メディアアートの4領域の史資料やコンテンツ等の「共同利活用を実現する」ため、特に史資料やコンテンツの利活用のモデル(案)として、連携展覧会(領域横断・資源シェア型)が効果的であることを実証する「モデル展覧会(案)」の立案を行うことにあります。
昨年度事業として実施した「少女雑誌ふろくの歴史・展示」研究では、戦前から刊行されている代表的な少女マンガ雜誌・集英社『りぼん』とその「ふろく」に着目して、それらが果たしてきた社会的な意義、読者への影響などを読み解く「展覧会」を開催するための準備作業を行いました。
今年度はこの成果を基に、少女マンガ誌史上最高発行部数である255万部を達成した、1990年代の『りぼん』編集者や関係者への聞き取り調査を行い、オーラルヒストリーとしてのとりまとめを行っています。昨年と今年の研究成果は、12月から開催されている「LOVE♥りぼん♥FUROKU 250万乙女集合!りぼんのふろく展」の展示内容にも活用されています。
2.調査結果の公開
聞き取り調査は以下の方々へ実施しました。
| りぼん編集長 | 冨重 実也氏 |
|---|---|
| りぼん副編集長 | 後藤 貴子氏 |
| 元りぼん編集者/児童書編集部 編集長 | 江本 香里氏 |
| 元りぼん編集者(現在は集英社を退職) | 岩本 暢人氏 |
| 元りぼん編集者/学芸編集部企画出版 編集長 | 小池 正夫氏 |
| 元りぼん編集者(現在は集英社を退職) | 宇都宮 紘子氏 |
貴重な研究成果が得られたため、聞き取り調査の記録を公表することとしました。公表は、とりまとめが完了した順に実施していく予定です。
調査記録の公開に際して
1955年の創刊以来、日本の少女マンガ誌およびふろく文化を牽引してきた一つに『りぼん』があります。本誌は特に1980年代後半から1990年代前半にかけては発行部数が上がり1994年には少女マンガ誌史上最高発行部数となる255万部を達成しました。その記録はいまだに破られていません。当時の『りぼん』では、読者のことを「250万乙女」と呼び、作品のキャッチフレーズなどに採用していました。
さて、かつての「250万乙女」は今や30代。仕事に子育てに活躍している女性が主です。なぜ今のアラサー女子がこんなにもパワフルなのか?そのパワーの根源に『りぼん』は存在するのではないでしょうか?250万という膨大な数字が現在の女性たちとリンクしないはずはありません。『りぼん』は読者に明日を前向きに切り開く様々な術を教えてくれました。もちろん、この世代や『りぼん』に限ったことではありませんが、今回はこの250万乙女の原風景はいかにして作られたかに迫りたいと思いました。
今回のオーラルヒストリーで対象としたのは、80年代から現在までを対象に、『りぼん』を作った編集者たちの話です。特に、ふろくについては、70〜80年代までの研究蓄積は先行研究本や展覧会で語られることはありましたが、それ以降の年代については、ほとんど語られることが少ない分野になります。
なお、このオーラルヒストリーの内容は、京都国際マンガミュージアムで2016年12月から開催されている「LOVE♥りぼん♥FUROKU 250万乙女集合!りぼんのふろく展」の内容の参考にもさせていただきました。オーラルヒストリーと合わせてお楽しみいただければ幸いです。
倉持佳代子
京都国際マンガミュージアム
京都精華大学国際マンガ研究センター
調査記録1 冨重 実也氏(りぼん編集長)と後藤 貴子氏(りぼん副編集長)
現在の『りぼん』編集長は、90年代読者にとってはなじみのある「トミーのくねくね横丁」のトミーこと冨重実也さんです。冨重さんは『りぼん』の売上がまさにピークに達しようとする1993年に入社、『りぼん』の配属となり約10年在籍されました。その後、部署を異動されましたが2008年に『りぼん』に戻り、2012年より編集長を務めています。つまり、『りぼん』の激動の時代を知る人物であり、さらには『りぼん』の今を作っている方です。
また、副編集長の後藤貴子さんは、入社後10年ほど『マーガレット』編集部に在籍し、2004年より『りぼん』編集部へ。2010年からはふろくの担当者でもあり、現在の少女たちに向けたクオリティの高いふろくの提供に心を砕いている方です。
第一回目では、まずはこの二人に話を聞くことで、『りぼん』の90年代と今を探ります。
少女マンガ誌・およびふろくにまつわるオーラルヒストリー 第一弾
実施日:2016年10月13日(木)
- 対象者
- ■冨重実也(現りぼん編集長)1993年集英社入社
りぼん在籍期間:1993年5月〜2003年6月/2008年6月〜(2012年10月より編集長)■後藤貴子(現りぼん副編集長・現ふろく担当)1994年集英社入社
りぼん在籍期間: 2004年6月〜(ふろく担当は2010年4月〜) - インタビュア
- 倉持佳代子、ヤマダトモコ
- 構成
- 倉持佳代子
■250万部時代のりぼん編集部
―『りぼん』に最初に着任した時のことをおうかがいします。最初に担当したお仕事は何でしょうか? また、その際、『りぼん』のコンセプトやテーマなど、当時の編集長や同僚の方から教えられたことなどはありましたか?
<冨重>
最初の担当として割り振られたのはギャグマンガ3作品と新人マンガ家さん2人、あと読者ページですね。言われたことは特にないですね。本当に自由でした。今だったら考えられないなと思うのは、読者ページ「トミーのくねくね横丁」第1回目のときに一度も先輩なり上司なりのチェックが入らなかったのですよ。どんなことをやりたいのか先に教えろとか、そういうことは全く言われなくて。それぐらい自由でした。
あとは仕事としては電話対応。着任した1993年は、部数が200万部超えていた時代なので、小学生が学校から帰ってくる時間帯くらいから午後6時ぐらいまでは編集部は電話の対応で仕事にならなかった。よくあったのは、「応募者全員大サービスが届かない」という電話。
―いわゆるクレーム対応ですか?
<冨重>
そういう対応ですね。あとは「好きな人がいるんですけど、どうしたらいいですか」という電話がかかってきたこともありました。会社に入って数日後ぐらいの時だったので、保留して横にいる先輩に「どうしたらいいですか」と聞いたら、「それは君の人生経験踏まえてちゃんと答えてあげたらいいよ」と。それで「あぁそうか。これも仕事なんだ」と思い電話で話し始めたら、「真に受けてんじゃねえよ。ばーか」と、がしゃんと切られました(笑)。そういうこともありましたが、小学生が『りぼん』に電話をかけるとしたら、それは初めて家族や親戚以外にかける電話かもしれませんよね。また、懸賞や応募者全員大サービスは、初めて親戚以外から自分宛に荷物が届くという経験かもしれない。なので、しっかりミスがないように対応しなければと編集長からは指導されました。
<後藤>
私は冨重の1年後の入社で最初の配属は『マーガレット』でしたが、そこから見ても『りぼん』はとにかく電話がじゃんじゃん鳴っているなという印象はありましたね。それとすごく遅くまで残って仕事をしているという印象も。「りぼん漫画スクール」も後々聞いたら、当時は毎月すごい数の投稿があったようです。
<冨重>
一番多い時に700通くらいかな。300を切ることはなかったですね。毎月、300〜500通の作品の投稿がありました。
<後藤>
編集者は1人100本ぐらい投稿作を読まなければいけなかったみたいで、朝までかかってもずっと原稿読んでいるなと感じていました。
―すごい数ですね! 当時の編集部は何人ぐらいいらっしゃったのですか?
<冨重>
私が入った時は9人でしたね。それが11人ぐらいまで増えることはあったけど。今もそんなに人数は変わらないです。
―当時、誌面のあらゆる読者投稿コーナーも賑やかだった印象があります。そっちもすごい数の投稿があったのでは?
<冨重>
「こちらまんが情報」というコーナーも担当していましたが、そこでよくキャラクターのなんでも人気投票をやっていました。(「こちらまんが情報」のページを見て)ここに書いてあるような票の数字は本当に実数でした。全部足すと軽く1,000は超えますよね。私は1票とかまで載せるのが好きで。子どもの頃、自分が読んでいた雑誌で1票まで全部載せていたのがあって、それが好きだったので、そうやっていましたね。
―先ほど、漫画スクールが多いときは700通くらいの応募があったっておっしゃっていましたけど、読者からのハガキの応募数は?
<冨重>
そうですね。すごい応募があったものだと、よく読者参加型の企画「〜ちゃんのファッションイラスト大募集」とか「年賀状グランプリ」みたいなのをやっていましたが、あれはその企画専用のアルバイトを雇わなければならないほどでした。3万から5万くらいの応募があったので。
―懸賞や全サ(応募者全員大サービスの略称)はもっと応募が来ていたってことですよね?
<冨重>
全サはたぶん10万は余裕で超えていましたね。「ママレード・ボーイ」の銀はがしの懸賞では、アニメでバンダイが出したおもちゃのボイスメモが当たるもので、これは45万通ほどの応募があったはずです。
―当時、私(倉持)は応募した側でしたが当たるわけがないと納得(笑)。そして、電話が鳴り止まない状態になるのもうなずけますね。
<冨重>
全サは小学生の読者がポストに投函した次の日から自分の家で待っているわけですからね。郵便の仕組みがまだわかってないから仕方ないですよね。小学生だけでなく、締切日を過ぎた翌日とかに親から電話がかかってくることもありました。母親が子どもに「出しておいて」と言われたのをカバンの中に入れっぱなしにして、どうにかならないかというのはよくありましたね。
―お母さんが嘘ついて、応募したのに届かなかったって今でも思っている子がいるかもしれませんね。全サはそもそもどんな仕組みだったか教えていただけますか?
<冨重>
4、5月号で応募できる全サでは、だいたい3月号で「来月はこれがもらえるよ」と商品を誌面で見せるのですが、その号のアンケートでどれが一番人気かデータをとるのです。アンケートの実績から商品の数を出して、生産個数をきめていました。それがずれると商品が足りなくなってしまうので。それで追加で生産して発送が遅れるというのはありました。全サは基本的には宣伝部が宣伝プロモーションとしてやっているものなので、採算が合わなくなっても、余分に作ってでも、ちゃんと読者の手元に発送できるようにというのはありましたよね。
―当時は切手で450円とか500円位でしたね。
<後藤>
今、30代から40代の方によく言われるのが、「今のふろくって昔の全サみたい」と。当時の全サと同じレベルのものが今ではふろくでついていますから、「今の子どもたちはなんでも持っていてずるい」みたいなことをよく言われます。全サの応募方法はある時期から切手から、郵便小為替に変わりました。昔、切手はどこのおうちにも結構ありましたよね。当時は子どもにはいい企画だと思っていたんですが、為替は子どもにとってハードルが高かったかもしれませんね。
―冨重さんはふろくを担当されたことはありましたか?
<冨重>
ふろく担当ではなかったです。ただし、小さいシールとかは担当じゃなくてもたまに割り振られましたね。
―つまり、メインのふろくはふろく担当者で、細かいふろくはそれぞれの編集者も受け持つことがあったということですね。
<冨重>
そうです。私は最初に担当したふろくで間違いを犯してしまって。当時の副編集長から「このシールをずっと机に貼って、社員生活をおくるように」と言われ、言いつけを守っているつもりじゃないけど今でも貼っています。
―どんなシールですか?
<冨重>
1994年5月の「チャチャのキラキラシール」。四角いやつなんですが、キャラクターに沿って抜き取るシールなのに、抜き型の指定をし忘れたんですよ。
―当時使っていましたが、気づきませんでした(笑)。
売上が左右するような、部数に影響力のあるふろくなどはありましたか?
<冨重>
『りぼん』の場合、2月号と9月号というのが非常に大きい号です。2月号は12月28日発売になる号です。つまり売り期間が一番長く、冬休みに読まれることになります。
9月号は8月3日に発売される号。夏休み中に出る号ですね。つまり、両方とも小学生の読者にとってお財布が増えるタイミングです。
―冬休みや夏休みは、おじいちゃんおばあちゃんからお年玉やお小遣いがもらえますからね。雑誌を買いやすい時期ということですね。
<冨重>
そうです。なので2月号と9月号は特大号という設定にして豪華な付録をつけます。今でもそうです。全サも2号連続にしていた理由は、多くの人が買ってくれる9月号と2月号とその次の号も買わせるためのブリッジの企画です。だから2、3月号を全員大サービス、9月、10月号を全員大サービスにすることによって、次のちょっと冷えてしまう号を買ってほしいというのがあったということです。
―2月号と9月号は新連載も多いですよね。何かを仕掛けるタイミングでもあるわけですね。
<冨重>
あとは4、5月号と連続にして学年の切り替わりの時に備えるということですね。しかし、どのふろくをつけたから売上が、というのは実際にはそんなに感じなかったです。1993〜94年あたりは、まさしく2月号と9月号がおそらく最大部数になっていたと思うのですが、基本的に発行部数に山と谷はあまり作ってなかったと思います。
<後藤>
当時は読者の数がすごく多くて、クラスの女子の多数がりぼんを読んでいました。すぐに共通の話題で盛り上がりたいため、みんな毎月買うのが当然と思って買っていた。だから、予告を見てこんなふろくだったら来月は買わないというふうに思わなかったんじゃないかと思います。回し読みすらしなかったんじゃないでしょうか。
―マンガ家がふろくを依頼されるタイミングはだいたい半年前位だと聞きましたが。
<冨重>
そうですね。人気のマンガ家さんだったら、例えば、次の9月号から新連載が決まっているから、半年前にどんなストーリーを描くとか決まってなくてもふろくのイラストを描く必要がありました。ふろくで初めて新連載のキャラクターの顔を描いたマンガ家さんもいたはずです。矢沢あい先生がこの前、東映のアニメムック1のインタビューの中でそんな話をしていましたね。
主人公のビジュアルを先に決めなければいけないので、前回のヒロインがロングヘアだったから今回はショートヘアにするか、とかそういう位の感じで決めるしかないですよね。
―お話が決まっていなくても描かなければならないって大変そうですね。
<冨重>
フジテレビの月9のドラマって、どんなストーリーとかより、とりあえず人気俳優の誰々と人気アイドルの誰々を抑えておこう、そのために合う脚本をどうしようかという感じじゃないですか。それと近いというか、例えば、次の9月号から吉住渉先生の新連載をやるって決めていたら、吉住先生の絵のキャラクターのふろくが欲しいので、ストーリーが決まる前に依頼をしていたかもしれません。
―なるほど。では、ふろくのキャラクターの印象と実際始まった連載のキャラの印象がちょっと変わってしまうことも......?
<冨重>
それは大ありですよね。矢沢あい先生の「下弦の月」とかは大変だったと思いますよ。
―今までのとは違った感じでしたものね。この作品もそうですが、ちょっと影のあるヒロインみたいなのが増えていったような印象もありました。そういう作品はふろくにするのが大変だったのではと思います。しかし、すごくシリアスな本編の「下弦の月」でもふろくではすごく可愛くて。切り分けて描けるのが矢沢先生のすごいところですね。
<冨重>
「下弦の月」は私もかなり衝撃を受けましたね。矢沢先生がもう『りぼん』の小学生相手に描くのがいっぱいいっぱいだっていうのがあったかなと思います。
『りぼん』は10代でデビューする人が多いので、マンガ家さんも大人になるにつれ、常に10歳向けのマンガを書き続けるのはハードになっていきます。今の自分が感じているテーマを描きたいと思うのはマンガ家の常ですよね。だから年齢を重ねても長い間『りぼん』で描き続けることができた水沢めぐみ先生は奇跡の存在です。
―水沢先生は『りぼん』でずっと少女の瑞々しい初恋を描いていらっしゃいましたよね。
「下弦の月」が連載されたあたりは、矢沢先生に限らず他の先生もこれまでと違ったテイストの作品を実験していたような......。吉住渉先生の「君しかいらない」とか藤井みほな先生の「秘密の花園」とかもこれまでとちょっと違うな、と感じた作品でした。なんというか、『りぼん』攻めてるなと思っていました(笑)。
<冨重>
「秘密の花園」は担当でした。みんなの心にトラウマを植え付けた連載ですね(笑)。今の時代では許されないでしょう。「龍王魔法陣」という作品も連載しましたが打ち切りになって、「秘密の花園」もそんなに読者に受けなくて。自分が好きなものを描くのではダメ、売れるためには読者が受けるものをと藤井先生が考える契機になった作品だったと思います。「秘密の花園」の打ち合わせでは、私がネームを読んでいる時、目の前で「ゲーテの詩集」を読んでいる藤井先生がいました。ファッションも全部そんな感じで。そのあと「GALS!」を描いて大ヒットしましたが、その時の藤井先生は本当に「GALS!」の世界から出てきたみたいなファッションでした。そういう意味では、藤井先生は全身全霊のマンガ家さんですね。
―藤井先生かっこいいですね!
模索的とも思える作品が次々と登場したのは、マンガ家の年齢が上がって描きたいテーマが変化した中で生まれたものだということですが、当時の読者の年齢層も少し上がっていたからなのかなとも思っていました。そうした背景はありますか?
<冨重>
読者の年齢層は実は上がっていないと思います。『りぼん』の宿命ですが、基本的に女の子の方がこの雑誌をレジに持っていくのが恥ずかしいという瞬間が訪れると思います。女子中高生が『りぼん』を買うのは、男がエロ本を買うよりも恥ずかしいっていう言い方をする人もいたりとかして。でもそれはいいことだと思っています。
―『りぼん』を卒業するにあたっては、読者が「私の世代が過ぎた」「新しい時代に生まれ変わった」と思うマンガ家の登場も大きいと思います。例えば、ヤマダさんは水沢先生が登場した時だし、私(倉持)は、種村有菜先生が登場した時でした。編集側はそうした生まれ変わりというのは意識してやっているのでしょうか?
<冨重>
意識しないからいいのだと思います。こちらから仕掛けて何かを当てようということは多分あんまりうまくいかないと思います。それよりもマンガ家さんのエネルギーを信じた方がいいというのが旧来のつくり方です。今それが正しいかどうかは別ですけど。
矢沢先生の話だと、小椋冬美先生とかが描いていた頃の『りぼん』はおとなっぽくて、そういう雑誌だと思ってデビューしたら急に年齢が下がり、どうしようと思っていたそうです。
<後藤>
「GALS!」が始まった時は、私はまだマーガレット編集部にいた時でしたが、あれもびっくりしましたね。基本的には『りぼん』らしい元気なヒロインだと思うんですが、ギャルだし、派手だし、言葉遣いは乱暴だし(笑)。子ども向けにギャルとかやってもいいんだと、すごい衝撃を受けました。
―たしかに「GALS!」も新しい時代を感じた作品でしたよね。
<冨重>
「GALS!」は、新連載なのに巻頭カラーじゃなかった。前作の失敗が響いてそこまで期待されていなかったのかもしれません。でも「すげえおもしれえじゃん!」と思って。編集部内では「こんな下品な漫画を載せるのはどうかと思う」という声もありましたが、絶対受けると思っていました。
―「GALS!」は『りぼん』の色合いの変化にも影響を与えていませんか? 『りぼん』はどんどん鮮やかにきらきらになっていって。藤井先生のカラーは、元々カラフルなほうではありましたが、「GALS!」はさらに鮮やかだった印象があります。原色×原色みたいに。そうした作品が影響しているのか、または時代的な流行だったのか。当時は、ナルミヤグループの少女むけのファッションブランドも台頭した時代でした。そういうのもすごく派手だったので、時代的なところも影響しているのかなと。あとは印刷技術の問題ですか?
<冨重>
色合いの変化は『りぼん』だけに限りませんが、デザイナーの手作業からMacでの作業に変わったことが一番大きいでしょう。昔はすべての色は、Y(イエロー)何パーセント×M(マゼンタ)何パーセントというように指定していました。
<後藤>
グラデーションもできなくはないけど指定が大変だったんです。
<冨重>
Macが導入されてから、ふろくのデザインもグラデーションの多用も含めて変わってきました。まさに「GALS!」が連載していた2000年ぐらいですね。しかし、マンガ家さんの好みもあります。「GALS!」は極彩色みたいな感じで、種村先生もあざやかな色で目をひくものがありました。おそらくこの2人の印象が強いのだと思います。そんな中、高須賀由枝先生はそういう色はあまり使わなくて淡い色合いで。
―つまり編集サイドからこういう色にしてくれとかっていう要望は特にせず、マンガ家が自らやったわけですね。
<後藤>
「ほっぺがピンクすぎると、印刷では濃くなっちゃうので薄めの方がいいんじゃないか」とか「原画にキラキラしたシールとか貼ったら立体になるのでダメ」とかそういう要望はしますけどね。それもマンガ家さんの個性ではありますが。
読者の好む色も変わってきていて、以前はとにかくピンクと水色だったのですが、今ではグリーンとか紫とかが好きっていう子がすごく多くて、それはふろくのデザインに結構反映されています。
―流行の色もあるけど、『りぼん』も含め少女マンガ誌がどんどんキラキラした鮮やかな色合いになっていくのはデジタルが導入されたことが大きく影響していたのですね。
お二人は他にも様々なものがアナログからデジタルに移行していくところを見てきたと思いますが、それによってマンガ家を取り巻く環境や編集者の仕事でほかに変化したことはありましたか?
<冨重>
『りぼん』ではデジタル作画の走りは矢沢あい先生や藤井みほな先生だと思います。「天使なんかじゃない」の途中から導入し、「ご近所物語」からはカラー扉は基本フルデジタル。あの時はデジタルの印刷の精度も良くなかったので、紙焼きをプリントアウトしてそれと併用してやっていたと思います。さっきも言いましたが、色指定を細かくやっていたものから全部デジタルにできたというのはやはり作業としては大きく変化しました。
今は、カラー原稿がフルデジタルになっている人はもう連載作品の半分を超えていて、モノクロ原稿はデジタルに完全移行している作家は連載ではまだ2、3人じゃないかな。
そのほかでは、昔は編集者があらゆる資料を書店から買ってきてそれを先生方に送っていたのが、インターネットでなんでも調べられるようになりましたからね。トータル的に考えると、作画を含めてもいろんなことがデジタル化でマンガの執筆環境をがらりと変えたでしょうね。
―グーグルで画像検索したら、どこの国の景色でも出てきますものね。
<冨重>
しかし、パソコンが目の前にあってインターネットが常につながっていて、というのは、仕事が効率化されるどころか逆に仕事が増えていくという状況もあります。
―いい面もあるし、悪い面もありますね。原稿の入稿の仕方や打ち合わせの仕方も変わりましたか? 地方でより描きやすくなったと思いますが。上京される方が減ったとかは?
<後藤>
週刊誌とかだと引っ越してきちゃうと思うのですが、少女マンガ家さんであまり聞かないですね。
<冨重>
昔からあまりないですよ。例えば、池野恋先生はずっと岩手から出たことない先生ですし。また、愛媛県は『りぼん』のマンガ家さんが伝統的に多い地域です。
―データ入稿がない時代は飛行機で原稿を?
<冨重>
送ってもらっていました。9.11のテロの直後は大変でした。航空貨物は爆発の危険があるから1日寝かせて危険がないということがわからないと載せちゃいけないというのがあって。松山空港までピックアップするための出張に何人か行っていましたよ。
―打ち合わせの仕方とかは変化がありましたか? 今だとスカイプとかLINEを使ったりもしているのでしょうか?
<冨重>
LINEは聞きますけどね。
<後藤>
スカイプは聞いたことないですね。LINEも連絡事項だけですね。メールで何かを済ますというのは本当に連絡事項のみではないでしょうか。カットのサイズとかスケジュールなどは口頭では忘れてしまうと思うので、メールでも送ったりなど。
―打ち合わせは基本会って話すか電話ということですか?
<後藤>
それは絶対ですね。今でもアナログって言えばアナログなんですよね。
―必ず一度は会いに行かれますか?
<冨重>
もちろんそうですね。直接お会いしてお話ししないと分からないことがいろいろありますから。
■紙ものふろくからモノふろくへ
―ふろくを取り巻く環境は今と昔とでは大きく変わりましたよね。2000年代始めまではふろくの素材は紙ものが中心で、シールやノート、紙製のボックスなど、ひと月にたくさんのふろくがつくことが普通でした。例えば、「10大ふろく」とあれば、ひと月に10個のふろくがつきました。2001年に日本雑誌協会が雑誌のふろくの規定を大幅に変えたことから、紙に限らないふろくが一般的になりましたが、市販の商品と変わらないバッグやポーチがふろくに付くようになりました。豪華な分、点数も一点だけの場合もあります。紙じゃないそうしたふろくをここでは「モノふろく」2と呼びたいと思いますが、紙ものふろくからモノふろくに変わったことは、ふろく史上で最も大きい変化だったと思います。ふろくを作る体制の変化についてお話をうかがえますでしょうか?
<冨重>
まず、90年代くらいのふろくの決め方を説明すると、例えば、「メインの付録はシールで、とにかくたくさんつけたい、予算規模が例えばそれが50円として、次に第2ふろくを箱の組立もの、その他も含めて提案してください」というのを何社かの印刷業者に投げる。それで各社が「うちはシールだったらこんなものがつくれます、組立ものだったらこれがたったの20円でつくれます」といった提案がたくさん出てきて、それをとりまとめてこれにしましょうというのを決めていたと思います。
<後藤>
ふろくもどこか1社にすべて頼むのではなく、同じ号のふろくでも細かくわけて複数の会社に頼んでいたのですよね。
<冨重>
そうです。例えば、1枚のペラのB5版の紙から組み立てて何か作るというのは図書印刷さんが得意でした。松下印刷さんはふろくをビニール袋に袋詰めすることも含めて担当されていました。トランプをセットして詰めることも内職の手作業でしたね。
―カルタとかは自分でピリピリと点線にそって破いて作るものでしたが。
<冨重>
カルタはね。そこまでのコストはかけなかったですけど、トランプは自分でぴりぴりやるっていう時点でテンション下がるじゃないですか。トランプはすぐに使える形で一枚一枚切り離されてセットされている。だからトランプのことで電話がかかってくることも多かったですね。「私のトランプ、ダイヤの4が2枚入っていたんですけど」とか。
―そういうのはどのように対応されていたのですか?
<冨重>
送ってあげていましたよ。そういうミスは手作業でやることですから仕方ないですよね。内職でやっていました。徳島の内職工賃が安かったみたいですし、内職の組織がしっかりしていたことも大きいです。
―印刷会社はずっと国内ですか?
<冨重>
90年代末頃から海外の工場も。初めて海外で印刷したのは、カレンダーのはず。海外で刷ると安いとかで。
―国内で作るのと違いはありましたか?
<冨重>
スケジュールだけですね。スケジュールが早いというのと、海外の場合は『りぼん』の印刷は、基本的に3FCという3色プラス、FCP(フラッシュカラーピンク)を使うのですが、海外の工場の印刷は基本4色分解の4色印刷しかないので、だいたいピンクの塗りが悪いというのが海外印刷の特徴だったのですよ。今はマンガ家さんもみんなカラーをデジタルで描くので、原画と色が違うとかそういうのはないですから、海外で印刷するストレスはあまりないですね。
―2001年にふろくに関するルールが変わり、紙ものふろく以外の素材のふろくがつくようになりましたね。そこから『ちゃお』が一気に台頭してきたと思いますが。
<冨重>
当時は規制が変わっても「ふーん」ぐらいにしか思わなかった。例えるなら、ランプで暮らしている一族が『りぼん』という村に住んでいて、一山越えたところで『ちゃお』という村にガスが通じて電気が通じて......。でも『りぼん』村の住人は「別にランプでも不自由ねえし」と思っていた(笑)。
―『ちゃお』は2001年1月号からビーズのブレスレットをつけたりしているのですよね。
<冨重>
そうそう。だから『りぼん』だったら全サでもらえるものが、『ちゃお』はふろくでついてくるじゃん、と読者は思ったはずですよ。
―では、『ちゃお』が一気に仕掛けてきたところで、『りぼん』はちょっと焦って、急いでモノふろくをつけた感じですか?
<冨重>
『りぼん』の部数が落ちてきて、『ちゃお』が上り調子になってきたので。トミー(現:タカラトミー)など玩具メーカーとのタイアップというのもいち早くやっていて。
―アイドルとのタイアップ企画も当時目立ちましたよね。『なかよし』では当時圧倒的な人気のアイドルグループのモーニング娘。のふろくをずっとやっていました。本誌でもモー娘。の連載を1年ぐらいずっとやっていて。
<冨重>
そう流れが他誌である中、『りぼん』は「いや、うちはマンガで勝負するから」といったスタイルでした。
―2001年10月号の『りぼん』で初めてバンダナがついた時の表紙の扱いは大きかったですよ。
<冨重>
今見るとすごい表紙だ。このバンダナは綴じ込みふろくだから。さっき言った内職の仕事にかからないんですよ。雑誌の製本の締切に間に合えばいいので、急に突っ込んだというのは関係者が見ればすぐわかりますね。
―なるほど。では、元々表紙もこんなにバンダナを大きく入れるわけではなかった?
<冨重>
いやそこまで急じゃないですね。表紙の依頼は10月号だったら7月下旬とかだから、バンダナの写真が入ることは想定して頼んでいたと思います。
―そのあとも「特別ふろく」という形で缶バッジがついたり......それからどんどんモノふろくの割合が増えていきましたね。
<冨重>
原価を無視し始めるという。『ちゃお』は原価を無視してでも『りぼん』を抜くということが社命として下っていたと思います。
―『りぼん』も対決するしかなかったわけですね。
<冨重>
対決するしかないけど、『りぼん』はモノふろくのノウハウがまったくなかったので。小学館は学年誌ですでに色んなノウハウがありましたから。
―すでにモノふろくをつけている雑誌が小学館にはあった。いろんな業者さんも小学館はご存知でしたでしょうしね。
■現在のふろく
―現在のふろくの内容はどんなふうに決定していますか? そもそも何号前から決まっているのでしょう?
<後藤>
だいたい半年前に決めて、発売の2ヶ月前に完成しているようなスケジュールです。
―90年代のふろくの制作現場とは全く変わりましたか?
<冨重>
ちょうど後藤がふろく担当になった2010年頃からかなり変わりました。モノふろくがメインになっていく中で、大きな内職の組織を解体しなければならなかったので。
<後藤>
モノふろくはすべて中国で製作、箱で梱包するので、一社にお願いせざるを得ないのです。
―時代の流れとはいえ、一大事でしたね。苦渋の選択もあったと思います。この10年ぐらいで海外への発注に切り替わった。逆にいえば、最初に海外にカレンダーを頼んだときから考えると、完全に切り替えるのに10年かかったともいえますね。
<冨重>
すべては紙もの以外の素材が認められてからですね。
<後藤>
どんなふろくにするかの決め方も大きく変わりました。昔はメーカーからのプレゼンテーションがあって、「こういうものができます」といった中から選ぶ形だったのですが、私のときから、外部の意見も取り入れようという話になった。提案会議というものがまずあるのですが、そこに『りぼん』の年代により近い若いライターに協力してもらい、街中でおもしろいもの、かわいいものみたいなものをとにかく調べて持ってきてもらっています。それをもとに話し合い、まずテーマを決めて、数社から見積もりをもらい、検討して再見積もりを貰って......といったやり取りを経て決めています。
―マンガ家へのイラスト依頼はどのような流れで依頼していますか?
<後藤>
今はマンガ家さんにイラストを頼むふろくの数がそもそも少なくて、シールぐらいしかないんですよ。あとは手帳とカレンダーですね。何月を担当だからこういうものを描いて、とかお願いして描いてもらうことはあります。例えば、10月だったらハロウィンのコスチュームをキャラに着せて、とかはあります。
―今はちょうどハロウィンですが、季節ごとのイベントに合わせたりなどあると思いますが、〜月号はこういうふろくをつけるのが定番とかありますか?
<後藤>
ハロウィンは昨今すごく盛り上がって、定番化したのはこの2、3年ぐらいの流れですね。
あとはバレンタイン。最近では手作りチョコが作れるシリコンの型抜きが3月号の定番です。3月号というのは2月3日売りになりますから、ちょうどピッタリでしょ!と。そして一番人気の2月号手帳。
<冨重>
昔だったら1月号に着物の表紙とかやっていた。でも1月号は12月1日発売で読者はクリスマスの気分の時です。そういう意味では、りぼんの長い歴史の中で、私が編集長になってまっさきに変えたことの1つが「新春特大号」とかの表記をやめたことです。「お正月特大号」、「2月新春特大号」「夏休み特大号」「新学期特大号」、その表記を全部やめたのです。
―読者のリアルに合わせたということですね。それはいつごろからですか?
<冨重>
2013年からですね。
―最近では「まんが家セット」もブームになりましたね。『りぼん』は昔から新人育成をしっかりやってきた雑誌でしたし、マンガ家になりたいという読者が一つ大きな読者層としていますね。それはやはり意識的に?
<冨重>
めちゃくちゃ意識しています。集英社の中でも『りぼん』が漫画家を育てて読者を育てる雑誌にならないといけないので。
―『りぼん』は集英社にとって先行投資でもあるわけですね。
<冨重>
だから「小学生まんが大賞」というのをやったりしています。
<後藤>
『りぼん』はどんなマンガのセットをつけるか、という時、なんちゃってマンガ家にならないものを付けたいという思いがありました。60周年号となる2015年9月号のふろくは集大成にもなるので、「まんが家デビューセット」でも、ふろくを使ってそのまま投稿までできるというのをやりました。
<冨重>
イラストとマンガの定義の違いとか会議でみんなで話し合って。編集方針じゃないけど、読者の小学生を子ども扱いしちゃ絶対駄目だというふうに思っています。だから、「小学生まんが大賞」も大賞作は普通の作品と一緒に載せないと意味ないと思っていたし、小さく縮小して1ページに2ページ掲載とかいうのは絶対やりたくなかった。小学生は小学生で自分たちは大人だと思っているわけだから。だから、2015年9月号のふろくも、このふろくで一作品を描ける、それで投稿というところまでやりたかった。酒井まゆ先生に同じふろくの道具だけを使って一作描いてもらうとか、そういうのもやりました。やるからにはそこまでやらないと。
<後藤>
「投稿するなら『りぼん』だよね」というイメージを作りたかった。このふろくが出た時にちょうどこのふろくを使って応募できる特別マンガ賞も作りました。「60周年コンテスト」というもの。ふろくには8枚原稿用紙がついたので、それで応募できちゃう。1枚でもいいという条件にしました。原稿用紙のサイズも、他誌の漫画家セットだとポストカードサイズですが、『りぼん』では本誌のサイズのぎりぎりまで大きくしてA4に近いサイズにしました。これに描いてそのまま送ってね、という形です。中には、マンガなんか別に描かないといった子もいたと思いますし、60周年の記念ふろくとしては地味に見えるかもしれません。でも、潜在的にちょっと描いてみたかった子というのはいる。未来のマンガ家の掘り起こしのためのものです。
―これをきっかけにマンガ家を目指す子もいそうですよね。それ以外のふろくも色々ありますが、どんな思いで作られていますか?
<後藤>
『りぼん』を好きな子のためのファンサービスアイテムにとどまらず、『りぼん』どころかマンガも読んだことのない子の目にとまり、それからマンガを読んで好きになってもらう導入のアイテムでありたいと思います。
<冨重>
昔からふろくって、「まんが家セット」も含めて憧れのアイテムであるということには変わらないと思います。その時の10歳の子たちが何に憧れてなにがほしいかというものをつけている。昔の組立もので本棚とかあったと思いますが、今の懸賞の賞品でも家具系って意外と人気なのですよ。座椅子とか家に送られてきたら、親は迷惑だろうと思うのですが。子どもたちってパーソナルなものが大好きです。
<後藤>
実際の小学生の話を聞き取りしたりもしています。バレンタインのシリコン型もそういう中で生まれた企画です。「みんな友チョコ作ってるよー」といった話を聞いて。
―いわゆるモニターですか? どのくらいの頻度で聞き取りされているのでしょうか?
<後藤>
月一回のペースです。日曜日に。今の小学生は習い事とかで平日とか土曜日は忙しいので日曜日に来てもらってお菓子を食べながら、「このふろく、デザインこんなのあるんだけど、どっちが好き?」とか「今は何が流行ってるの?」みたいなことをリサーチしています。
■思い出のふろく
―これまでのお話にも色々出ていますが、お二人の思い出のふろくはありますか?
<冨重>
やはりさっき話した60周年企画の「まんが家デビューセット」ですね。自分の編集長としての方針として、いいふろくをつけることができたと自負しています。それ以外だと、CD-ROMをつけたときかな。
―2003年に初めてCD-ROMをつけたときですかね。
<冨重>
そうです。私は『りぼん』のホームページの立ち上げも担当していて、無料のゲームがやたら人気で。当時インターネット回線が遅かったので、オフラインゲームとか、そういうコンテンツができるといいなと。それでミニゲームなどが入ったCD-ROMをつけた。今だとネット回線が遅くてということもないですが、時代を反映したふろくです。その後、私が転属になったあとも、CD-ROMをふろくにつけているから好評だったのだと思います。
―本誌のほうでは、このふろくについてのかなり細かい説明のページが割かれています。
<冨重>
マウスを「クリックする」とかパソコン基本用語まで載っている。使い方がわからない読者のために専用の電話番号まで作りました。制作の人に常駐してもらって。
―後藤さんは思い出のふろくはなんですか?
<後藤>
私がまだ専属のふろく担当じゃなかった時でしたが、2010年にオールカラーで本文96ページある本格的な手帳をペンとセットでつけたことがあり、それが印象的でした。正直、「子どもにこんな本格的な手帳いるのかな?」とか思っていましたがそれが受けて。次の年にもつけましたが、売上率がすごく良かった。今では定番です。昔から手帳は花形のふろくだけど、改めて人気があるのだと驚きました。大人が考えるより子どもは自分のことを子どもと思っていないですね。読者の少し上の大人っぽいデザインが今も昔も変わらず読者は好きです。そういうデザインのものを作らないといけないと思わされたのが手帳でした。
■これからの『りぼん』
―『りぼん』に投稿したいと思っている読者にどんなことを伝えたいですか?
<冨重>
何を描いてもいいんだよと。さくらももこ先生や岡田あ〜みん先生が生まれた雑誌だぞここはと。少女マンガでも恋愛じゃなくたっていいじゃんって。例えば、今だと「なないろ革命」というマンガがありますが、友達関係のことが主題です。そういうものがどんどん増えてもいいし、『りぼん』はこうだというのを誰も決めていない。マンガ家さんも編集部もみんな『りぼん』はこうだと考えないで、色んなものが出てくるといいなと思います。『りぼん』というタイトルで10年後、20年後、全く全然違うものになっていっても、それはそれでいいかなというぐらいに思っています。
―逆に『りぼん』としてやっちゃいけないラインというか、タブーといったものはありますか?
<冨重>
アンケートで「誰が買いましたか?」の質問では回答の4分の1が母親です。なので、90年代に私が担当として通しちゃったセックスシーンは今では基本的に駄目ですね。編集方針は、ざっくりとしているけど、『りぼん』に関わっている人みんなが幸せになる雑誌にしたい」という話はしています。例えば、見たくもないシーンを見てしまうというのは不幸になることだから、差別表現もそうだし、それを読むことによって不幸な気持ちになるようなものは載せない。『りぼん』に接した人みんなが幸せになるものというのがそうした方針に含まれています。
―なるほど。『りぼん』の黎明期では「お母様のページ」というのがあったりしましたが、親の目線というのは今、またすごく重要になってきているわけですね。
<冨重>
サイン会などで、「お母さんも一緒に読んでいます」と言われることとが結構多いです。そういう意味では、やっぱり親子一緒に楽しめるものという時代になっているのかなと。本当は親に隠れてこっそり読むぐらいのもののほうがいいとは思いますけどね。私が入社した頃は10代の投稿者に入賞したことを伝える電話する時に、まず自分が怪しいものではないというところから説明をしなければいけない名残があったけど、今では小学生大賞なんかもあるから、「りぼん編集部から電話よ! 〜ちゃん! きゃーっ」て親が喜ぶという。
―今や親もかつて一生懸命『りぼん』を読んでいた世代になっていますからね。昔だと、親は監視者。今は一緒に楽しむ存在ということですね。
<冨重>
60周年企画で、『ちゃお』に勝てるころは、お母さんが読んでいたところだなと思い、そこは意識してやりました。あとは、書店さんが少なくなっているというのも大きい。お小遣いをもらっていない子が今はすごく多いし、本屋さんが自分の半径500メートル以内にない子たちも多い。学校帰りに、発売日に自分で買うとか、そういう子がすごく減っている。休みの日に家族でイオンモールに行った時に書店で買ってもらうとか、そういう流れが多いようです。親子で一緒に買うところから始まっているわけですから。
―最後に今後、『りぼん』はどんな雑誌にしたいか? またなっていくべきかなどお考えをおきかせください。
<冨重>
3年後の女の子が何に興味を持っているかなんては何も想像ができません。その時その時の読者とキャッチボールをして一番いい状態の雑誌でいられればいいなと思います。その中で、初めてマンガという素晴らしいエンターテインメントに触れ、これからもずっとマンガを読みたいというふうに思ってくれるといいなと思います。
<後藤>
「子ども」じゃなくて「女の子」に向けて楽しみを提供する雑誌として、努力をしないといけないと思います。この二者はまた別の人種なのだと考えています。「女の子」が一度形成されると、これって多分一生続くのですよね。このメンタリティーは特有なものだと思います。『りぼん』はその玄関口だと思うので、非常に重大な使命を負っているなと思います。
ふろくについては、ちょっと大人でおしゃれというのは、多分昔から『りぼん』で受け継がれてきたことだと思いますが、そういう風にあり続けていきたいですし、「女の子」に向けて作るので、「女の子」というものを見失わないようにしないといけないなと思います。
<冨重>
今、幼稚園ぐらいの子がタブレットとか使って育っているわけですから、この世代がほんの5年後くらいには『りぼん』の読者になってくるわけで、そうなった時にその子たちを満足させるのはなにがいいのかというのは、また違うこと考えなきゃいけないだろうなと思います。
―どうなっていくかは予想できない。『りぼん』の未来は予測不能だけどこれからもきっと進化していく雑誌だと思います。本日はありがとうございました。











