9月19日(土)から9月27日(日)にかけて「第23回文化庁メディア芸術祭受賞作品展」が開催され、会期中には受賞者らによるトークイベントやワークショップなどの関連イベントが行われた。9月20日(日)には特設サイトにて、アート部門新人賞を受賞したSebastian WOLF氏とアート部門ソーシャル・インパクト賞に選出されたLauren Lee McCarthy氏が登壇。モデレーターにはやんツー氏と萩原俊矢氏を迎えて、アート部門 受賞者トーク「私たちと機械の向こう側の人たち」が配信された。本稿ではその様子をレポートする。
 トークイベントの様子。左から、やんツー氏、McCarthy氏、WOLF氏、萩原氏
トークイベントの様子。左から、やんツー氏、McCarthy氏、WOLF氏、萩原氏
「人 vs 機械」という二元論を超えた体験
このトークは東京のバーチャルスタジオから、やんツー氏、萩原氏のモデレートで配信され、受賞作家からはドイツのSebastian WOLF氏と米国のLauren Lee McCarthy氏(米国)がオンラインで登壇。両者の作品を起点に、機械と人間の関係について多様な意見が交わされた。
WOLF氏の受賞作『drawhearts』は装置型インスタレーション。ガラス壁上を電気式アームが移動し、小型噴射器から蒸気を噴きかけ曇らせては、そこにハートの形を描くという動作を繰り返す。懐かしい遊びを思い出させるその動きは、機械が人間のためではなく、自身のために動いているような印象も与える。WOLF氏は「本作は、機械等による自動化と、そこにおける感覚(センス)の有無、また人間の労働の価値などを取り上げる連作のひとつ。私はテクノロジー自体に加え、それが詩的あるいはエモーショナルな可能性を持つことに関心があります」と語った。
 『drawhearts』
『drawhearts』
© Yaqin Si
やんツー氏は「この作品では、機械が子どものような動きをすることや、メカニズムの美しさを見せている」とコメント。WOLF氏は装置を生物などに似せて「かわいく」つくることは極力避けたというが、「それでもこれらを前にすると、人間側に『感情』が生じますね」と語り、私たちが機械に対して抱く独特の感覚に言及した。また萩原氏から「機械が人間の仕事を奪う」といった議論も含め、両者の関係性についてどうみているかを問われたWOLF氏は「私はそこについては楽観的です。問題は、機械の背後にも常にある、人と人の関係性。これが人間と、機械やテクノロジーとの関係を良くも悪くもするのでしょう」と返答した。
 やんツー氏
やんツー氏
McCarthy氏の受賞作『SOMEONE』は、対話式スマートスピーカーによって身近になりつつあるスマートホーム(AIが住宅の電化製品制御などを支援するシステム)を扱う。ただし、住人とやりとりするのはAIではなく遠隔地にいる鑑賞者だ。作家に協力した4組の参加者宅にカメラ、マイクとスマートデバイスを設置し、それらを展示ギャラリーとインターネットで接続。鑑賞者は各家庭の映像を目にし、住民から呼びかけられればデバイスを遠隔操作して要望に応える。McCarthy氏は同作の背景をこう語った。「テクノロジーは便利で有用ですが、(自覚せぬまま)プライベートが侵される可能性もあります。人間が果たしてきた役割に機械が取って代わるとき何が起こり得るのか。あるいは『向こう側』(システム側)から見たとき、そうしたやり取りはどう体験されるのか。これらの関心から本作に取り組みました」。
 『SOMEONE』
『SOMEONE』
© Lauren Lee McCarthy
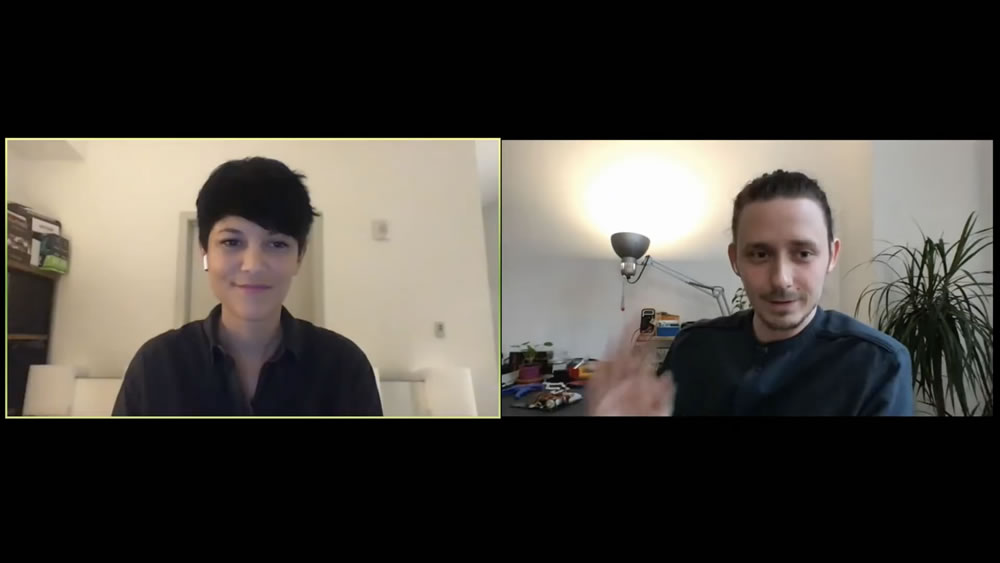 左から、アート部門においてソーシャル・インパクト賞を受賞したMcCarthy氏、新人賞に選出されたWOLF氏
左から、アート部門においてソーシャル・インパクト賞を受賞したMcCarthy氏、新人賞に選出されたWOLF氏
「向こう側」に存在するものを想像する大切さ
McCarthy氏によれば、『SOMEONE』でスマートホームAIの代役を体験した観衆は多様な反応を示したが、おおむね住人との友好的で親密な関係がみられたと語った。作品内容を知ったうえで協力した居住者にとっては、機械ではない「誰か」の存在感がネットワークの向こう側にあり、一方の鑑賞者側でも、参加することで互いにその認識が高まるという。同作がテクノロジーへの問題提起であると同時に、新たな生活環境での親密な関係性構築など、希望にも光をあてるものになっていることを示唆した。
親密さに関連して、萩原氏は『drawhearts』からは、小さなころ窓に息を吹きかけ絵を描いた記憶を挙げた。WOLF氏も「そうした各々の記憶があるので、見る側がこの機械とのつながりを感じるのだと思う」とした。またハートが手描きのような形なのは「試作中に偶然こうした歪んだ形になったのですが、むしろ個性があるようで良いと思いそのまま使いました。ただ、毎回同じ歪みかたで描くという点では、(機械として)完璧に動作しているとも言えます」と、本作の持つ人間らしさ/機械らしさの両面に言及。本作が一見すると自己完結した(=閉じた)世界観で成立しているように見えて、実際は観衆の感情や記憶を喚起し、機械やテクノロジーと人間の関係性を考えさせる作品であることを印象付けた。
WOLF氏は、作品における遊び心や、結論を押し付けないオープンさの重要性も語った。『SOMEONE』にもそれがあるとし、「遊び場のような形で探索するなかで、自らの結論を引き出すことができる環境を提供している」とした。McCarthy氏は両作に通じる点として、「実際の目に見えるインタラクションだけでなく、『向こう側』にいる者について想像することが重要に思える」と言及。『drawhearts』の場合は装置が人間のように見えることも、まったくそう見えないこともあり、その中間性の感覚が興味深いとした。また萩原氏からは、彼らの作品がシリアスなテーマを内包しつつ、ユーモアを共存させているとの指摘があった。
 萩原氏
萩原氏
ほか、『SOMEONE』が示唆するような、情報化社会における利便性とプライバシーの関係について、現在ではネットを基盤とした巨大プラットフォームが世界中のユーザのデータを吸い上げていることの危険性も話題となった。今や生活基盤となったネットをめぐるこの問題は今後も避けがたいとしつつ、市民の発言機会や、複数の選択肢を確保できることの重要性が語られた。McCarthy氏は「新型コロナ感染症の拡大でそれが試練に晒されている」ともコメント。接触確認アプリなどから見えてくる課題を登壇者が語り合う場面もあった。
最後にモデレーター陣から登壇作家たちに、新型コロナによるさまざまな制限下でも遠隔対話などでコミュニケーションが続く現在、改めて人と人、あるいは人と機械の関係性について貴重な視点が得られたことへの謝意が示された。萩原氏の締めの言葉「コロナが落ち着いたら世界のどこかで直にお会いしたいです」は、今や世界中で交わされる挨拶にもなった。そうした日がきたとき、人と機械の関係性はどこへ向かうのか。そうした「向こう側」への想像も喚起させるトークとなった。
(information)
第23回文化庁メディア芸術祭 受賞者トーク・インタビュー
アート部門 受賞者トーク「私たちと機械の向こう側の人たち」
配信日時:2020年9月20日(日)10:00〜11:00
出演:Sebastian WOLF(アート部門新人賞『drawhearts』)、Lauren Lee McCarthy(アート部門ソーシャル・インパクト賞『SOMEONE』)
モデレーター:やんツー(美術家)、萩原俊矢(アート部門選考委員/Web デザイナー/プログラマ)
主催:第23回文化庁メディア芸術祭実行委員会
https://j-mediaarts.jp/
※受賞者トーク・インタビューは、特設サイト(https://www.online.j-mediaarts.jp/)にて配信後、10月31日まで公開された
※URLは2020年12月14日にリンクを確認済み











