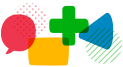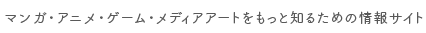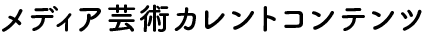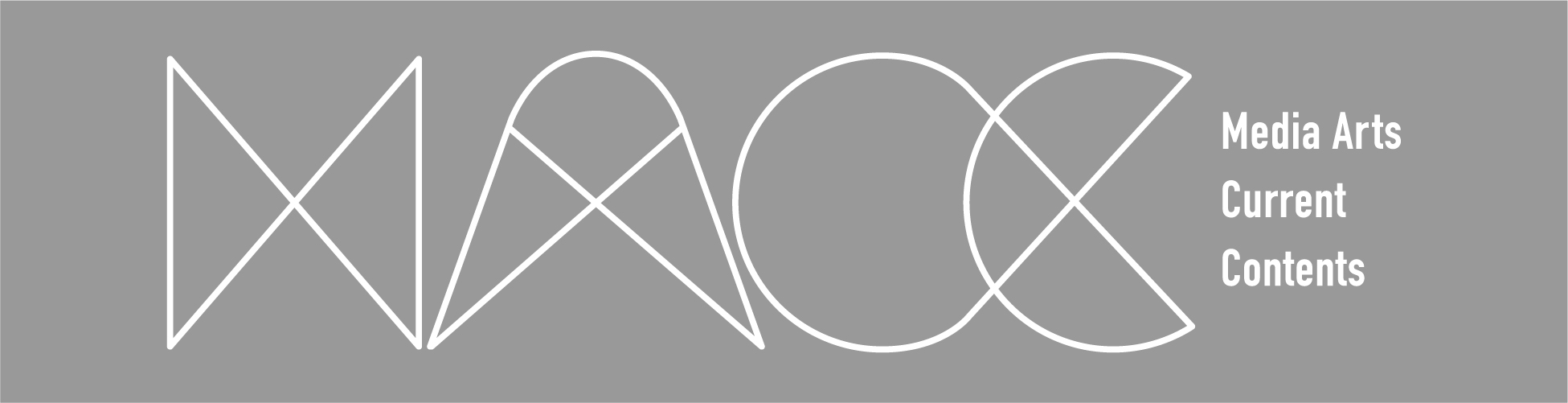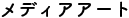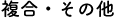読まれている記事一覧
青少年向け小説における表紙イラストレーションは、1970年代中盤からマンガやアニメと接近しはじめ、1990年代前半までには、その絵柄に近い印象の表紙を持つ...
「特撮の神様」とも呼ばれる円谷英二(つぶらや・えいじ、1901-1970)の出身地にして「特撮文化推進事業実行委員会」にも参画する福島県須賀川市で、2019年...
戦後日本のアニメーションは、様々な文化的・産業的影響を強く受けつつ発展してきました。しかし、そういった我が国アニメーションに反映された多様な社...2014年3月14日 更新
公開から30年を経ても、未だ世界中に根強いファンを持つリドリー・スコット監督の映画作品『ブレードランナー』(1982)。その続編としてドゥニ・ヴィルヌー... 現代の映像視聴環境、制作環境は、常に激しい変化の中にある。特に近年のスマートフォンなどデジタル端末の普及に象徴される、デジタルデータの活用法の変化...
1971年より始まった「仮面ライダー」シリーズは、2020年に放送を開始した『仮面ライダーセイバー』でテレビシリーズ32作目を迎えた。昭和、平成、令和と... アニメーターの黄瀬和哉は「リアル系」という言葉で形容されてきたアニメーターであるが、ここで言われているリアルとは何だろうか。1995年に発表され、2013... 全114巻が刊行された『水木しげる漫画大全集』。監修を務めた、水木しげる門下でもある小説家の京極夏彦氏がその制作過程について語る。前編では同氏が本シリ... 2018年、日本のアニメ雑誌御三家のなかで最も古い「アニメージュ」が、創刊40周年を迎える。これを機会に、3回にわたって、アニメのあり方とともに変わってい... もとは日本製のコンピュータRPGを指す「JRPG」だが、近年ではJRPGの様式を取り入れた海外製のRPGをも内包するジャンルとしての意味合いが強くなってきている...田中 治久(hally)2021年12月24日 更新
2000年代、2010年代のアニメソング・アニメ劇伴界を代表する作曲家・神前暁さん。前編は、学生時代までの音楽に親しんだ経験、ゲームメーカーでの作曲の...
「特撮の神様」と称される円谷英二の故郷である福島県須賀川市に、2020年11月3日「須賀川特撮アーカイブセンター」がオープンした。近年の特撮文化推進事...
『ベルサイユのばら』をはじめとして、これまで宝塚歌劇団によって数々の少女マンガが舞台化されてきた。本シリーズでは、宝塚と少女マンガの融合によって... 「マンガ」という語から大抵の現代人が思い浮かべるのは、コマ割りされ、絵と吹き出しによって物語が進んでいく「ストーリーマンガ」だろう。しかし、辞書に...
戦後、アメリカの大衆文化を反映して生まれたポップ・アート。欧米で現代美術としての評価が確立されていくなかで、次第にその影響が日本の作家にも現れ... 2013年から2019年にかけて刊行された『水木しげる漫画大全集』。そのラインナップを見てみると、誰もが知る『ゲゲゲの鬼太郎』『悪魔くん』『河童の三平』か... アーティストとして、大がかりなインスタレーション作品や知覚と関連付けたインタラクティヴ作品を発表し、教員として、メディアアートの制作教育に携わった...
PlayStation®4で発売されたアドベンチャーゲーム『Detroit: Become Human』。自我を持つ3体のアンドロイドを巡る運命を描いた本作は、さまざまな意味で今年...
2000年代半ば以降、「アートゲーム」と呼ばれるビデオゲームのカテゴリーが目立ったかたちで現れてきた。本稿では、アートゲームの特徴を大まかに示したう...
2020年末にPlayStation® 5と次世代Xboxが出るタイミングに合わせ、ゲーム業界の識者に各方面からこれまでの5年間を振り返り、そしてこの先の5年間の未来...
ページの先頭へ