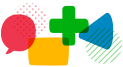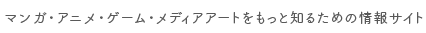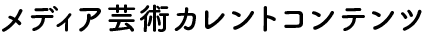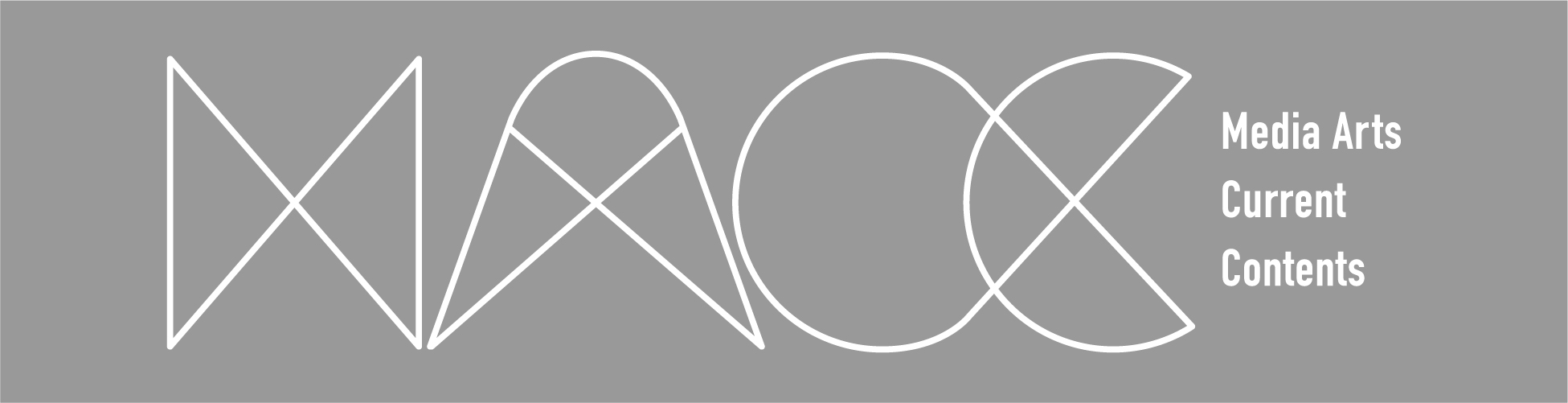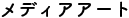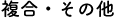北米のメディア芸術記事一覧
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)との対峙も3年目に入り、ポストコロナを迎えつつある2022年。海外のアニメーション・シーンでは、アニメーション映画祭... 「Rhizome」のプリザベーション・ディレクターのドラガン・エスペンシードにインターネット・アートの保存活動について聞く本コラム。Rhizomeで働くまでの経... インターネット・アートの保存活動を行っているアート機関「Rhizome」のプリザベーション・ディレクターとして働くドラガン・エスペンシードにインタビューを... 第25回文化庁メディア芸術祭で功労賞を受賞した株式会社ポリゴン・ピクチュアズ代表取締役の塩田周三氏は1991年に新日本製鐵株式會社(現・日本製鉄株式会社... 第25回文化庁メディア芸術祭で株式会社ポリゴン・ピクチュアズ代表取締役の塩田周三氏が功労賞を受賞した。塩田氏は、2D作画が多い日本のアニメーション制作... Ever since the launch of Space Invaders (1978), Japanese video games have been taking the world by storm, but in addition to becoming hits, some of...2022年8月16日 更新
前回はアメリカ合衆国を中心としたシリアスゲームの歴史を第二次大戦直後の1948年のアメリカ軍によるオペレーションズ・リサーチ室(Operations Research Off... アメリカの教育現場では、社会問題をテーマとする「シリアスゲーム」が授業に取り入れられている。本稿ではこのシリアスゲームの歴史を、アメリカ軍のシミュ... 「Small Data Industries」創設者のベン・フィノラディンに、同社の取り組みおよびデジタル・プリザベーションとメディア・コンサベーションについて聞く本コ... デジタル資料の長期保存や保護を表す「デジタル・プリザベーション」、そしてメディアや映像を用いた芸術作品の保存を指す「メディア・コンサベーション」。... もとは日本製のコンピュータRPGを指す「JRPG」だが、近年ではJRPGの様式を取り入れた海外製のRPGをも内包するジャンルとしての意味合いが強くなってきている...田中 治久(hally)2021年12月24日 更新 アニメ・マンガ・ゲームを中心的な研究対象として取り扱うメカデミア(MECHADEMIA)国際学術会議が、2021年6月5日(土)~6日(日)に開催された。当初、2020... 俳優であるジョージ・タケイの太平洋戦争中の経験が描かれたグラフィックノベル『〈敵〉と呼ばれても』。日本とアメリカを含む連合国が戦うなか、彼は自らが... 昨今、国内で数多く公開されるようになってきた海外の長編アニメーションだが、お披露目の場となる国際的なアニメーション映画祭、さらには制作の現場におい...
アメリカのアニメーション史を語るうえで、ウォルト・ディズニーと並んで欠かせないフライシャー兄弟。本稿では、誰もが知るようなキャラクターが登場す...
『スペースインベーダー』(1978年)以降、日本のビデオゲームは広く世界を席巻してきたが、なかには単にヒット作となるに留まらず、ひとつの様式やジャ...
1993年にアメリカで発行され、マンガ研究の基礎文献として位置付けられているスコット・マクラウド著『マンガ学 マンガによるマンガのためのマンガ理論』...
翻訳をテーマにした企画展「トランスレーションズ展−『わかりあえなさ』をわかりあおう」が、21_21 DESIGN SIGHTで2020年10月16日(金)から2021年6月13...
前編では、『ジミー・コリガン 世界で一番賢いこども』から、「マンガを読む」ことについて考察した。後編では、稀有な方法により紡がれたこの物語が、...
「マンガを読む」という体験について、考えたことはあるだろうか。テキストやイラストを自由にレイアウトしたグラフィックノベル、クリス・ウェア『ジミ...
ページの先頭へ