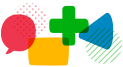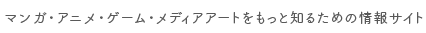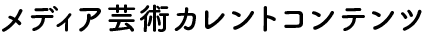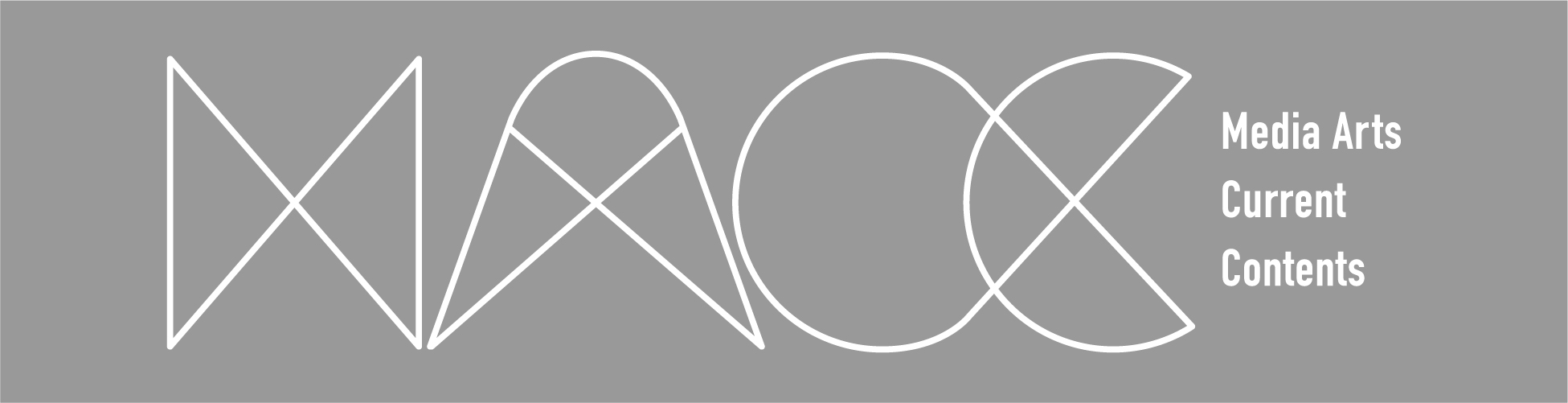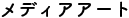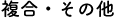読まれている記事一覧
アメリカやフランスと比べて、コミック文化のイメージが一般にはまだ浸透していないアフリカ。実際のところアフリカのコミック作品を紹介される機会も少ない...
海外の盛り上がりとは裏腹に、国内で活躍の場を失いつつある怪獣たち。かつて銀幕やブラウン管で所狭しと暴れ回っていた彼らは、もはや絶滅危惧種と言って... マンガの出版市場の縮小が止まらない。紙から電子へという大きな変化が起きていることは間違いないが、マンガ雑誌の凋落はそれだけでは説明がつかないほどド...
2019年9月に公開された伊藤智彦監督のフル3DCGによるアニメーション作品『HELLO WORLD』。SFからミステリーまでを手がける小説家・野﨑まどが脚本を務め、...
4K、HDR、ハイフレームレートなど、本コラムではこれまでデジタル技術やAIによる映像表現の意味と可能性について、今進みつつある変化を興味の赴くままに... マンガ雑誌黄金期をよく知る編集者から、編集部の裏側を聞き出すコラム。前回に引き続き、今も現役のコミック編集者として活躍する佐藤敏章(さとう・としあ...
2020年末にPlayStation® 5と次世代Xboxが出るタイミングに合わせ、ゲーム業界の識者に各方面からこれまでの5年間を振り返り、そしてこの先の5年間の未来... 夏目真悟が監督・脚本・原作を手がけ、江口寿史がキャラクター原案を、マッドハウスが制作を担当したオリジナルテレビアニメーション『Sonny Boy』。「SF青春...
新型コロナウイルスが全世界で猛威を振るっている。こうしたなか、品薄状態が続いているのが2019年10月に発売された『リングフィット アドベンチャー』だ。...
前回は、集英社の週刊少年ジャンプ編集部が運営する海外向けマンガ配信サービス「MANGA Plus by SHUEISHA」(以下、「MANGA Plus」)について、「少年ジャ...
2010年代以降、「美少女」や「日常」といったくくりで語られることも多いアニメーション制作において、高い支持を得てきたアニメーション制作会社・動画...
海外においてまだ日本のマンガが浸透していなかった90年代に、アメリカのファンダムで“最もよく知られた日本のMANGA家のひとり”であったまんが家・一本木蛮... Animation is usually appreciated focusing on painted/drawn pictures and images. But animation also incorporates various effects of lenses, such as ...OGURA Kentaro2022年8月18日 更新
80年代の後半から原画マンとして活躍し、メカニックの重量や質の表現、爆発や煙炎などのエフェクト、重量のある動きが感じられる人物描写など、「リアル...
平成24年夏に東京都現代美術館で開催された「館長 庵野秀明 特撮博物館 ミニチュアで見る昭和平成の技(以下、特撮博物館)」などを契機に、...2013年5月21日 更新
1995年の開館以来、マンガ原画の収蔵に積極的に取り組んできた横手市増田まんが美術館。2019年には原画保存とその活用に重点を置いたリノベーションを行...
国や地域の垣根を超えて国際的な人気を獲得しつつある“グラフィックノベル”。日本でも浸透しつつあるグラフィックノベル作品を、「越境」をキーワードに紹... This is a series of interviews with artists who have pioneered the expression of sounds in the world of media arts, including the fields of animati...
2000年4月から2001年3月にかけて全6話のOVA(オリジナルビデオアニメーション)としてリリースされた、ガイナックス制作の鶴巻和哉監督『フリクリ』。こだ... 「ライトノベル」というジャンルはここ20年でますます拡大しているが、その特徴として欠かせないもののひとつがイラストレーションではないだろうか。そんな...
ページの先頭へ