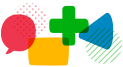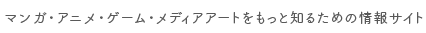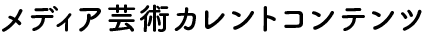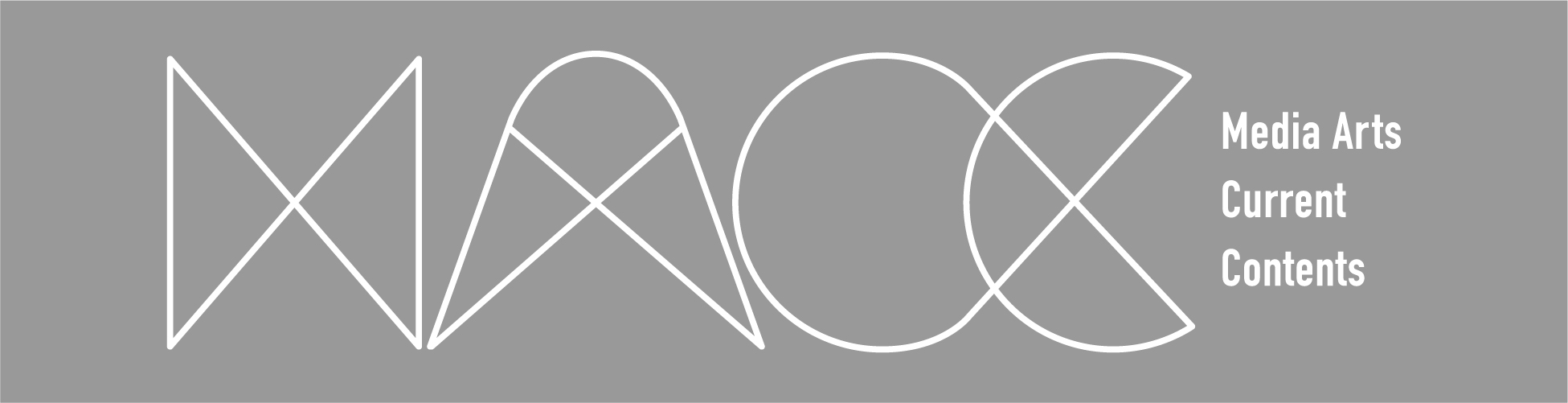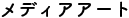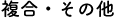読まれている記事一覧
新型コロナウイルスが全世界で猛威を振るっている。こうしたなか、品薄状態が続いているのが2019年10月に発売された『リングフィット アドベンチャー』だ。...
「ピクセルアート」という視覚表現がある。ピクセルアートは、1970~90年代のビデオゲームのグラフィックの主流であったおかげで、「レトロなゲームのグラ... TANAKA Kohei is a unique composer who has been specializing in creating music for animation and video games since the 1980s until today. He started...
2020年6月に米国・ニューヨークのクラウン・パブリッシング・グループより『Pure Invention: How Japan's Pop Culture Conquered the World』が刊行され... マンガ雑誌の黄金期を支えた編集者の証言から、当時のマンガ出版界を見ていく連載の第5回。今回は「週刊少年サンデー」や「ビッグコミック」に携わり、今も現...
マンガ雑誌が熱かった時代の現場の様子を当時の編集者に聞くシリーズ。第9回と10回は、「青年コミック誌の先駆け」と言われる『Weekly漫画アクション』の黄...
報告者 立命館大学 衣笠総合研究機構 松永伸司氏
研究マッピングゲーム領域実施メンバー
細井浩一氏、井上明人氏、福田一史氏、松永伸司氏の4名(い...2017年3月30日 更新
マンガの出版市場の縮小が止まらない。紙から電子へという大きな変化が起きていることは間違いないが、マンガ雑誌の凋落はそれだけでは説明がつかないほどド... 夏目真悟が監督・脚本・原作を手がけ、江口寿史がキャラクター原案を、マッドハウスが制作を担当したオリジナルテレビアニメーション『Sonny Boy』。「SF青春... 「ファミリーコンピュータ」(1983年7月15日発売)、「スーパーファミコン」(1990年11月21日発売)をミニチュアサイズでリバイバルした「ニンテンドークラシ...
80年代から現在まで、一貫してアニメ・ゲームの音楽を専門に創造し続ける稀有な作曲家・田中公平さん。作曲家としてのキャリアをスタートさせたのはCMやド...
1971年より始まった「仮面ライダー」シリーズは、2020年に放送を開始した『仮面ライダーセイバー』でテレビシリーズ32作目を迎えた。昭和、平成、令和と...
ゲームは現実世界の抽象化と誇張化の産物だ。その一方で近年、両者の関係性をゆるがすような出来事が、良い意味でも悪い意味でも起きている。ゲームと現実...
日本マンガの海外における受容を考えるために
多くの日本マンガが1990年代以降、アニメをきっかけに世界に広がっていくことになるが、手塚治虫の...2010年3月27日 更新
2000年代後半から勃興した、コンピュータゲーム文化の新たな潮流「インディーゲーム」。日本では80年代から豊かな個人制作ゲーム文化として「同人ゲーム」「...
1980年代よりキャラクターデザイナーとして長く活躍を続ける美樹本晴彦。35年に渡るその仕事を振り返ることのできる画集が『美樹本晴彦キャラクターワーク... 年春、東京藝術大学に立ち上がった「未来創造継承センター」。同大学がこれまでに生み出し、そしてこれからも生み出し続ける文化・芸術を、次の創造に活用可... 『テルマエ・ロマエ』(2008~2013年)などのマンガのヒット作のほか、旅、食、家族などを切り口としたエッセイ等の著作、最近では山下達郎の新譜ジャケット... Composer KOSAKI Satoru has led the world of animation songs and animation incidental music in the 2000s and 2010s. The first part of this interview...
妖怪ウォッチ、アマビエ、そしてゲゲゲの鬼太郎。日本は“怪獣大国”であると同時に、“妖怪大国”でもある。かわいくもあり、恐ろしくもある彼らは、まさに似...
ページの先頭へ